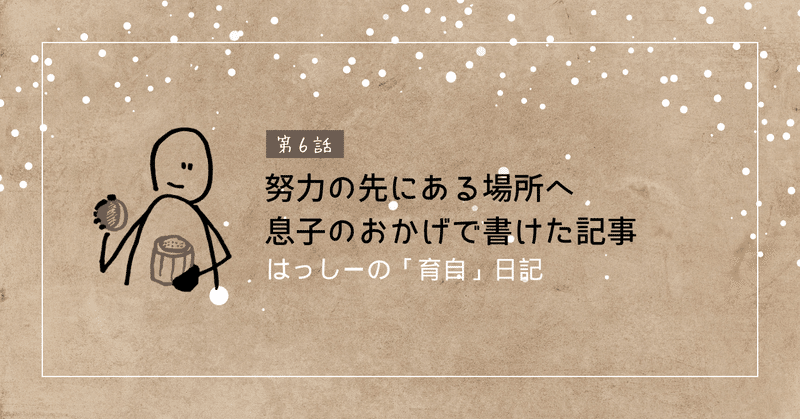
努力の先にある場所へーー息子のおかげで書けた記事
僕は聖教新聞に勤めて16年目の記者です。妻、小学1年の息子、幼稚園年少の娘と4人で暮らしています。2019年に第2子が誕生し、翌年にはコロナ禍のステイホームを経験して、子育てにもっと関わりたいと思うようになりました。そうした中、長男が「幼稚園に行きたくない」と宣言。小学校に入学してからも、学校に行ったり行かなかったりという今に至ります。家族と歩む中で、僕自身もメンタルヘルスを崩したり、部署を異動したり、いろいろなことを経験しました。それは、今も現在進行形で、僕という人間を大きく育ててくれています。そんなわけで、「育自」日記として、思い出を含めて書いていきたいと思います。
いつか、もう一度「君のおかげで」と伝えたい
僕が取材を担当し、自身の人生の節目ともなった記事は、2022年8月の聖教新聞に掲載されました。パパ、ママ、小学4年の長男と小学1年の次男(当時)の4人家族の歩みを通して、子育てを考えるルポです。紙面の中で大きな文字で表記する「見出し」は、次のような言葉としました。
・「親と〝学会家族〟で見守る、子どもの成長」(1面のタイトル)
・「日常こそが宝の思い出に」(1面のメイン見出し)
・「多くの人と出会える価値」(1面から続く3面のメイン見出し)
・「頑張る姿を、子どもは見ていてくれる」(3面のサブ見出し)
見出しは、忙しい読者も、それを見ただけで内容が分かり、それを順に追っていくと1つのストーリー(流れ)を構成していることが大切、と言われます。(この「見出し」のつけ方は奥深くて、自分はもちろん、多くの記者が頭を悩ませるものだと思います)
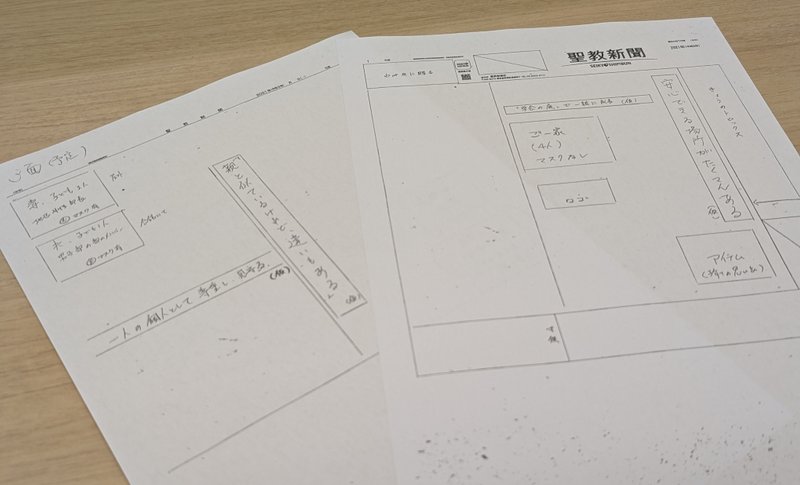
記事は、長男の誕生から始まります。ワンオペ育児で心身ともに疲弊した妻を目にした夫が、自分にできることを模索しながら、育児に尽力していく姿。そして、創価学会の会合にお子さんを連れていく中で、男子部の仲間たちが子どもと遊んでくれた思い出が描写されます。
そして、目線が妻へと引き継がれます。学会の仲間たちへの感謝は、夫と同様に妻も抱いていました。例えば、未就学時に人見知りが激しかった次男と、学会の女性部の先輩も交えて家庭訪問に歩く中、大人との信頼関係が芽生え、次男が人にあいさつできるようになったこと。
記事が進むにつれ、妻と次男、女性部の先輩が地域を歩く写真とともに、女性部の先輩による、子育ての回想コメントが入ってきます。
「やんちゃなわが子たちで、幼い頃は、会館に連れて行くたび、他の部屋の会合に〝乱入〟して、お騒がせしました(笑)。でも、のびのびと過ごさせてもらったおかげで、人との関わり方を育むことができました。だから、今の親御さんにも、気持ちを楽にしてもらい、学会活動で動く日々を、楽しい〝宝の思い出〟にしてもらいたいです」
さらに、最近の子育てに関する一家の悩みごとを紹介しながら、記事は結びへと向かいます。まず、親御さんの思い。
「息子たちには好きなことを大切にして、自信をもって社会で生きていってほしい」
そして呼応するように、結びの核心は長男の、パパとママに対する思いです。
「学会の会合に来た人たちに『ありがとうございます』と声をかけたり、帰る時は最後まで見送ったりする。団長(男子部大学校団長)だからとか、白ゆり長だからやっているんじゃなくて、それが、きっとパパとママにとっての当たり前なんだよ。偉いなって思う」
「家庭訪問」というのは、学会のリーダーの人が仲間の自宅を訪ね、生活の様子など近況を聞きながら語らう、という創価学会の伝統的な文化です。(会合に集まるだけではなく、一人一人に思いをはせ、会いに行くということですね)。そして「団長」や「白ゆり長」というのは、パパとママが担っている学会の役職を指しています。

記事掲載に当たり、僕が自らに問いかけたことが2つあります。
1つ目は、長男のコメントを結びに置くことが妥当か否かです。ストーリーとして分かりやすく流れていて、事実にも即している。(前提として、取材対象者の一家、長男にも次男にも、内容を親御さん経由で読んでいただき、次男には趣旨もかみ砕いてご説明いただき、了承を得ています)
その上で、掲載すれば読者の中から次のようなご意見を頂くことを、確信に近い形で予想しました。
〝まだ成長過程の子どものコメントを、最後の結びにおいて、オピニオン(主張)のように据えるのは、いかがなものか。子どもは親(大人)の期待をくんで、その通りのことを言うものなのだから〟
子どもは親の期待をくむ――それは専門家もしばしば、言及することです。では、実際に長男を取材した記者として、僕はどう判断すべきなのか。僕は取材の日、写真撮影をメインに、長い時間をお子さんたちと過ごしました。自分の息子とも、信頼関係を築きたいと過ごしていた時期でしたので、取材相手のそのお子さんたちとも、本気で遊びました。もう〝仕事と思うことをやめよう〟と決めて臨みました。
撮影は休憩をはさみながらも長時間にわたり、日も傾いた頃、僕から長男に「疲れていると思うからこれで終了にするね」とお伝えした時、「お話(取材)はいいの? 疲れてないよ」と言ってくれたため、僕は心の中で〝10分間〟と決めて話を聞くことにしました。
撮影をした創価学会の会館脇にはベンチが1台ありました。話を聞こうと移動した時、長男が「パパはあっちに行っていて」と言いました。そして僕と2人で話すこととなりました。僕からは「パパとママって、どんな人ですか」と、問いかけさせてもらいました。そうして返ってきた答えが、記事に掲載したコメントです。

記事を作り、紙面をデータで組み上げ、掲載日が近づいてきても考え続けて、僕は、この記事構成が「適切」であると結論しました。〝この10歳の取材対象者の思いは、個人の考えとして伝えるべきものだ〟と。
仮に掲載後にご意見を頂いても、記事には記者(僕)の署名が入っています。責任は僕にあり、間違っても一家が非難されることはない。〝署名記事で良かった〟と、プレッシャーに感じるのではなく、初めて真摯に感謝することができました。
※仕事のプレッシャーも相まって、メンタルヘルスを崩した経緯はこちらに ↓
掲載に当たり、自らに問いかけたことの2つ目は、見出しに(というか記事も含めてですが)〝目を引くような話題がない〟ということです。突出した結果(表彰とか業績とか)があるのではなく、大きな逆境(病気や障害、あるいはマイノリティーである苦しみ等)を乗り越えたということでもない。
そうした話を1面のトップと3面全部を使って掲載する。それが、新聞という業界のセオリーからして、読者に違和感を抱かせないだろうか、と当時は考えていました。
〝記事の中で社会的な問題に関する言及を増やしたほうが良いのだろうか? ワンオペ育児の問題点とかを掘り下げるとか・・・〟
そんな迷いが、デスク(記事の監修者)に見せる前の段階で、記事の原案を書いている時に生じました。
当時は、息子を寝かし付けた後に記事を煮詰めることが多かったのですが、その日は息子が深夜に起きて、自分を迎えに来ました。
「ああごめんね、一緒に寝ようねー」と言って、パソコンを持って寝室に行きました。もうこの頃(夏)は、春に見られたような、かんしゃくや夜泣きは、家ではある程度落ち着いていたので、背中をかいてあげると、すぐ寝てくれました。ただ、また起きてもかわいそうなので、しばらくは、ベッドの上でパソコンを開いて、静かに記事を推敲していました。
原稿の内容を自問自答しながら、息子の寝顔を眺めました。すやすやと穏やかな顔をしています。それを見て、〝ああ。今回の記事に、時事解説的なものは最小限で良い〟と思いました。
伝えるべきメッセージは明確に「見出し」に集約され、そのために必要な詳細は、一家の経験した事実として「記事」にある。
少なくとも僕は、一人の親としてそれを必要としている。
家族構成、親の働き方、子どもの性格や特性・・・世の中に同じ家庭など、1つもないけれど、相通じる思いというものは、きっと存在する。
〝子どもには、好きなことを大切にして、自信をもって社会で生きていってほしい。そのために、学会というコミュニティーでいろいろな人と交流する。会館に居るだけでもなんでもいい。その日常が、親の願いをかなえることに通じる〟――集約すれば100文字余りになるそのことを、僕は読者と分かち合いたいのだと、あらためて自覚できました。

掲載後、読者から、複数の感想のお便りをいただきました。〝子どもは親の期待をくむもの〟〝子どもにプレッシャーをかけないでほしい〟というご意見もありました。謹んで受け止め、今も胸に刻んでいます。
〝自分と共通することが多くあり、胸を熱くして読みました〟との声もありました。そして、このような趣旨のメールもいただきました。
〝日常の中に多種多様な悩みがあるのが今の日本社会だと思います。それぞれの悩みや課題を、学会員の前向きさと温かい励ましや助言で乗り越えていく姿が記事から浮かぶようでした。小ドラマの集積が過不足なく丁寧に書かれており、見事だと思いました〟
賛否、そして背景にわたる考察まで。このようなコメントを頂けることに、幸せを感じました。
記事が掲載された日の朝、息子から、「今日はパパの記事なんだね」と声をかけられました。妻が伝えてくれたみたいです。僕は「君のおかげで、パパはこの記事を書くことができたよ」と伝えました。
20代の頃から、根性だけはあるはずだと自分に言い聞かせ、人並みに努力を重ねてきたけれど、30代半ば頃から、記者として目の前に立ちはだかる〝壁〟のようなものを感じてきました。それは、成長の踊り場といえるかもしれないし、成長の限界ともいえるものだったと思います。
この記事が紙面になった時、自分にとって、努力だけでは越えられなかったその壁の向こう側へ行けた気がしました。そして、その場所へ自分を連れて行ってくれたのは、他ならない、自分の息子だと思いました。
僕から「君のおかげで」と聞かされた息子は、「ふーん、そうなんだ」と言ってはにかんだように見えました。当然ですが、その意味するところを、詳しくは分からないと思います。だから、感謝の気持ちを、彼が大きくなったら、もう一度、伝えたいと思っています。
そして季節は秋になり、僕はあることを考え始めました。
〝年が変われば3学期、そして小学校へ進学する季節がやってくる。彼のために、働き方を変える(部署を異動する)ことも視野に入れるべきではないか〟。
人知れず葛藤する日々の中で、エールを送ってくれたのは、僕の父でした。
(つづく)
聖教新聞の記者たちが、公式note開設の思いを語った音声配信。〝ながら聞き〟でお楽しみください ↓
日記へのご感想や、聖教公式noteで扱う企画のご要望なども、下の吹き出しマークの「コメント」欄にお書きいただけけたら幸いです。ぜひ、よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
