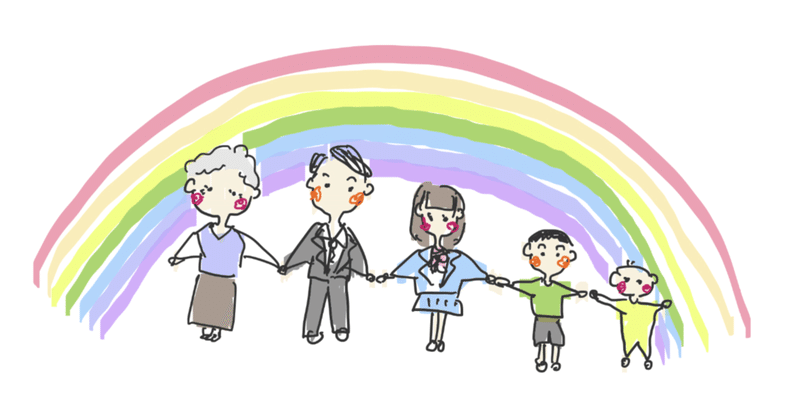
「何」を「いつ」まで持続可能にするのか?
「持続可能な」世界、「持続可能な」社会、「持続可能な」開発、、、持続可能、持続可能って繰り返されすぎて、もはや四字熟語みたいなってきてる今日この頃。
でも、「何」を「いつまで」持続することを可能にしたいんだ?
明確な”定義”がないと、その”定義”をみんなが共有してないと、ただ曖昧な「スローガン」で終わってしまう。
「いや、あるよ!!
2015年に国連サミットで採択された『2030年までに持続可能な開発目標(SDGs)を達成する』のがゴールなんだ!!」
って言う人もいるかもしれない。でも、2030年にそれをもし達成したとしたら、その時点で「私たちの世界」は「永遠に」持続可能なのか?????
そんなわけない。
あなたは、「何」を「いつ」まで持続可能にしたいのか、考えながら読んでみてほしい。
1.地球温暖化とは
先月、7月27日国連本部のグテーレス国連事務総長が「地球温暖化の時代は終わった。地球沸騰化の時代が到来した」と発言した。
"The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived."
そもそも、地球温暖化とは何なのか。
環境省によると、「人間の活動によって、大量の温室効果ガスが大気中に放出され、地球の気温が上昇し、自然界のバランスを崩すこと」とある。
もう少し詳しく解説すると、太陽放射から熱を得た地表面は、赤外放射をして熱を宇宙に放出する。その時、地球には大気があることでその大気中の温室効果ガス(二酸化炭素など)が赤外線を吸収、放出することにより地表面が再び暖められる。
しかし、大気中の温室効果ガスが増えすぎると、宇宙に放射される赤外線量が減り、地表面が暖められすぎてしまい、地球の平均気温が上昇する、というわけだ。

2.異常気象=温暖化!?
結論から述べると、異常気象=地球温暖化ではない。
前提として、毎年の天候は、原因がなくとも不規則に変動する。これは「内部変動」と呼ばれたりする。例えば、今ちょうど関西地方を北上中の台風だって、毎年不規則に発生して、強さや経路が異なる。また、年単位だと、エルニーニョ現象やラニーニャ現象が有名だ。
天候とは、そのような内部変動の複雑な組み合わせで決まる。
しかし、原因があればそれに応じた変化が起こる。これは「外部要因」と呼ばれる。下の図に細かく示したのだが、自然起源の火山噴火・太陽活動など、人間起源の温室効果ガス排出・土地開発による陸地の物理的特性の変化など、がそれにあたる。

気象庁によると、異常気象とは「30年に1回起こる程度の珍しい気象」のことである。「異常」なんだけど、違った見方をすると「内部変動」によってたまたま「異常」なことが起こることだってありうるよねってこと。
したがって、「異常気象」は「地球温暖化」がなくとも起こる。しかし、「地球温暖化」によりその頻度は年々増している、と言うのが正解なのかもしれない。
3.気温が2℃上昇したらどうなるの?
地球温暖化対策の話になると必ず出てくるのが、気温上昇を2℃もしくは1.5℃以内に抑えないと大変だって話。具体的には「世界平均気温上昇が産業化前を基準に2℃を超えてはいけない」って国際的な取り決めの文書に出てくる。
(2009年イタリアのラクイラでのG8サミットでの首脳宣言、2010年メキシコのカンクンでのCOP16での国連気候変動枠組条約、2015年フランスのパリでのCOP21のパリ協定では1.5℃)
IPCCの1.5度特別報告書(2018年)によると、世界の平均気温は既に産業革命前に比べて、人間活動によって約1℃上昇しており、このままの経済活動が続けば、早ければ2030年には1.5℃の上昇に達し、2050年には4℃程度の気温上昇が見込まれているらしい。
じゃあなんで2℃なん?
温暖化が進めば進むほど異常気象は増加するし、温度上昇に伴って直接的に海面上昇、水不足、野生生物種の絶滅、、等が起こると言われている。これらの悪影響は結局は連続的に起こるから、程度の問題なんだけど、いくつかの気候システムはある一定の値を超えると不連続的な変化をする、と言われている。これを「ティッピング要素」と呼ぶ。
ティッピング (tipping) は、ひっくり返るって意味。
例えば、「ししおどし」は竹筒に水が入っていくと竹筒が重くなってって、ある水位を超えると、急に傾いて水がこぼれる。
この竹筒が傾いて水が放出される瞬間みたいに、それまで連続的だった変化が、ある点(ティッピングポイント)を超えると、突然不連続な変化を生じさせる。これが、気候システムの中にもあると言われている。

具体的には、グリーンランド・南極の氷床減少の不安定化、アマゾン熱帯雨林の枯死、海洋深層の循環の停止などが挙げられる。
下に「氷床減少」の例を挙げる。
現在も、気温上昇により氷床は減少しているけど、今くらいの気温で温暖化が止まれば、氷床の減少は止まると考えられてる。でもティッピングポイントを超えてしまうと、
①氷床が小さくなったせいで日射の反射率が小さくなる
②氷床の表面の標高が低くなったせいでより暖かい空気に触れる
という二つの理由から、さらに氷床が加速的に減少してしまうという。

4.化石燃料をどうするか
気温上昇を2℃に抑えるためには、2075年頃には脱炭素化する必要があり、努力目標である1.5℃に抑えるためには、2050年に脱炭素化しなければならないと言われている。(IPCCの1.5度特別報告書(2018))
炭素排出量を減らさないといけないって話ばっかりだけど、
そもそも、資源は有限で、化石燃料って足りてんの?
答えは、「少なくとも今見つかってる分使い切ったら、余裕で2℃超えるくらいにはある」ってこと。
気温上昇2℃以内に抑えるには、炭素5000億トン相当の温室効果ガスが排出上限であって、それを排出したとして達成できる可能性は50%らしい。
じゃあ、まだ足りてる(?)化石燃料を使いつつ二酸化炭素を排出しないようにしたらいいんちゃうん?って思うかもしれん。その通り。
今は、CCS(炭素回収貯留)って言って排出した二酸化炭素を地下の帯水層に注入して封じ込める技術とか、化石燃料にアンモニア混ぜて二酸化炭素の排出を減らす技術とか、いろいろ開発されてる。
でも、よく考えてほしいのはそれは根本的な解決にはなってないってこと。その場しのぎでしかないのが現実。

火力に頼る、技術の拡充を検討しているらしい。。
5.国際的な枠組み
上の議論から、私たち人類は将来にわたって炭素5000億トンに相当する量しかもう排出が許されへんってことになる。こうなると「炭素排出枠」が有限な資源だと見なされないといけない。したがって、この「炭素排出枠」を世界各国に、各国内で、また、現代から将来にわたる各世代で、どうやって分配するかが大きな問題になってくる。
しかし、一度この分配ができてしまえば、自分に分配された分は、勝手に使ったり売ったりできるし、足りなくなったら誰かから買ってくることができる。これが「キャップ・アンド・トレード」という考え方であり、先進国の間でこれをやったのが京都議定書。
この「キャップ・アンド・トレード」って方法、実は経済学的にも合理的らしい。炭素排出枠が売り買いされると、その市場が形成されて、取引価格が決まる。これによって、自分がコストをかけて炭素排出を減らすよりも市場から買ってきた方が安ければ排出枠を買えばいいし、逆に自分で減らすコストの方が市場価格よりも安ければ、自分で減らして、排出枠を売ればいい。この結果、コストの安い人から順番に排出を減らすことになるから、世界全体で合計してみたとき、もっとも安いコストで排出を減らすことができる。

6.未来の人類のこと
じゃあ、実際問題、どれだけの人がコストかけてまで「未来」の世代のため、「今」温暖化対策の必要性を感じるのだろうか。また、温暖化対策にどれほどの「経済価値」があるのだろうか。
実際に、必要な対策費用を見積もった時点で、対策によって失われる経済価値が大きすぎるので「現実的ではない」あるいは「国益に反する」という主張がなされることも多い。
特に、「コスト・ベネフィット分析」=費用便益分析を行ったときに、この主張がなされやすい。費用便益分析では、まずすべての温暖化の影響を経済価値に換算し、便益を被害額から差し引く。そして、対策費用も計算し、様々な規模で対策を行った場合について計算する。
将来の温暖化影響や対策費用の経済価値をすべて「現在価値」に換算する(すなわち将来の価値を低く「割引して」見積もる)ことは、人が主観的に将来よりも現在を重視する傾向や、経済成長によって今持っているお金には将来利子がつくことが関係しているようだ。
しかし、この「割引率」 により結果はかなり変わってくるし、将来世代を軽視することの倫理性も問われており、現代世代と将来世代は平等であるべきだ、という「世代間衡平」の意識は誰しも自然に持つものだと思う。
また、人命や自然環境の価値をどう経済価値に換算するかという問題もあるし、将来起こる温暖化の影響を評価する難しさも残されている。
そしてそもそも、「経済価値」を大きくしたからと言って人々が幸せとは限らない。

7.あなたにとっての持続可能は?
このように、地球温暖化対策に”絶対的”な基準や正解はない。
それを決めるには、社会全体で「守るべき価値は何か」という判断が必要になる。それは、気象の専門家が決めるわけでも、経済の評論家が決めるわけでもなく、市民が民主的に判断することが求められているのだ。
では、われわれ市民にできることは何なのか。それは、社会全体での「意見形成」である。1987年の「国連環境と開発に関する世界委員会」において「持続可能な開発」という言葉 が使われ、それ以来「持続可能性」は専門家や政府が未来を考える際の中心的な考え方になってきた。
持続可能とは「なに」を「いつ」まで守り続けることなのか。この問いには 1 人 1 人の 主観的な意見があり、価値判断があると思う。
だからこそ、「今地球で何が起こっているのか」「自分が守りたい価値基準は何なのか」そうしたことに興味を持ち、自分の意見を持ってほしい。
そして、身近な人と議論でき、専門家から提供される知識・情報に簡単にアクセスでき、政府に物申せる。 そんな社会構造ができてきたとき、はじめて「地球温暖化対策」は良い方向に進んでいくのではないかと思う。
参考文献
この記事は、書籍『異常気象と人類の選択』江守正多氏の解説をもとに執筆させていただきました。
素晴らしい学習機会をいただきまして、本当にありがとうございました!
https://www.amazon.co.jp/異常気象と人類の選択-角川SSC新書-江守-正多/dp/4047316229
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
