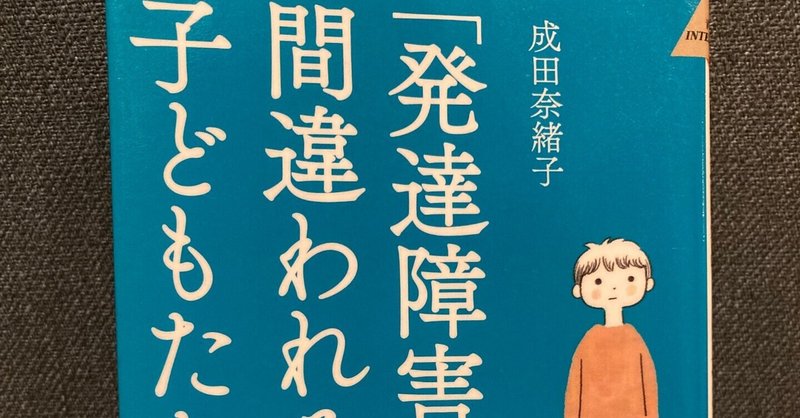
【教育 本#3】成田奈緒子『「発達障害」と間違われる子どもたち』
こんにちは、三太です。
このnoteでは「吉田修一さんの作品をもとにした映画ガイド」を作っています。
もちろんこれからもそこが軸になるのですが、中学校教員ということもあり、仕事のベースは当然「教育」にあります。
そのため「教育」関係の本を読んだり、「教育」について考えたりすることは普段からたくさんあります。
せっかくならそれもアウトプットしてみたいなと考えました。
月に1本ペースぐらいで「教育」に関する記事(主に本のまとめになると思いますが)をあげていこうと思います。
今回はその3回目になります。
少し月1ペースは崩れてしまいましたが・・・。
では、こちらの作品を読みます。
今、自分が「教育」で興味のある分野が「発達障害」です。
これまでの「教育」シリーズの投稿でも「発達障害」に関わる本の投稿をしてきました。
勤務先の図書室に入っていた本書が興味深かったので、読んでみることにしました。
要約
本書では、タイトルの通り、「発達障害」の診断がつかないのに、それと見分けのつかない症候を見せる子の増加の謎を扱います。
そのような子を著者は「発達障害もどき」といいます。(著者が作った造語であり、医学的診断名ではありません)
発達障害もどきの子が増えているのはどういうことか、そこからどのように抜け出せるのかといったことを本書は詳述していきます。
感想
(もう少し要約を続けて、感想につなげます)
「発達障害もどきを改善するということは、すなわち『子どもの脳育て』をしていくということ」(p.64)と著者は述べます。
子どもの脳育てをするためには脳の仕組みを知ることが大事で、それについてもわかりやすく解説されます。
著者は脳を簡単に次のように説明します。
からだの脳→脳幹・間脳・扁桃体などになどにあたる部分。
おりこうさん脳→大脳新皮質。
こころの脳→前頭葉、「からだの脳から前頭葉につながる神経回路」。
そして、「からだの脳→おりこうさん脳→こころの脳」の順番に、脳の部位を育てていくことが健全な発達には欠かせない(p.72)と述べ、特に「からだの脳が育っていない子は、『発達障害』と勘違いされてしまうことも往々にしてあるのです」(p.73)といいます。
では、そうならないためにはどうしたらいいのか。
脳をつくり直すたった1つの方法は「生活の改善」です。
著者は具体的に3つの方法を述べます。
1 朝日を浴びる
2 十分に眠る
3 規則正しい時間に食べる
この3つをすることが脳をつくり直していき、発達障害と勘違いされるような行動の改善につながるようです。
つまり、とても当たり前の生活をすることが大事だということです。
同時に脳の仕組みについて知っていることが生きやすくなることにもつながります。
改めて脳科学の知見というものに興味が湧きました。
そして本書を読み通して思ったのは、「病院に行く前にできることをしてほしい」というメッセージがあるのではないかということです。
私の少ないながらの経験から言わせてもらうと、発達障害の検査を受けようとすると、すぐには検査を受けられず、軽く半年ぐらいかかるというようなことをよく聞きます。
それだけ混み合っているということです。
でも、そこにはもしかして本書で述べられているような「発達障害もどき」の子も多く含まれるのかもしれません。
当たり前の生活をすることで、それらの子がよくなるなら、本当の発達障害の子もしっかりとした検査を受けられやすくなります。
現に著者はASD、ADHDの診断方法を説明した上で、「診断はときに主観的であり、流動的なものでもある」(p.57)といいます。
それは診断を下すにあたって、当事者の周囲の人が、質問に答えていくからです。
つまり、発達障害は「まわりの人の主観」によって生み出されるものでもあるのです。
主観で生み出される可能性がある発達障害なら、違う可能性も大いにありそうです。
そういったところから、本書が暗に示すメッセージを受け取りました。
逆に言うと、当たり前の生活をすることが難しい世の中になっているのかもしれないですね。
本書はどちらかというと「発達障害」についての本ではなく、むしろそうではない、疑いを持たれるような人たちについて書かれたものだったのだと思いました。
今回は成田奈緒子『「発達障害」と間違われる子どもたち』の紹介でした。
当たり前の生活の重要性を改めて実感する読書でした。
それでは、読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
