
ドキュメンタリー映画「気候戦士〜クライメート・ウォーリアーズ〜」を観た。

気になっていたドキュメンタリー映画を観てきた。その名も、気候戦士。よかったらぜひ観てみて欲しい。現在は、ヒューマントラストシネマ渋谷で上映されている。
制作者は、カールAフェヒナーというドイツ人のジャーナリスト・映画監督である。約30年間、社会課題をテーマとしたテレビ番組や映画を制作してきており、中でも2010年に公開されたドキュメンタリー映画「第4の革命-エネルギー・デモクラシー-」は、ドイツで13万人を動員、同年ドイツで最も多く観られたそうだ。また、東日本大震災後にテレビで放映された際には、200万人が視聴。同国の脱原発に一定の影響を与えたとの話もある。
本作について以下公式HPより引用する。
気候戦士(クライメート・ウォーリアーズ)とは、気候変動を阻止するため、また環境汚染を止め、美しい地球を保全するために活動する気候変動活動家のことです。
映画では、環境を守るために立ち上がった環境汚染の被害者、子供達、そして実業家など様々な背景の気候活動家たちを紹介しています。これは化石燃料との闘いで、平和で安全な環境に生きるための人権を勝ち取るための闘いです。気候戦士たちは、業界のロビイストや劣悪な環境汚染の現実を塗る変えるために、最先端のテクノロジーや創造的な社会変革行動により解決方法を提示しています。
(HPはこちら)
映画で紹介されている活動家たちの活動と対比するように、トランプ大統領の演説動画がたびたび差し込まれていた。その理由は2つあるだろう。
1つは、トランプ大統領は2016年に合意されたパリ協定という、気候変動問題に関する国際的な協力体制を、離脱することを世界で唯一表明した(合意した当時はオバマ大統領。)ということ。
もう1つは、温暖化に最も大きな影響を与えているのはエネルギー産業なのだが、その中でも火力発電の比重は大きい。火力発電を行うことは、石炭を扱うため、二酸化炭素を大量に排出することになる。そのため、これまでは環境規制も行われていたが、それを取り払い、石炭などのエネルギー産業開発をより推し進めて新たな雇用を創出しようとしていること。この2点が、パリ協定を始めとする世界的な環境対策の流れと逆行しているため彼の動画を入れているのだと思う。
正直、タイトルが戦士とあるように、激しいデモなどの様子が多く紹介されて、危機を煽るような内容なのかと思ったが全く違った。もちろん、アジテートのようなシーンはいくつかあったが、それよりも今起こっていることを紹介し、私たちに気づきを促す方が多かった。ちなみに、観客は20名もいなかったように思う。平日なのに17時15分放映スタートだと会社員は観ることができない。勿体ないと感じたが、おそらく映画館の仕方がない都合なのだと思う。収入が上げられる人気作をその時間に割り当てたいはずだから。
この映画を観て印象に残ったことがいくつかある。それを紹介したい。
■ドイツの取り組みとその歴史
私はドイツが国を挙げて脱原発やその他のエネルギー産業をシフトさせようとする動きを世界でも先進的に進めていることを知らなかった。もともと、ドイツと日本は産業構造が似ているなどの理由で日本にとってモデルになるという話を聴いていたが、こういった活動についてもモデルにできるのかもしれない。この監督によれば、もともとドイツは、デモをしたり、政府に立ち向かうような国柄ではなかったが、30年間、脱原発活動が国で続けられてきたことにより、社会全体の雰囲気が変わったという。その変化の中で、政治的、経済的にエコロジーやグリーンムーブメントに力を入れる政党も登場していったそうだ。この変化を推進していく土台となる空気作りがどのように進んでいったのかに興味が湧いた。
■アメリカのパリ協定離脱にみる「国家の目的と手段について」
先月出版された落合陽一氏の「2030年 世界の地図帳」という書籍がある。
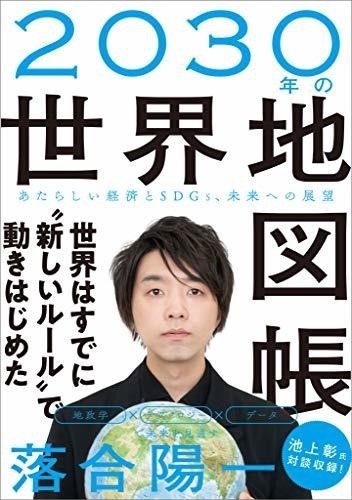
この書籍は非常に面白いのでぜひ読んで欲しい。この書籍の中ではこれからの世界で影響力を発揮していく国とそのメインとなる武器について書かれている。(もちろんそれだけではない)
取り上げられているのは、アメリカ、中国、ヨーロッパなどである。アメリカは、例えばシリコンバレーに代表されるような、データをフル活用できるITプラットフォーム産業がそれにあたる。
一方でヨーロッパは何がそれに当たるのか。その文脈で、今話題のSDGsが語られているのだ。落合氏によると、SDGsはヨーロッパの国が上位を占めていて、それらの国が評価されやすい指標になっているそうだ。ランキング上位ということは、世界から取り組みのモデルとなることができる。つまり、SDGsは国家間の影響力争いという文脈では、ヨーロッパが優勢になるという武器と言えるのだ。何事も、評価する側に立つと強いし、有利になる。
この観点から見ると、トランプ大統領は、影響力を下げないために他人が作ったルールの中で勝負するのではなく、そもそもルールを作るために離脱を表明したように思える。個人的には、この辺りの自ら勝てる土俵を作る、ルールは守るものよりも作るものという欧米のマインドはすごいと思っている。
しかし、映画でも紹介されているようにトランプ大統領の取り組みに反対する民意はある。実際に、パリ協定を離脱しないと表明している州もあるらしい。(調べていないので、それができるのかも分からないが)そういう意味では、トランプ大統領の進退によってアメリカ全体の施策は変わってくるが、その進退自体はもはや世界中のバランスにも影響を与えるので、1つだけを見て評価・判断できないのが現代なのだと思う。
特に印象に残ったのは以上となるが、上の気づきで触れた国際政治、パワーバランスなどは今一番興味関心があり、勉強しているところだ。というのも、日本が国際的に影響力を高めていけなければ、条件が悪い条約を結ぶことになり、それが国内情勢に影響を与え、国内の平和を保つことも難しくなるのではないかと思うからだ。
勉強し始めて思うことは、個人、国家の経済・政治、国際経済・政治、それぞれの階層において異なる力学が働いているということだ。言い換えれば、ある階層での好手が別の階層では悪手となるということ。
私はどこかで、1つのルールで全てが統一されていくことが平和なのかと思っていた気がする。しかし、最近その認識が変わってきている。まだうまく言語化できないが、例えるなら太陽系のイメージ。それぞれの星ごとの調和状態がある。つまり、複数の調和状態が同時に存在する方がより自然なのかもしれないということだ。まぁ、意味がよく分からないと思うのでまた整理できてきたら書きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
