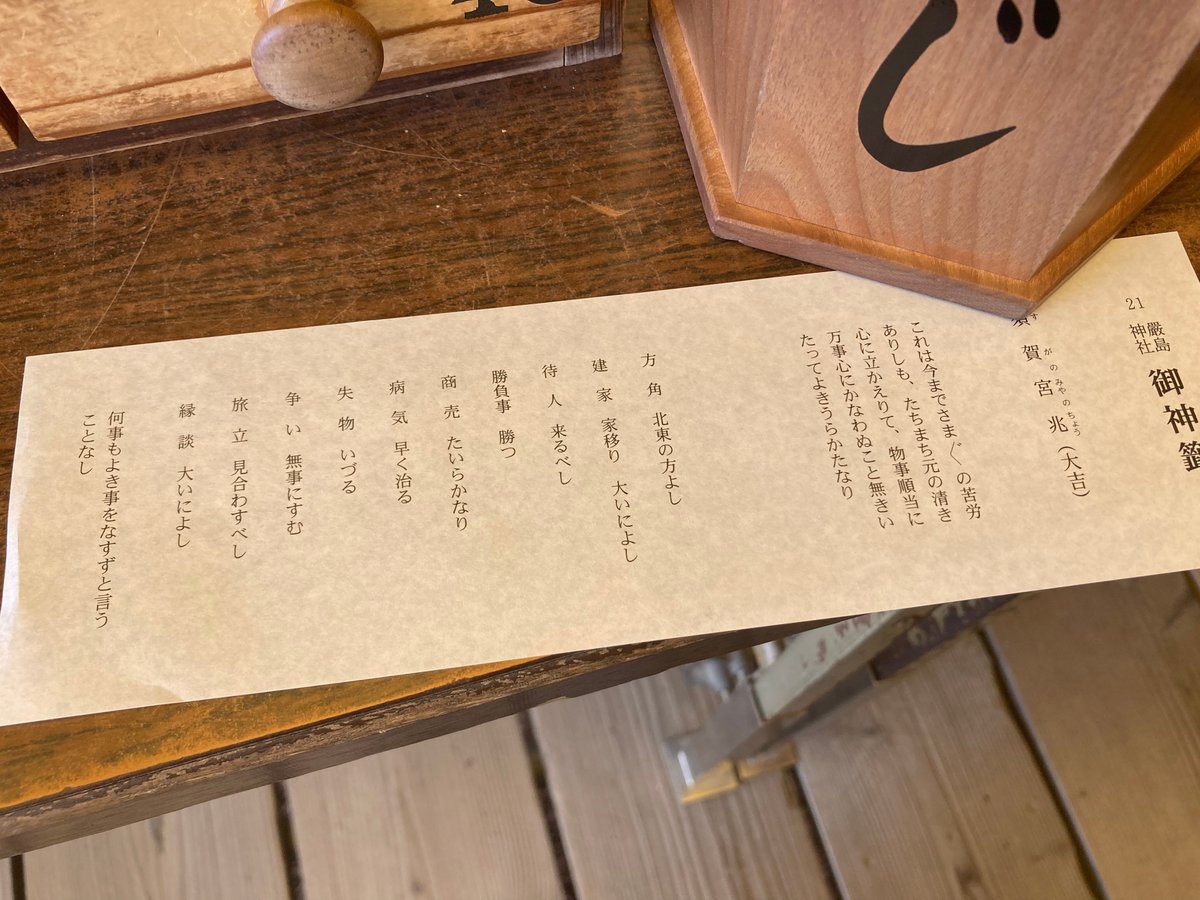傷に寄り添って生きる:2023年初秋の読書記録
長らく更新をおやすみしていました。
引っ越しなどでバタバタしていて、ようやく最近ゲーミングパソコンを購入して執筆環境を整えることが可能になりました。
最近は今まで精神状態上読むのが難しかった本を読むのが楽しく、積読をひたすら崩す日々でした。読んだ本を紹介します。
歴史
1.小野寺 拓也,田野 大輔『検証 ナチスは良いこともしたのか?』
史学専攻の人間としては読まねばという一冊です。今年のSNSにおける歴史本の台風の眼ですね。
もともとナチに関しては多少読んではいたので「こんな視点はなかった!」という驚きそのものはなかった一冊ですが、SNS上に渦巻く「この本に対しての反発」こそが最も驚くべき点ではあります。「ナチは良いこともしたでしょう」と同様の認知の歪みがいたるところで起きていて、そしてわたし自身にも浴びせられているのだということを痛感させられる日々で、ナチに興味があっても、なくても、誰もが読むべき本だと思いました。
なぜなら私たちはかつてナチが存在して、今も影響力を及ぼし続けているこの「良くない」世界に今、ここで生きているからです。
個人的な読書体験としては、知っている分野+薄めのこれを読破できたことで「新書やブックレット程度のボリュームなら読み切れるかも」という自信がつきました。
2.石濱裕美子『物語 チベットの歴史 天空の仏教国の1400年』
佛青方面からおすすめしていただいた一冊。私も石濱先生には学部一年の頃講義でお世話になっていました。
信じられないくらいいい本です。というか、ダライ・ラマ13世の人生と政治的な動き、とりわけダライ・ラマ13世の「大移動」については日本語で読める初めての研究であり、「なぜこれが学術書ではなく新書に……」という驚きとともに読み進めました。
ダライ・ラマの大移動が各地に散らばる(特筆すべきはソ連-現在のロシア領土)チベット仏教徒を鼓舞し、それぞれの地域でナショナリズムの醸成に大いに寄与したという部分については目から鱗が落ちる思いでした。また、13世~14世に対する日本人・大日本帝国の関与についてもくわしく述べられており、点と点が線でつながりました。
非常にかっちりとした史学の本でありながら「物語」とタイトルにつけた著者の想いにも頭が下がる心境です。
3.吉浜 忍,林 博史,吉川 由紀『沖縄戦を知る事典』
この夏は「戦争」について学ぼうと思った夏で、まず手に取ったのが沖縄戦でした。
コザと那覇へ訪れる予定が8月初頭の台風と怪我で中止となり、そんな中で「鉄の暴風」について何冊か手に取ったなかの一冊です。
日本に生きている人間として読まなければならない本です。
沖縄を捨て石として戦争を継続した本土の人間として。
文学
4.峠三吉『原爆詩集』
Audibleと岩波版を購入。広島旅行から帰って以来毎日聴いていました。
「わたしをかえせ わたしにつながる にんげんをかえせ」というあまりにも有名な序文から綴られる詩の数々。
峠三吉自身被爆以降命を長らえたのは8年弱で、今年は没後70年にあたります。彼がほぼ唯一残した作品であることも念頭に読まねばなりません。
岩波版は解説も秀逸です。日本の差別の問題を考えるにあたり、やはり「ヒバクシャ」からは逃れられないと痛感しました。


5.市川沙央『ハンチバック』
芥川・直木賞候補作の中で唯一受賞前に読んだ一冊です。読んでいて涙が止まりませんでした。今年刊行された小説の中で最高傑作を挙げるなら間違いなく『ハンチバック』です。
私はある種の「障碍」を抱え、健常者からは隔絶している立場の人間ですが、「障碍者はみな善良な人」「神様は乗り越えられる試練しか与えない」「聖性」「性別のない存在」といった数々の「差別-逆差別」を受け続けて疲弊しきっていた身に、唯一文字として、あるいは言葉として染み渡るのはこの本だけでした。
市川さんが再三訴えていらっしゃる読書バリアフリーについては、私もこの夏ケガで一時期視力を失っていたこともあり、「進んでもらわなければ困る」という心境でいます。
もともとKindleの読み上げ機能は使っていましたがやはり物足りないところがあり、この夏からAudibleを導入しました。便利です。
6.津村節子『紅梅』
数年前読んだことがあるのですが再読しました。
たまたま吉村昭『天狗争乱』を自分とパートナー双方のルーツにつながる小説として父に紹介され、吉村と津村の小説をもう一度きっちり読みたいと思い、まず手持ちの私小説の中で最高の味わいがある『紅梅』を手に取りました。初めて読んだのは6年前のようです。
当時と違って、幾人かの身近な人の死を目の当たりにしたこともあり、読んだ印象はぐっと変わりました。
介護する側、される側双方の忸怩たる思いを読みつつ、「自分もこの先親族の介護に直面する」という事実を否応なしに突き付けられます。
そして淡々とした筆致の中にみられる育子の心情として印象的なのは、慈しみよりもむしろ慟哭に似た悔悟です。
人間の生のなかでもっともプライベートな事柄である「死」を描いた物語は数多くありますが、ここまで徹底的に「公」を排除して私的に描かれると、読者である自分や、その周囲の大切な人に投射して読まずにはいられません。
7.北大路翼『流砂譚』
北大路翼の句集はこれが初めてなのでほかの句集と比較できていないのですが、やはり俳句に「パンク」という概念があるとするならこの一冊かなと思います。
特に新型コロナウイルスの猖獗でだれもかれもが家に籠り、季節の流れすら感じ取れなくなった「あのとき」に有季の句を詠み続けたということ自体、俳句の世界にあまりなじみがない私としては「とても無理だ」と思わざるをえないところがあります。
気に入った句を三つだけ。
名残梅マスクを顎にずらしつつ
紫陽花のような女の蹴り心地
盲牌でわかる八索花疲れ
良いなあ。
エッセイ・ノンフィクション
8.チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ『イジェアウェレヘ フェミニスト宣言、15の提案』
たまたま本屋で見かけて買いました。アディーチェの小説はときどき読んでいましたが、『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』以外のフェミニズムにまつわる本は読めていなかったので、いい機会だと思い。
これは「イジェアウェレという名前の女の子を出産したが、『女だから降りかかる理不尽な体験をさせずに育てるにはどうしたらいいか』」という友人からの問いに、アディーチェが答えた手紙です。
私は今のところリプロダクトとは縁がありませんが、心の底から買ってよかった本だと思います。これを「出生時診断で女の子を授かった母親のためだけの本」だと決めつけるのは、すこし読む本の幅を自分で狭めてしまっているように思います。
なぜなら、ひとびとの「子供をこう育てたい」という願いは、ほぼすべてが「自分はこうやって育ちたかった」に紐づいているからです。セックスやジェンダーは関係ありません。
この本はたしかに「ある人がよりよいフェミニストとして生きるための本」ですが、その主体は女性に限りません。
すべての人々が自らや他者の生きづらさを自覚し、内面化し(血肉にすると形容してもよいでしょう)、よりよくこの世をsurviveするために。シンプルかつきわめて重要なことを投げかけてくれる一冊だと呼べるでしょう。
9.宮地尚子『傷を愛せるか』
著者はトラウマ研究の第一人者です。ケアやトラウマといった本をここ最近集中的に読んでいましたが、どの日本語の文献でも、この著者の本や論文は参考文献としてほぼ必ず上がってきます。あきらかに一般向けであるエッセイである『傷を愛せるか』もです。
メンタルクリニックに通って、信頼できると思える先生を見つけても、「五分診療」の壁は立ちふさがっているわけで。話したいことがあふれて困ったときに、私はしばしば医師の書いた本を紐解きます。
この本の白眉は最終章「傷を愛せるか」だとやはり感じます。
ベトナム戦没者記念碑という、米国人だけを悼むワシントンDCの黒い碑。
トラウマ研究は「欧米の人間が困ったとき」にしか進まないようで、「ようやく第一歩が踏み出された」と呼べるのはベトナム戦争の敗色が濃厚になったときだそうです。いつ終わるかわからない。いつ駆り出されるかわからない。そうした不安定な状況で、人間を砲弾から機械に再構築する――労働力としてふたたびアメリカ社会に参与させるために推進されたのが、トラウマ研究の歴史だそうです。
私には大災害や戦争、ジェノサイドに由来するトラウマはありませんが、それでも「PTSD」の診断の射程に入る体験がいくつか存在します。
私のケアは、私の社会への参与が必要とされるのは、いったいいつなのだろう、と思いつつ読み終わりました。
冒頭の「なにもできなくても」は何度も読んでしまいます。念仏のように。マントラのように。
10.みき いちたろう『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体 』
「発達障害のような気がするけれど、知能検査をしても凹凸が見られない」。診断が下りないが発達障害にきわめてよく似た症状がみられる。そうしたひとびとが実は「トラウマによってそのような症状を呈しているのではないか」として、第四の発達障害として「発達性トラウマ障害」という概念を提起した新書です。個人的には腑に落ちるところが多いです。
私は明白に発達障害の診断が下りていますが、それは「トラウマ由来の生きづらさがない」ということを意味するものではありません。発達障害の特性を「ダメな人間」「人間じゃない」として烙印を押されつづける日々。そうした小さな抑圧は連続すると、今の症名でいう「複雑性PTSD」になるわけですが、しかしPTSDは先述の通り「日常の小さなトラウマ」は対象となっていません。なのでここではトラウマの射程を大幅に広げ、症名にとらわれない、よりよい治療を目指そうといった趣旨の本です。
対症療法ではなく原因そのものに光を当てる。
根本的な「寛解」には遠回りなように見えますが、傷に寄り添って生きることを肯定しなければ、人は先に進めないような気もするのです。