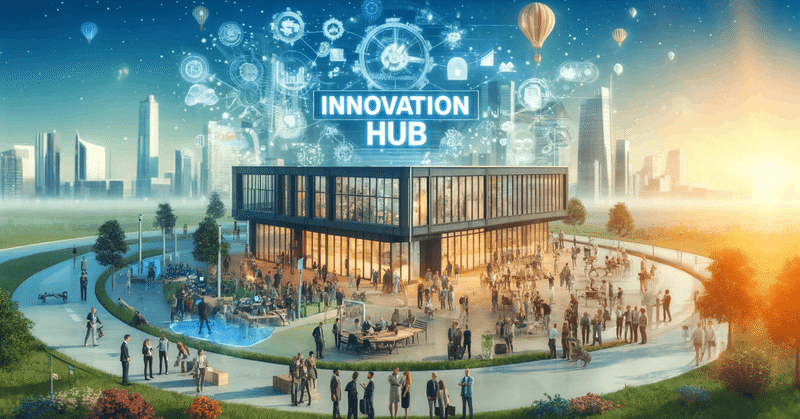
イノベーションを起こす中間支援組織のあり方
はじめに
スタートアップ、研究開発、社会課題解決 etc…新たにイノベーションを起こそうという機運が現在の日本では高まっています。勿論、地域社会の持続可能な発展と活性化の鍵もイノベーション(ソーシャルイノベーション)が握っています。そんな中、日本各地にイノベーションのハブとして、産業、起業、研究開発など多様なアクターを結びつけ、新しい価値を創造する中間支援組織が多く設立されました。しかし、これらの中間支援者が本当にイノベーションを起こすためのエコシステム構築に役立っているのでしょうか? この記事では、中間支援者が持つべき本来の役割と現状のギャップに焦点を当て、真のエコシステムにおけるイノベーションハブとはどうあるべきかを考察します。
エコシステムにおいてのあるべき姿
ハブという言葉は、もともと「車輪の中心部」を指します。車輪のハブは、多くのスポークが外側に伸び、外側に引っ張られることで車輪を支え、安定して回転させる重要な役割を担います。ハブは複数のスポーク(ビジネスにおけるプロジェクトやアイディア)を支え、ホイール(コミュニティや市場、エコシステム)が均等に力を受けてスムーズに回転することを助けます。イノベーションにおけるハブとしての中間支援者も、車輪のハブのように機能すべきです。つまり、中間支援者は内向きに他者リソースを吸収するのではなく、外向きの支援と連携を通じてエコシステム全体のバランスをとり、持続可能な発展を促進する役割を担うべきです。真のハブ機能とは、エコシステム内で受け取ったリソースや情報、エネルギーを有効に活用し、さらに外に向けて放出する「give」の精神を持つことが重要です。そうすることで、中間支援者はただの中継点や中央主権的な存在ではなく、エコシステム全体の活性化と成長を促進するキープレーヤーとなり得ます。
現状の問題点
しかしながら、現在、多くの中間支援者は、外部からリソースを「集積させる」ことに重きを置きがちです。これにより、エコシステム内の他主体との協力や連携よりも、組織自身の目的達成にリソースを集中させてしまっています。自立分散的な拠点として発信していても、実態は中央集権的な機能を担ってしまっている現実があります。特に、まだ何も有していないスタートアップや研究者は中間支援者に頼りきりになり、自身の本来の目的が達成されなくなることが起きえます。この結果、エコシステム全体にとって有効な連携や資源の循環が阻害され、エコシステム全体の健全な成長が妨げられます。
改善の提案
中間支援者が本来の役割を果たすためには、以下のような改善が必要です。
外向きの支援の強化: 外部のアクターとの協働を促進し、リソースを共有することで全体のバランスを取る役割を果たすべきです。これには、スタートアップや地域コミュニティ、教育機関との積極的な連携が含まれます。
開放性と透明性の向上: プロジェクトの選定や資源の配分に際して、公平かつ透明なプロセスを確立することが重要です。これにより、ハブ自体の信頼性が高まり、より多くのイノベーターや投資家を惹きつけることができるでしょう。
持続可能な戦略の採用: 短期的な利益よりも長期的なビジョンに基づいて行動することが求められます。持続可能な開発目標(SDGs)に沿った取り組みを推進することで、地域社会やグローバルな規模での影響を考慮した戦略を展開する必要があります。
結論
イノベーションエコシステムにおける中間支援者は、単なるリソースの集積地ではなく、動力源としての役割を果たすことが求められています。そのためには、内向きの利益追求を超え、エコシステム全体の調和と持続可能な発展を促進する実践的な行動が不可欠です。中間支援者が真にその機能を果たすためには、全ての関係者が協力し、新たな価値創造のための土台として機能することが重要です。この理解を深め、具体的な行動に移すことが、我々の社会にとっての次の大きなステップとなるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
