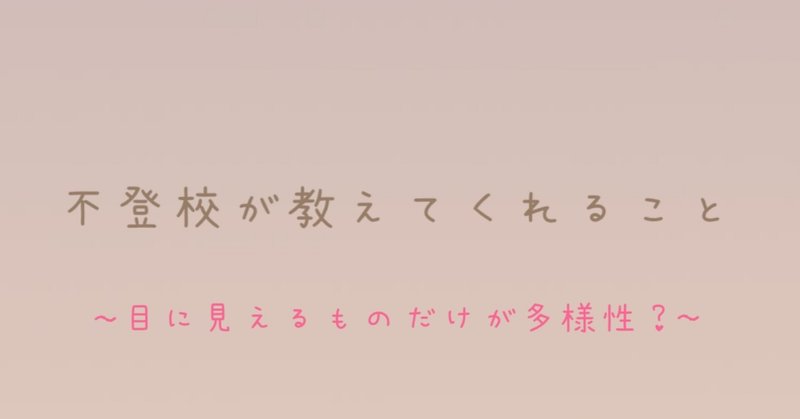
不登校が教えてくれること~目に見えるものだけが多様性?~
今回は、不登校を10年以上経験してきた私が、多様性について考えてみました。
私が行きしぶりを始めた頃、幼いながらに私は人と違うんだと感じていました。
しかも、不登校の中でも珍しいパターンだと親も私も思っていました。
なぜかと言うと、担任からの過度な指導から行けなくなっているからです。
当時、先生との相性で不登校になっている子のことは、少し珍しいのではと思っていたのです。
ですが最近は、少しずつですが先生との相性の話をよく聞きます。
そして、HSC.HSPという言葉も知られるようになってきて、私が敏感で感じやすいところがあったことも分かりました。
そんな、少しずつ広まってきた不登校という言葉。
でも、実際まだまだすべての人に理解してもらうのは難しいようです。
ですが、今多様性が認められてきた中で、不登校の理解が深まってほしいなと思います。
それとともに、不登校から人と人とが認め合う社会が広がっていって欲しいなと思います。
そのように私が思うのは、最初にお話ししたように、私自身人と違うことに悩んできました。
人と違うと言っても、見た目で分かることではありません。
目に見えない違いだからこそ、理解してもらえず苦しむこともありました。
私の悩みは、心だったのです。
学校にトラウマを持ち、それから強迫性障害も発症しました。
目に見えないことだからこそ、隠そう隠そうとしていました。
隠したら、いわゆる普通の人になれるから。
でも、それは自分をかなり苦しめていたのです。
心が孤独になってしまっていました。
でも、それから私の心が楽になった瞬間がありました。
それは、親に話せたことです。
今まで自分の事さえ理解できず、言葉にすることも難しかった私が、自分を理解し親に言葉として話せたことは本当に嬉しかったです。
そして、親は私の壮絶な学校生活を知り、不登校を理解してくれました。
それが、私にとって自分を認めてもらえてた瞬間でした。
今まで、否定し否定されてきた学校に行けない自分が、生きていく上での安心感を得ることが出来ました。
その、安心感ってどこから来るのだろうと考えることがあります。
よく聞かれることでもあります。
でもそれって、不登校の自分を認めて受け入れてくれる=生きていく上での選択肢が増える、ということになります。
学校に行かない、家やフリースクールや居場所で過ごす、そういう選択肢が増えるのです。
学校に行くだけしか選択肢がなかったら、生きる選択肢まで減ってしまうと思うのです。
自分で自分の選択ができる、それが安心です。
そして、その選択を誰もが認めてくれることが安心へ繋がるのです。
これこそが、不登校の私が経験してきたことです。
では、これが多様性とどう関係しているのかというと…
不登校から様々な選択ができる社会になってほしいということです。
学校や仕事、髪型や服装も多様性だと思います。
みんな一人一人違うことで、この社会は発展していくのです。
だから、学校に行かない(みんなと違う選択をする)ことも、決して悪いこととして捉えて欲しくないのです。
そして、人と違うことに苦しまないで欲しいです。
私自身も感じた、人との違い。
でも、それは今となれば強みになっています。
敏感だからこそ、人の気持ちに気付くことできたり、危険に察知できたりするのです。
学校に行かなかったからと言って、もちろん勉強に関してはできないことも多いですが、生きています、生きていけます。
逆に言えば、みんなと同じ行動ができるように集団行動を促す学校は、まだ古い考えで止まっているのだと読み取ることもできます。
ただ、人よりすごくならなきゃいけないわけでもありません。
大事なのは、一人一人色々な生き方があって、それをみんなで認め合えることです。
でも、ここから私が言いたいのは、見えているものだけで判断しないで欲ししということです。
人間には、心があります。
その、目には見えない心を認め合うことで、更に多様性を深めていって欲しいのです。
先程お話した、私が感じた見えない悩みこそが、心の中の事です。
その、心を認め合うのが、不登校です。
何らかの苦痛がある学校に行かない選択をする子どもたち。
でも、その苦痛を感じる心は目で見えないので、どうしても隠れてしまいがちです。
そして、学校側からすると、学校に来ていない子はどうしても見えない見ようとされないのが事実です。
でもそれって、多様性ではないですよね。
一人一人違いを認め合うのが多様性なら、一人一人と向き合うことが大切です。
もしそれが、学校という場所の人でなくても、フリースクールや居場所や相談機関などの人でも、一人一人をサポートし受け止めることが理想です。
そう、理想であって、今のところ現実的には少ないのが事実です。
その背景には、学校からの支援がされていなかったり、その他の支援を利用しようとすると金銭面が関わってきます。それと、まだまだ学校以外の選択肢が知られていなかったり、敷居が高いと感じたり、ということがあげられます。
こういった現実から、多様性はまだまだ広まっていないのかなと感じたりもします。
性別など、目に見えて分かることに対して多様性が認められてきていることはもちろん素敵なことだと思います。
でも、今私が伝えたいのは、目に見えないところを忘れていないか、ということです。
不登校だけではありません、精神疾患や、そのほかの疾患でも、目に見えないものに苦しんでいる人たちは沢山います。
もしかして、見えていないのでははく、見て見ぬふりをしているのではないのかとも思ってしまいます。
だからこそ、こうやって沢山の人に伝えていきたいと思います。
多様性を認め合う社会への些細な一歩だとしても、不登校を一つの選択肢とすることは、小さな命を守ることにも繋がります。
そして、多様性を認め合うには、ある程度のサポートが必要です。
最近は、少しずつ不登校に対しての理解が深まってきたものの、サポート体制はまだまだ固まっていません。
家庭への負担は大きいです。
そういった多様性から、沢山の大人に不登校の支援のあり方について知ってほしいです。
小さな支援だとしても、大きな結果として帰ってくる日は来るはずです。
それは、不登校の子が元気になって活躍することもあります。
そして、何よりも不登校から大人にとって学ぶことは沢山あるからです。
これこそ、一人一人の選択を認め合い、一人一人が安心して生きていける世の中をつくることに繋がるためになると思います。
私自身も、不登校など沢山辛いことを経験してきた中でも、安心して生きていくためにはどうしたらいいかを考えるきっかけになりました。
そんな不登校は、沢山のことを教えてくれるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
