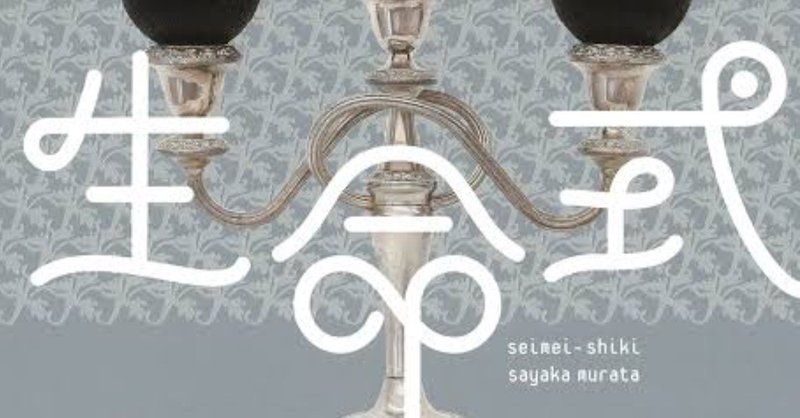
人肉を食べるということ、昔の常識が今の常識に変わるとき
どうも、お久しぶりです。
ウサギノヴィッチです。
約二ヶ月くらいの充電期間をいただいてからの復活、再開、season2の始動になります。
さて、充電期間中はなんにもしないでいた事の方が多く、本もあんまり読んでいるという意識がありませんでした。
ただ、再開一発目で、批評エッセイをやるということで、実際にはもうエネルギーは本当に充填されていたのだと思います。
今回は村田沙耶香さんの「生命式」の中の『生命式』です。
以前の批評エッセイの中で女性を取り上げることは少なかったことは少なかったと思いますし、新刊も同じだったと思います。
内容は、おそらく現代でもちょっと違うのは、男性が亡くなったら、みんなが集まってその死体を調理して食べる。そして、そこで知り合った男女が合意すれば、式からお暇してセックス(作品中は「受精」と書かれていた)をする。政府は、その式を奨励していてる。つまり、子作りを応援している。ただし、そこでできた子供は一夜だけの関係なので、センターと呼ばれる場所出産され、預けられる。つまり、結婚することなく、子供が出来ているのである。
主人公の女性は、昔は人肉を食べることは異常だったということを鮮明に覚えている。それを会社の別の課の男性の同僚と飲みながら話していた。ある日、その男性が死んでしまう。その男性の母親から電話がかかってくる。母親はお付き合いをしている相手かと思っていた。男性の意思で自分の肉を美味しく調理してくれという遺書みたいなものが見つかる。その話を聞いた主人公は手伝うことを申し出るのだった。
なんか久しぶりにやるとあらすじ先行型になってしまうなぁ。
この小説を前知識なしで読み始めてドキッとしたのは、人肉を食べるいう風習が定着しているということ。つまり、人肉を食べるという描写を読んだところである。
「あっ、この小説、普通の現代社会舞台に置いていないんだ」とびっくりする。
そして、その後にその世界が少子化に悩まされているというちょっとしたディストピア感のあるところだ。
そこでふと頭の中で過ぎるのが、「これはひょっとしてSF的な展開があるのではないだろうか?」ということだ。
だが、その予想は外れる。主人公と同僚の人肉を食べることへの倫理観みたいな会話があったり、同僚が死んだあとの人肉を調理するシーンがあったりと、ドラマがグルっと展開するようなことは起きない。
でも、最後の最後に同僚を亡くしたことに対する寂寥感が主人公を襲い、夜の鎌倉へと向かわせた。そこでゲイの男に出会い、主人公が生命式で作った人肉料理を同僚の妹にわたされたタッパーに入れられたものを一緒に食べた。そのときの会話が印象的だ。
「そのこと、変だって思いますか? せかいはこんなにどんどん変わって、なにが正しいのかわからなくて、その中で、こんなふうに、世界を信じて私たちは山本を食べている。そんな自分たちを、おかしいって思いますか?」
男は首を横に振った。
「いえ、思いません。だって、正常は発狂の一種でしょう? この世で唯一の、許される発狂を正常と呼ぶんだって、僕は思います」
「・・・・・・」
「だから、これでいいんだと思いますよ。この世界で、山本さんは美味しくて、僕たちは正常なんです。たとえ100年後の世界で、このことが発狂だとしても」
この会話は、非常に印象的だった。今現在という所に焦点を置き、過去や未来には囚われていない。それは究極的な楽観的なコメントや、上辺な慰めをする言葉ではないと思う。つまり、「正常」と言うのは常に危ういものであって、我々が抱いている「常識」もいつかは「異常」になりかねない。それは時代の経過によって変わるものだということだ。
それを証明するかのように、男が去った後に海辺には、受精をする男女がいる。昔は、快楽を求めるために行われていた「セックス」がいつの間にか、神聖化されているということに疑問を持つ。
この小説は、大雑把に言ってしまえば、世の中で「正常」と呼ばれているものに対して疑問を持つ。過去の歴史の積み重ねで、変わってきたものに対して疑問を持つ。
そういう風にぼくは読み取れた。
もっと大きく言ってしまえば、世界の仕組みはなにかしら、だれかしらが、握っているように書いているように感じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
