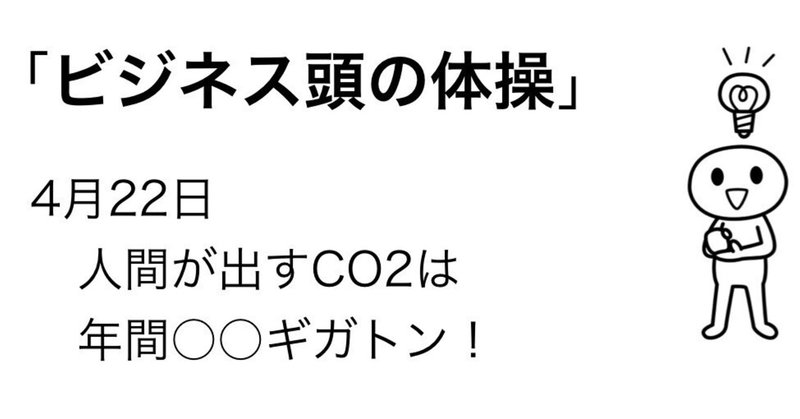
4月22日 人間が出すCO2は年間○○ギガトン!
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→オイルショックは原油コスト増を通じて日本の省エネ技術を飛躍的に高めた。二酸化炭素でも、排出権取引など市場を通じて効果を高めようとする取り組みが始まっている。排出権取引以外に市場原理を使って二酸化炭素削減の実効性を高める仕組みはどのようなものが考えられるだろうか?
1970年のこの日、アメリカの市民運動指導者で、当時大学生だったデニス・ヘイズが提唱した「アースデー(地球の日)」です。
この「アースデー」は、2009年の国連総会で制定し、翌2010年から正式に国連の記念日「国際母なる地球デー(International Mother Earth Day)」となっています。
この日に合わせて様々なイベントが開かれるようです。ご興味がある方はアースデイ東京の公式サイトをご覧ください。
地球。
テーマとしてデカすぎて困りますが、ここでは地球温暖化について調べてみました。もう、何度か目にした内容かもしれませんが改めて。
まず、温暖化って何?ということですが、気象庁のHP「温室効果ガスに関する基礎知識」から引用します。
工業化時代以降、特に20世紀に入ると急速に、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、人工物質であるハロカーボン類などの温室効果ガスが増加しています。これらの増加がもたらす地球温暖化は、自然の生態系や人間社会に大きな影響を及ぼすことから、人類の生存基盤を揺るがす問題となっています。
では、具体的にどれくらいの気温上昇が起こっているのでしょうか?
同HPから世界平均地上気温の偏差を見てみましょう。ちょっとわかりにくいですが、0.8度程度上昇していることが読みとれます。

その原因の1つである二酸化炭素(CO2)濃度の変動は以下の通り。よく見るやつですね。

赤線が年間の平均値。増加トレンドであることが分かります。緑の線を見ると、季節変動があることが分かります。これは夏季は植物の光合成が活発となって二酸化炭素が吸収されることによるものです。
次に、1年ごとの二酸化炭素の増加量を見てみましょう。

毎年の増加量には結構なばらつきがあることが分かります。これにはエルニーニョ現象と関係あるそうです。以下引用します。
エルニーニョ現象が発生すると、陸上生物圏では熱帯域を中心に高温・乾燥化することにより、植物の呼吸や土壌有機物の分解による二酸化炭素の放出の強化と光合成による吸収の抑制が起きます(Keeling et al., 1995)。また、その高温・乾燥化は森林火災を発生させやすくなり、二酸化炭素の放出が強まることも知られています。一方、海洋においては、太平洋赤道域の東部から放出される二酸化炭素の量が減少しますが、これは陸上生物圏による放出の増分より小さくなっています。結果的に、二酸化炭素濃度の年増加量は増大する傾向となります(WMO,2018)。
毎年の二酸化炭素吸収量とエルニーニョ現象の発生時期(ピンクの部分)を合成したグラフがこちらです。…関係あり、そうですね。

二酸化炭素濃度上昇は主に人間の活動によるものだと言われています。だとすると、昨年からの自粛、ロックダウンによって減少してしているはずです。
実際、昨年の4月初旬まででCO2排出量が17%減、通年でも7%減少するとされています(出典:WIRED記事、日経記事)。
あれだけの自粛や経済活動の停止があって、たったの7%しか減らない、というのは、「カーボンフリー」という目標の高さが実感できます。
日経記事の中に、2019年のものになりますが、排出量と吸収量の実数がありましたので、ご紹介します。ppmなどより少しですが実感が出る気がします。
■ 人為的な排出 11.5ギガ(ギガは10億)トン
● 大気に蓄積 5.4ギガトン
○ 海洋で吸収 2.6ギガトン
○ 植物で吸収 3.1ギガトン
→オイルショックは原油コスト増を通じて日本の省エネ技術を飛躍的に高めた。二酸化炭素でも、排出権取引など市場を通じて効果を高めようとする取り組みが始まっている。排出権取引以外に市場原理を使って二酸化炭素削減の実効性を高める仕組みはどのようなものが考えられるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
一昨年の7月から続けてきました。以下のマガジンにまとめておりますのでよければご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
