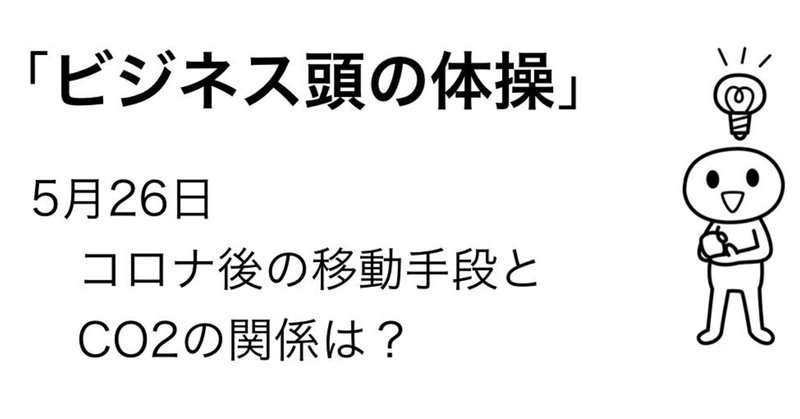
5月26日 コロナ後の移動手段とCO2の関係は?
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→感染症の観点から車での移動が増え、中古車も売れているという報道も見かける。CO2削減の観点からは鉄道の方が圧倒的に有利だが、アフターコロナでは移動手段はどうなるだろうか?
1969年のこの日、大井松田IC~御殿場ICが開通し、東京から愛知県小牧市まで346kmにおよぶ東名高速道路が全線開通した、「東名高速道路全通記念日」です。
高速道路。
今回は、民営化されたんだよな、ぐらいの認識しかありませんでしたので、改めて調べてみました。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構「高速道路機構ファクトブック2021」の<道路関係四公団民営化の枠組み>が端的にまとまっています(下図)。

高速道路を作り続けた結果、40兆円もの債務を抱えることになり、高速道路の建設・更新、管理、料金徴収を担う「東日本高速道路株式会社」「中日本道路株式会社」「西日本道路株式会社」の3社と、高速道路の保有・債務返済を担う「日本高速道路保有・債務返済機構」が作られた、というのが大枠です。
高速道路の建設は各道路会社が担うんですね。で、完成したら機構側に債務とともに引き渡し、その後、各道路会社は料金収入を減資に機構に貸付料を支払い、機構はそれを原資に債務を返済する、という仕組みです(下図)。

同機構「高速道路機構の概要2021」によると、令和元年度末時点でその総延長は10,360km、年間利用台数は31.1億台となっています(下図)。

全国で1日あたり約980万台が利用している計算になります。
気になる安全面ですが、高速道路における死傷事故率(1万台の自動車が1万キロ走行した場合の事故件数)は、平成18年度から約7割低下しているそうです(下図)。

各道路会社では、「安全・安心の確保」、「快適なサービスの提供」という2つのテーマに対して、死傷事故率、逆走事故件数、渋滞損失時間などの指標ごとに目標値を設け、改善を図っています(下図)。

こうした取り組みで40兆円もの債務は減っているのでしょうか?同概要に債務返済計画と実績がありました(下図)。

おそらく金利の大幅な低下もあると思いますが、計画を上回るペースで債務の削減が進み、11兆円を超える返済がなされ債務も減少しています。
機構が抱える債務の返済は進んでいますが、各道路会社の経営はどうなのでしょう?
直近通期決算である、令和元年度決算(2021年3月期)では以下の通り、コロナによる料金収入減で赤字になっています。
☑️ 東日本高速道路株式会社 料金収入:7,143億円(対前年16.6%減)、賃借料:4,809億円(同21.3%減)、経常利益:△25億円
☑️ 中日本道路株式会社 料金収入:5,762億円(対前年16.5%減)、賃借料:3,802億円(同22.6%減)、経常利益:△38億円
☑️ 西日本道路株式会社 料金収入:6,610億円(対前年17.2%減)、賃借料:4,457億円(同21.9%減)、経常利益:△32億円
(各社決算資料より)
この、賃借料、というのが機構に対して支払う道路の利用料なのですが、料金収入が一定割合を超えて減少した場合、賃借料も減らしてくれる取り決めがあり、が、料金収入の落ち込みほど大きな赤字にはなっていません。
独特な仕組みで支出も減るという要因もありますが、JR各社の数千億円にもなる赤字決算に比べると影響は少ないと言えそうです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
高速道路。なるほど、そんな仕組みになってたんですね。
このような投稿を一昨年7月から続けています。以下のマガジンにまとめていますのでご興味あればご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
