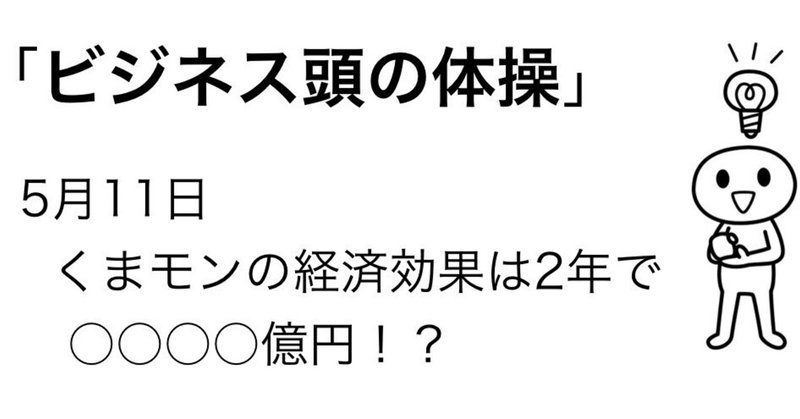
5月11日 くまモンの経済効果は2年で○○○○億円!?
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→自治体のゆるキャラ。参入障壁自体は低い(ぬいぐるみデザインして着ぐるみ作る)市場で埋没するという実例の一つだと思うが、では後発で成功するためにはどのような差別化、マーケティングが考えられただろうか?
滋賀県彦根市に本部を置く一般社団法人・日本ご当地キャラクター協会が2014年(平成26年)に制定した「ご当地キャラの日」です。
日付は「ご(5)とう(10)ち(1)」(ご当地)と読む語呂合わせからです。
ご当地キャラ。
いわゆるゆるキャラとして大ブームになりました。
様々なキャラクターが登場し、一時は全国に3千体とも言われました。
私、勝手に「くまモン」が最初なのかと思っていましたが、「くまモン」の登場は2010年2月で、2007年には「ひこにゃん」が登場して2008年には彦根市で「ゆるキャラまつり」が開催されていたんですね。チーバくんも2007年(千葉県公式になったのは2011年1月)とは…。全く認識不足でした。
さて、なぜ自治体がゆるキャラを、ということですが、初期は「ひこにゃん」は「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターとして、「チーバくん」も「ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉県大会」のマスコットキャラクターとして誕生しています。
ところが、「くまモン」あたりからゆるキャラがブームになると、いわゆる横並び、という意識もあったのでしょう、とにかく作って知名度をあげよう!という自治体も見られるようになり、結果的には埋没してしまうものもあったようです。
「くまモン」が一気にメジャーになった理由は複合的なものがあろうかと思いますが、元来お堅い自治体が予算を割くきっかけになったであろう報告書が、2013年12月に日本銀行熊本支店が公表した「くまモンの経済効果」でしょう。
同報告書の概要は以下です。
☑️ 「くまモン」登場から2年間に熊本県にもたらした経済波及効果は、 1,244億円
☑️ 同期間に「くまモン」がテレビや新聞に取り上げられたことによる広告効果は90億円以上
経済波及効果の分析は以下の通り。

☑️ 直接効果(くまモン利用商品による県内生産の増加)761億円
☑️ 一次波及効果(直接効果によって県内産業にもたらされる生産誘発額)277億円
☑️ 二次波及効果(一次波及効果によって増加した雇用者所得が消費に向けられることによって県内産業にもたらされる生産誘発額)193億円
観光への波及効果については以下の通り。

☑️ 観光客増加効果(県内観光でくまモンの3次元画像を取り込んだ写真撮影ができるアプリのダウンロード数と2013年のくまモン誕生祭の来場者数)18.8万人
☑️ 観光客増加による経済効果(上記をもとに推計)12億円
しかも、この報告書は、この「くまモン」による経済波及効果(2012年単年度分508億円)を他府県におけるNHK大河ドラマ等の経済波及効果と並べる、という「評価」もしているのです(下表)。

大河等の経済波及効果平均は205億円で、「くまモン」の508億円を上まったのは2010年の「龍馬伝」だけ、という、衝撃の結果でした。
この結果は、まさにゆるキャラブームの真っ只中にあって様々なメディアで取り上げられました。
各地方自治体が慌てて「やらなきゃ」となったことが容易に想像できます。
改めてなぜあそこまでゆるキャラが増えたのか、原因の一端が理解できた気がします。
→自治体のゆるキャラ。参入障壁自体は低い(ぬいぐるみデザインして着ぐるみ作る)市場で埋没するという実例の一つだと思うが、では後発で成功するためにはどのような差別化、マーケティングが考えられただろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
一昨年7月から投稿し続けており、だいぶ溜まってきました。
以下のマガジンにまとめていますので、よろしければぜひみてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
