
11月2日、11月3日 KOSEN水素フォーラムinOITAと大分ハイドロエキスポに参加してきました♨️
11月2日
11月2日大分県別府コンベンションセンターにて開催された、KOSEN水素フォーラムinOITAに研究室学生、マテコン学生、配管探傷学生を含む計25名で参加しました。(大型のシャトルバスで移動しました)

基調講演
はじめに理事長挨拶からはじまり
・九州大学松永教授による講演
「九州大学・水素材料先端科学研究センター(HYDROGENIUS)の取組みと最新の研究成果」~安全で安価な水素社会の実現に向けて〜
・三菱重工業(株)総合研究所 副所長 兼グローバル R&Iセンター長 茨木誠一様の講演
「三菱重工のカーボンニュートラルへの取組み」~水素エコシステムの実現~
佐世保高専学生によるプレゼンテーションがありました。

こちらはニュースで取り上げてもらった時の様子です。
こちらは2023年の講演
こちらでは、九州大学、三菱重工以外に、大分県、大林組、みずほ銀行、佐世保高専の水素エネルギーの事業紹介を頂きました。
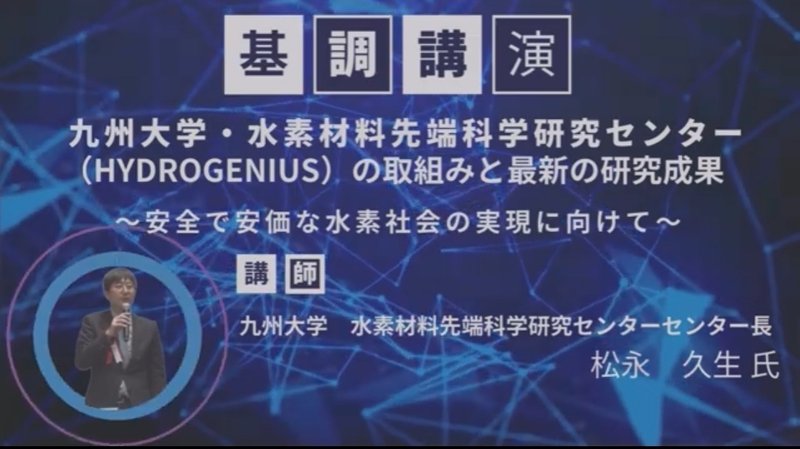



こちらは2022年の講演
杉山先生からは、
カーボンニュートラルに向けた水素と国際ネットワークの役割と題して、ご略歴、水素エネルギーの背景、東大先端研の取り組みをご紹介頂きました。
河野先生からは、
ウクライナ危機で加速する水素エネルギーの導入
と題して、ご略歴、水素エネルギーの導入背景、実際に取り組まれている事業についてご紹介頂きました。
ポスター展示・企業ブースの紹介
同時間帯には別室でポスター発表と企業ブース展示がありました。

企業ブースでは、
株式会社Asian Bridge様
日本電子株式会社様
株式会社Fusic様
には、佐々木から直接企業ブース展示のお声がけさせて頂きました。
当日は株式会社 Asian Bridge 洲崎様とお話しさせて頂きました。明るく物腰柔らかなところは小西社長と重なるところを感じました。
Asian Bridge様にお声がけをしたのは、以前の講演を聞いた学生以外にも、Asian Bridge様の存在を広く知ってほしいと考えたからです。
特に、アプリケーションやサービス開発で社会をどのように変化させる(スポーツバンクの場合は、スポーツ選手のセカンドキャリア問題を解決する、そのことにより、スポーツ選手になる夢を諦めなくてすむ社会をつくる)かは大変参考になると考え、お声がけさせて頂きました。
久留米高専からは機電系専攻の専攻科生に声をかけて、その姿を見てもらいました。
日本電子様には、マテコン学生が持ってきた自分たちで鍛えた試験片の破面観察を楽しませていただきました。エントリーモデルでありながら、小型でポンプの音も静か、振動を少なくするための簡単に試験片を固定できる機構、高精細な電子顕微鏡像、タッチパネルによるスマホと同じピンチイン、ピンチアウト機能。超高速な成分分析(ここには以前高専で講演頂いた塚本様のノウハウも存分に生かされているとのこと)。
高専に限らず大学の先生方、企業の方も必ずSEMがここまで来たか、、、と思える電子顕微鏡を触らせて頂きました。


株式会社Fusic様には、これまで久留米高専の学生はインターンや就職で何人もの学生をお世話になっております。
佐々木が担任した材料システム工学科の学生がFusic様に就職して以来、そのご縁が続いています。
他高専の学生さんも就職して働かれており、現在はディープラーニングを活用した共同研究にも積極的な会社さんです。
材料分野はマテリアルズインフォマティクスと銘打たれているものの、佐々木は「まず、その前に、、、」と実験や数値解析で研究を回すところで済ましてしまいます。
その中にあって、株式会社 Fusic様の取り組みは、佐々木のみならず他の高専、大学の先生の参考になるところもあるかもしれない、また、その具体的な話が機電系専攻の専攻科生には参考になると考え、ご依頼差し上げました。
(教務系サービスも提供されているので、そちらの方が高専は助かるのでは、と思います)
配管探傷ロボットの実演とプレゼンテーション
また、配管探傷ロボコン学生は、自身のロボットの実演とプレゼンテーションをたくさんの聴衆の前で行いました。材料システム工学科では、ロボット組立も、ロボットを動かす回路設計の授業もありません。キットに基づいて学生がしっかり動かせるように作り上げてくれました。(佐々木は本当に場所とキットの提供のみで、ポスターすら手を入れてません。ほんとにすごい学生です。)

11月3日 佐々木の講演と市岡元気先生のサイエンスライブ
11月3日は別府コンベンションセンター横広場にて開催された大分ハイドロエキスポにて、11時から
「水素と材料のおはなし」
をテーマに30分講演させて頂きました。
水素エネルギーに関しては
ほんまに必要なんか?
何に困ってんねん?
どうやって解決するねん?
を柱にお話ししました。
材料に関しては
水素エネルギー活用に材料って必要?
はちゃめちゃに難しい材料はどんな人がつくるの?
材料っておもしろいんか?
を柱に、高専マテリアルコンテストも含めて、お話ししました。



佐々木の講演のあとは、目玉であるYouTubeで科学実験をおもしろく実演されている市岡元気先生のサイエンスライブを見学しました。
1時間、ほんとに圧巻でした。
さすが、プロ。
ネタを選んだ理由とみせる順番、現象の見せ方、音楽の使い方、科学の多様な遊び方を勉強しました。子ども達が楽しく手をあげる仕掛け、水素エネルギーの説明にも視覚的にわかりやすく仕掛けをたくさん、実験器具のおもしろさもわかりやすくたのしく要所要所で説明されました。
子どもだけでなく、大人もたのしいイベントでした。
1時間の間、一瞬も飽きさせることなく、水素エネルギーの使い方を上手に説明してくれました。
市岡元気先生のサイエンスライブを拝見して感じたことは、水素エネルギー社会実現にあたっては、
産業(企業の方々による社会実装)
学協会(高専、大学、研究所による技術開発、研究)
官(国、県、市町村からの支援)
民(市民の理解)
が必要だと言うこと。
その中において、市岡元気先生のサイエンスライブというのは、小学生中学生と「工学に携わらない人々」の理解を得るうえで、とても大事で、貴重な形であると感じました。
多くのフォーラムは、企業さん、学協会、そして官(国、県、市町村)の連携がまずありきで、とても重要です。
この場合、工学やものづくり産業に携わる人々には、水素エネルギーの価値は理解して頂けるのですが、社会実装を見据えた時、小中学生そして「工学に携わらない人々」に水素エネルギーを伝えることが重要であると感じました。
考える前に、まず触れる。
「みんなで水素エネルギーを楽しむ場」として、今後の水素フォーラムがあっても良いと感じました。
ちなみに、市岡元気先生のクイズをいくつか紹介します。
Qコーラがはいったペットボトルを液体窒素に入れたら、どうなるか?
Q水素ガスのシャボン玉に火をつけるとどうなるか?
Q 酸素ガスもいれて火をつけるとどうなるか?Q90°のお湯に液体窒素をいれるとどうなるか?
ぜひ、考えてみてください。
実験の作業自体は非常にシンプルでありながら、とても効果的に科学的な特性を目や耳、触覚で学ぶことができる、体感できる、ものになっています。
最後に、市岡元気先生に
「大変勉強になりました。ありがとうございました。」
とお伝えして、写真を撮らせて頂きました。
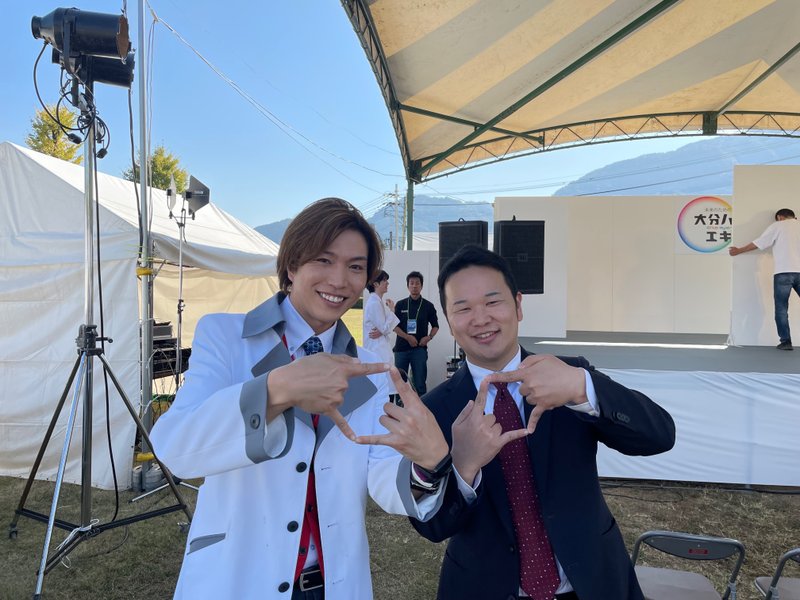
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
