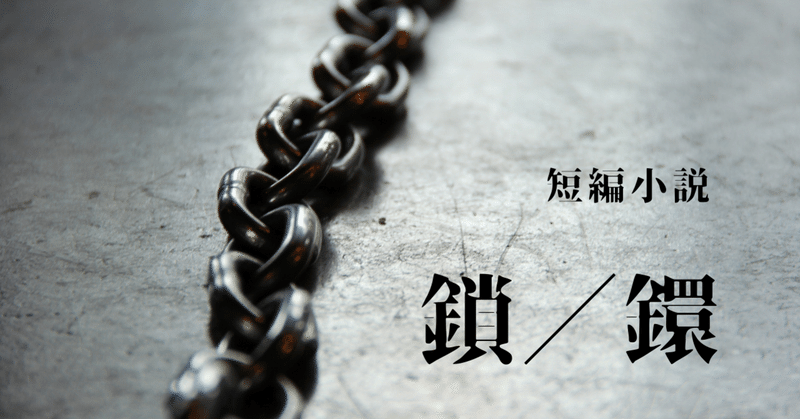
短編小説 『鎖/鐶』
鎖《くさり》を成す鐶《わ》を一つ一つ、素手で外してばらばらにすることなど不可能だし、鎖は鐶が連なっていてこそ有用なものだから、それを分解してしまうだなんて無駄な行為を誰が好き好んでするだろう。けれど、生きるということは、そうして鎖を鐶へと戻していく行為なのだと、あなたはそう考えている。あなたという命の過ごした、その膨大な時間がひしめくこの場所で、たった一人、冷たく重たい金属の一つ一つを取り去り、解《ほど》いていくことなのだ、と。
目の前の鎖は果てしなく長く、先もなければ元もない。ようやく鐶を一つ解いたとしても、そこで鎖は分かたれず、同じように掌にある。
無数の鐶の連なった、その鎖。その鐶の中にはよく見知ったものもあれば、それが自分のものであるかさえ確かではない遠いもの、それどころかまるで覚えのないものすらある。けれど、それでも鎖はあなた自身のもので、あなたもまた、それをよく理解している。
だからこそ、この場所で、あなたはそれに向き合っている。一つ二つ、三つ四つ、解ける鐶は多くはない。それほど人の生は長くない。けれど、その魂は生き死にを繰り返し、人の世を巡りながら鐶を繋ぐ。鐶を解く。
無論、解くばかりが人ではない。知らず、鎖を長くするばかりの者もいれば、振り返り、その長さに絶望するだけの者もいる。それを知りながら手にも触れない者がいる。解きたいと思いながらも術を知らず、途方に暮れる者がいる。それは無駄だと嘯く者がいる。流言に惑い、呑まれるだけの者がいる。
人の思いは様々あれど、だが鎖はあなたのものだ。触れるも触れぬも自由である。しかし、どうあがけど解くことは困難であり、それを思えば、見て見ぬ振りをする楽は何物にも代えがたい。
その鎖とは一体何なのか。あなたは、なぜそんなことをしているのか。静寂の狭間、揺蕩《たゆた》う思考を追うように、あなたは時折手を止める。あなたを過ぎていった幾多の人生。鎖は、その長い時間の中で連なっていったものかもしれない。
だとすれば、それはなぜなのか。何が鐶を成し、鎖としたのか。
それは閉じられた時間より漏れ出るもの――あるいはあなたの過去のその一つ、その日は雨が降っている。
あなたの手のひらに柔らかな頬の感触を残し、幼子は頭から床へ倒れ込んだ。ゴン、という鈍い音。雨音さえ怯んだかのような、一瞬の静寂。その後、幼子は火がついたように泣き出す。騒ぎの大きさに苛立って、あなたは再び彼を打《ぶ》つ。何度も何度も繰り返す。
あなたは乱暴な人間ではなかった。その証となるかどうか、あなたは喧嘩をするどころか、他人を打ったことなど一度もない。いつも目立たず大人しく、目の前にあるものが一つきりなら、必ずそれを他人に譲り、自分は遠慮をするような、あなたはそんな人間だった。
だが、それがどうしたことだ。いま、あなたのその手は幼子を打つ。何度も何度も、掌の痛みにすら耐えながら。それはあなたの幼子だというのに、あの苦しい十月十日、果てには身が裂かれるような痛みに耐えて、その子を産み落としたのだというのに、その辛苦を無に帰すように、あなたは幼子を打ち続ける。
一体、それはなぜなのか。問われても、あなたには分からない。初め、それはあまりに幼子が泣くせいだったかもしれない。抱っこにオムツにおっぱいに、疲れ果てたあなたはほんの軽く、泣き止まない幼子の足を叩いたのかもしれない。つねったのかもしれない。そうするうちに緩やかに激しさを増した感情が、あなたの肉体を操るようになったのかもしれない。そして、そうなってしまえばもう歯止めは効かなかった。
幼子が泣くたび、あなたは彼を打った。そうして更に泣く子をうるさいと打った。黙っていても打った。あなたを恐れ、見上げる目つきが気に入らずに打った。果てには、その子の幸せそうな笑顔にさえ、苛立ちを覚えて打った。
彼の満足そうな顔は、あなたの胸を掻き乱した。『こんなことは間違っている』。なぜそう思うのかは分からなかったが、込み上げる思いのそのままに、あなたは腕を振り下ろした。そうして幼子が無様に倒れて泣けば、安堵が胸に広がった。そう、これがあるべき姿。彼は常にこうあるべきなのだ。内なる声に従って、再び腕を振り上げる。
雨足が強くなる。しかし、その音はあなたの耳には届くことなく、窓ガラスを濡らしている。
そうして、そのときあなたは幼子の命を奪ってしまったのだった。殺そうという気は無かったのだから、それは結果としか言いようがない。『幼子を打てば、死んでしまうかもしれないということくらい分かるだろう』と他人は言い、あなたの気持ちをでっち上げようと必死になるが、例え脳細胞の一つ一つまで調べようとも、そこに無いものは無いのである。
幼子をあるべき姿に留めるべく、あなたはいつものように彼を打った。しかし、とっさに倒れまいとした彼はよろめいて――不運にも石へ頭を打ち付け、そのまま動かなくなってしまった。その少しでも右へ倒れていれば、あるいは踏ん張らずにそのまま倒れていれば、幼子は無事であるはずだった。ということは、彼の命を奪ったのは彼自身の意思ともいえただろう。あなたに抵抗しなければ、彼は生きて一生を終えたはずなのだ。
けれど、あなたの周りの人間たちは、あなたを理解しなかった。「幼子の死」という一つの事実はそのままあなたの「罪」となり、あなたはその後の人生を他人に謗られながら過ごすこととなった。
その、幼子の命を奪った罪。それがあなたが鎖を解く理由か。その生において償いきれなかった罪の代わりに、あなたはいま鎖を解くのか。ここで鎖に向き合うあなたは、あのときのあなたでありながら、しかし決して同じ人間ではなく、幼子の名前も顔もその身に起きたことさえ、その記憶には蘇らない。
それでも厳かに直向きに、あなたは過去の咎《とが》を償うか。「幼子の死」という罪は、それほど重いものなのか。
そのとき不意に激しさを増した雨の中から、鋭い雷鳴が轟いた。天から落ちたその一撃に、あなたはほんの僅か、体を強張らせた。大木を焦がし尽くすような、あるいは地をも貫くような激しい雷鳴は何度も轟き――いや、これは誰かの声だ。耳を覆いたくなるほどの怒鳴り声だ。
それはどこから聞こえてくるのか――そうだ、これもいつかあなたの居た場所。あなたが生きた、いつかの時間。
あるいはあなたの過去のその一つ、そこにはいつも怒声が満ちている。
その父親は、気に食わないことがあるたびに怒鳴り声を上げるのだった。
例えば、背広に埃があったとき。玄関の靴が乱れていたとき。食事の味付けが薄いとき。単に機嫌が悪いとき。雷は落ちる時も場所も選ばず、不意にあなたに降りかかる。彼の子供である、あなたという存在に。あなたにできることは一つだけ――できるだけ父親の機嫌を損ねないよう、息を潜めていることだ。
けれど、あなたはヘマをする。彼の怒りに触れてしまう。瞬く間に暗雲は立ち込め、あなたの頭上で雷鳴は轟く。『おれは、暴力は振るわないぞ』。口答えをすれば両親に殴られ育ったというその父親は、あなたに決して手を出さない。それがたった一つの彼の矜持《きょうじ》だ。だからあなたは打たれはしない、蹴られもしない、けれどその大きな声は、脳味噌をひどく揺さぶる。それが一時間二時間と続くうちに、あなたの頭は真っ白になる。立ちっぱなしの足は感覚をなくし、血流は止まり、全身は震え、直立不動の姿勢のまま、あなたはとうとう倒れてしまう。
果たして父親は怒鳴ることをやめるだろうか。いいや、やめない。彼は殴られても立ち上がった。だというのに、殴られもせずに倒れるあなたは軟弱だとばかりに、声は一層大きくなる。稲妻が何度も体に走る。
そうして何百回、何千回目か、沈みゆく意識の中で、あなたはその心に誓う。子供など決して持つものかと、もし持つことになったとしても、子供を殴ったという祖父母や、怒鳴る父のようには絶対ならない。
そう決意したあなたは、その後どんな大人になったか、それとも大人になどなれなかったか。壊れた心と肉体で、生き延びることは難しい。あなたは刃をその手に握り、自分の胸を刺し抜いた。そうして時間の幕を閉じ、新たな生へと向かったか。
いずれにしても、いま遠のいていく雷鳴は、あなたという魂が相反した二つの立場を内包していていたことを教えていた。打つ者と、怒鳴られる者。あるいは力を振るう者と振るわれる者、暴力というものの両端に、あなたは立ったことがあるのだった。
無論、それらは違う時間、違う場所に収められた記憶であって、ここに在るあなたという存在もまた、直接知ることのないものだ。けれど、かつてのその時間があなたという唯一無二の存在に集約していたことに変わりはない。
しかし、それならなぜ、あなたは幼子を打ったのか。あの父親はあなたに怒鳴り、あなたはそれを己に戒めるばかりか、子供を持つまいとまで強く誓った。そもそも両親に殴られたというあの父親も、暴力を振るうまいと誓いながら、結果的にはあなたを壊した。それは肉体を傷つけはしない、けれど暴力であったことには変わりがない。その暴力というものは、どうしてあなたに関わりを持つこととなったのだろう。
それはこの場所この時間、あなたの掌に閉じる冷たい鐶。その鈍い色を見つめれば、水底から浮かび上がるように、ある言葉が姿を見せる。暴力の連鎖。それは、あなたは打たれた記憶から打ったのであり、怒鳴られた記憶から怒鳴ったのである――つまりは、あなたは誰かに暴力を受けたからこそ、誰かに暴力を振るったのだという、諦めと悟りの言葉である。
暴力は連鎖する。親から子へ、子からその子へ受け継がれていく。それは例えば病原菌のようなもので、一度触れてしまえばあなたは簡単に蝕まれ、そうなれば、治ることはおろか、症状を抑え込むことすら困難となる。
泣く幼子を、あなたが打ったのはそのためか。彼をあやすでも放っておくでも、はたまた誰かに任せるでもなく、何度も打ったのはそのせいなのか。あの不機嫌な父親があなたを怒鳴り、追い詰めたのもそのせいか。暴力という病に感染していたせいなのか。
しかし、それが病だという比喩をしても、実際に暴力を媒介する菌はなく、それは物質的な病ではない。ゆえに、それを嘆じても、現実は何も変わらない。
『あなたはなぜ、いつかの幼子を打ったのか』という問いの答えが『いつかの父親があなたを怒鳴ったから』であるというのは確かだろう。あの父親もまた、彼の両親に殴られたからこそ、あなたを気絶するまで怒鳴り続けたのだ。暴力は連鎖する。言葉の通り、それは振るわれた者に受け継がれていく。
しかし、この問答は一見成り立っているようで、実はまるで成立していない。なぜ父親の暴力が、幼子にそれを振るう理由になるのか。暴力の連鎖という言葉は、その問いに答えていない。もしもそれが復讐だというのなら、その感情は幼子に向くはずがないし、あの父親もまた、その怒りをぶつける先はあなたではなく、彼を打った人間であるはずだ。だというのに、暴力の向く先は、いつでも別の人間だ。
それは、あなたの掌の鎖も同じだ。その目の前の鐶を連ねた鎖が連鎖であると、もしそう誰かが言うのならば、あなたが解かねばならない鐶は死んだ幼子の分のみであり、その残りを解くべきは父親か、誰かその他の――あなた以外の人間であるべきではないのか。
しかし、あなたは先の見えないこの長い鎖に、たった一人、向き合い続ける。
なぜなら、『暴力の連鎖』。それは、あなたの辿り着いた答えではない。その先には何もないような、まるで行き止まりのように見えるその言葉は、未だ思考の過程であり、その先にあるものこそが、あなたが鎖を解く理由なのだ。
過去から轟く雷鳴は、既に遠ざかりつつあり、その代わりであるかのように、別の遠い時間から、何もかもを飲み込むような沈黙が漏れ出してくる。
あるいはあなたの過去のその一つ、その罅の入った時間から染み出した冷たいものは、あなたの影に手を伸ばす。
体温を吸い尽くすような石の床、その上にあなたは座している。一体いつからそうしているのか、朦朧として定かではない。ただはっきりと理解しているのは、ここがあなたにふさわしい場所ではないということ。否、それがあなたでなかったとしても、罪人が死を待つこの場所が、他の誰に似合うというのだろう。
人を殺したという罪で、これからあなたは殺される。一と釣り合うものは、一である。つまり、奪われた彼女の命と釣り合うのは、奪われるあなたの命なのだ――と彼らは言った。いや、彼らが直接あなたにそう言ったわけではないが、それが彼らの考えだった。けれど、殺されてしまった彼女はあなたを殺すことができない。だから、彼女の代わりに彼らがあなたの命を奪うのだという。
殺しの代行。彼らの理屈がそれならば、あなたには納得がいかないことがある。
それはあなたの生まれる前のことだった。彼女の先祖とあなたの先祖は土地を巡って殺し合いをした。結果は、彼女の先祖の勝利だった。あなたの先祖は殺されたばかりか、忌み嫌われて追いやられ、祖母は今際の際まで『帰りたい』と涙を流した。
だから、もしも殺人の代行が許されるというのなら、あなたは殺された先祖の代わりにその権利を行使し、彼らの子孫を――彼女を殺したということにはならないだろうか。無論、彼女だけでは釣り合わない。あなたはもっとたくさん殺すべきところを、彼女一人で収めたのだ。だとすれば、彼らに咎め立てされる理由など、これっぽっちもないだろう。
鉄の柵が軋《きし》んで開く。そのときが来たとあなたに告げる。銀の刃が落ちるその瞬間まで、あなたは虚空を睨み続ける。
あなたの言い分は受け入れられず、奪った命との釣り合いを取るため、あなたは彼らに命を奪われた。殺された先祖たちの命を、彼らは保証しなかった。それは建前上であれ、あなたと彼らが一つになる前の話だった。過去は過去、今は今。あなたがあなたであることを彼女たちがどんなに蔑もうと、あなたたちはいまや一つであり、それ以前の歴史はないこととされたのだ。
しかし、それは彼らの言。あなたは未だ覚えている。否、思い知らされている。彼女とあなたの違いによって、彼女たちがあなたに向ける蔑むような眼差しによって。だからあなたもまた、あなたの歴史を思い知らせた。一つの命に釣り合うのは、ただ一つの命だけ。その台詞に則るのなら、彼女たちこそあなたに殺されねばならないだろう。そして、あなたは甘んじて彼女の血を引く誰かに殺され、またその誰かをあなたの子孫は殺し、またその子孫は彼女の子孫に殺され――それはまさに連なる鐶、連鎖と呼ぶにふさわしい。
けれど、彼らは力で理屈を断った。彼らは彼女の代わりにあなたを殺すが、彼らを殺す者は現れない。なぜなら、あなたを殺した彼らというのは、一人の人間ではないからだ。彼らという存在そのものが、肉体や命を持つ、いわゆる人間ではなかった。しかしそうでありながら、彼らは声を持ち、肉体を持った個人を操る。あなたに何の恨みもないどころか、関係さえない人間に、あなたの首を切り落とさせる力を持っている。
一体、彼らは何者か。種を明かせば、それは肉体を持たない、たくさんの意識――ある幻想を共有する意識の集合体である。例えば、肌の色が同じである、目の色が同じである、祖先が同じである、あるいは言葉や食べ物や生活様式が同じであるから私たちは同じであるという、共同幻想を持った巨大な集団。
それが幻想であるというのは、彼らは同じではないからである。血の繋がった家族でさえ、個人の違いは存在する。だというのに、彼らはその巨大な集団を『同じである』と定義する。その中には、奪った者と奪われた者、あるいは奪われた者と奪った者――彼女やあなたでさえ含まれているというのに。そう、あなたを殺した彼らとは、あなた自身をも含んでいたのだ。
それなら、なぜあなたを殺した彼らの意思に、あなたの意思が反映されていないのか。それは集団となり、彼らとなった人々は、個人としての自我をなくしてしまうからだ。彼らはあなたを含んでいるが、あなたは決して彼らではない。
個人という肉体を離れ、彼らとなった人々は、その利益のためならば人殺しも厭わない。本来ならば個人が感じることのない憎しみを、彼らは大きく掻き立てる。誰かはあなたを殺すべきではないと言っても、それは一人の意見である。一人の意見は殺される。
彼らの使うこの力。これもまた暴力だった。一人二人ならばともかくも、人間が集団で生きるには規則が必要であり、その規則を破れば罰がある。いつかの時間、あなたが幼子を打ったように、父親があなたを怒鳴ったように、今度は彼らがあなたに罰を与える。
となると、こういうことか。彼らはあなたに罰を与えてもよく、父親はあなたを怒鳴り続けてもよく――あなたもまた、幼子を打ってもよいのだと、そういうことにはなるまいか。彼らが振るっていい暴力を、あなたは振るうことが許されない――それも彼らの暴力的な罰によって許されないというのは、彼らにとって都合の良すぎる話である。
彼らが暴力を認めるならば、あなたもまた暴力を振るっていいのである。もしも、その暴力を止めようとする力があるのなら、あなたは暴力にて、その力に抗えばいい。暴力には暴力を。彼らが繋いだ、ひときわ大きな鐶に抗うためには、特大の暴力が必要である。
この世の中を支配するのは、なんと単純な理屈だろう。いつかのあなたもそう気づき、その拳を振り上げた。
あるいはあなたの過去の一つ、そこには怒りの炎が見える。いや、これは本当にあなたの過去か。何十、いや何千何万という人々の怒りが炎の中で燃えている。悲鳴と叫喚と絶叫の中で、あなたの血潮は燃えたぎっている。
大通りを大挙して行く人々に混じり、あなたは声を張り上げている。言葉にするのは、差別、不平等、平和に共生、あなたたちの信じる思想。それらを世の中に通すため、あなたたちは行進している。この大通りを埋め尽くす、これほどたくさんの人間が賛同しているのだ、信じているのだ、それをあなたたち以外の人間に知らしめるため、あなたたちは声を張り上げる。
正義の横断幕をあなたは掲げる。そのとき、あなたたちを抑圧していた彼ら――その象徴である旗を燃やし、彼らを模した人形を串刺しに掲げ、彼らに与する家々のガラスを割り、この行進に参加しない人間を怒鳴りつけ、あなたたちは行進を続ける。
彼らはあなたたちを抑圧した。暴力でその行動を制限した。若者たちを暴力の舞台――戦争へ送った。貧しい暮らしを強いた。悲しませた。搾取した。あなたがあなたらしく生きられる環境をつくらなかった。
だから、あなたたちは怒っている。その思いの丈をぶちまけている。あなたたちは被害者である。加害者は彼らである。その彼らの中に、あなたたちの存在が含まれているとしても。
行進の先頭で、悲鳴が上がった。黒い煙が空を汚した。あなたたちを制圧すべく、彼らの部隊が出動したのだ。『彼らを潰せ!』。一人の声をきっかけに、あなたはさらに大声を上げる。周りの人間もそれに倣う。全体が一つになったような、この力。この力こそが、あなたたちの正義。
その正義が過ぎ去った後、大通りはがらんとしている。割れたガラスの隙間から、息を殺した誰かが覗く。忘れ去られた燃えかすが、風に吹かれて燻っている。
暴力で虐げられた弱者たちが、固めた拳を振り上げる――その時代、あなたたちはそれを民主主義と呼びならわした。力を持たない民衆が、彼らに抗うための術。国と呼ばれた彼らの間違いを正すため、あるいはあなたたちの声を届けるための行動である。しかし、やはりその手段は暴力だった。それは確かにそうだった。
それは違うと、もし、そうではないというのなら、なぜあなたたちは集団をつくり、行進するのか。叫び、騒ぎ、音を鳴らし、大きな通りを歩いていくのか。それは知らしめるためだろう。そうしてあるいは脅すためだ。これだけの人間がその思想を良しとしていて、だというのになぜ、彼らはそれを無視するのか。若しくは、なぜこの正義の行進に参加しない人間がいるのか。少しでもあなた方に脳味噌があるのなら、この行進に加わっているはずではないか、と。
もちろん、民主主義という仕組みの理想を語れば、それは数の問題では決してない。けれど、実際のところはどうだ。それがどんな思想であれど、数の多い方の意見が通る。声の大きさが方向を決める。それなら、どんな手段を使ってでも――例え心地良いばかりの嘘偽りを言ってでも、数を集めるが民主主義の最適解だ。そうして声が大きくなればなるほど、数で圧倒すればするほど、彼らも無視ができなくなる。あなたたちはそうやって、彼らの暴力に対抗する。
あなたたちは暴力によって押さえつけられ、それを嫌い、否定しながら、だというのに誰よりも暴力という力を信じている。それがこの世で一番確実で有効なものであり、あなたを救うただ一つの手段であるということを、固く固く信じている。
なぜなら、この世界を成り立たせているのは暴力であることを、あなたは過去から膨大な時間をかけ、思い知らされているからだ。
あるいはあなたの生きるその時代、世界は暴力に支配されている。
共同幻想で支配された集団はそれぞれの軍隊を持ち、もしも攻撃されたなら、報復の準備は整っていると示すことで、危うい均衡を保っている。また、その中でも巨大な幾つかの集団は、核兵器というさらに巨大な暴力を有し、周囲に睨みを効かせている。俺たちに逆らったらどうなるか、分かってるんだろうな――その力はどれほどの不平等、不均衡でさえも平等であると言い張ることのできる強さを誇る。弱者からの搾取を可能にする。
そうして互いを脅し合い――あるいは一方的に脅し、保たれる世界を、あなたは平和と呼んでいる。それを有難がり、感謝し、虐げられる集団から目を背け、あなたは強い集団の中の一人として生きている。
暴力で成り立つ世界は、根底から暴力を肯定し、それを娯楽として楽しむことさえ可能にする。例えばそれはスポーツの世界。あなたは贔屓のチームの勝利を願い、相手チームを罵ることで、快楽をその身に得るだろう。例えばそれは物語の世界。映画にドラマ、アニメに小説、そこには必ず『正義』があって、彼らは『悪』を倒すため、暴力を解決策として用いるだろう。戦争反対に核兵器根絶、環境保護に動物愛護、何を訴えるにしても、あなたは暴力を使うのだろう。その集団に加わらない人々を、怒鳴り、蔑み、馬鹿にし、時には制裁を加え、あなたの思想を誰かに強制するのだろう。
あなたはしかし、その手にあるものが暴力であることに気づいていない。それどころか、それはあなたが忌み嫌うものの一つである。だからこそ、あなたはあからさまな暴力に顔をしかめる。ああ、また小さな子供が暴力によって死んだらしい。何かあるとすぐに怒鳴る人が増えたらしい。死刑が執行されたらしい。どこかとても遠い国で戦争が起きたらしい。それに反対している人々が通りで暴動を起こしたらしい――。
解けない鎖にしばし手を止め、あなたは小さく息をつく。冷たい鐶。鈍色のそれ。いつか幼子を殺し、あなたを殺し、彼女を、彼を、先祖を、大勢のあなたと同じ人々を殺し、いまも連なり続ける暴力の鎖。あなたの掌にあるその鎖は、世界に繋がれているのだった。
一体、その最初の鐶は何だろう。人間が手にした、最初の暴力は何だろう。始めに暴力があったからこそ――あなたは虐げられたからこそ、他の誰かを虐げた。虐げられた経験が、あなたに暴力を教えたからこそ、暴力でそれを解決した。そして、今度はあなたが暴力を振るった相手に教えたのだ。暴力こそ、人間が手にするべき解決策であるのだ、と。
そうして鐶は繋がった。一つ二つ、三つ四つ、繋がり続けて鎖となった。最早、簡単には辿れぬほど、長い長い鎖となった。その長い鎖が、いまも弱きを苦しめている。泣くことしかできない幼子を、声を届ける術を知らない人々を。
あなたはそれをひどいことだと嘆きながら、己のその手に暴力を掴んで離さない。
なぜなら、あなたはよく知っている。
声を上げねば虐げられるだけだということを。数で圧倒せねば無視されるだけだということを。時には拳を振り上げ、刃で脅さなければ、あなたは征服されるだけだということを。あなたは叫び、しかしその声は虚しくも、暴力によって封じられる。
そして、暴力はあなたを粉々にした。
幼子だったあなたは親に打たれ、仲間にはいじめられた。助けを求める声は無視をされ、存在をないがしろにされ、意見を言えば一笑に付され、何も言わなければ馬鹿にされた。謂れのないやっかみや憶測で蔑まれ、勝手が分からず呆れられ怒鳴られ、ささやかな抵抗は悉く潰され、どこを向いても非難された。
だから、あなたは暴力で誰かを粉々にした。
他人を馬鹿にし、差別し、罵り、生きる価値がない人間を皆殺しにした。他人の罪を探し、批判し、喧伝し、攻撃の的とした。その数を知らしめる行進をし、気に入らない者をいじめ、または殺し、牢に閉じ込め、怒鳴り散らし、幼子をその手で打って世界の理を教え込んだ。
振るい、振るわれ、また振るい――あなただけでは抱えきれないほどの過去の記憶が、静寂の中を姦しく行き交う。これほどの過去があなたにはあるのか、それともこれは他の誰かの物語も混じっているのか。これほど長い鎖を成すための鐶は、あなただけが生み出したのか。否、そうではないだろう。
冷たい一つ一つの鐶は、あなたが見た全ての記憶。あなたが聞いた悲鳴の記憶。あなたの属した集団の記憶。国の、その歴史の記憶。血族の記憶。あなたはあなたという個人でありながら、同時にたくさんの記憶を背負い、誰かが受けた痛みもまた、あなたの鐶となり鎖となり、あなたの足を絡めとる。人々は正義と名付けた暴力を振るい、その暴力を止めようと試みる。その結果、より鐶を太く、解けなくした鎖を引き合う。その耳障りな音は消えることなく、あなたの鼓膜に響き続ける。
もし、あなたが鎖に向き合うことを辞めたなら、あなたの口からは叫びが溢れ、その不快な音は消えるだろう。あなたもその鎖の音を響かせる側になるだろう。けれど、あなたはそうしない。そうしないと心に決めた。
悲しみはもう十分だった。痛みももう、必要なかった。暴力の記憶は、あなたという存在を満たし、これ以上は溢れ出してしまいそうだった。だからそうなる前に、あなたは鎖を解こうと決め、その最後の鐶に恐る恐る手を伸ばした。指の動きは緩慢に、けれど次第に確かになった。あなたの中に確信は芽生え、薄皮を剥ぐように少しずつ、あなたの存在は輪郭を増した。
いま、世界はやり方を改めるべきだった。あなたの幼子を打つなというのなら、誰かの命を奪うのはいけないことだと諭すのならば。それを教えるための世界が、暴力を振るうことは許されない。その首筋に刃を当てながら、人を殺してはいけないと説くことのおかしさを、どうして世界は許容するのか。暴力を垂れ流し続けるのか。
それに気づき、変えない限り、鐶は連なる。連鎖は続く。止まることなく、繋がり続ける。
いま、静けさが満ちるこの場所で、あなたは鎖と向かい合う。そして、それを鐶へと戻す。あなたのものであり、あなたのものではない鎖を、膨大な数の鐶を、終わりの知れぬその行為を、あなたは黙々と続けている。一つ二つ、三つ四つ、解ける鐶は多くはない。それほど人の生は長くない。けれど、その魂は生き死にを繰り返し、人の世を巡りながら鐶を繋ぐ。鐶を解く。
無論、解くばかりが人ではない。知らず、鎖を長くするばかりの者もいれば、振り返り、その長さに絶望するだけの者もいる。それを知りながら手にも触れない者がいる。解きたいと思いながらも術を知らず、途方に暮れる者がいる。それは無駄だと嘯く者がいる。流言に惑い、呑まれるだけの者がいる。
人の思いは様々あれど、だが鎖はあなたのものだ。触れるも触れぬも自由である。しかし、どうあがけど解くことは困難であり、それを思えば、見て見ぬ振りをする楽は何物にも代えがたい。
けれど、あなたは鎖を解く。あなたという存在がここにある限り、鎖がそこにある限り。
そうして鐶に戻った鎖は、まるで夜空の星のように、人の行く先を照らすだろう。世界を静かに導くだろう。例え、地上の光に興じる人々が、空を見上げることがなくとも。そこに夜空があることも知らず、あなたの光を見上げる人間が、ただの一人もいないとしても。
あなたはその鎖を解く。たった一人で解き続ける。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
