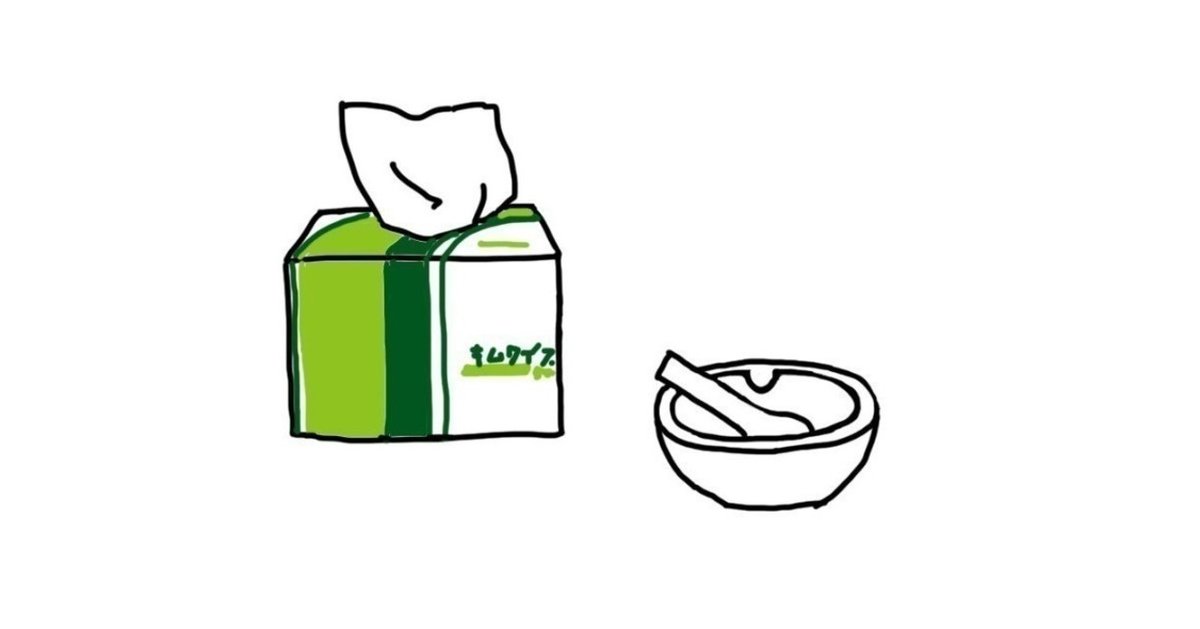
博士の採用
博士号取得者の採用が増えているとのこと。
個人的にはやっときましたか。。。
という印象です。
まずは、その背景となる流れを本文より引用したいと思います。
文部科学省は1996年度から2000年度に博士号を取得した研究者(ポストドクター)を1万人創出する「ポストドクター等1万人支援計画」を打ち出した。2000年度には目標を達成し、05年度には1万5000人を突破した。ところが、大学の若手研究者のポストは減り、企業も博士の採用に消極的なことから就職できないポスドクが増え、問題になった。文科省は解決に向け、06年から博士人材を大学や公的研究機関だけでなく、企業などへの就職を支援する政策を打ち出した。
私自身はこの流れの後の2004年に免疫学の分野で博士号を取得しました。
修士課程を終えて、一旦就職した経緯がありますが、その就職活動も結構大変でした。時は、就職氷河期と呼ばれる時代でしたから。
私の場合は、
就職するもやはり研究がしたく、1年を待たずして退社し、
博士課程に入り直しました。
その当時でも、修士から博士に進む人の割合は1割以下だったと思います。その割合が少ない大きな理由は、
この記事にあるように博士号取得後の企業就職の道がほぼないことでした。
その頃のキャリアパスとしては、
博士号をとった場合はそのまま研究を続け、
アカデミアでのポストを追求するというのはほぼ一般的でした。
ですので、
そのころは産業界は博士号取得者を望んでいなかったような印象です。
ですが、企業での基礎研究の縮小が進み、
自前で研究を進める社内インフラがボロボロになったので、
今になってやっと博士号取得者のポテンシャルを利用しようとしている
のだと思います。
産業界のニーズに対応しようと、
博士人材の育成強化に動いている大学もある。
大学側からのこの上記の反応については、賛否両論あるのかなと思います。大学では一昔前のような自由な研究というのが色々な理由に実施しにくい。なので、企業とパートナリングが進めば研究を進められますし、
企業側も研究の一部を任せられるのですがから、
時代的な背景によって関係性がより近くなっているのだと思います。
企業での博士号取得者の就職率が上がるということは、
アカデミアでの研究を支える研究者が減るということなので、
それはそれで日本の研究力の低下に繋がるかもしれません。
ですが、多様なキャリアパスという観点からは良いことだと思っています。
企業は博士号取得者の獲得に向けて、企業での研究の魅力について訴求し、それが功を奏しているわけですから、それは良い取り組みだと思います。
一方で、大学などのアカデミアにおいても、企業に負けない魅力的な研究環境や研究経験を提供し、アカデミアで働くことの素晴らしさをもっとアピールしても良いと思っています。これからこうした研究人材の争奪戦が大学と企業においても激しくなるのかもしれません。
産業の発展の基礎には科学研究の成果があるわけで、良いバランスで進めてほしいなと思います。まあ、サイエンスという視点から見たら、産業界とかアカデミアといった括りももう一昔前の考え方なのかもしれません。。。
ちなみに何ですが、これまでの私のキャリアパスを簡単に書きます。
修士課程修了
→理科学機器メーカーに就職(正社員)
→博士課程に再入学/博士号取得
→米国留学(NCIでポスドク)
→産総研(ポスドク)
→国内製薬企業で基礎研究(正社員)
→外資系企業でライフサイエンス関連のコンサルタント(現職)
私のような、こんな曲がりくねった紆余曲折のキャリアの道もあります。
キャリアの道は一本だけではないので、
色々と世の中を見渡しても大丈夫かなとは思っています。
この記事を読んでいただいたみなさまへ 本当にありがとうございます! 感想とか教えて貰えると嬉しいです(^-^)
