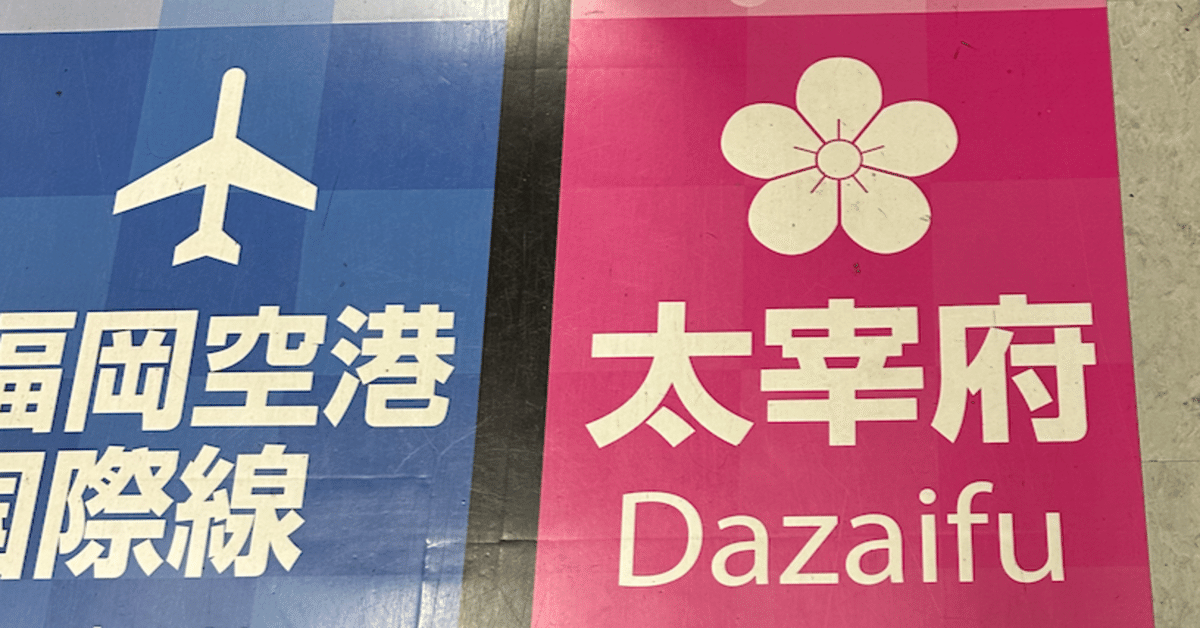
いったいどこまでリスキリングすれば良いんですか???
みなさーん、リスキリングしてますか?アンラーンしてますか?勉強、学問、学習、様々な言い方がありますが、人生100年時代では常に学び続ける必要があるそうです。大変だこりゃ!!!
今回は「リスキリング」をキッカケに、「個人が獲得するスキル」と「チームに必要なスキル」について考えてみたいと思います。
リスキリング界隈が盛り上がっています。
なぜごちゃまぜにして語ってしまったのか。。。
サイボウズ社内には学び直しの制度があります。学び続けやすい環境です。
kintoneのスキルを公式に証明する「kintone認定資格」もあります。kintoneを活用したい方にオススメです。
さらに経産省からは「DX推進スキル標準」というものが公開されています。
こちらが策定された背景はこちら。
「DXを推進する人材の役割や習得すべき知識・スキルを示し、それらを育成の仕組みに結び付けることで、リスキリングの促進、実践的な学びの場の創出、能力・スキルの見える化を実現するために策定しました。 」
次から次へと新しいスキルが定義され、学ばなければいけない!成長しなければいけない!さぁ!さぁ!!さぁ!!!と言われ続けているような気がします。。。
私たち、いったいどこまでリスキリングすれば良いんですか???
個人的には学ぶことは好きな方だと思います。若いときは資格試験も受けましたし、本を読んで新しい発見をするのも好きです。しかし、「終わりの見えない成長しろ圧力」「〇〇するためには勉強が必要だという圧力」による学びはやはりしんどいです。。。
勉強しても自分のものにできなかったらどうしよう。。。?
提示されたスキルや資格を身につけたら本当に役に立つのかな。。。?
一番費用対効果の大きなスキルってどれだろう。。。?
という不安や打算も頭をよぎります。。。「個人が獲得するスキル」にゴールはあるのでしょうか?
チームに必要なスキルってなんだろう
一方で「チームに必要なスキル」ってあんまり話題に上がらないなと思いました。
チームに必要なスキルを考えるにあたっては、
自分のチームには今どんなスキルが存在するのか?
誰にどのスキルを習得してもらえば良いのだろうか?
スキルを身に着けてもらうことでどんな効果が期待できるのか?
と言う疑問が浮かびます。
ちなみに前述の「DX推進スキル標準」にはこのような記載があります。
なお、「デジタルスキル標準」で扱う知識やスキルは、共通的な指標として転用がしやすく、かつ、内容理解において特定の産業や職種に関する知識を問わないことを狙い、可能な限り汎用性を持たせた表現としています。そのため、個々の企業・組織への適用にあたっては、各企業・組織の属する産業や自らの事業の方向性に合わせた具体化が求められることに留意する必要があります。
そうなんです、DX推進スキル標準では(当たり前ですが)「可能な限り汎用性をもたせた表現」になっています。つまり「自分のチームに必要なスキルは、自分たちで考える必要がある!」ということです!
このことに気づかせてもらったのはこちらのnoteです。ありがとうございます!
では、「個人が獲得すべきスキル」と「チームに必要なスキル」をどう設定する?
ここからは「kintoneを使った業務改善」に話のスコープを絞ってみたいと思います。
サイボウズでは、2018年にkintoneを使った業務改善をするためのスキルを証明するツールとしてkintone認定資格を作りました。
kintone認定資格の立ち上げ経緯や、その時の想いはこちらのnoteに書きました。
kintoneを使った業務改善のスキルがあり、業務改善に取り組んで成果を出せる人が増え、その方々が世の中できちんと評価される仕組みとしてのkintone認定資格をつくりたい。業務改善の新しい価値基準・価値のモノサシになりたいと思っています。

2023年でkintone認定資格は丸5年となりました!🎉🎉🎉
おかげさまでkintoneで業務改善に関わる人が「個人で獲得すべきスキル」を定義し、それを証明するツールとして成長することができました。ありがとうございます!
しかし、それだけではkintone認定資格のビジョン「kintone人材市場の健全な発展に貢献」を実現するには、片手落ちなのではないかと気づきました。
「チームに必要なスキル」を定義する
認定資格は、それを取得すること自体は目標であっても目的ではないはずです。目的は「チームの業務改善をすすめる」であったり「自分の市場価値を高め、より面白い仕事に就くため」でしょう。その観点で考えると「個人が獲得すべきスキル」がどこで求められているのか?どのように活かせるか?が見える化されると良さそうです。
つまり、「kintone人材市場の健全な発展に貢献」するためには、「個人が獲得すべきスキル」と「チームに必要なスキル」が明確になっており、かつそのスキルが同じモノサシで定義されていることが必要です!
しかし、現時点でkintone認定資格をモノサシとして「チームで業務改善を進めるために必要なスキルマップ」は提供できていません。。。

この図の左側「チームで業務改善を進めるために必要なスキルマップ」があれば、チームとしては規模や状況に合わせて「チームで必要なスキル」を明確にすることができます。
また、チームに属する個人としては自分の役割や得意領域に合わせて「自分が獲得すべきスキル」が明確にすることができ、安心してスキルアップ・人材育成・業務改善に取り組むことができるでしょう。
そしてその「チームで必要なスキル」と「個人が獲得すべきスキル」が共通のモノサシとして定義されていることが重要です。
ちなみに前述のDX推進スキル標準も、「個人が獲得すべきスキル」は明確になっているものの「組織でDXをすすめるために必要なスキル」が明確になっていないという、同じ構図になっているのではないでしょうか?

「スキルマップ」のイメージ
ここで「チームで業務改善を進めるために必要なスキルマップ」のイメージについてまだまだ倉林の頭の中の構想ではありますが簡単にご紹介します。
kintoneを活用するチームは本当に多種多様で、そこに関わる人数やスキルの有無・高低、チームメンバーの社内・社外の比率、kintoneの活用年数などはチームによって全く異なります。そのチームごとに個別のスキルマップを準備するのは現実的ではないですし、チームの状況が変わった時に必要なスキルに過不足が生じたり、必要なスキルが分からなくなってしまう、という可能性があります。
そこで、kintone SIGNPOSTのように「ガイドライン」として提供するのが良いと考えています。

「固定的なスキルマップ」ではなく「スキルマップのガイドライン」として提供することで、ご自身のチームの状況に合わせて「チームに必要なスキル」を自ら考えることができます。
また、チームメンバーは「チームに必要なスキル」を認識し、同じモノサシで「個人として獲得すべきスキル」を設定することができます。そうすることでリスキリングの目標に対して自分なりの納得感を持って取り組むことができるのではないでしょうか。
チームも個人も成長する
この「スキルマップのガイドライン」の特徴として「チーム・個人の成長」という観点も織り込みたいと考えています。
kintone認定資格やDX推進スキル標準に定義されているスキルはあくまでも「ある時点のスキル断面」です。その表現自体が悪いわけではないのですが、「どんな人がそのスキルを目指せるのか?」「自分の現在スキルからどのようにそのスキルを目指せるのか?」という「チーム・個人の成長」をフローとしてガイドラインに織り込むことができれば、学びを止めてしまったり、逆に背伸びしすぎて学びが辛くなってしまうこともなく、継続的にリスキリングすることができると思います。
フィードバック募集!
ここまで書いた内容はまだまだDRAFTの構想段階の草案の下書きレベルです!😅
ぜひ「学び」に関して皆さんの課題感やフィードバックをいただけたら嬉しいです!
(2023.02.17 追記)
併せて読んで欲しい続編はこちら
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
