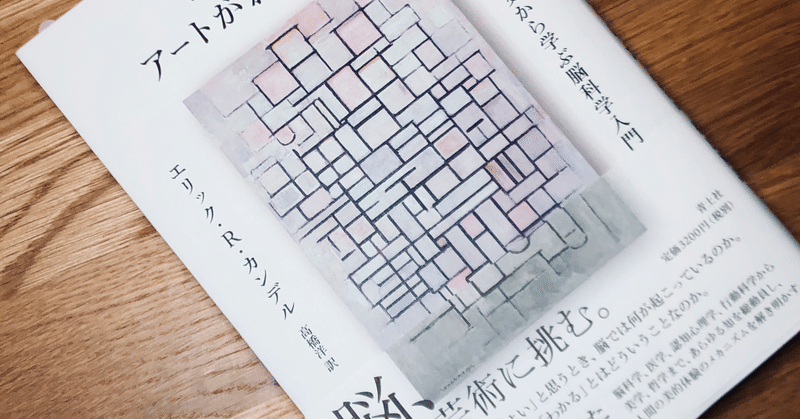
還元主義は使えるかも 『なぜ脳はアートがわかるのか』
読んだ本:
なぜ脳はアートがわかるのか 現代美術史から学ぶ脳科学入門
エリック・R・カンデル
Reductionism in Art and Science Bridge the Two Culture
還元主義の本でした
タイトルに惹かれて買ってしまった。建築学生だった頃は好奇心とかっこつけでよく手に取ったけど、近年は芸術関係の本を読むことはめっきり減ってしまった。
入門となっている通りで、美術や脳科学に関心ある人には新鮮さは少ないかもしれない。でもこの2つ分野を橋渡しする書籍は珍しいし、ぼくは楽しめた。邦題は「現代美術史」だけれど、原題には「Reductionism in Art」つまり「芸術における還元主義」になる。邦題に偽りあり、扱う領域は狭いじゃないか!とも思ったけれど、読了する頃には還元主義の可能性に思い巡らせた。
ひと言でいうと、抽象絵画の還元主義は脳が活発な状態を生む、という話だ。具象絵画はリアルで網膜から取得された像を大きく変えずに認識することができる。もちろん、宗教画などは背景を読み取らなければならないけど、キャンバスの表面においては視覚を頼りにして絵画を理解する。
脳が理解する時に2つの処理が存在する。視覚や聴覚などを通ってくるボトムアップ処理、そして蓄積された記憶や経験が作用するトップダウン処理だ。これらが並行、相補、創発しながら状況を理解する。ザックリとした言い方をすると、具象絵画はその輪郭や色から、具体的にボトムアップ処理をしてく。抽象的な還元主義はボトムアップ処理に加え、過去の学習や知識がトップダウン処理され双方のイメージをかさねながら絵画の像を理解する。この双方処理が脳を活発にする。
トップダウン処理と還元主義
本書は、いろいろな画家が出ているけれど、ニューヨークの5名をメインの案内人として還元主義の可能性を示す。まずモンドリアンがブロード・ウェイ・ブギウギに代表される線と色に還元した。次に、線に還元したウィルム・デ・クーニングとジャクソン・ポロック、色に還元したのがマーク・ロスコとモーリス・ルイスだ。
ぼくなりに線引き直すと、「感情や記憶」に対し還元主義で挑んだデ・クーニングとロスコ、「絵画の概念」を超えるために還元していったポロックとルイスとなると思う。
まずデ・クーニングは線、ロスコは色彩に還元した。線や色に絞りながら、トップダウンを通じて感情や記憶を想起させる試みをした。もう一方の還元では、美術史的なものだ。ポロックは描くことの定義を変え、描く対象より「描く行為」を重視した。イーゼルからキャンパスを外し床に置いたのも新しかった。ルイスは、意味を問い直した。具象を書きながらも、周到に意味を不在にしたのだった。
著者のカンデルは一番伝えたかったのはデ・クーニングとロスコの還元主義だったと思う。
新しきものの同化、すなわちイメージの創造的な再構築の一環としてのトップダウン処理の動員が、本質的に鑑賞者に甲斐をもたらす理由は、一般にそれによって創造的な自己が刺激され、ある種の抽象芸術作品を前にしてポジティブな経験をもたらせるからです。
還元主義で何ができるか
還元主義はどんな方法なのだろう。どうしたら日々のコミュニケーション、アイデアを出す方法のヒントとなるだろうか。
企業のビジョンや商品や企画のコンセプトにも活かせるかもしれない。ひと言で表す、3点に絞って説明する、ブランドのロゴをつくる。これらは還元がうまくいっていないと伝わらない。還元で大切なのは相手の想像力に託すことだと思う。デ・クーニングが描いたように、単純化した要素で手渡し、受け手の脳内で広がっていく。イメージの濃縮果汁還元とでも言えようか。
そのためにはどう還元するかが大切だ。絵画の例が示してくれたのは、具体的ではダメということだ。言葉なら正確すぎるもの、たとえば定義や数値は好ましくない。イメージの余白を残ししながら、かつ丁寧なコミュニケーションをするということだ。丁寧とは、期待しつつあとは受け手に託すとでも言えば良いだろうか。理解の仕方を丸投げしてもダメだし、規定してもダメ。その頃合いは鍛錬が必要そうだ。
とはいえ、還元主義がメインであったけど、他のアートからもヒントになることはありそうだ。美術史の背景のウンチクも面白いけど、考え方や方法を汲み取れるともっと楽しめそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
