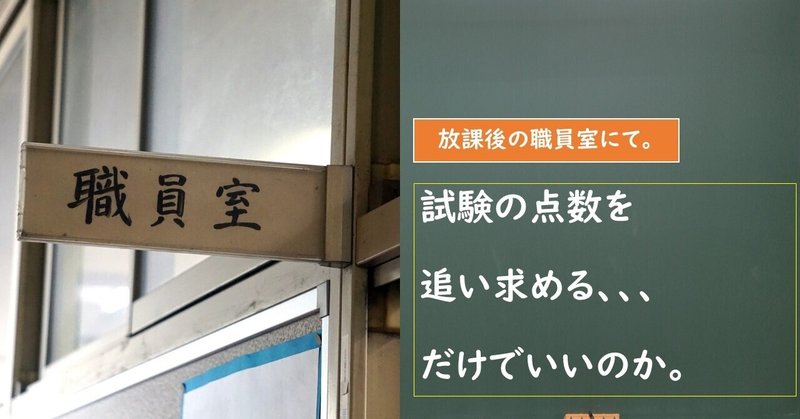
試験の点数を追い求める、、、だけでいいのか。
先日の放課後、職員室で数人の先生と1時間ほど教育談義で盛り上がりました。
コロナ感染拡大の影響で飲み会が全くないので、みんな話す機会に飢えていたのかもしれないな、、と振り返って思います。
こういう、何気ない会話から生まれる先生同士との話し合いは、個人的にはすごく好きです(笑)。
話の内容にはとても考えさせられました。
その内容とはずばり、「試験の点数を追い求めるだけの教育は何か違うのではないか」。
話の経緯を大まかに説明しながら、談義の中で出た意見をまとめつつ、自分の考えを書いてみたいと思います。
■進学実績が下がる中での「小テスト」導入の議論。
熊本県をはじめ、いわゆる地方の学校ほど「国公立大学」重視の傾向があります。
学費が安く、低所得でも通えて、将来の就職の保障もある程度できるから、重視する傾向があるのかなと思います。
私が勤務している高校も例外ではありません。
それゆえ、毎年の国公立大学進学者の数が重視されています。
例年より低くなると、「底上げしなければならない」とピリピリしてきます。
学力を高めるために会議の中で出たのが、「毎日小テストをする」という対策でした。
それに対して「、、、、ちょっと待って!それ今まで授業の中で散々してきましたよ!」という意見。
テストを何回やっても、点数はなかなか伸びてない現状がある。
もっと違うアプローチが必要なのではないかという意見で会議を終えられたそうです。(和私は所用で会議の場にはいませんでした(^_^;))
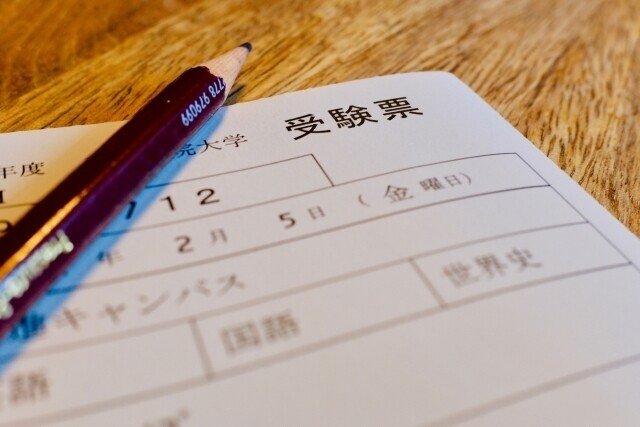
■大事なのは「モチベーション」では?
そして、その意見を言われた先生方を含め、「私は勉強のスイッチっていつ入ったのかな?それはなぜなのだろう?」と経験談をし始めました。
先生たち同士で話していく中で、たどり着いた結論が「モチベーション」という言葉でした。
なりたい職業。
興味のある学問。
学んでみたいこと。
やってみたいこと。
そのあたりの深掘りが必要だし、生徒と一緒に考えていく必要があるよね、と思いました。
同時に、「友人にテストの点数で負けた!とか、そういう仲間どうしの競争も充分モチベーションなりうるよね、」と。
もちろんテストの点数をあげていくために、小テストは必要です。
でも、それだけではいけない。
私の高校の先生が言っていました。
「見えないものが重要。数字はあとからついてくる。」
思えば高校時代、日本史が大好きで、毎週大河ドラマからモチベーションをもらっていました(笑)。
どっちかではなく、どっちもやる。
複合的にアプローチすることが結局大切だな、と思った談義でした。
■大学入試はあくまで通過点。
そして最後、同僚の先生の話を聞いていて思ったことが、
「大学入試はあくまで通過点」であるということです。
その先生は、「社会に出た時に、どういう人になってほしいか」を軸に日々の授業を組み立てられている方です。
その言葉に私はハッとさせられました。
日々の授業や卒業時の進路をどうするかで悩みがちだけれど、もっと大事なのはその先。
大人になってからどういう人になるか。
本質的で、非常に重要な視点だと、久しぶりに心が震えました。
教師として、まだまだだなと思った放課後の時間でした。
■まとめ ~帰り道の頭の中~
子どもたちにどういう人になってほしいのか。
ぼんやりあるけれど、まだまだ悩みながら仕事をしているな、というのが今の私の現状です。
ただ、向上心や熱意を失った大人になってほしくは無いなと思いました。
落ち込むことはあれど、何歳になっても目がきらきら輝いている。
そういう、自分が情熱を注げるものを見つけてほしい。
心にふっと思ったのは、それでした。
それを求めながら、明日からの仕事、頑張ります(^^)

教育のこと、授業をしている倫理や政治経済のこと、熊本の良いところ…。 記事の幅が多岐に渡りますが、それはシンプルに「多くの人の人生を豊かにしたい!」という想いから!。参考となる記事になるようコツコツ書いていきます(^^)/
