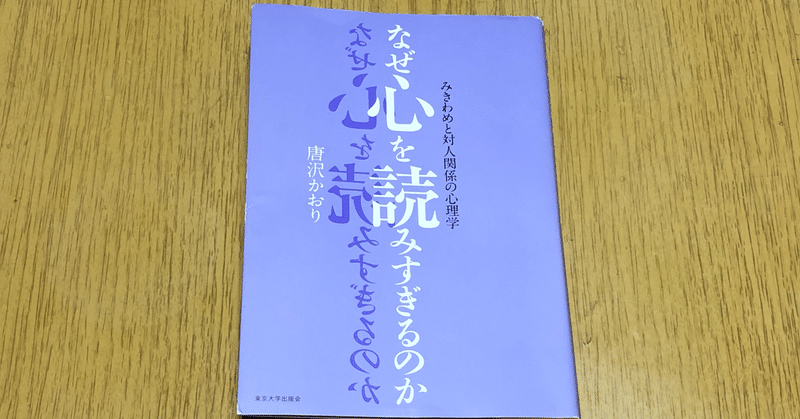
書評「なぜ心を読みすぎるのか −みきわめと対人関係の心理学−」
他者を理解することは、社会的動物である私たちにとって重要な行為である。あなたは障害のある人と関わるときに、どのように相手を理解しようとするだろうか。
ニンチ(認知症)があるかないか、クリア(知的な能力が保たれている)かどうか、つまり認知機能に問題があるかどうかをまず考える人が意外に多い。もちろん、私自身もだ。
たいていの場合、高齢であるほど認知機能が低下しており、身体の障害が重度であるほど認知の障害も重度であると考える傾向がある。
これはステレオタイプといわれる対人認知の方略のひとつであると考えられる。
ステレオタイプは差別や偏見の原因として論じられることが多いが、対人認知における認知資源を節約できるという利点もある。簡単に言えば、理解を深める余裕がない場合には型どおりの理解で済ませられるということである。
障害のある人が何らかの理由で暴力的な行動をとってしまうと、認知機能に問題があると考えられていたかどうかで、その後の評価が大きく異なる場合がある。
認知機能に問題があれば、○○機能の低下や性格の変化といった内的な特性を行動の原因として考えるのが普通で、周囲の対応の問題といった外的な特性に目が向けられることは少ない。
これは対応バイアス(または根本的な帰属のエラー)といわれる推論の誤りが強く現れているものと思われる。
対人認知は、ただ相手を知るだけではなく、どういう人なのかをみきわめて評価的に判断する過程であると筆者は主張している。そのためには、相手の心を読むことによって行動を予測し、どのように相互作用を進めていくのかを決めなければならない。
しかし、心を読むことにはさまざまなバイアスが付きまとう。バイアスは認知的錯覚とも言われるように、自覚することが難しい。そのため、まずは知識のレベルで理解を深めることが必要である。
本書は、タイトルだけを見ると人間関係を円滑にする自己啓発本のようにも思えてしまうが、そのような底が浅いものではない。バイアスも含めて、社会心理学の核となるテーマが詰まった良書である。
特に、第5章「人間としてみる」は、障害のある人に関わっている方々におすすめしたい。虐待の問題や津久井やまゆり園のような事件も、対人認知というテーマは決して無関係ではない。いじめやハラスメントの問題も然りである。
唐沢かおり 著 (2017年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
