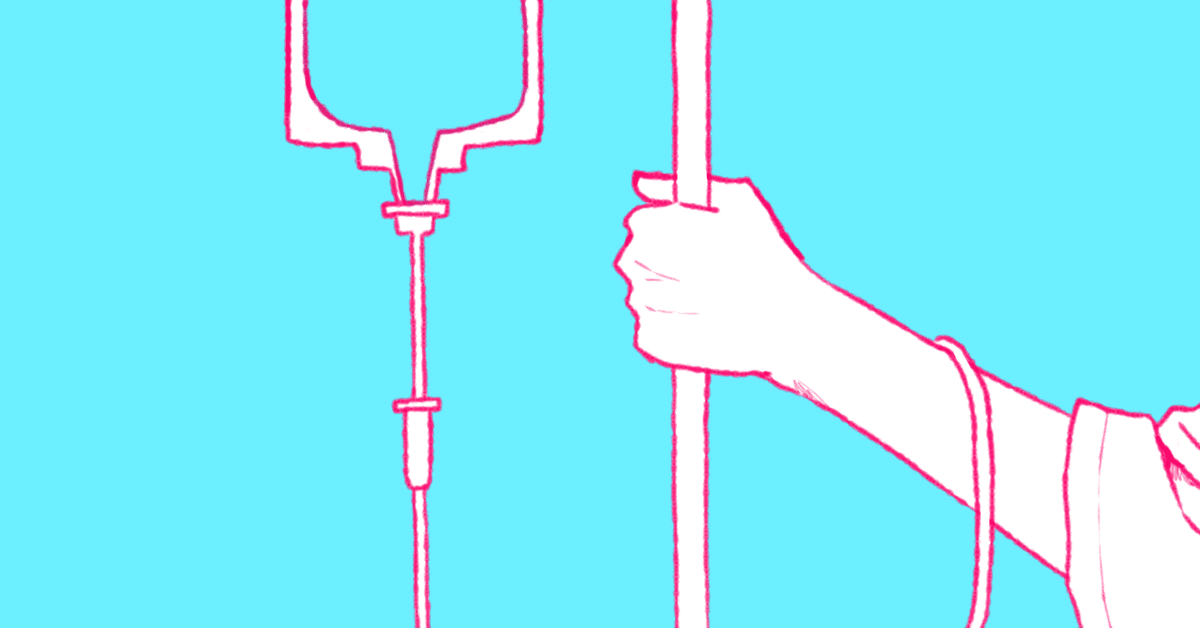
お仕事で気をつけていることの話
私はどちらかというと病弱な子でした。
以前、そんな話を書いたこともあります。
なので、幼い頃は健康優良児の人と比べると、それなりに病院通いを体験しているのかもしれません。
その体験を経て、今、自分が医療福祉職として働いている時に自然と気をつけていることがあるかもしれないなと思ったのです。
そう思ったきっかけは「SNS医療のカタチTV2023」の視聴イベントに参加したことでした。
(このイベントの公開収録に参加した内容は後日、noteに書こうと思っております。夫と久しぶりにデートもしたのでそれを合わせて書こうかなと…)
このイベントは毎年行われています。主に医療情報にまつわる話をそれぞれの立場から対話形式ですすめていく内容ですが、今はアーカイブを視聴している最中です。
その中で今回の考えをあらためて振り返るきっかけとなったのは、写真家の幡野広志さんと看護師さんのかげさんが登壇されていた「患者学」のパートです。
(チケット制のアーカイブも残っています。
でも、550円でこの内容が見られるなら私はかなりお得なんじゃないかなぁ..と思っております。
医療情報にまつわる話やもやもやを抱えている人。それこそ専門職や患者さん問わず興味のある方は覗いてみてほしいのです)
「患者学」の話に戻りますが
「患者と医療者のコミュニケーション」
と言う話を幡野さんがされています。幡野さんは血液がんを患っていて、病院通いも回数が多いかなりのベテラン患者さんです。
お2人で「いい看護師さん像とはなにか」というお話をされていました。
「仕事ができるできないはあると思うけども、こちらが思うのは、まず医療的な知識や技術でもなく単純にいい人かどうか。これは全ての仕事に共通するものだと思う」
「結局は性格」
と幡野さんが話されていて「ああそうなのかもなぁ」とすんなりと私の中に幡野さんの意見が入ってきたのです。
そこで私が思い出したのは、幼い頃に接した看護師さんや医師たちの姿でした。
私は小児喘息を患っていて、ネブライザーや点滴治療のお世話になることが多かったのですが、そこで出会ったスタッフたちを思い出してみたんですよ。
苦手だなぁ…と思うスタッフは、イライラしていたり、怒りっぽかったり、こちらの話したことを馬鹿にするような態度であったり、高圧的な態度を感じました。
関係性が築きやすいなと思うスタッフは、こちらが話しかけやすい雰囲気を持っているんですよね。笑顔が見られたり、馬鹿にするようなこともない。いつでも意見が伝えやすいような方はこちらからもアプローチしやすいし、本音も話しやすかったです。
点滴がもう少しで終わりそうですとか、お手洗いに行きたいですとか、すぐに意見が言える看護師さんと、なかなか言い出しづらい看護師さんがいて、子供心にも配慮しながら頼んでいた記憶があります。
看護師のざきさんが話していた内容で「それは看護師にもある」という話が興味深かったのですが「たとえば、こうしてほしいと患者さんに頼まれて、急いで今行っている業務を終わらせて患者さんのところへ行った時に『遅い!』と怒鳴られたりすると、看護師も気持ちとしては悲しくはなる」とのことでした。対人間として悲しみはあるとのこと。
患者さんと医療者の人間関係の構築は「患者」と「医療者」という役割の前に
対人間なんだな
という気持ちをお互いに持てるといいなぁという話だと私は今回受け止めました。
医療福祉の関わりでは、情報共有が要だと思っています。
情報をどのように取るのか、どのように共有するのか、それをどのように活用するのか、いつの時代でも、ITが発展した今でも、同じことで悩んでいるような気がします。
まず患者さんが、自分の思ったことや感じた症状などを「話しやすい」状況を作り出すことが、情報の取りやすさに繋がり、医療者にとってもメリットがある話だと思います。
医療者も患者さんの状況を想像しながら接しているとは思うのですが、ご本人の真意や状況までは共感できなかったりします。そこで何気ないことでも話してもらえる信頼関係が築けていると、スムーズに対応できる場面が増えると思うんです。そして欲を言えば、あらたまった面接よりも、雑談にけっこう本音や価値観が含まれていることが多いのです。
私の幼い病院通いの記憶と、今回のイベントの話を聞いて、私が日々気をつけていることに話を戻します。気をつけているのは以下のことです。
「話しかけやすい雰囲気を作ること」
話された内容をすぐに否定しない。
どんな方にも敬う心を忘れない。
上からの立場で話さない。
たまたま、私は作業療法士としての知識は有していて、相手はそれを持ち合わせていないだけで、相手の方は私より他の分野でもっと知っている知識があったり、体験していないことを体験していたり、患者さんや利用者さんと医療者はどちらがえらいとか上とかということはないと思います。
その中で、まず人間として信頼してもらうこと。
信頼してもらうことで、情報が伝わりやすくなること。
そんなことを念頭に置いて接していきたいのです。
おまけの話ですが、幡野さんが「ありがとう」が言えない患者さんの話をされていました。
「貨幣と一緒で日常的にその人が言われているかどうか。病人になったらありがとうと言われる機会が減って、自分からありがとうを言えなくなってしまうのではないか」
「だから病人に『ありがとう』と言えるような場面を作った方がいい」
とおっしゃっていて「病人になるとやらなくていいよと仕事を奪って、何にもやらせない家族もいるけども、そうではなくて家事でもなんでも少しやってもらってありがとうと言うと、その方も相手に言えるようになるかも」と話されていました。
聞いていて、なるほど〜と思いました。
貨幣のように考えたことはなかったのですが、私は作業療法士として、狙っている目標の一つとして「誰かに感謝される場面を作る」というものがあります。
誰かはその方の好きな人が一番よろしいのですが、まず、とっかかりとして、私が「ありがとう」と言えるような場面を意識して作っています。
わざと頼れる時は頼ったり、何かを教えてもらった時に「ありがとう」と言うと、お互いの雰囲気が柔和になるような印象があるのです。
今回の話は医療福祉の現場だけでなく、さまざまな仕事の場面でも活用できることかなと思いますし、仕事以外の人間関係でももしかして生かせるものかもしれません。
(私はまだ未熟な人間なので、プライベートにおいてはこの限りではない部分もおおいにあることを追加情報として書いておきます。でも、仕事ではなるべく気をつけてるつもりです)
ひとまず本日の記事はここで終わりにしたいと思います。また続きは後日!
この記事が参加している募集
サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。
