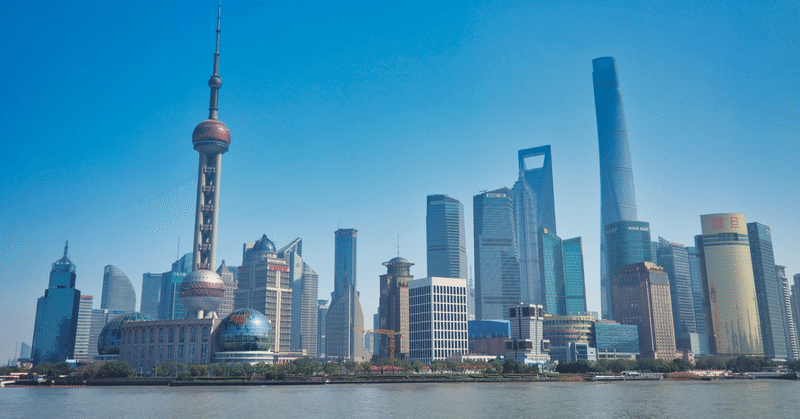
【読書感想】リベラルファンタジーは神話学へと進化する。『百島王国物語』2
気候が春めいてきて、旅情がわき上がってきます。最近はあまり遠出ができないので、物語の力を借りて遠い地への憧れを満たしてみようとファンタジーを読むことにしました。
『百島王国物語 竜騎手の反逆』 佐藤二葉
あらすじ
竜を育む西の海の領主娘“小竜公”ラヴァンドルの冒険と成長!
「この震えは、恐れではない。運命が動くときの予兆なのだ」
音楽と魔術で織り上げた本格ファンタジー、シリーズ第2弾!
「――我々の魔術を冒涜し、破壊しつくす、あたらしい力、穢れた力を帝国は手に入れました」
古来、善にして真なる王が魔術政を布いて治める国、百島王国。その中心、〈王の島〉イスリルの王都にそびえる王の大宮殿に強大な力を手にした帝国から使節団がやってきた。どうやら、帝国の新しい力は「魔術を滅ぼす力」らしい。“小竜公”ラヴァンドルは王女の勅使となり、帝国の力の源を探りに行くことになる。
前作『滅びの王と魔術歌使い』について
前作を読んだときの興奮を思わず長文noteにしたためたものの、読んでから1年半経過していることもあり、細かい設定はすっかり忘れていました。前作を座右に起きながら、本作を読むために必要な設定を振り返ってみると、
①本作の主人公ラヴァンドルは、前作クライマックスに配された、エスリエンタ王女による竜召喚の”ペテン”に同席し、自らの竜に対する思いの深さに反して、竜は自分に目を向けてくれなかったことに挫折と失望を抱いていること
②同じく相棒役のソルヴィグは、ラヴァンドルの<影>として少しだけ登場し、前作主人公のタージェスヴェンに言葉少なながら良い印象を持っている様子であったこと
③東方大陸を治める「帝国」が、百島王国の大陸植民地(パヴァン)へ侵攻した事実が語られていること
などを思い出すことになります。
次に、オープンエンドに措かれていた前作のラストから読者が期待する次の物語を、自分の読書感想を参考に振り返ってみると、
Ⅰ ドヤ顔でグレートエスケープをキメたタージェスヴェンとアトルラーゼが打つべき次の一手は何かということ
Ⅱ タージェスヴェンの魔術院における同輩であったナーゼル、マレンダや、アトルラーゼの同輩であったラファルディーン、ニローファ、トリスベグなどは使い捨てキャラなのか、今後の展開に関わりを見せるのかということ
Ⅲ 光り輝くカリスマのエスリエンタ王女が、中国風味を感じる「帝国」と今後どのような外交関係を進展させ、王国の”秩序”を舵取りしていくのかということ
などがどこまで語られるのかを楽しみにして読み進めることになります。
なお、上記の読書感想で私は「ドンパチやるバトルが捨象されている」ことを指摘していますが、本作では第二歌で「マウラギニア競技祭」が盛大に開催され、その内容は帝国の使節団から「規則が、あなた方の武勇を単なる競技に、つまり遊戯に貶めている」(P144)と嘲笑されるものの、P474では「そなたたちはわが国の競技を遊戯だと笑ったが、遊戯でよいのだ。生きることそのものが戦いなのだから、わたくしたちはこれ以上むやみに戦う必要はない。力や、武勇は、遊戯であるべきだ。」と力強く論駁されるに至り、「バトル」に対する著者の姿勢が明示されます。
また、そうであるにもかかわらず、というべきですが、情勢がどんどんキナ臭さを増してきて、本作のクライマックスは軍事衝突によって互いの陣営の重要キャラクターが傷つきながら、最後には革命の鬨の声を揚げる形で締められており、欧州で勃発した戦争の時代を繁栄したかのような物語が展開されていくことになりました。
相対化される音楽
さて、本作は上記のⅠから語り起こすものと思っていたら、Ⅲが起点となり、しかもエスリエンタ王女自身ではなく、その忠実な部下として振る舞ったラヴァンドルが主人公となるのは、しかし必ずしも意外というわけでもなかったように思います。前作主人公の対立陣営に属し、居丈高に権威を振りかざしながら、それでいて弱さを抱え、もがき苦しむ人物として造形されていた彼女は、むしろ続編の視点人物として掘り下げられることを待っていたとも思えるからです。
エスタブリッシュメントとしてのラヴァンドルは、出自においては音楽=魔術を基調とした百島王国の統治システムに縛られている(それは例えば<島付き魔術師>という中央集権の代官役に象徴される)にもかかわらず、彼女が領主の娘(小竜公)を務めるイリーンという西方の半自治州では魔術による農産業のコントロールを嫌悪しており、そうした文化に属する彼女は同時に、彼女自身の才能として、音楽が分からず、従って魔術が使えないことで、二重の意味でシステムから疎外されているという自我の危機を孕んでいます。
そしてまた、<竜>との共生を強く内在化したイリーンの文化の内部においても、竜が島にすっかり寄りつかなくなり、遺された卵は一向に孵化の兆しを見せず、彼女自身も肺が弱いことから竜騎手として空を飛ぶことができないことで、自らの領主としての適格を疑い、孤独を深めています。
そんな彼女に「生きる意味」を与えたのがエスリエンタ王女であり、首都イスリルへ苦手な船旅を押して往還し、忠義を果たすことは、同時に、故郷イリーンを留守にし、自ら敷いた針の筵から逃避する格好の口実となっていることが明らかになります。
首都における調教を振り払うかのように、すっかり幼児化・ワガママ化したタージェスヴェンが当てこするように、「あんなに頑張ってるのに、まるで自分に価値がないみたいに言ってました。それは、誰かがそう思わせてたんじゃないですか? 価値がないおまえでも、自分の傍なら、自分のために働くなら、価値ある存在になることができる、って」と図星を指すように、エスリエンタ王女につけ込まれた隙(”息苦しさ”)は、実はイリーンの画一的な「竜至上主義」がラヴァンドルを抑圧することで生み出されていたと読み取ることができないでしょうか。古い性別役割分業の価値観を残した西方の4州・・・北海道、沖縄に続き、ここにも令和の日本のアナロジーが表現されているように感じます。
前置きが長くなりましたが、そのように音楽=魔術のシステムから疎外されたラヴァンドルが主人公となることで、前作と異なり、音楽を中心とした表現は後景に退き、タージェスヴェンやアトルラーゼ、あるいはマレンダが行使する魔術は、前作のように「言語化された音楽」を行使者が即興で思索し、工夫を加えながら練り上げる魅力的な芸術としての営為から、単に傷の治療や攻撃に対抗する防御結界などの効用(結果)のみが目撃される対象に留まることとなり(ラヴァンドルの眼からはそのように見えるという意味ではいっとう正しいのだが)、少し残念だったように思います。
「大デリウの弓型琴(サンドゥーカ)」も重要なイベントアイテムかと思ったら、タージェスヴェンはその使用感について特段の感想を寄せておらず、アトルラーゼをパヴァンに呼び寄せるためだけの具材に留まっていたように感じます。また、禁忌と設定された「死者の口寄せ、呪殺、幻術」について、前作に続き、「死者の口寄せ」はやはり登場しませんでしたので、これは次作以降への持ち越しになるのだろうと思います。
前景化する「神話」
その代わりに前景化し、読者を満足させてくれるのが、作中に散りばめられた「神話」でした。著者は12世紀のビザンツ帝国における女性歴史家『アンナ・コムネナ』の漫画化に取り組んでいる人物ですが、その取材過程で得た知識や経験が注ぎ込まれているように見えました。
まずは、アトルラーゼが旧友ニローファへの語りを通して、聖典のイスリル第三写本と、イニエンの書庫に眠っていた写本を比較し、王家により正統とされたイスリル第三写本の真正性に疑義を呈します。この点は「建国正史の嘘」を暴いた前作から続く問題意識でしたが、「より難しい方、より意味が取りにくい方が、古くて、原本に近いかもしれないって考えることがあるの」といったセリフなどは、ギリシア・ラテンの古典を渉猟し、女性歴史家を扱った作品に取り組む著者の面目躍如となっています。
そして、真実を知ろうと前のめりになるアトルラーゼと、自らの世界が揺らぐことを恐れるニローファが対立する描写からは、開明的な啓蒙者と頑迷な保守主義者を対比しているように(読者には)見えつつも、実は愚かな陰謀論者と、理性的な常識人の対話とも捉えられるギリギリのバランスで成立しています。
「あんなに・・・・・・あんなに敬神の念に篤かったあなたが・・・・・・あなたがこんなことを・・・・・・」
ニローファの声が震えているのを聞いて、アトルラーゼは何か鋭利なもので胸が突き通されるように感じた。
「・・・・・・神々を・・・・・・信仰を手放してしまうほどに、その子のことが大事なの? その、滅んだ民の生き残りがあなたを異端の道に引きずり込んでしまったの?」
「ニローファ、勘違いしないで。私は、神々と星々の霊感を信じている。だからこそ、本当のことを知りたいの。それに、私は≪北の僻地である≫エル育ちだもの。そもそも、<誤った>神話をまだ語っている僻地で生まれたのよ。神の物語が揺らぐのには慣れているの」
次に、竜にまつわる神話が、ラヴァンドルの回想するイリーンの信仰と、タージェスヴェンが歌う<翼なし>の物語の両面から語られます。①竜が人間たちに混じり合い、人間に魔術を伝えたという開闢の物語と、②人間が魔術の使い方を誤ったがゆえに、竜は去り、竜との共生が破られたのではないかという不安は、①→②の時系列によって統合されると思い込んでいたら、実は①の世界が物語の舞台である”現代”にも生きていた、という仕掛けは面白かったです。
そして、パヴァンの人々が信仰する「石榴石(ガーネット)の君=エレヴァル」の物語は、ラヴァンドルをエレヴァルの再来として見なすことで、彼女を擁立し、帝国との交渉へと人々の行動を牽引していきます。ラヴァンドルはその僭称意識(詐欺師感情)に悩みながらも、最後にはそれを引き受ける覚悟を決めます。
もう、後戻りはできない--女神や英雄と同一視されることの恐ろしさ--あたらしい苦しみが、ラヴァンドルの心を縛り上げ始めた。このまやかしを解くのは難しい。もう、始まってしまったのだ。
神話を”担う”人間
以上挙げたように、神話はそれ自体で完結するものではなく、それを語る者、利用する者、読み解く者、鼓舞される者といった神話-人間間の関係において重要なものとなります。
ここで考えてみたいのが、第6歌、竜の卵が孵化する章のラストで、ラヴァンドルの月経が開始することです。物語をグルーブするためには、例えば、帝国の<人質>となったラティ卿と、エスリエンタ王女の間のつばぜり合いが、王命によるエスリエンタ王女の投獄によって中断されたように、場面を転換する推進力が必要となるのは技巧として理解できますが、ここで何故、月経が利用されることになったのか。
もちろんそれは、ラヴァンドルが「子どもを産めない」という喪失感・不能感を示すためでもあります。足を折られたキリオン、水子を作ったニローファ、武勇を競うことは反面、武勇に劣る者をあぶり出すマウラギニア競技祭・・・この物語の登場人物や舞台は「不虞」であることの劣等感に苛まれる、ファンタジーの世界にあって、極めて人間らしい設定に満ちあふれています。
しかし、それに加えて、この月経は、ラヴァンドルが「人間である」ということを強くシグナルとして読者に示すための表現にも思えました。このシーンで、私は井上ひさし『新釈遠野物語』に、演劇評論家の扇田昭彦が寄せた解説文を思い出しました。少し引用が長くなりますが、
「『遠野物語』が名著であることは、むろん疑いようがない。だが、元来が語りものであった土地の昔話が活字として定着したとき、大きなものが失われてしまうことにも注意しなくてはならない。さらに東北出身である私には、どうもこの名著に”収奪”という感じを抱いてしまう。地方の文化が中央に召し上げられたという気がする。・・・」
こうした立場から、井上氏は『新釈遠野物語』を書くにあたって、『遠野物語』では省略されていたもの、つまり昔話の語り手と聞き手、そして語りの調子を復活させた。それはいいかえれば、もともと語り手と聞き手という親密な関係の場がなくては成立しえない、演劇的行為としての物語の構造を重視するということである。柳田国男が、それ自体としてはまぎれもなくすばらしい緊密で簡潔な文語体を駆使して、見事な民俗学的、文学的世界として成立させた説話を、井上氏はより原型的な方向へ、つまりより演劇的な方向へ引きもどして再構築してみようとはかったのである。
こうして、この九編からなる連作物語集は、遠野から遠からぬ山のほら穴に住む、語り手としての「犬伏老人」と、聞き手としての青年の「ぼく」との対話というスタイルを終始保ちつつ、のびやかに展開する。語りものとしての構造を崩すまいというのだから、当然、話には中断があるし、「ぼく」からの質問や異論も出る。とくに話が山場にさしかかると、「犬伏老人」は決まってもったいぶって煙草を一服吸いつけたり、鉄瓶からおもむろに白湯を飲んだりして、「ぼく」と私たち読者をいらいらさせるのだが、これも往時の昔話の雰囲気や間合いを復元しようとする作者の楽しい工夫である。
この議論に引きつけて考えると、本作が面白いのは、人間たる語り手-聞き手の関係だけでなく、語られる対象もまた人間であるということです。具体的に言うとそれは、マレンダの告白です。P409からP411まで一気呵成に(オタク特有の早口で)語られる自らの立志編を要約すると、ラヴァンドルが「新しい女」としてイスリルの王宮に出入りし、活躍するロールモデルとなったことで、自分は両親を説得して魔術学院に入学することができた、というストーリーです。ここでは、あえてクリシェのような言い方をすれば、ロールモデルたる先駆女性の存在こそが神話であったということが語られています。(そして、マレンダの境遇からは、西方の4州がやっぱり令和日本の”あの島”のアナロジーのように感じられます。)
先述したような、「石榴石(ガーネット)の君=エレヴァル」の物語をラヴァンドルが引き受けるに至ったのは、この「神話で語られている対象もまた人間なのである」というマレンダの鼓舞による気づきがあったからこそ、ということだったのです。私の前作読書感想Ⅱの伏線、マレンダというキャラクターは、ラヴァンドル-アトルラーゼ-マレンダという投獄三人衆のシスターフッドの成立という形でしっかりと回収されたこととなりました。
そして、ラヴァンドルの思索はさらに一歩踏み込み、「神話で語られる人間」が、そうした役割に囚われることがあってはならない、という信念へと至ります。
「エスリエンタさまは間違っておられる--国の安寧のためなら、何が犠牲になっても構わないと思っておられる。地方の島々も、パヴァンも、わたくしの命も、そして--ご自身の心や、幸福でさえも。そんなことは間違っている! わたくしは抵抗する!」
そしてまた、女王に即位したエスリエンタ自身も、国家の「犠牲獣」となった自らの境遇に自覚的であることが示されます。
ふいに、エスリエンタの耳の奥に、良く知った声が聞こえる。
--差し出がましいことですが、エスリエンタさまという、ひとりの、かけがえのないお方の、喜びや幸福はどうなるのでしょう。
鷹揚なふるまいの内に、傷つきやすい魂を隠した娘。自分の幸福を願っていた娘。イリーンからやってきた領主の娘、可愛いラヴァンドル。
ああ--エスリエンタは自分を嘲るように頭を傾け、額に手をやった。
--あの娘は、この世界でただ一人、わたくしのことを人間だと思っている娘だったのか。
エスリエンタは、波のように押し寄せる感情に、名前を付けることを拒んだ。しかし彼女の手はこの時、自分の傍らにあるはずだった手を、あるはずだったぬくもりを求めて宙をさまよっていた。もう片方の手で、エスリエンタはその手をつかむ。
握りしめた手の中にあるのは、虚ろで、そして巨大な権力のみだ。
ここに来て、物語は、竜の末裔たるタージェスヴェンが虚偽により成立し運用されている百島王国の王家を打倒する革命の物語ではなく、魔術(タージェスヴェン・アトルラーゼ)とシスターフッド(ラヴァンドル)とが手を取り合って、王家というシステム(神話)に囚われたエスリエンタ女王という”個”(人間)を回復する、救済の物語を志向していくこととなったのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
