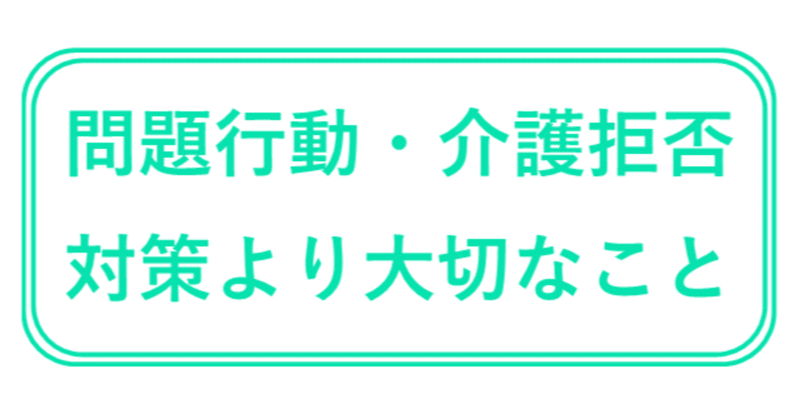
すぐ対策を講じることは必ずしも良いとは限らない。様子見により「なぜ?」を見極めることも介護の役割
■ 問題行動と介護拒否
認知症介護では「問題行動」という言葉が使われる。そこそこ介護に携わった方であれば、この言葉が不適切だということはご存知であると思う。
問題行動としているのは介護者であり、認知症である当人にとっては自身の行動を問題なんて思っていない。
だからこそ、下手に介護者側の認識で制止しようとしたり、介護者側の常識を押し付けようとすると、認知症である当人から反発される。
これは状況によって「介護拒否」という言葉になる。介護者は当人にとって必要な支援をしようとしているのに、その当人から反発されるものだから”拒否”という言葉を用いる。
・・・まぁ、問題行動とか介護拒否とかいう言葉を使いたくなる気持ちはよく分かる。そして、これらに対して「何とかしなければ」という考えになる気持ちもまたよく分かる。
■ すぐ「どうすればいい?」を考えるのは良い?
しかし、認知症介護における問題行動や介護拒否に対して、すぐに「何とかしなければ」という対策を講じるのは早計だと思う。
問題行動や介護拒否に対して対策を講じることは介護現場ではよく見かける場面であるが、私が危惧しているのは「なぜ?」を見極めていないのに、すぐに対策として「どうすればいい?」ばかりに目を向けていることである。
例えば、介護施設で入居されてる認知症の高齢者が、館内のどこにも見当たらないと思ったら独りで外に出ていたとする。
独りで外に出ると迷って戻れなくなったり、足腰が悪いと転んで怪我をする可能性だってある、と施設職員たちは思うだろう。
そのため、今までは開錠したままの玄関の鍵を今後は施錠することとした。
――― このケースは世間的には「徘徊」と呼ばれる問題行動であり、それに対して玄関の鍵を施錠するというのは対策としては有効だろう。仮にご自身で鍵を開けられる方であっても、開けるまでの間に施設職員が止めることができる期待もある。介護者たる施設職員もひとまず一安心であろう。
・・・が、果たしてこれで良いのだろうか?
■ 問題解決なのに「なぜ?」がおろそかにされる理由
この手のケースは一時的には有効であるが、その後にまた別なカタチの行動として表れたり、入居者が何とか外に出ようと強硬手段におよぶなどの事態に発展することもある。
なぜかと言うと、そもそも「なぜ外に出ていたのか?」に目を向けないまま対策を講じているからである。
しかし、このような「なぜ?」をすっ飛ばした検討の仕方は、介護現場ではよく見かける。とにかく問題行動や介護拒否があれば、すぐに「どうすればいい?」を考えようとする。
そして、それっぽい対策を立てて満足しては、それが大きなトラブルに発展することに気づかない。
――― ではなぜ、介護現場では問題行動とか介護拒否といった出来事に対して「なぜ?」に目を向けないまま「どうすればいい?」を考えるのだろう?
その答えは単純だ。
――― 「なぜ?」を検証するには時間がかかるからだ。
――― 「どうすればいい?」を考えたほうが楽だからだ。
つまりは「なぜ?」に目を向けてから「どうすればいい?」を考えることが面倒なだけなのだ。
■ 介護者の安心感のための対策になっていないか?
また、問題行動や介護拒否に対してすぐに対策を講じることによって、早く安心感を得たいという心理もあるのだろう。
確かに「なぜ?」を起点に、特に認知症の方の行動原理を探ることは難しいし、見極めには時間と忍耐を要することは間違いない。
しかも、「なぜ?」を検証している間は対策を立てられないので、また同じような問題行動や介護拒否といった動きに出る可能性もある。これは介護者としては落ち着かない。
そのため、一時的にでも安心できるよう、それっぽいものでもいいから対策を講じてほしいと思うようになる。
もちろん、この気持ちは理解できる。介護者だって人間なので、なるべく早めに安心感を得たいだろう。しかし、認知症の当人に目を向けていないという事実もある。
だからこそ、可能な限りで構わないので、問題行動とか介護拒否という言葉で一括りにすることなく、「なぜ〇〇さんは、このような行動をするのだろう?」「なぜ✕✕さんは、あのような言動をするのだろう?」という思考を最初にもって欲しいのだ。
■ 時間をかけて「様子見」をする
介護では「様子見」「状態観察」「見守り」といった言葉がある。介護者によってはコレに抵抗を抱く人も少なくない。
それは介護を要する高齢者に何もしないというイメージがあるせいだ。
しかし、何かしらの事象を探るためには「見る」ということが欠かせない。原因や効果を見極めるためには、時間をかけて「見る」ということが必要である。
考えてみてほしい。医者だって場合によっては「このまましばらく様子見しましょう」と言う。
現状起点として観測を続けることで治療という対策を講じるからだ。よくわからないまま「あなたの病気の原因はコレだ!」なんて言わないし、下手に断定して薬や手術をしないだろう。
つまり、ときには「なぜ?」を見極めることに時間がかけて、そのうえで「どうしたらいいか?」を定めたほうが良いこともあるのだ。
そのためには、介護者自身が肝に免じなければいけないのは、特に認知症の高齢者の行動に対して、安直に問題行動とか介護拒否なんていう言葉を使って分かった気にならず、相手の行動に興味を示すことである。
もちろん、一時的には苦しいかもしれない。もどかしいかもしれない。
しかし、「なぜ?」に時間をかけて向き合うことは、将来より良い介護を提供できる可能性につながる。それはある意味での投資である。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
