
オムライスの端っこへスプーンを突き立てるときに始まる幸福論。
小さいころから好きなのはオムライス。
いつも母に「作って作って」とねだっていた。
ケチャップライスを炒める香りが台所に充満したあと、卵の薄皮を作るバターの濃厚で柔らかな香りに部屋が包まれるのも好きだった。
お皿の上にドーンと黄色いオムライス。
所々に褐色の焦げ目があるのも香ばしさを予感させて。
そこに真っ赤なケチャップをかけて、その上から少しウスターソース。
それをグリグリとスプーンの腹で混ぜて、
端っこの方からスプーンを立てて食べ始める。
幸せを目の当たりにした子供の頃の記憶。
中学生のときも高校生になっても、いっぱいにつめこまれたオムライスのお弁当のときはテンション上がった。
身体が大きくなるにつれて
「もっと大きいの」
と僕は母にねだり続けた。
いくら食べてもお腹が減るし太りもしないそんな10代後半。
しかしオムライスはある一定の大きさ以上になることはなかった。
「これ以上は大きくできんとよ」という母の困った顔は今でも覚えている。
オムライスのサイズが振るうフライパンの大きさによって規定されるということを知ったのは、ずっと後のことだ。
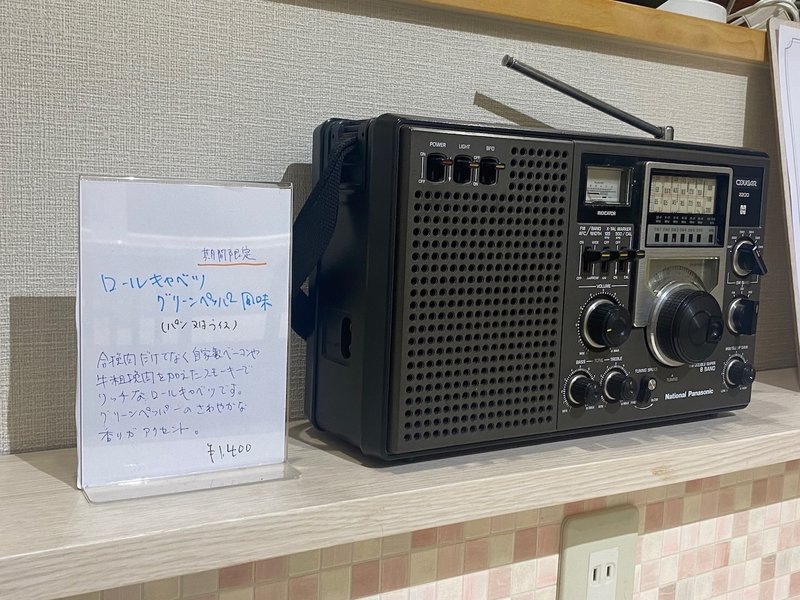
大学に合格した僕は熊本の家を出た。
独り住まいの東京ではオムライスを食べることはなかった。
限られた仕送りとバイト代。
腹を満たすのは率のいい学食のカレー大盛りとスパゲティ、年金生活者が集いばあちゃんが客の憂さを宥めて回る近所のおでん屋と定食屋。
あるいは炒め物など簡単なものの自炊。
そういう毎日。
大学を卒業してそのまま東京で就職した。
毎日が深夜帰宅になった。
そのとき住んでいた町で深夜まで開いていたのは学生向けの寿司屋とラーメン屋と焼肉屋、そして牛丼の松屋だけ。
コンビニ飯がまだそれほど美味しくなかった時代。
そうしたある日、僕は結婚した。
新居は都内北部の丘の上のマンション。
駅から徒歩17分のそのマンションからは晴れた日には新宿の高層ビルの向こうに富士山が見えた。
それほど料理が得意ではなかった妻だけど、たまにオムライスを作ってくれる。
22センチ径のフライパンで作られたその小ぶりなオムライスの上には、ケチャップでハートの形があしらわれていた。
しごとも夫婦も順調に行っていたある日、ぼくは思い立って生まれた熊本にUターン就職を決めた。
突然の帰郷だったので住む家の準備が間に合わない。
最初は父母の住む実家に転がり込んだ。
久しぶりに見た台所の鍋には焦げ付きの跡があり、ターナーのプラスチックの取手は溶けた跡があった。
久しぶりに寝起きを共にした母はあまり台所に立つことはなくなっていた。
そして父が脳梗塞の発作をおこし入院がちになると、母の認知症は進行していった。
新たに勤め始めた会社は市街中心地にあった。
昼休みには近所にお昼ご飯を食べに行く。
そうして幾つかのお店にお世話になるうちに、懐かしい味のオムライスを見つけた。
母のオムライスの具材は玉ねぎ、ピーマン、にんじんを細かく刻んだものと小指の指先くらいに切られた鶏の胸肉。
見つけたお店のオムライスの具材はタンパク質部分が小エビやイカだった。
それでもケチャップが濃厚でしっとりずっしりとしたオムライスは、懐かしい母のオムライスの系統だった。
盛りの良さが有名なお店だった。
大きさから考えるとオムライスは径28センチかそれ以上のフライパンで作られていたはずだ。
大きなオムライス、しかも母のオムライスの面影あり。
嬉しくて僕は2週間に一度くらいのペースで通い詰めた。
その後、生まれた熊本から福岡、長崎へ転勤し、また生まれた街に帰ってきた。
そうして遭遇した熊本地震。
街の様相は変わってしまった。
ある日、以前行っていたそのお店のオムライスを食べに行った。
見た目と大きさは同じ。
スプーンの腹で表面のケチャップをグリグリして、端の方にスプーンを突き立てる。
「すかっ」
いや別にそんな音がしたわけではない。
なんだろう、以前のようなしっとりずっしり感がなくなっている。
気になって2、3度食べに行った。
同じだった。
考えてみれば四半世紀前に僕はここのしっとりずっしりのオムライスに出会ったのだった。
僕も歳をとったが、このお店でフライパンを振るう方はその先を歩いておられるはず。
腕っぷしも弱ってくるだろう。
料理のやり方も店の経営状態も変わったはずだ。
そしてオムライスも。
あの母の匂いのする懐かしいオムライスはもう食べられなくなっていた。
こうして僕らはある日突然に、包み込まれるような優しさに心を委ねていた何かとの決別を突きつけられるのだ。
昨年は大事な人々との別れが身に沁みた一年だった。
義父もその一人だった。
妻は気づいてないと思うけれど、僕は義父が好きだった。
僕の父とは全く違う感じ。
父は聡明で、泥臭く、戦後のややこしい時代をややこしく生きる、この世の実を尊ぶ人だった。
義父はそれとは違い、戦後の世界を必死ながらも上手く立ち回り賢く生きる人だった。
父を細川隆元タイプとすれば、義父は梅宮辰夫タイプ。
義父は戦後に米軍キャンプへ潜り込んで通訳や商売をしながらボクシングなどを習い、試合に出たりもしていたらしい。
父が貧しくて苦労していたころ義父は自家用のクルマで舗装されていない道をかっ飛ばし、箱根にドライブ旅行に行っていた。
義父の若い頃の思い出話には怪しいところもたくさんあった。
父と義父は同世代で二人とも軍隊経験があるのだけれど、父が学徒出陣で入隊した先の陸軍部隊から北京陸軍経理学校に行って主計になったという話をしたら、義父も「私の兄も軍の経理学校に行きましてねぇ」と。
横で聞きながら「ほう!」とは思ったのだが、ちょっとあれは張り合う気持ちが走ったのではないかと思っている。
そういう我が家の来歴とは異なる昭和の男の話を聞くのは、緊張もしたが、楽しかった。
話し言葉も都内の北の方の下町らしい方言があって。
まさに辰っつぁん。
2022年5月。
その義父がコロナ禍で面会が叶わないなか、高齢者施設でひっそりと亡くなった。
さらに時代を読む大事な指標としていた本の著者である思想史家の渡辺京二さんも「やっと出会えた!」と思ったすぐに、氏の死と向き合うことになった。
なんでプランナーが渡辺京二さんとの邂逅がそんなに嬉しかったのかについては別項で書こうと思っている。
まずは思想的思考的にとても懐いていたとのだと思ってもらっていい。
そんなこともあって年末から何かを表現することについて指が動かなくなってしまった。

年が明けて。
うつうつとしていたそんなある土曜日。
「そうだオムライスを食べに行こう」
そう思った。
向かったのは熊本市西区の田崎市場内。
洋食屋「ターレ」。
店主の山本一哉さんは僕と同い年。
熊本の市街中心部のフランス料理「ケルン吉本」で知り合った。
当時のシェフは木村さんで、のちに木村さんから譲られる形で山本さんが店主になった。
僕が東京からUターンして帰ってきた頃はまだ木村さんの時代。
それからの仲だからすいぶん長い付き合いだ
「ターレ」のオムライスは母の味とも、件の喫茶店のものとも全く違う。
やや厚みのあるタイプの薄焼き卵で包まれていて。
中のケチャップライスはケチャップよりもバターの濃厚な香りがする。
バターのおかげでライスはケチャップを纏いながらもべちゃっとならず、一粒ごとにもっちり感がある。
とても上品な洋食をいただいている感じだ。
見た目には大きくないオムライスなのに食後の満足感は十分。
よそゆきのオムライス。
けれど心に染み渡るオムライス。

山本さんは「ケルン吉本」を後輩に譲り、自分の次の人生を創るために「ターレ」を開業した。
それまでチームでこなしてきたしごとを一人で回す。
その試行錯誤と工夫について伺いながらいただくオムライスは、ジャンルは違うが新しい人生に踏み出す気持ちを共有する、今の僕にはそんな滋味に満ちた味に思えた。
このオムライスがあれば、まだまだ僕も「端っこにスプーンを突き立てる喜び」が味わえる。
久しぶりに書くnoteはオムライスの話にしよう。
食べ終わる頃までに最初の1行をどう書こうかと、考え始めていた。
もし、もしもですよ、もしも記事に投げ銭いただける場合は、若い後進の方々のために使わせていただきますね。
