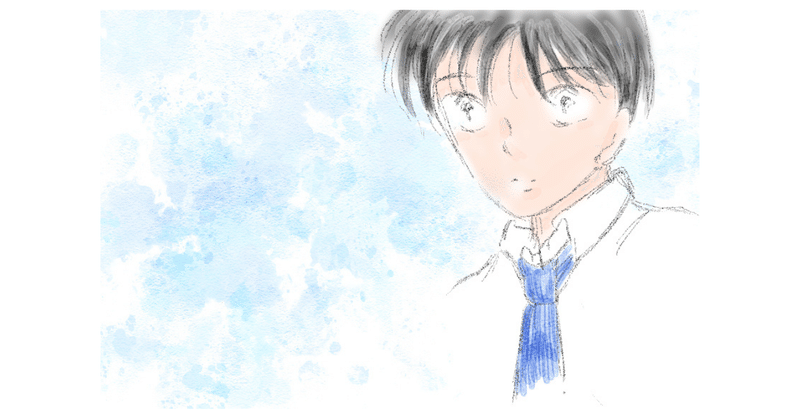
【短編小説】温かい。それだけで十分だ。
8月27日につぶやいた140字小説を元に書き上げた短編です。
自死表現あります。苦手な方は自衛願います。
『運命だと思った恋が終わった。もう、誰かを好きになるのは、止めようと思った。こんなに辛い想いを二度としたくはなかったから。
だから、優しくしないでほしい。笑顔を見せないでほしい。
好きだという気持ちを思い起こさせないで。
そう思った僕は、既に君に心を寄せている。』
「で、どこまで、聞いているんですか?今回のこと。」
「・・何の話?」
目の前で、僕の所属部署のリーダーである島本さんが、その顔を酒で赤く染めつつ、分かりやすく首を傾げた。
周りは、それぞれ自分たちの話しかしておらず、辺りに目を配っている様子もない。居酒屋なんてそんなものだ。彼女もそれが分かっているから、僕をここに連れてきたのだろう。
会社の片隅で話を聞かれるよりはよっぽどいいけど。
借りたかったのは、お酒の力か、それともこの話をしても誰にも聞かれないだろう雰囲気か。
会社に頼み込んで、今まであまり使っていなかった有給休暇を消化した。理由は、社長と部長にしか伝えていない。社員が50人もいない小さな会社だ。彼らが部下たちに、僕が休むことをどういう理由で話しているのかは知らない。流石にそのまま伝えてはいないだろうと思う。同僚が僕に対する態度は、休み前と全く変わっていなかったから。
ほとんど部署のメンバーで飲みに行くことはないのに、珍しく彼女から飲みに誘われた。しかも、同僚たち含めてではなく、俺しか誘われていなかった。それだけで、きっと彼女は僕が休んだ理由を知っていて、気遣ってか、それとも好奇心かで、その内容を聞きたいのだろうと思った。
好奇心で聞いてくるような、浅はかな人物ではないと思っていたが、プライベートでの付き合いはないので、僕の思い違いかもしれない。
「私は単に飲みたかっただけだよ。」
「お酒強くないですよね?」
「そうね。自分が飲むよりも、飲むのを見ている方が好き。」
ほら、飲んで飲んでと、彼女は俺にメニューを渡した。
僕は、メニューの中から、サワー系を選んで、注文した。あまり強いものを飲むと、早めに酔ってしまうだろうと思ったから。ここ最近は、あまり眠れていないので、酔いが早いし、スイッチが入ると記憶がなくなるまで飲んでしまう。だから、外で飲むのも控えていた。島本さんに迷惑をかけるわけにもいかないだろう。
「はい。かんぱーい。」
注文したレモンサワーが来たところで、今日何回目かの乾杯をする。自分が口をつけて飲むのを見た後に、彼女は全然減っていないモスコミュールに口を付けた。
「あの、気遣ってくれなくていいですよ。」
「気遣う?」
「何で、他の奴誘わなかったんですか?皆で飲んだ方が楽しいんじゃあ?」
彼女は、目を瞑って、うーん。と唸った。頬が上気していて、あぁ、島本さんは生きているんだな。と思った瞬間に、彼女は目を開いて、言った。
「聞かれたくないこともあるかなって、思ったから。」
「やっぱり、聞いてるんじゃないですか?」
「シフト組んでるのが、私だからね。」
「・・他の奴には話してないんですか?」
「身内に不幸があったってことになってる。」
身内。
僕はそれにすらなれなかったのに。
「休み明けても、会社には来てるけど、ミスが多いし、顔色も悪いし。」
「それは・・申し訳ありません。」
「いいよ。部長からしばらくはついて、フォローするように言われてるし。私も心配してるから。ちゃんと寝て、食べてる?随分痩せちゃったんだよ。」
「・・。」
島本さんは、僕の様子を見て、ため息をついた。この状況に困っているというよりも、何と話を進めていこうか迷っているようにも見えた。
「辛かったら、もう少し休んでもいいと思うけど。休んでも仕方ないとは思うし、シフトは何とかなるから。」
「何かしていた方が、気が紛れるんです。それに、これ以上休むと給与減らされるし。」
既に有給休暇はすべて消化した。これ以上休むと、その分は無給になってしまう。頼めば休ませてはくれるだろうが、実際今まで通りの毎日を過ごしていた方が、落ち着くと言えば落ち着く。あれこれ考えたり、思い出したりしなくて済むから。
1ヵ月前、自分の交際相手が、命を絶った。
彼女を見つけたのは自分だった。
その少し前から彼女と連絡が取れなくなった。心配に思って、彼女の家に行き、水を張った浴槽に、服を着たまま揺蕩っている彼女の姿を発見した。
大量の睡眠薬を服用し、おまけに手首を切っていた。
彼女の冷たい体を浴槽から何とか出して、抱きしめてからの記憶が、あまりない。
僕は何とか彼女の家族に連絡を取ったらしい。離れて暮らしていた彼女の家族が、彼女の遺体を引き取り、彼女の自宅も引き払っていった。ただ、交際していただけの僕は、何もできなかった。彼女の葬儀に出ることすら。僕は彼女の家族とも顔を合わせていなかったから、認知されていなかった。
何がいけなかった?
僕は彼女の不安定さに気づいてはいたが、そこまでとは正直思っていなかった。もちろん、仕事のこととかの愚痴は漏らしていた。将来の不安も。でも、笑って話していたし、僕らはまだ若いと思っていたし、深刻なものとは思っていなかった。
一番近くにいたのに、彼女は自分に何も語ってはくれていなかった。僕は彼女の思いに気づけなかった。僕は彼女のことをこの世界に留めることができなかった。
結局、彼女は何も残していかなかったから、彼女が何を悔いて、何が嫌で、命を絶ったのか、今でもはっきりしたことは分かっていないのだ。
僕は、死んでしまった彼女が、今でも好きだ。
例え、自分を置いて、この世界からいなくなったとしても。最後の最後まで、僕を信用しきれずに、自分の気持ちを吐露してくれなかったとしても。そのことに少なからずショックを受けていたとしても。これは運命の恋だと思っていたのが、自分一人だったと突き付けられたとしても。
黙って、手元のレモンサワーを飲んでいる自分を見ている島本さんが、眼差しに心配の色を載せながらも、声音は明るくしようと努めて、少し高めの声で告げる。
「まぁ、明日は休みだし、この場は私がおごるから。好きなもの飲んで、食べていいよ。」
「本当にいいんですか?」
「居酒屋で申し訳ないけど。」
「いえ、嬉しいです。ありがとうございます。」
僕が礼を言うと、彼女が安堵したように微笑む。
実を言うと、一人でいる時間を減らしたい。
本当は休みなく、働いていたいと思ったりする。会社には少なくとも人がいる。一人になることがない。
一人でいると、どうしても彼女のことを思い出してしまう。それも、最後に見た青白い目を閉じた顔を。冷たく硬直した握り返してくれなかった手を。
眠ったところで、浅いせいか、悪夢を見て、飛び起きる。飛び起きるくらいだから悪夢だろうと思っている。内容は全く覚えていないけれど。
島本さんに視線を向けると、顔を顰めながら、モスコミュールを飲んでいた。
このまま、酔いつぶれてくれないだろうかとも思う。
そうすれば、何かしら理由をつけ、一緒にいてくれるのではないだろうか。職場では何かしら目をかけてくれる彼女のことだ。今の自分が放っておいたら、消えてしまいかねない危うさを感じてくれていることだろう。
今、死んでしまった彼女のいるところを、他の者で上書きしてしまいたいと思う。こう思ってしまう自分は、やはり冷酷なんだろうか。
その後、よく回らない頭で、心配してくれる彼女を困らせてはいけないと思い直した。それに、心配といっても、同じ部署で、今の自分になった理由を知っているから、気になっているだけだろう。そこに、特別なものなんて、きっとないんだろう。
自分でも、自分の気持ちが不安定に揺れ動いていることを感じている。何かに縋ってしまいたい。その気持ちに抗うのは、とても困難だ。
「島本さん。」
「どうしたの?具合が悪くなったとか。」
「いえ、そうではなくてお願いが。」
「何?」
「僕と握手をしてくれませんか?」
「握手?いいけど。」
島本さんは、理由を聞かずに、自分の左手を、僕に向かって差し出した。白いが、指は短めで、指輪の嵌っていない、少し荒れた手。ネイルすらついていなかった。彼女の手はどうだっただろう?
僕は恐る恐る自分の左手を出して、その手を握った。
温かかった。
島本さんが、自分の顔を見てハッと息を呑み、その顔を泣きそうに歪めた。
「我慢しなくていいと思うよ。」
その言葉と共に彼女の温かさが、心にしみわたるのを感じる。
僕は、唇を噛みしめて、何度も頷いた。
繋いだ手をどうしても離すことができなかった。
終
運命の恋というものをしたことがありません。恋愛小説を書いている身ではあるのですが。だからこそ、創作できるのかもしれません。
私の創作物を読んでくださったり、スキやコメントをくだされば嬉しいです。
