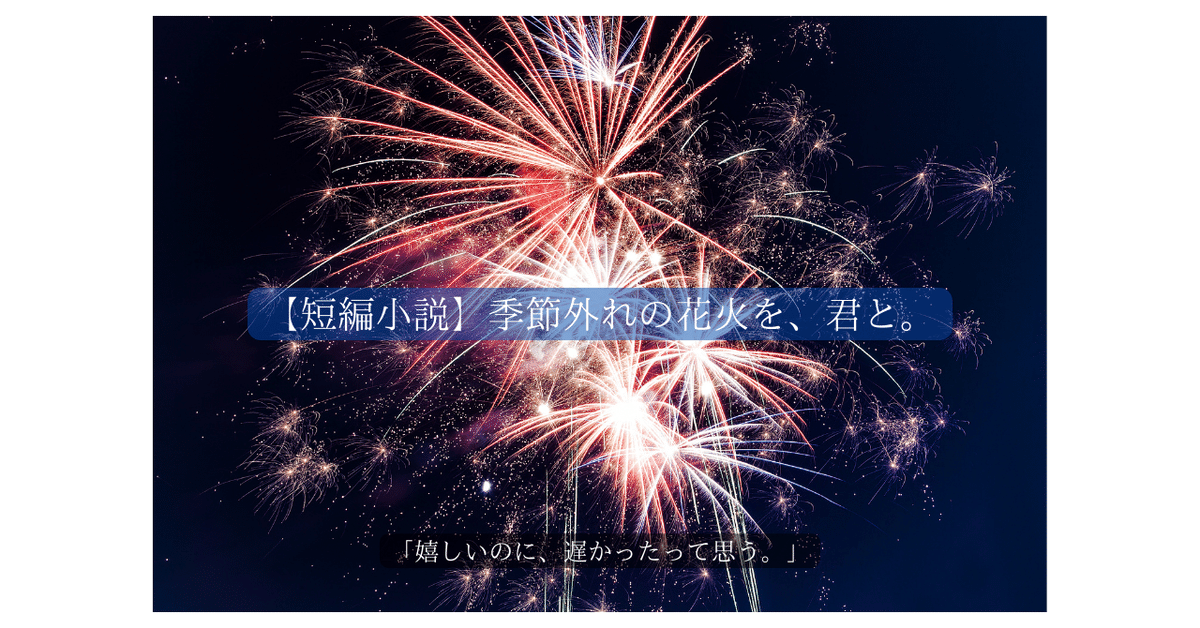
【短編小説】季節外れの花火を、君と。
妻が出産のため、実家に里帰りをすることになった。3ヶ月くらい。
妻の実家はかなり遠く、土日の休みの度に、俺がそちらに向かうのも無理な話だった。だが、出産には立ち会ったし、その前後は有休を使って、彼女の実家に一時的に滞在させてもらった。
産まれたのは、男の子だった。自分に似ていると、妻が相好を崩して言ってくれた。役所への出生届などは、自分が提出し、会社への報告なども終わってしまうと、途端にやることがなくなった。妻とも、毎日連絡は取り合っているが、お義母さんと連携して、うまくやれているようだ。月に一度は、妻の実家に行く話になっているが、それ以外は、久しぶりの一人暮らしを謳歌することとなった。
自分一人のために食事を作ったり、家の掃除をするのは、意外と面倒くさいものだと気づいた。掃除機をかける回数も減り、食事は近くのスーパーで、総菜を買って済ますことが増えた。妻がいたら、怒られただろうが、彼女が帰ってくる前に、掃除をしておけば分からないだろう。
そんな折、自分も久しぶりに実家に帰ることになった。自分の両親は、まだ俺の子どもには会えていない。代わりに、出産時に撮った動画や写真を見せようと思った。妻からも無事出産した旨、伝えてくるよう言われているし、彼女が戻ってきて落ち着いたら、また子を連れて行かなくてはならないだろうが、それを待っては日が経ってしまうからだ。
実家に連絡を取って、今週末の土日に帰る旨を伝えたところ、その日は祭りがあるから、駅前が混むかもと告げられた。祭りがあるのは、通常8月だ。なぜ、11月の今頃と疑問に思い、ネットで確認したところ、8月の祭りが例の感染症で延期となり、11月に開催されることになったらしい。それも、今週末の土日だった。
妻がいたら、一緒に駅近くの出店等を回ったのだろうが、一人で回っても仕方ない。土曜の夜には、花火大会も開催されるが、現地に一人で行ってみるのもどうかと思う。両親は既に高齢だから、人混みの中に行こうとは思わないだろう。一緒に行く自分も心配になる。連絡を取る地元の友達もいない。
幸い、花火は自宅近くからでも見られるだろう。地元の花火を見るのは何年ぶりだろうか。意図せずとも自分の心は高鳴った。
幸い、今週末は天気が良くなった。妻に実家に帰る旨と、祭りと花火大会が開催される旨を伝えたら、とても残念がられ、代わりに動画か写真を撮ってほしいとせがまれた。向こうでご両親と共にそれを見ると言っていた。
花火を綺麗に撮るのは、難しそうだが、妻たちが喜んでくれるならと、了承した。
早めに地元の最寄り駅に着くようにしたので、駅前は思っていたほど混んではいなかった。また、出店は花火大会が開催される川沿いに集中している。自分の実家がある方は、それとは逆方面になるので、人通りもそれほど激しくない。実家では、家族が以前と変わらない様子で迎えてくれた。妻や子を撮影した動画などを見せて話をする内に、時間はあっという間に過ぎていった。
花火を撮影するところは予め決めていた。人通りが少なく、実家から近い、それも川にかかる橋の上だ。川があるから、目の前が開けており、住宅の明かりも少ないからだ。ただ、同じように考える人はそれなりにいて、橋の上や川沿いは、花火を見ようとする人が大勢いた。日が暮れると寒いくらいなのに、浴衣の上にコートを着ている人もいる。浴衣の下に、なにか着こんでいるのだろうか?
人々の隙間に入り込んで、カメラを取り出そうとしていると、隣から声をかけられた。
「石井くん?だよね。」
声をかけてきたのは、自分と同じくらいの年齢と思われる女性だった。明るい青の薄手のコートを着て、手にはカメラを持っている。顔はマスクをしていて、上半分しか見えていない。多分、知り合いだと思うが、はっきりしなかった。自分の様子を見て、分かっていないと思ったのか、彼女は苦笑して言った。
「・・原口聖だよ。中学の時、同じクラスだったし、石井くんの家にも遊びに行ったことあるんだけど。」
「原口?マジで?久しぶりだなぁ。」
「石井くん。全然変わってないね。」
「ん?でも、原口、結婚したって聞いたけど。なんで、ここにいるの?」
「今日は一人で実家に帰ってきてるの。そしたら、今日に夏祭りが延期されたって聞いて、花火の写真を撮ろうかと、ここまで来てるってわけ。」
まだ、花火が打ち上げられるまで時間がある。自分たちは、その場で近況報告や思い出話をし始めた。自分の事情を話すと、彼女は納得したように頷いた。
「石井くん。随分年下の人と結婚したんだね。結婚・出産おめでとう。」
「まぁ、出産は俺がしたわけじゃないけど。」
「ちゃんと奥さんを支えてあげないとダメだよ。働いてお金を落とすだけじゃダメ。家事や育児にも手を出してね。」
なぜか、得意げに言う彼女に、俺は笑ってしまう。その俺の様子を見て、彼女はちょっと不満げな様子をした。
「これに関しては、私の方が先輩なんだから、ちゃんと聞いて。」
「そうだな。旦那や子どもは元気なの?」
「元気だよ。今頃、子どもが習い事している頃かな。旦那さんはそれに付き添ってると思う。」
「こんな時間に習い事?」
「そう。スイミング。送り迎えをして、買い物もして帰るのが、通常の土曜日。」
彼女はフフッと笑って、こちらを見た。目が緩く弧を描いている。そう、彼女はこういう笑い方をする子だった。
「今日は石井くんに会えるなんて、特別な土曜日になりそう。」
「俺にとっても、今日は特別な土曜日だと思う。」
「・・・やっぱり、石井くんは全然変わってないね。」
「そんなに変わってない?」
「簡単に『特別』なんて、言ってはいけないんだよ。」
「・・・先にそっちが特別って言ったんだろ?」
「私は、意識して言ってるからいいの。でもね。中学の時に思ってたんだよ。石井くんと夏祭りの花火を一緒に見たいなって。」
「・・・・。」
「まさか、こんなに時間が経って、願いが叶うとは思ってなかった。」
彼女の言葉の語尾が湿った。彼女の表情を見ると、笑おうとして失敗しているような顔になっていた。目尻の雫が光る。
「嬉しいのに、遅かったって思う。」
俺は彼女に向かって、手を伸ばした。彼女の体を引き寄せて、その背中を、リズムをつけて叩く。少しは彼女が落ち着けばいいと思って。
「石井くん。」
自分の腕の中で彼女のくぐもった声がする。
「もうすぐ花火が始まる。写真か動画撮って、家族に見せるんだろ?」
「・・・うん。」
「泣いてたら、うまく撮れなくなる。ただでさえ、花火は取るのが難しいのに。」
「そうだね。」
「俺も、原口に会えて嬉しかった。こうして一緒に花火が見れて、よかったと思ってる。」
腕の中で、彼女が大きく首を縦に振った。
辺りがざわつき始めた。俺たちを見てではなく、もうすぐ花火が始まるからだ。俺は彼女の背中を叩くのを止め、彼女の顔を覗き込んだ。涙は引いていたが、その瞳は揺らめいている。中学の時の彼女の面影が重なった。なんだ。君も全然変わってない。
マスクの上から、彼女の左頬に手を当てて、自分の顔を近づけた。やはり、マスク越しの感覚はよく分からなかったけど、それがお互いの今の状況を守っているかのようだった。お互いの状況を分かっていて、でも、過去の思い出に引きずられて、ふと湧き上がったこの思い。きっと、長くは続かない。この花火が終わる頃には、俺たちは今まで通りの日常に戻る。
顔を離したら、彼女がこちらを責めるような目で見つめた。
「石井くん。」
「・・・特別な日ってことで。」
「一生抱える秘密ができてしまった。」
「俺も、この秘密は墓場まで持っていく。」
口の前に人差し指を立てると、彼女がそれを見て、視線を柔らかく崩した。
終
突然ですが、明日・明後日と実家に帰省します。地元で通常、夏に開催されるお祭りが、今週末に延期になったと聞かされ、この短編を書きました。
これで、私の地元がどこか?探せば分かります。お祭りと重なったのは全くの偶然。
ということで、帰省中はつぶやきになると思います。ご了承ください。もし、綺麗な花火の写真が撮れたら、合わせて投稿しますね。
サポートしてくださると、創作を続けるモチベーションとなります。また、他の創作物を読んでくださったり、スキやコメントをくだされば嬉しいです。
