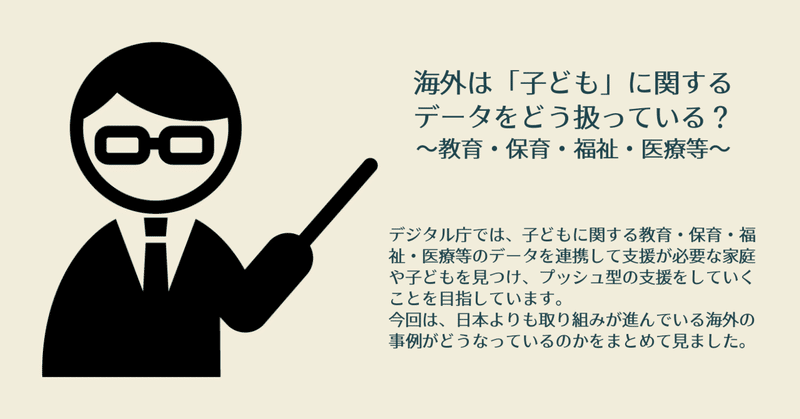
海外は「子ども」に関するデータをどう扱っている?〜教育・保育・福祉・医療等〜
2021年9月にデジタル庁が創設され、「こども」に関する情報・データを連携していくための検討プロジェクトチーム(こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム)が組織されています。
各所に分散している教育・保育・福祉・医療等のデータを連携し、支援が必要な家庭や子どもを見つけ、プッシュ型の支援をしていくことを目指しています。
データを連携するといっても、留意点は多くあります。
会議メンバーの赤池内閣府副大臣は、「教育や福祉をはじめとする情報は、まさに国民、住民のプライバシーの塊であるため、個人情報保護法令の整合性だけでなく、国民の意識に沿った慎重な検討が必要」と述べています。
赤池氏副大臣からの発言からもわかる通り、国は慎重な姿勢を示しており、「国が一元的にこどもの情報を管理するデータベースを構築するわけではない」としています。
とはいえ、各種データを必要に応じてスムーズに閲覧できる、または活用できるシステムの構築が進められていくことを目指しています。この難しい課題を解決するために、協力自治体と連携して先行事例を作ったり、海外の先行事例を調査するなどの取り組みが進められています。
詳しくは、以下の記事で紹介しています。
今回は、このプロジェクトチームでまとめられた海外の先行事例についてまとめました。
1.イギリスの事例
イギリスでは、2002年より日本の文科省にあたる英国教育省管轄のもと「全国児童生徒データベース」(NPD)というシステムを整備しています。
【データ取得の目的】
公費維持学校(日本の公立学校にあたる)に通う子どもの教育プロファイルの作成を目的として開発されました。
現在は、予算配分、学校評価、政策立案、調査研究等を目的として活用されており、調査研究の目的しようされる場合は、取得データと外部データとの紐付けも想定されています。
【取得データの項目】
イギリスでは、2,700項目データ項目を以下の4分類で整理しています。
①基本属性(年齢・特別な教育的ニーズ・言語・家族・ジェンダー等)
②到達度(学習成果、個別学習者記録等)
③欠席と停退学(欠席状況、停退学の理由等)
④支援を必要とする子ども及び社会的養護を受けている子ども(社会福祉サービスの支援記録等)
【データ取得の方法】
児童生徒の個票データは、日本でいう公立の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校で収集し、「学校国勢調査」「特別指導施設調査」等の調査を通じて、定期的に教育省に送付しています。
全国児童生徒データベース(NPD)データは、個人が特定されない「レファレンス番号」で登録されることで、複数データの紐づけや経年変化分析が可能になっています。
【個人情報への配慮】
「データ共有承認委員会」という組織を設置し、個票データ共有の適切性や 倫理性を監督しています。また、データ管理者からは独立した「情報コミッショナー」がデータ保護法制の遵守状況を監査しています。
2.デンマークの事例
デンマークでは、内務省傘下のデンマーク統計局により国民一人一人に個人番号(CPR番号)が割り当てられ、様々な国民生活において活用されています。CPR番号に紐づいて様々な行政分野においてさまざまな「レジスター」(行政記録の集合体)が構築され、教育レジスターという分類も用意されています。
【取得データ項目】
●中央人口レジスター
氏名、住所、CPR番号、生年月日、出生地、 移民記録及び国籍、家族の情報等
●教育レジスター
①児童生徒レジスター
②国民教育レジスター
③学習成果レジスター
④成人教育・障害訓練レジスター
教育レジスターは、個人の時系列的な就学記録・教育機関レベルのデータと、各児童生徒の個人データの接続を実施しています。
【データの利活用例】
統計局の協力のもと、子ども教育省では、教育の質の向上を目指す教育機関 や地方自治体の取組を支援するための教育データウェアハウス(データを集約する倉庫のようなシステム)を開発しています。
また、大学・研究機関が調査研究を実施し、中退学予防などの教育課題の解決に役立てています。
【個人情報への配慮】
EU(欧州統計に関するEU規則)とデンマークの各法律に基づきデータ保護とプライバシー保護を徹底しています。
3.アメリカ・フロリダ州
アメリカのフロリダ州では、1980年代以降、州教育局の各部門および、各学校や学区が経営判断を行うために必要な情報を収集するシステムとして、「児童生徒情報システム」と「教職員情報システム 」を整備しており、アメリカ連邦の中でも統合的な教育情報システムを構築しています。
【目的】
フロリダ州は、州内の各学校のパフォーマンスを評価し、年次報告書を作成するために教育データを収集しています。また、課題やニーズを特定し、州・学区・学校レベルの短期・長期計画の策定に利用するなど、政策形成の基盤としています。
【取得データ項目】
●児童生徒情報システム:必須データ項目が412項目(以下、詳細)
●教職員情報システム:必須データ項目が93項目(給与計算、専門能力開発、基本的な人事記録等)

教育データ項目に関連した調査研究の実施状況(文部科学省説明資料)より
【データの取得方法】
データは、州教育局が、学校に対し定期的に実施する調査を通じて取得しています。各児童生徒及び教職員に固有のIDが割り当てられ、キャリア全体を通じて一貫して使用されています。
【データの利活用例】
データは、州教育局が学区や特定地域、人種ごとに、卒業率、出席及び在籍状況、中退率等を整理した報告書を発行し、教育機関の予算組みや教育政策立案に役立てています。
また、一般に利用可能な匿名化されたデータは、教育局が運営するデータウェアハウス上で公開もされています。
【個人情報への配慮】
州法及び連邦法により、個人特定記録の開示は教育機関又は研究組織での特定の研究目的に限定されています。
【アメリカ連邦政府としての取り組み】
フロリダ州だけにとどまらず、アメリカ連邦政府としても教育データの管理・活用などができるようにサポートを行なっています。
①州全域での時系列データシステム(SLDS)補助金プログラム
各州が教育データを正確に管理、分析、利用できるよう支援することを目的とした補助金プログラムです。ウィスコンシン州の教育データを活用した指導支援アプリの開発や、ミネソタ州の時系列教育データシステムの開発など、さまざまな案件で活用されています。
プログラムが創設された2006年から2020年4月までの間に、55の受領者に対し、合わせて8億2,600万ドルの補助金が配分されています。
②共通教育データ標準(CEDS)
教育セクターを構成する様々な機関において用いられているデータの解釈を統一し、データ活用の効率化を進めることを目的とする教育データ標準化プロジェクトです。
日本においても同様のプロジェクトが文科省を中心に進められています。
③全米教育統計フォーラム
初等・中等教育データの品質や利便性を向上させ、活用を広げるための成功事例等を共有する自主的活動の場を用意しています。
連邦教育省の教育データに関わる部署に加え、全米50州、海外領土・自治領及びコロンビア特別区政府や各自治体の教育行政部門及びその他の教育を管轄する部門、初等・中等教育のデータに関連する活動を行う全米規模の団体等が参加しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
