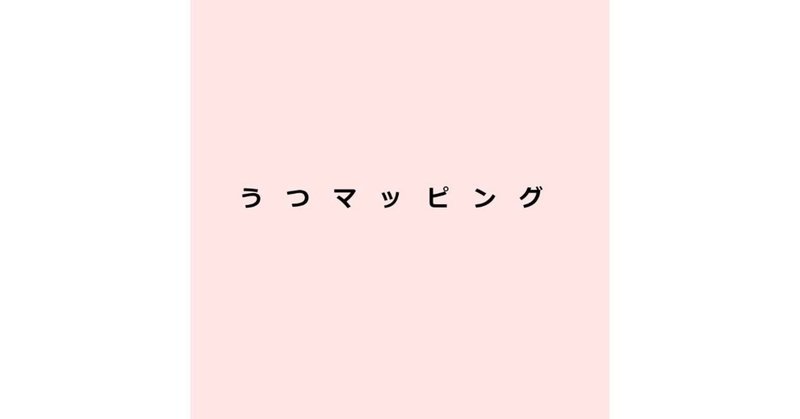
書籍部 (うつマッピング解説 その3)
リンク
書籍部
愛着障害・アダルトチルドレン 克服記録
ADHD 克服記録
前回はこちら
書籍部 (うつマッピング解説 その2)
6. 感情軸 (表層⇔深層)

さて、だんだん話が深くなってきました。
次は、感情軸です。
精神の病…。
これをどう捉えるかは、立場によりまちまちでしょう。
ビジネスマンは、「気の持ちよう」
世間は「メンタル弱い残念な人」
行政は「支援が必要な人」
脳神経科の医師は「神経科学・脳科学的に異常をきたした人」
精神科医は「完治の見込みが危うい精神異常者」
怪しいメルマガは「いい金づる」
怪しいセミナーは「いいカモ」
怪しい教祖は「収入源」
…こんなんで、いいんすか?
僕はいやですよ。
(上の中で、好意的に捉えてる人がいないのがうける笑)
わかりやすいように、「時間軸×感情軸」の図も加えて置きます。

― ― ― ― ― ―
① 表層
そもそも、私達人間の内側って、「1つ」しかないんでしょうか?
こうゆう、哲学的な問いから、話を始めてみます。

改めて、同じ図。
こういった時、人はわかりやすいように、二元論を使います。
「頭と身体」
「頭と心」
「理性と感情」
「意識と無意識」
「表層心理と深層心理」
「顕在意識と潜在意識」
私達の内部の動きとしては、大きく「考える = 思考」と「感じる = 感情」に分けることができます。
脳科学は勉強中なんで、触れずにいきます。
(知識を身に着けたら書きまーす)
(あと、おそらくこの内部の構造に異常をきたし、人格を乖離させることで、解離性障害 = 二重人格や多重人格、心理的未発達、健忘などを引き起こすのでしょう)
私達にコントロール可能なのは、思考だけです。
それも、意識的に認識できる「顕在的な思考」だけ。
これを司るものが、「理性」と呼ばれるものです。
何が合理的なのか?
物事の順番は?優先順位は?
これはどうゆう仕組みなんだろう?
こうゆう理屈で動いてるんだ。
脳内に「顕在」と「潜在」があるように、身体にも「顕」と「潜」があります。
筋肉を動かす、床に着いて眠りにつく、ものを食べる…
これは「顕在的」な動き。
でも、筋肉の傷を修復する、心臓を動かす、寝てる間に脳や臓器の疲労を癒やす、食べ物を消化する…
これは、意識的にコントロールすることができない「潜在的」な動き。
(我々ができることは、規則正しい生活を工夫して潜在的動きのサポートをする、が限界です)
僕がうつ病克服の「表層」として挙げたのは、これらの「顕在的」なものたち。
本質的に克服するには、「潜在的」部分にアプローチしていきます。
(ほっしーさんの本では、潜在意識は軽く流されていました。でも、ここが本質です)
― ― ― ― ― ―
② 中間層

・長期的な目標を立てるには、潜在的・深層的意識の理解なくしては不可能です。
・抗うつ薬は脳内の神経伝達の動きのコントロールをサポートしています。つまり、自分の意思ではできない部分を肩代わりしてもらっているわけです。
・本質的に認知を改善するには、潜在的・深層的部分まで改善する必要があります。
・こういった先人の知恵を得るには、読書をして勉強する必要があります。
― ― ― ― ― ―
③ 深層
③-1. 理解者の存在
あなたには、理解者がいるでしょうか?
いるなら、その人はどれほど深層的な部分を理解しているでしょうか?
結局、理解者ってのは、オプションなんです。
たとえ、どれだけ深ーく理解してくれる人がいるとしても。
当の本人が到達している深層より深い部分に、他人がアプローチできるわけないんです。
③-2. 自己理解
これは、過去軸とも合わせて考える必要があるのですが…
自分の過去を、どこまで客観的に、同時に主観的に捉えられるか?
・今の自分
・苦しみに気づいた自分
・会社・家庭・人間関係でつまづいた自分
・成長した子供を育てる自分
・会社・病院・役所…で昇進する自分
・結婚・出産・育児をする自分
・パートナーに出会った自分
・仕事を始めた自分
・学校を卒業した自分
・バイトをがんばる自分
・部活やサークルを頑張る自分
・友達と遊ぶ自分
・中学生の自分
・小学生の自分
・幼稚園・保育園の自分
・自分の父・母・家族の中における自分
・幼児期の母と自分
・乳児期の母と自分
・この世に生を受けた自分
客観的視点は、事実関係や、自分と他人の間の事実誤認の溝を埋めるのが重要です。
この、事実誤認の溝は、認知行動療法にも通ずるところ。
でもね、客観的視点は、あくまでスタートの足場を固める材料に過ぎません。
本質は、それぞれの場面、場面における、「自分の意志」です。
・嫌な経験をした、その積み重ねがうつ病を引き起こしている。
・うつ病発症の直前までのさまざまな場面で、自分の意志 = 感情や欲求を抹殺し続けてきた。そのツケがうつ病発症のトリガーであり、うつ病という病理状態となるわけです。
・そのトリガーに至るのは一朝一夕の感情抹殺ではなく、かなり小さなころからの積み重ねです。
これが…
・学校や職場における「いじめ」に起因する人
・衝撃的な出来事に遭遇した人 (災害・性的被害・心的外傷)
・幼児期の親子関係・養育環境に起因する人 (アダルトチルドレン)
・乳児期の母子関係に起因する人 (愛着障害)
という話になっていきます。
細かくは僕の note にまとめてありますがね。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7. 独力軸
こうゆう、自分自身の、極めてコアな部分へのアプローチは、独力でしかできません。
これが最後の、独力軸、です。
いかに良き理解者がいようと、お金が潤沢にあろうと、自分の深層へのアプローチは他人には不可能です。
自分の本質・在り方と向き合うことから逃げ続けるか?
自分を取り戻し、蘇生させて、立ち直るか?
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8. 最後に
3回にわたって、ほっしーさんの「うつマッピング」の解説を述べてきました。
こういったメカニズムを考えると、「うつ病などの精神疾患を薬で完治しよう」というアプローチ自体が、なんにもわかってないなぁと思わざるを得ません。
そもそも、対症療法ではなく、根本治療に向けた薬というものは、生体がもつ「自己修復能力」をサポートするものです。
抗生物質や真菌薬は感染した生物の細胞活動を弱めて免疫系による排除を促す。
抗がん剤も、従来のものはがん細胞の活動を正常な細胞を道連れにして弱めて、免疫系や自己細胞死による排除を促す。
でも、精神疾患の薬ってのは、対症療法にすぎない。
根本的治療薬の開発も試みられているのでしょうが、それは脳内の神経活動の本質を人間が解明しきらない限りは無理でしょう。
だから、自分の身体がもつ、修復能力をいかに取り戻すか、です。
この深層へのアプローチと精神の在り方の改善ってのは、精神疾患の自己修復能力を取り戻す方法として、今後スタンダードになっていくと僕は自負しています。
(だって論理的に考えて、"そりゃそうだよね~" って話じゃないですか?)
まぁ、がんばってね~
おわりンゴ!
サポートの目安はアサヒ・ザ・リッチ1本文です。
