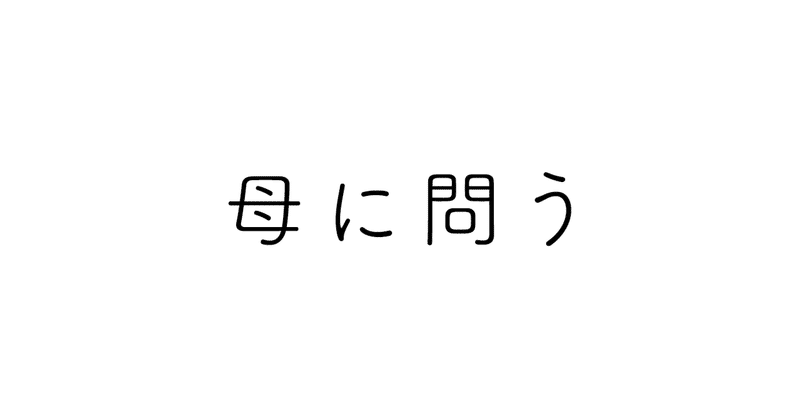
「このままテレビを見続ける人生でいいの?」
「何かやりたいことはないの?」
正月のこと。
母と鍋をつつきながら、母の人生について問いかけていた。
なんとなくだが、母が生きる道標みたいなことを見失っているように感じていた。心にぽっかり穴が空いているとまではいかないが、隙間から生気が抜けていっているような、覇気のない佇まいと丸まった背中が気になっていた。残りの命を確かめているようにも思えた。
ぼくが介護の仕事をするようになって、よりそうなってしまったかも知れない。というのは、家で母とぼくの会話が、必然的に介護の話題になってしっまっていたからだ。ぼくから切り出す話題が介護の話ばかりだった。
「認知症の利用者さんがいてさ、排便がひどくてお尻グチャグチャ」
「しっかり運動している方は、やっぱり頭もしっかりしてるわ」
「お尻の褥瘡がなおらなくてさ、ほおっておくと椅子に座れなくなるから心配だわ」
他人のこと。母には無関係なことだ。いやそんなことはない。高齢者という括りではダイレクトに母に関係している。ぼくは無神経さを装い、確信犯的に母に警鐘を鳴らしていたのだ。
「足腰が弱らないように、毎日散歩してね」
「ボケないように、趣味を見つけてね」
「太らないように、食事に気をつけてね」
こうしたストレートな言葉は反発を生む。本人の意思を無視した一方的な、ぼくの押し付けでしかないから。押し付けたら当然、跳ね返ってくる。以前、そうしたことで空気が悪くなった経緯もあった。
だからといって、回りくどく介護の話題を持ち出すのも愚策。
そうして正月、万策尽きたぼくは、母と鍋をつつきながら「生き方」について問うてみたのだ。
母は、少し黙ってしまった。
母の日常は突っ込まれることも落ち度もない。べつに昼に水戸黄門の再放送を見ようが、夜に海外の衝撃映像を見ようがいいじゃないか。でも、テレビを見ている後ろ姿が、息子にはどうも虚しく見えてしょうがなかったのよ。
お前は何様なのだ。わたしの人生に口出しするな。無礼者。
そう思っていたかどうかはわからない。正月から数日後、母は黙々と家の不用品を整理し始めた。
「わたしね、己書(おのれしょ)やってみようと思う。前から興味あったの」「今度ね、近くで作品展あるから観に行ってみる」
パッと目が覚めたように、母はぼくに真っ赤に生きる宣言を告げた。
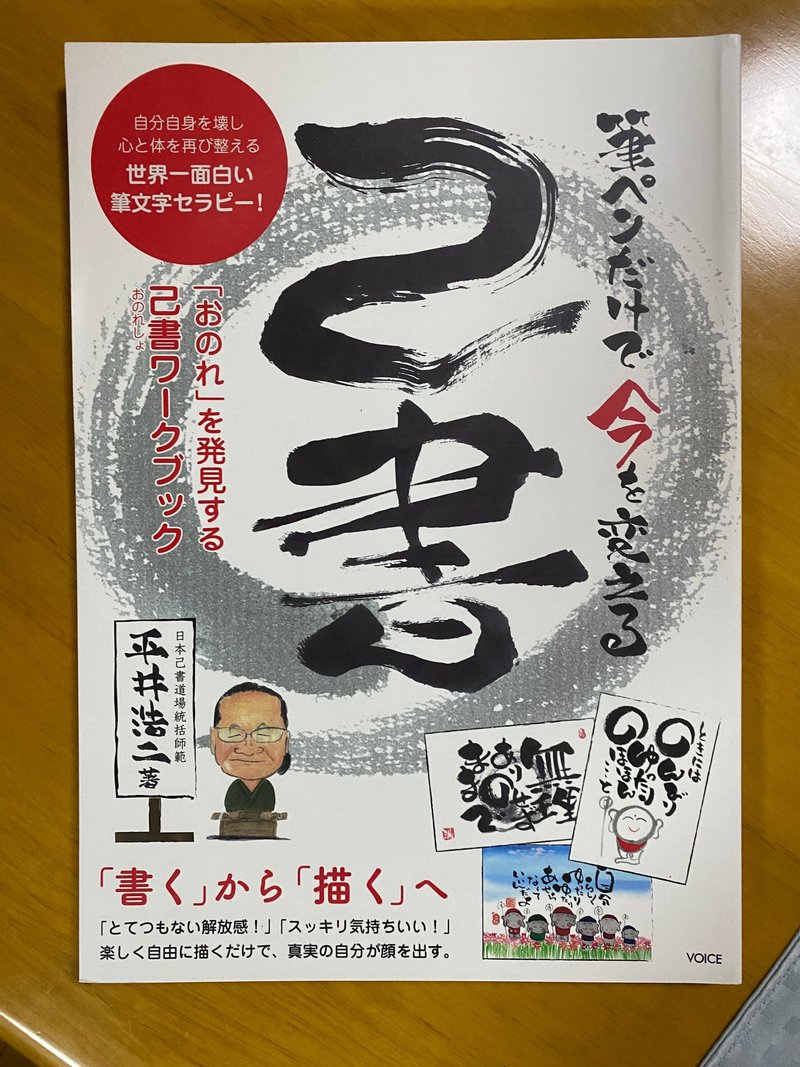
介護は大変。介護職はキツイ。そんなネガティブなイメージを覆したいと思っています。介護職は人間的成長ができるクリエイティブで素晴らしい仕事です。家族介護者の方も支援していけるように、この活動を応援してください!よろしくお願いいたします。
