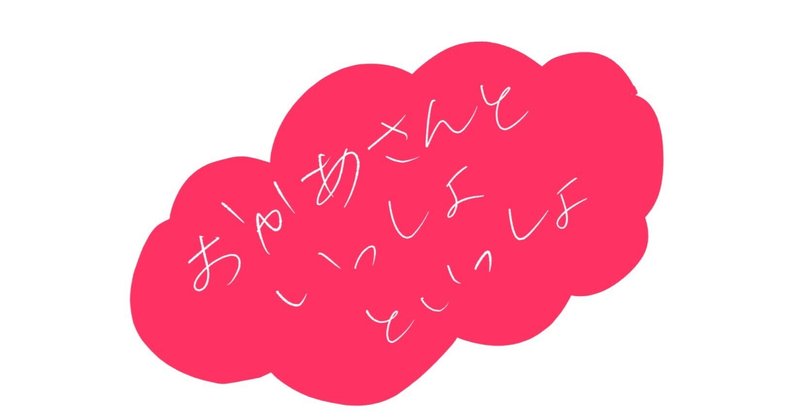
♪こねこのパンやさん(「おかあさんといっしょ」1987年4月)
今回は、「こねこのパンやさん」。
こどもと「おかあさんといっしょ」を見るようになって、「わー!この曲なつかしー!」と(こどもが真顔で見ている横で)ひとり興奮することが多いのですが。
「こねこのパンやさん」は、そんな個人的「懐メロ」のうちの1曲。
調べたらなんと、1987年4月のうた、なのだそうですよ。
なるほどなるほど。
80年代、まさにこどもとして「おかあさんといっしょ」を見ていた私には、それはそれは懐かしいはず。
(じゃじゃまる・ぴっころ・ぽろり世代です。)
作詞は冬杜花代子さん、作曲は林アキラさん。
(こどもとして聴いていた頃には知りませんでしたが、)林アキラさんは、元うたのお兄さんで、ほかにもいろんな曲を手がけていらっしゃいます。
「♪まあるい おおきな わがあれば…」の歌い出しの、「おおきなわがあれば」も林アキラさんの作品。
最近でも、かなり頻繁に流れていますね。
お兄さん・お姉さんたちによる、フラフープをつかったさまざまなパフォーマンスとともに、受け継がれている曲です。
あと、コロナ禍に何度か放送された「スタジオライブ」では、ゆういちろうお兄さん&あつこお姉さんと、ピアノで共演されていたのも、印象的でした。
さてさて、少し話がそれました。
「こねこのパンやさん」、まずメロディにかんして探ってみると、とても親しみやすい一方、歌うにはとても難しい曲。
というのは、音の跳躍がわりとあるので、きちんと歌おうとすると、なかなかハードなのです。
出だしから、ぴょんと上がって、下がって…の繰り返し。
極めつけは最後の「(低音)こねこねこ、こねこねこ…(オクターブ上がって↺)こねこねこ、ねーこ!」。
(テキストで表現するのにはやはり限界が…。)
と、たしかに歌うのは難しいのですが、曲全体に散りばめられた、こうした音の跳躍によって、
こねこのパンやさんの、「ガチャガチャ感」が見事に表現されています。
もし、仮にですが、メロディーがなめらかに繋がったものだったとしたら?
ちょっと想像してみると、きっともっと落ち着いた雰囲気になり、少なくとも、ここまでの「ガチャガチャ感」は感じられないのでは…。
こねこのパンやさんのキャラクターも、だいぶ違ってくるでしょうね。
そしてそして、この曲で忘れてはいけないのは、やはり歌詞のユニークさ。
まず、この曲のベースにあるのは、「こねこ」と「(こねこね)こねる」、近しい響きで最大限に遊んでいる、とても楽しいことば遊び。
こういったことば遊び、爽快だし、耳に残りますよね。
「こねこねこ、こねこねこ…」と聴いているうちに、「こねこ」なのか「こね」ているのか、何だかわからなくなる感覚。
パンやさんの、あの独特なキャラクターをつくりあげるのに、すごく効果をあげているのではないでしょうか。
それから、こねこのパンやさんが、パンにまぜているものが、なかなか強烈。
「にぼしに かつおぶし ちくわに チキン」…思わず「ええっ?」と二度見ならぬ二度聴きしてしまいます。
(ちなみに私はずっと「ちくわに チーズ」だと思いこんでいました。)
たしかに好きなもの、入れたいよねー、気持ちはわかる!と言いたいところですが…。
(イロイロ入れて、焼くこと忘れて一心不乱にこねているパンやさん、かわいすぎるよ…。)
「にぼし」と「かつおぶし」の語尾の「し」、
「ちくわ」と「チキン」の語頭の「ち」、が韻を踏んでいるところも、とてもいいアクセントになっています。
こういう韻があると、歌っていても、より楽しいもの。
細かいところもよく練られていて、もうさすがとしか言いようがありません。
ちなみに、私は一番の歌詞に出てくる、「メリケンこ」(小麦粉)の部分も好き。
なんというか、すごく時代が感じられるから、なのですが。
そういえば、小さい頃におばあちゃんの台所のお手伝いをしたとき、おばあちゃんも「メリケン粉」って言ってたような…
などと思い出して、ノスタルジックな気持ちになるのです。
…と、そんな昭和の時代にうまれた、「おかあさんといっしょ」の名曲でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
