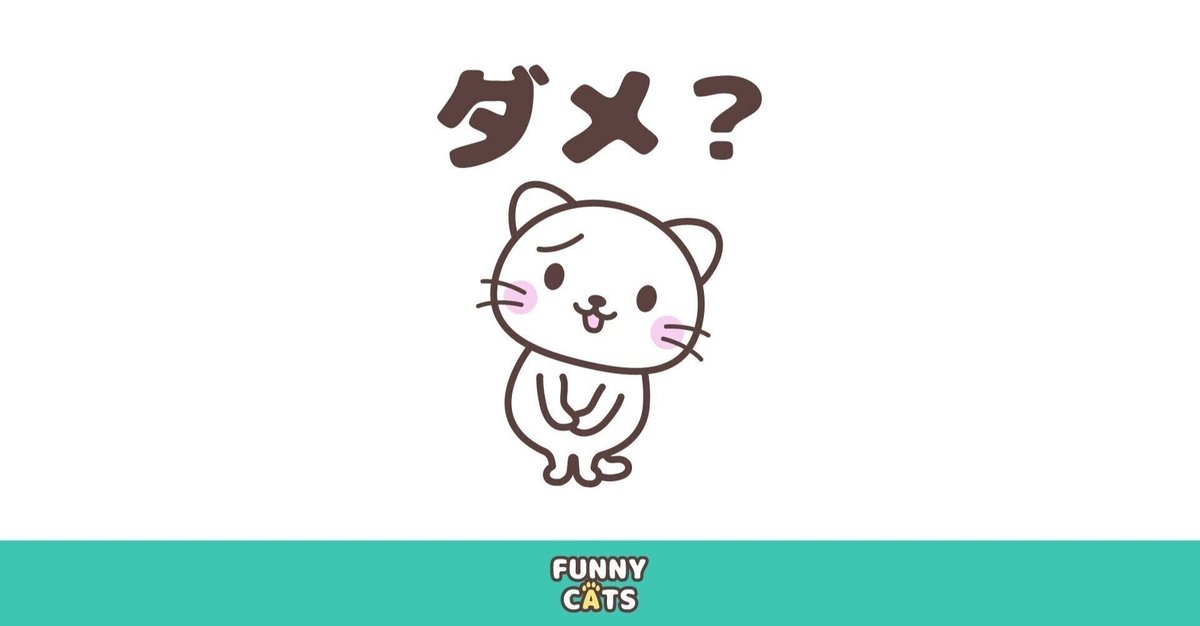
お願い、彼の好きにさせて!
ほんの感想です。 No.36 志賀直哉作「清兵衛と瓢箪」大正2年(1913年)発表
なぜ、志賀直哉の「清兵衛と瓢箪」を今まで読んでいなかったのか? いえいえ、そうではなく、最近の、志賀直哉作品の読書体験で、ようやく、「清兵衛と瓢箪」の面白さがわかるようになったのでした。
清兵衛という十二歳の少年のある熱中が、大人の無理解から阻まれる、という物語です。清兵衛にはつらい話ですが、妙に笑える失敗談も含め、瓢箪に夢中な彼の日常が、とても楽しい。
文庫版で8頁という短い作品ですが、ユーモアを交えた物語の中に、作者のメッセージを考えてしまった作品でした。
―・―・―・―・―・―
ここで、物語の重要アイテムである瓢箪について、説明させてください。瓢箪は、ウリ科の蔓性一年草で、ユウガオの変種です。中身をくり抜いて乾燥させて容器として使い、水や酒などの液体、あるいは穀物を入れていました。「清兵衛と瓢箪」を読むと、この乾燥させた瓢箪の愛好家がいて、大きさや形、そして表面の美しさにこだわったことが察せられます。
物語では、清兵衛が、好みの瓢箪を作るため、いつも、頭の中を瓢箪で一杯にして、瓢箪に関わっている様子が描かれています。それは、例えば、次のように描かれています。
清兵衛が時々瓢箪を買ってくる事は両親も知っていた。三、四銭から十五銭位までの皮つきの瓢箪を十ほども持っていたろう。彼はその口を切る事も種を出す事も独りで上手にやった。栓も自分で作った。最初茶渋で臭味をぬくと、それから父の飲みあました酒を貯えておいて、それでしきりに磨いていた。
これに対し、父親や教師は、「こんなことをしている者には、到底将来は見込めない」と言う理由で、清兵衛の熱中を否定し、瓢箪を破壊します。父が玄能(げんのう)で、一つひとつ瓢箪を壊すのを、清兵衛は、ただ青くなって黙って見ているしかありませんでした。
―・―・―・―・―・―
この作品で興味深かったのは、清兵衛の父が、瓢箪に対する保守的な美意識の持ち主であることです。清兵衛の瓢箪は、父の美意識に適わず、父は、「ほんの子どもに過ぎない息子に、瓢箪が分かるわけがない」と思っています。そして、自分には理解できない美意識に膨大なエネルギーを費やす清兵衛を否定したのです。
志賀直哉の作品中に「父と子が理解し合えない」という設定を見つけると、志賀直哉の実体験を連想するせいか、「この設定で伝えたい何かがあるのでは?」と、探ってみたくなります。終盤に感じた嬉しさから、次のような、志賀直哉からのメッセージを想像してみました。
どれほど父に否定されても、それに負けず、自分の美意識を信じることができたのは、自分が、「小説を書く」ことに熱中できたから。だから、みんなも、負けるな!
ここまで、読んでくださり、どうもありがとうございました。
*志賀直哉作品に関する過去記事です。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
