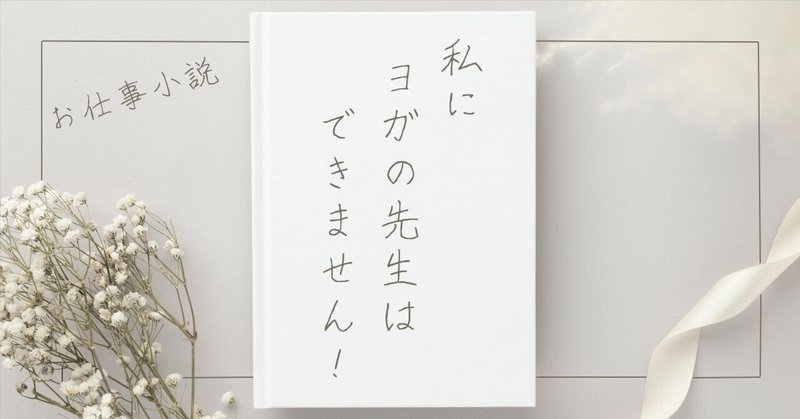
私にヨガの先生はできません!【第十六話】えりかさんの反省
【第十六話:えりかさんの反省】
カレンの住んでいるマンションから帰る途中、私はホットヨガスタジオ・Vegaに寄ることにした。
ペンタスガーデンの玄関は、夕陽に照らされてオレンジ色に染まっている。冬に比べると遅いけれど、七時前になるとさすがに日は沈んでいくみたいだ。
「おや、こんばんは。これからですか?」
玄関の辺りを箒でてきぱき掃きながら、光坂さんが言った。七十代くらいの彼は、ビルのオーナーだ。こうやって清掃しながら、テナントのスタッフとコミュニケーションをとったり、ビル前に違法駐輪しようとする人に注意したりしている。
「こんばんは! 少し、用事があって」
「そうですか、そうですか。行ってらっしゃい」
彼はニコニコとうなずいた。
いつ会っても感じがいい。そういや、久しぶりにお見かけする気がする。
「はい!」
私は光坂さんの横を通り過ぎ、銀色のエレベーターに乗り込んだ。
今日の締め担当は、えりかさんだ。今頃はスタッフルームかフロントにいるはず。日曜日は八時で閉店だから、締め作業を手伝って時間を作り、その後に少し話を聞いてもらおう。
「あら? どうしたの?」
休みのはずの私が顔を出すと、えりかさんは驚いたように首を傾げた。
「えっと、ちょっとお願いがあって……。あ! 締め作業、手伝います。それで、早く終わったら、少し話を聞いてもらえませんか?」
私の声は後半になるにつれて、小さくなった。
「もちろんよ。でも、出勤してない人に仕事させられないわ」
えりかさんがそう言ったとき、スタジオの扉が開く音がした。レッスンが終わったのだろう。スタジオからロッカールームへと流れ込む、ほてった人の気配が、空気越しにここまで伝わってくる。
「じゃあ! スタジオ借ります。これは、個人的なヨガの練習ってことで」
「あー、そうですよね……。じゃあ! スタジオ借ります。これは、個人的なヨガの練習ってことで」
「それなら、問題ないかしら。終わったら、下のカフェでお話しましょ」
「はい!」
えりかさんは、パソコンに向かい合いタイピングを続けた。多分、日報の文章を売っているのだと思う。
私はデスクの棚からヨガウェアを引っ張り出した。ときどき、風邪や急用で外部のインストラクターさんが来れなくなることがある。そんなときの緊急代行に備えて、ヨガのできるスタッフはみんなオフィスにウェアを置いておくのが決まりだ。
「よし」
着替えてほんのりと温かさの残るスタジオに入る。
アルバイトのスタッフ、大学生の桜田さんがヨガマットを一枚一枚拭いている。この作業は立ったり、しゃがんだりの繰り返しで、けっこう足にくる。
ヨガマットを運ぶのを手伝おうとすると「ダメですってば」と笑われた。
「有栖チーフから言われてます。笹永さんは勤務じゃないから、仕事を手伝おうとしたら断ってねって」
「うう。情報が早い……」
ちょっとくらい、いいじゃないか。
そう思うけど、えりかさん曰く「時間外労働はダメなのよ」とのこと。前にも何回か言われたっけ。
うちの会社も少し前までは当たり前のようにサービス残業があったらしいけど、現在は禁止。今みたいに「残業代はいらないから手伝うよ」という場合もおんなじだ。
これまでのアルバイト経験を含めても、ここのルールが一番、厳しい。
「笹永さんは、こっちのことは気にせず、ヨガの練習しててください!」
桜田さんはそう言って、手際よく締め作業を続けていく。
私は仕方なく、スタジオのすみっこに移動すると、鏡の前にあぐらの姿勢で座った。背筋を正し、両手の手のひらを天井に向け、右と左の膝の上にそれぞれ置く。
目を閉じる。
鼻から息を吸って、鼻から吐いていく。
ゆったりと腹式呼吸を繰り返していると、桜田さんがヨガマットを拭く音がだんだんと遠ざかり、やがて消えて行く。
今だけに集中する。
「……あれ」
目を開けたときには、スタジオ内には私しかいなかった。
この、日常からふっと離れる瞬間が、私は好きだ。
呼吸を繰り返すうちに、聴覚、視覚、嗅覚、あらゆる感覚が、身体の内側へと静かに吸い込まれていくよう。上下、左右、前後、時間という、当たり前の概念からも遠ざかっていく。
そして、再び戻ってきたときには、頭の中がリセットされてクリアになる。
とっちらかっている言葉のあれこれが、ふわりと浮いて棚にきっちり並んでいく。考えていることが、意識せずともきれいな文章となりノートにすらすらと書かれていく。
そんなイメージだ。
でも、自分のレッスン中は、そこまで集中しきれない。
だから、この感じは……。
「久しぶりかも」
そういえば、ここ最近は、自分のレッスンのことばかりで、人のレッスンを受ける時間が減ったかもしれない。勉強も兼ねて、他店や他社のレッスンも受けてみよう。
そうだ! 先日、助言をくれた橘さんのレッスンに行ってみるのもありかも。満員じゃないなら参加させてもらえると思う。
まだ、苦手意識はあるけど、多分、悪い人じゃない。
そう思いながら、私はいくつかヨガのポーズをとり、腕や足や腰の位置を鏡で確認する。
「お待たせ」
五十分ほど経った頃、スタジオの扉からえりかさんが顔をのぞかせた。
私たちは鍵をかけて、一階にあるカフェ・くじら座へと移動した。
一ノ瀬さんはいなかった。たまに見かけるスタッフが、今日は一日お休みなのだと教えてくれる。
珍しい、と思った。休業日の月曜日以外は、朝か夜のどちらかにいることが多いから。
すぐに、注文したコーヒーが二つ運ばれてきた。
「あの、すみません。急に……」
私はあらためて、えりかさんにそう言った。
「いいの、いいの。今日はとくに予定もないし。それで、どうしたの?」
えりかさんはそう言って、コーヒーカップに手を伸ばす。
「できればなんですけど、一度、私のレッスン、受けてみてもらえませんか?」
「……いいの?」
えりかさんの言葉は、イエスでもノーでもなかった。そのことに、少し違和感を覚える。
「はい! もう、気づいていると思うんですけど、最近集客が思うようにいかなくて。こないだ橘さんが参加してくれたときには、インストラクションに関しては、とくに気になることはないとのことだったんですけど、一回のみだと判断しきれないとも言われてて」
「それは、もちろんいいけど。……橘さんになにか、厳しいこと言われた?」
えりかさんが尋ねる。
「あー、自信のなさが伝わってくるって。このままじゃ、今よりも参加者が減るって言われちゃいました」
「そうなのね。念のため伝えておくと、いやがらせで言っているわけじゃないのよ。言い方はちょっときついんだけどね」
えりかさんの言葉に私はうなずく。
「はい。それは、大丈夫です! ご丁寧に、集客出来ないときのパターンも教えてもらいました」
「ああ。あの三つのパターンのやつね」
「それで、自信をつけるためにも、ダメなところを直して参加者を少しでも増やしたくて。リピーターさんつけるには、やっぱりレッスンの質を上げないといけないと思うんです。だから、気になるところを教えてほしくて」
「自信をつけるため……ね。なるほど。わかったわ」
「ありがとうございます! あの、ひょっとして、えりかさんも橘さんから、三パターンの話を聞いたんですか?」
「ええ。そうよ」
「それって……。つまり、えりかさんも集客できなかった頃があるってことですか?」
「もちろん。これって、私やいと葉に限らず、多くの人が通る道だと思うわよ」
えりかさんは、さも当然かのようにさらっと口にする。
「へえ。びっくりです」
「ふふ。よかったら、あたしが当時、実践していた集客作戦を伝授するわよ」
「やった!」
それから、私はコーヒーを飲みながら、えりかさんからのアドバイスを受けた。
入会の手続きをするときに自身のレッスン日時をさらっとお伝えすること、店舗の公式ブログでアピールすること、ヨガの知識や技術の勉強を続けること、他の人のレッスンを受けてみること。
どれも地味だけど、こういう積み重ねが参加者数アップに繋がっていくのだと彼女は言った。
その通りだと思う。
「まだ、できることが色々あるみたいで、安心しました」
私は少し肩の力を抜いた。
「また、他にもなにか思い出したら伝えてもいいかしら?」
えりかさんが聞いてくる。あれ? と思った。
さっきもだけど、彼女は私にアドバイスすることに対して、どこか躊躇しているような気がする。
「ぜひ、お願いします。あの……。どうして聞くんですか?」
「え? たしかに、そうよね」
えりかさんは私に言われてやっと、いちいち許可を求めていたことを自覚したらしい。
「なにか、理由があるんですか?」
それは、素朴な疑問だった。
「あー。あのね、いと葉が入社する少し前に、退職した社員がいるの」
「あ、前にちらっと、岩倉店長と話してましたよね。まだ半年も経ってなかったとか」
「そう。辞めちゃったの、あたしのせいなのよね」
えりかさんはそう言って、ため息を吐いた。
「そうなんですか?!」
「たぶんね。その人、入社したときにはヨガのインストラクターの資格、持っていてね。だから、すぐにレッスンデビューしたのよ。ちょうど、プログラムが入れ替えの時期だったからっていうのもあるけれど」
「凄い!」
いわゆる、即戦力というやつだ。
「でもね、集客がうまくいかなくなったのよね。入社して間もない頃だったから、顔なじみの会員さんもいないでしょ? だからなおさら」
「たしかに」
「それで、あたし、なんとかしてあげなきゃってヘンにはりきっちゃって、そのスタッフのレッスンに参加してアドバイスしたり、さっきいと葉に伝えたようなことを言っちゃったりしたのよね」
「それ、ダメなことですか?」
私は首を傾げる。
「プレッシャーをかけてしまったみたいでね。たしかに、今思えば、一方的過ぎたのよね。あたしが明るく励ますほど、自分がみじめな存在になったようで嫌だったって、退職するときにメールで言われちゃった」
えりかさんはぽつり、ぽつりと話してくれた。
「……そうだったんですね」
そのスタッフの気持ちは、わからなくもない。資格を持っていたんだから、そこそこ自信もあったんだと思う。
一人でなんとかできるから、参加人数が減ったことには触れず、あえてそっとしておいてほしかったのかも。呼吸をするように人を集める人気インストラクターのえりかさんにアドバイスをされて、プライドが傷ついたのだろうか。
そんなような気もする。
「あたしなりに反省したのよ。もう、おんなじことはしないって。だから、あれこれ言いすぎないようにしていたのだけど……。いと葉ったら、自分から聞いてくるんだもの。びっくりしたわ」
えりかさんが小さく笑う。
「私はむしろ、色々教えてもらえるのがありがたいです。ほんとに」
「そう。よかったわ」
今ならわかる。
えりかさんが意識してくれていたのは、レッスンのことだけじゃない。思い返してみれば、入社してから今まで、彼女が行動を押し付けてくるようなことは一度もなかった。私が話したくなさそうに言葉を濁せば、すっと身を引いてくれていたっけ。
それも、過去の経験があったからなんだ。
「あの、えりかさん、ありがとうございます。私、できることからやってみます」
私はそう伝えながら、心底思った。
思い切ってえりかさんに相談してよかった、と。
そうでなきゃ、アドバイスをもらうことなんてできなかっただろうから。
この連載小説のまとめページ→「私にヨガの先生はできません!」マガジン
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

