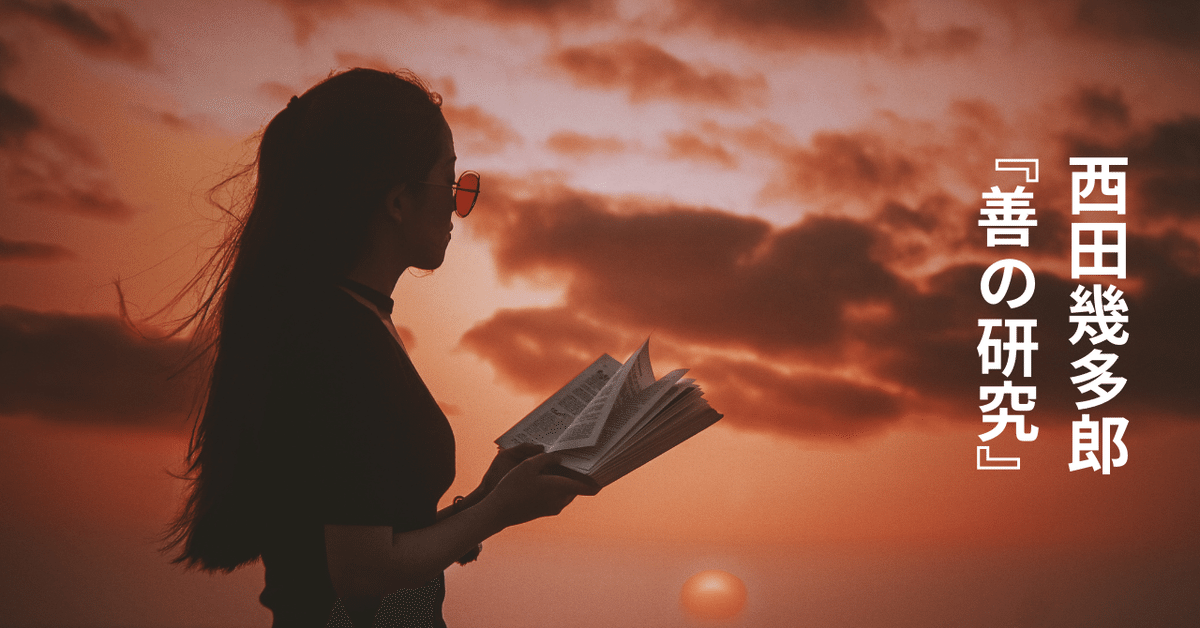
人格者とは何たるかに関する考察。 西田幾多郎『善の研究』との対話。
文字数:約8,730
かつてゲーテはこのように言った。
もし自分の生れつきの傾向を克服しようと努めないのなら、教養などというものは、そもそも何のためにあるというのかね。
あるいはこうとも言っていた。
いつも決定的に純粋なもの、倫理的なものにそれを求めようとするのは警戒しなければいけないよ。およそ偉大なものはすべて、われわれがそれに気付きさえすれば、必ず人間形成に役立つものだ。
私は私の邪悪な傾向性を恨みつつ、かといってこれらを完全に除去することはできないではないかと言い訳がましく諦める。人格とはなんであろう。世の中を見渡してみよ。いつだって気分が晴れやかで、にこやかで朗らかで、思いやりに溢れており、物腰や人当たりも柔らかく、丁寧かつ大胆で、言動には虚栄心のかけらもなく、少年少女のような純粋さをかね合わせ、彼らと対面した途端に不思議と微笑みがこぼれるような素敵な人間など、非常に希少な人材である。
私はここに正直に告白しようと思う。私の中に巣食う悪魔的考えの数々をここにばらまくように記載をすることでそれらと真摯に向き合い、彼らとの共存の道を探りたいのである。私は幾度も彼らを私の中から排除しようとしてきたが、彼らは私のそれらの抵抗に逆に抵抗するように、むしろその勢力を増していく。彼らに対しては歯向かうのではなく、向き合い寄り添うことが大切だと私は思う。彼らは私たち自身でもある。
性格が悪いと人は言うが、果たして完全に善良で性格の良い人間がいるかどうかは甚だ怪しい。性格の悪さを世の中に露見させてしまう人々は、彼らの闇を言葉や態度に乗せて世間に公表してしまうからこそではないか。もちろん、私たちはここでは犯罪者という極論は避けねばならぬ。私たちは犯罪者を性格が悪いなどとは形容しない。私たちは彼らをただ単に犯罪者と呼ぶのである。もはや性格の良し悪しなど関係がない。
むしろ罪を犯すものと法律を遵守するものとの差異は性格の良し悪しですらない。性格が良くても犯罪に加担することはあるし、性格が悪くても善良な国民であることだっていくらでもあろう。法律を犯すか犯さないか、ただこの一点が差異の分岐である。とは言え、法律に関する議論云々はここではひとまず置いておこう。
人は誰しも自分が間違っているなどとは思いたくないものである。いや、より精確に描写すれば、人は誰しもが自らの人格が歪んでいたり、他者よりも劣っているなどとは思いたくもないし、あるいはそのようなこと自体を思いつかないのである(「思いたくない」だとか、「思いつかない」だとかとは記載したが、実際問題として人間の尊厳には優劣などあり得ず、従ってそのようなことを「思う」のは間違っているのだと私は断言がしたい)。
外野からはいくらでも罵詈雑言を与えることができる。私たちの内のいくつかの人々はそうやって他者を自分よりも低い位置に貶めることで、自身の人格的安心感を得ようとするであろう。「あの人は性格が悪いよね」、「あの人の言動は良くないよね」、「あの人の態度は良くないよね」、そのような嫌味なニュアンスのフレーズの数々の裏側には、「私自身は彼らとは違い善良で人格があるのだよ」と言っているようにしか私には聞こえない。とは言え、自己を正当化することは自己の防衛手段として何も間違ってはいないのだから、私は彼らに反論したくはないし、私はここでは物事の批判ではなく、単にそれらの現象を分析したいだけなのである。
これらの私の考えを世の中の空気に漏洩させれば、おそらく私の性格は世間一般的には「あの人の性格は終わっている」のだとでも形容されるに違いがないとは思うものの、ここではあくまでも私自身のガス抜きとしてこれらを記載することを許してほしいと願う。それはどのようなことかと言えば、以下のような、いわゆる愚痴である。
私はこの人生において心から尊敬できる人間に出会ったことがほとんどない。優れた人格を持ち、健全で思慮深い人間に出会うことは非常に稀である。
俗にいう立場が偉い人々のうち、そのほとんどが立場に負けてしまっている。年下が年上に敬語を使うことは、年上が年下にタメ口を使う理由とは等しくはない。なぜ私たちが敬語を使うのか。それは他者を尊重する気持ちがあってこそである。従って、年下が年上に敬語を使わなければならないなどと教え込むのはその本質からかけ離れているのである。「使わなければならない」のではなく「使いたい」あるいは「使うべきだ」と思うからこそ敬語を使用しているのであり、それらは強要されるべきものであってはならぬ。
もし仮に敬語とタメ口の関係性でしか、彼ら自身の立場を示すことができないのだとすれば、そんな立場は果たして偉いものなのだろうか、甚だ疑問である。否、もし仮に偉い人々が彼らの威厳をタメ口や横柄な態度に託しているのだとすれば、彼らは全くもって器ではない。もちろん上下関係がはっきりとできていれば、上司と部下、先生と生徒、師匠と弟子とのスッキリとした師弟関係があるのであれば、自然と敬語とタメ口が使い分けられるはずであるが、現代社会においてはそのような関係性は稀であると言わざるを得ない。もはやそれらの価値観は過去のものである。
偉い人々はとことん偉そうである。なぜ彼らは偉いのであろう。単に年齢を重ねることが偉いのであれば、そのような社会はもはや過去の遺産であるか、あるいは現時点でも残っているのだとすれば、それは競争社会(資本主義社会とも呼ぶ)とは逆行する社会主義の萌芽なのである。私は働いていてつくづく残念に思う。権力を持っている人々が彼らの権力をうわべだけで示そうとすることにがっかりする。
彼らが権力なき歩兵に対して威圧的な態度を取ろうものなら、私の感情は荒ぶり、今すぐにでも反抗しその立場を逆転させてやりたいと思う。怒りは他者を萎縮させ、自らの立場を強制的に上げることができるが、そもそもすでに立場が上にあるのに、なぜその差異をさらに拡げようとするのであろう。彼らの怒りは真の意味での怒りなどではない。彼らの怒りは自らの弱さを隠そうとするが故である。つまり彼らの怒りには威厳がない。威厳なき怒りは他者を貶め、自らを正当化することにのみに焦点が当てられている点では、匿名による誹謗中傷と似た性質を持つ。
力無き者こそ権力を渇望し、情念が彼らの世界を支配する。権力がない歩兵が権力あるものに対して威圧的な態度を取ることはほとんどない。一般的な日本社会ではそのような光景はあまり目にしない。私は不思議で仕方がないのであるが、なぜ立場が上の人々は立場が下の人に対して横柄な態度を取って良いのに(実際問題としてそのような態度は許されざる行為ではあるが、あくまでも社会の空気的に横柄に近いニュアンスの態度が取られているということは日本社会の事実であろう)、立場が下の人々は立場が上の人々に対して横柄な態度を取ってはならないとされているのだろう。
試しに立場が上の人々の目の前に、彼らよりもさらに立場が上の人を置いてみよ。全く滑稽でばかばかしい。歩兵に戻った、あるいは現時点でもまだ歩兵である彼らの真の姿が暴露されるのである。私は彼らのことを人格者とは到底言えまい。ただ単に年齢を重ね、日本独自の社会規則的に給与が歩兵よりも高いだけとしか形容することなどできぬ。お金の有り無しで人間の尊厳が評価されるなどあってはたまるものか。
知識があり、頭が良い人々にも残念ながら偉さと同様の傾向を見出せる。全ては二項対立的に物事を考えるからこそ陥る思考の罠である。知識を持たない人々は知識を持つ人々に萎縮する。知識を持つ人々は知識を持たない人々を馬鹿だと思う。権力を持つ者は権力がない者を馬鹿にし、権力を持たない者は権力を持つ者に媚びへつらうばかり。
私たちは偉い人々を前に緊張することがあるが、それは緊張とは言えない。それは緊張ではなく、単に萎縮しているのみである。偉い人たちにどう評価されるのだろうと萎縮しているだけである。お酌をする手が震える。それは自らの根源がそのような行為を否定したがっているからである。だが世間は私たちに対して、何が正解で何が正義であるかを叩き込もうとする。お酌をしない若造を年上の人々が叱りつける。挨拶をしない若造に年上が食ってかかる。
ああ!くだらない!
実にくだらないことだ。
権力無き者による権力者への反抗、私たちはこれらを革命だとかデモだとかと呼ぶ。私は断言したいのだが、現代社会においてこれらの革命やデモは成功しない。自らを傷つけ、社会的地位を貶める結果にしか繋がらないことがほとんどである。私たちの社会は巧妙かつ複雑に構成されており、ちょっとやそっとの力ではこれらは動かすことはできぬ。それも国家がひっくり返るような大変革が起きない限りは、私たちの内なる革命家の野心が満たされることはない。
と、ここまで猛毒を吐き散らしてスッキリしているのだが(笑)、私の分析では他者への批判というものは実際には他者が間違っているのではなく、自らに落ち度がある可能性が高いのである。私がここに告白したように、私は偉い人々の人格を計測しようとしていて、彼らは器ではないと残念ながらそう思ってしまっているということについて、そのような視点自体が間違っている可能性である。
彼らは確かに横柄に見える。彼らは確かに命令口調のように聞こえる。だが、だからと言って彼らの人格の全てをそれだけの論拠で判断することは時期尚早である。繰り返すが、私たちの人間としての尊厳には優劣はなく、要するに人格についてすら私たちは優劣をつけるべきではないのである。人格の良し悪し、これらは自らに問いかければ問いかけるほどその神聖なる威力を増し、他者に問いかければ問いかけるほどその問いかけは邪悪で汚れたものへと変貌する。
では人格とはなんだろう?
それは自らが自らに働きかけるところの問いかけそのものであると私は感じている。そこには完全なる正解はないが、完全なる間違いもない。その中間地点を漂いながら、より良いと意志が判断される方向へと進む行為そのもの、それらを人格であるとか、善であるとかと呼ぶのだと私は思う。
つまり人格とは、自らの意志との一致であり、自らの意志自体の一貫性である。それは自らの否定でもあり、自らの再構築でもある。私たちは他者を判断するよりも前に、大いなる事業を担っているのである。
では善とはなんだろう?
そもそも善とはなんたるかを考えること自体が人格的である。善とはどのようなものであるかを自分自身に問いかけることそのものが人格の様相である。西田幾多郎は『善の研究』でこのように述べている(ちなみにこのnoteは西田幾多郎の『善の研究』を読んだ備忘録なのだが、もうすでに果てしなく冗長で申し訳ない)。
池に陥らんとする幼児を救うに当たりては、可愛いという考えすら起こる余裕もない。
善に関する自らの思想を深めていき、幾度も反芻すること。自らの感情を、理性において第三者的に分析すること。何が善であるか、何が人格であるか、そのようなものを思考し行為することそのものが善であり、かつ人格の形成そのものにほかならない。
『善の研究』の私なりのハイライトは言動の一致、思考と言動の一致、思考と本質との一致、である。言動の一致とは、文字通り、言ったこととやっていることとができる限り一致すべきということである。自らの言動が一致している限り、私たちは自らの誠実さを守れるのではないかと思う。
もちろん、言ったことは必ず守らなければならないと自らが自らに制約し続けることは必ずしも正しくない可能性もある。それでは単に意地っ張りや頑固である可能性があるからである。実際に動いているか、動いていないかは、ここでは問題ではない。もっとも動き出さなければ結果は伴わないが、動き出す前の自己の一貫性はあらゆる物事の土台ではないか。
そこで私たちは思っていることと、それらを言葉に出したり、行為に表したりすることとをできる限り一致させねばならない。とは言え私たちの思考は縦横無尽に駆け巡る取り留めのない代物でもある。あちらを思考しては、こちらを思考していく、あることないこと、本当に色々なことが頭のイメージに浮かぶ。私が述べたいのは、これらを整理すべきだということである。
そのためには、私たちは自らを自らの力で観察するべきだと私は思うわけなのである。思考なき行為は無謀であり、行為なき思考は臆病である。私たちは自らの思考を思考し、それらを深めていかねばならない。それらを見つめ、深めていった先にあるものは何か。西田幾多郎はそれこそが善であり、人格であり、愛である、と説いた。ここには彼のコスモポリタン的な思想も読み取れそうだ。
知は愛、愛は知である。例えば、我々が己の好む所に熱中する時はほとんど無意識である。自己を忘れ、ただ自己以上の不可思議力が独り堂々として働いている。この時が主もなく客もなく、真の主客合一である。この時が知即愛、愛即知である。数理の妙に心を奪われ寝食を忘れてこれに耽る時、我は数理を知るとともにこれを愛しつつあるのである。また、我々が他人の喜憂に対して、全く自他の区別がなく、他人の感ずる所を直ちに自己に感じ、共に笑い共に泣く、この時我は他人を愛しまたこれを知りつつあるのである。愛は他人の感情を直覚するのである。
「主客合一」。自己を滅却し、他者に愛を向けていったその先に、本来の自己を見出す。西田幾多郎の思想はとても暖かい。思考を深めていくその先に私たちは本質と出会う。本質とは客観的であるが、あまりにも主観的なものである。
私たちは普段、様々なフィルターをかけながら世界を見つめている。むしろ私たちの成長とは、様々なフィルターを重ね続けることとも言えるのかもしれない。経験を重ねるに従い、自らの思考のパターン、性格、人格なるものが徐々に構成されていく。これらのうちの多くは私たち自身のものではあるが、そのうちのいくつかは私自身によるのではなく、他者や世間のものである可能性が高い。
色眼鏡を外していく過程で、私たちは本質とはなんたるかを思考する。言動と思考と本質、それからこれらとの一体感、一貫性、統一性なるものに思いを馳せる時、そこに私たちは何を見出せるだろうか。
すべて我々の精神活動の根底には一つの統一力が働いている、これを我々の自己といいまた人格ともいうのである。
善とは一言にていえば人格の実現である。これを内より見れば、真摯なる要求の満足、すなわち意識統一であって、その極は自他相忘れ、主客相没するという所に到らねばならない。(中略)我々が実存を知るというのは、自己の外の物を知るのではない、自己自身を知るのである。(中略)道徳とは自己の外にあるものを求むるのではない、ただ自己にあるものを見出すのである。(中略)善を学問的に説明すればいろいろの説明はできるが、実地上真の善とはただ一つあるのみである、すなわち真の自己を知るというに尽きている。
繰り返そう。善とは何か、人格とは何か。私の考えでは残念ながらそこには決定的なる正解などない。だが、これは断言ができるし、したいのだが、私たちは「善」や「人格」や「性格」などに関連して、私以外の他者を批判してはならないということだ。「いやいや、そうは言っても」という声が聞こえてきそうだ。
私たちは賢い。賢いが故に、知識を得れば得るほど、様々な物事、人々を判断の対象としたがる。しかしながら、判断の対象とは己自身に向けるべきものではあるが、他者に向けてはならないのである。知識を得ているものが偉いのではない。勉強ができるものが偉いのでもなければ、お金を持っているものが偉いのでもない、地位があるものが偉いのでもなければ、社長が偉いわけでもなく、総理大臣が偉いわけでもない。もはやこの地点において、これら全ての権力は無関係なのである。それらはどうでもよい。
「あの人が苦手だなあ」、「あの人の言い方はなんだかムカッとするなあ」、誤解を恐れずに申し上げれば、これらは他者に原因があるのではない。私たち自身にその原因の多くが存在するのである。私たちの受け取り方次第で全てはその景色を変える。私たちの思考次第で全ての景色は変わる。
苦手な「あの人」を作り出しているのはほかならない、私自身なのである。なぜそのような思考になるのかという問題はここではおいておこう。恐らくは過去の経験上なんらかの理由があるのだろうが、少なくともそれらは私自身が作り出した考えであり、その全てが「あの人」のせいではない。
「あの人」の言動にイライラとすること。そもそもイライラとしているのは私自身であり「あの人」ではない。確かに彼らの言い方は間違っていたのであろう。しかしながら、それらに対して即座に反応することは私たちの感情のお仕事ではあるものの、私たちの精神のお仕事ではない。ムカッとした感情を「あの人」にぶつけたところでなんら解決にはならないばかりか、むしろ事態は悪化するに決まっている。そうではなく、ムカッとした感情は自己を観察することで緩和することが多いのである。要するにこれらは「あの人」にその全ての原因があるのではない。
他者を判断したい欲望に屈せず、己を観察していく行為、それこそが善であり人格である。主観を排除したその先に現れる客観、主観と客観との合一、すなわち主客合一とは、私たちが晴れ渡るこの青空を深く眺め入るときの感覚ととてもよく似ている。青空の下で私は私であり、私は他者であり、私は世界そのものであることを体感する。私たちは、愛すべきもにかこまれにていることを知る。
この青空の思想において、私たちはなぜ学ぶのかということを知る。世界を知り、他者を知り、それから自分自身を知る。自らの感情をクリアに観察でき、いやより正しく言えば、自らの感情としっかりと向き合うことができ、自分が今、何をしているのか、なぜこれをしているのか、自らを客観的かつ俯瞰的に把握することができるのである。全てはスッキリとしていて、シンプルである。シンプルであるものは美しい。それらは純粋であるが故に美しい。
私たちは人格者になどならなくても良い。正解を出さなくても良いし、善を尽くさなくても良い。それらは望んで手に入れるものではなく、元来私たちが持っているものなのだから。「人格者になれ!」ではなく、もうすでに私たちはある意味では人格者なのであり、「正義を目指せ!」ではなく、もうすでに私たちの心の底には正義や善とはなんたるかが宿っているのである。
このようなさっぱりとした思想が肝要である。
元来、真理は一つである。知識においての真理は直ちに実践上の真理であり、実践上の真理は直ちに知識においての真理でなければならぬ、深く考える人、真摯なる人は必ず知識と情意との一致を求むるようになる。(中略)近代において知識の方が特に長足の進歩をなすとともに知識と情意との統一が困難になり、この両方面が相分かれるような傾向ができた。しかし、これは人心本来の要求に合うたものではない。
とは言え、世間は厳しい。誰かから貶されることも、陰口されることも、嫌味ったらしく何かを言われることも、怒られることも、ネガティブな感情を喚起させる何らかの言葉を言われることも、いくらでもあるだろう。そして私たちは悲しみ、落ち込み、ふさぎ込み、気分は優れず、他者と会うことが億劫になり、あらゆる物事に倦怠感を覚え、人を嫌いになる、世界を嫌いになる。
これらに対して気にするなというアドバイスほど、逆効果な処方箋はあるまい。全く逆なのである。これらは私たちの感情そのものであり、私たちは私たちの感情そのものを仔細に把握しなければならないのである。だが、この暗い感情を見つめる行為はとても苦しい。それ自体が非常に苦しい行為であることには間違いがない。だからこそ、それらはなかなか成し得ない、私たちの勇気が最も試される事業なのである。
その前提として、まずは感情とはなんたるかを考えられる素地を作らねばならない。素地を作ることはつまりは学ぶことである。過去、これらのことは偉人たちが様々に思考を重ねてきた。文化や文明とは過去の記録と、それらの記録を土台にしてさらに進化させていったものである。ところが人間の感情とは、古代より現代に至るまで、ほとんど変わっていない。ほとんど、というかむしろ同じである。
だから、感情に関する書物(哲学的書物においてそれらが記されていることが多い)を紐解き、人間についての過去の偉人たちが辿ってきた思索をなぞる過程は非常に重要である。基礎なきものに応用はできない。現代資本主義社会において、哲学的思索ほど私たちの予防線たり得るものを私は知らない。
2023/11/22
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
