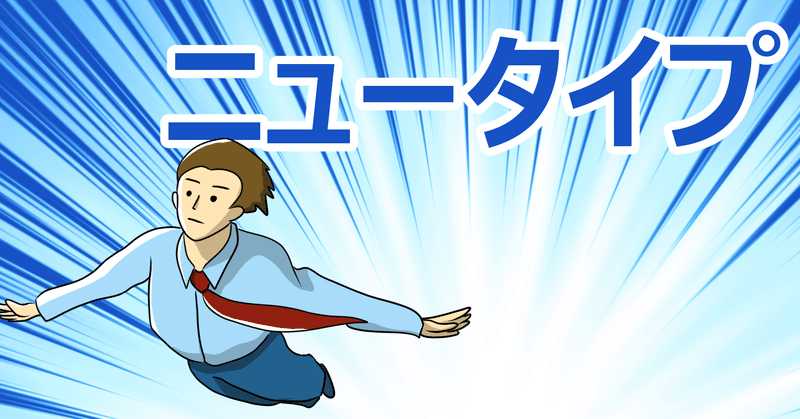
オールドタイプの私が『ニュータイプの時代』を読む
にわかファンの私が「山口周」を付け焼き刃で語る
山口周。独立研究者にして、著作家、パブリックスピーカー。
聞いたことない肩書きを、しかもダブルではさんでくるあたり、只者ではありません。
私が初めて山口の存在を認知したのは2019年のこと。
きっかけはまさにこの「ニュータイプの時代」でした。
今はなき、浜松町は「文教堂」。入り口入ってすぐ右のビジネス書コーナーに並んでいたことを覚えています。しかも半年ちかく同じ場所に並んでいたはずです。ガンダムを知っている世代なら100%反応してしまうタイトル。文教堂にいくたびにムムっ?となってました。にもかかわらずスルーしつづけた私。
#この時点でオールドタイプ確定
2年の時が流れ・・・文教堂も失ってしまったこの世界線で・・・ついにご縁があり読了いたしました。きっかけは牧野圭太「広告がなくなる日」。本文で引用されていた「成熟した高原社会」という言葉に惹かれて検索。著作一覧に「ニュータイプの時代」を発見した、という流れでした。
それにしても本屋がなくなるのってほんと寂しいですよね・・・。
特に大きな本屋だとそれもひとしお。大型書店に足を踏み入れたときに感じるあの高揚感、胸の高鳴り、見知らぬ本との僥倖。amazonでは味わうことのできないあれやこれ。年々、世界から失われていくのは残念でなりません。
とはいえ諸行はすべからく移ろいゆくもの。
歴史のなかに沈んでいったあまたの伝統や文化と同様、ときおり人々に思いだされては懐かしまれる。そういうものと受け止めて、今ここにあるものを最大限に享受しながら生きる、そんなとこなのかもしれませんね。
話がそれましたが、ここで一つ衝撃の事実を。
実は2008年だったのです・・・。山口との本当の最初の出会いは、2008年だったのです・・・!でもこんどは自分を攻められません。なぜならばペンネームだったからです。
その名も「岡本一郎」。
#爆発かっ!?
あ、でも山口は美術好きだから納得かもしれません。なんかのセミナーで「ほんとは美術館の館長になりたかった」と発言してましたしね。
その山口が岡本一郎名義で上梓したのは「グーグルに勝つ広告モデル」。
ありましたよ・・・。
いまでも自宅の本棚に刺さっていました。過去2回の引っ越しにともなう書籍の大虐殺を経てもなおしぶとく生き残ってきた精鋭部隊にバッチリ入隊しておりました!生存確率2〜3%くらいなんで、なんかほんと、運命感じちゃウ!山口!
#百恵か!
山口は1970年生まれなので、2008年時点では38歳。30代にして仕上がっている恐るべき知性。
久しぶりにちょっと黄ばんだ書籍を手にしてパラパラと眺めてみました。
今なお色褪せることのないキレッキレの文章でした。そして、いまのマスメディアを2008年時点で見通してたというか・・・山口が提言していた未来がそっくりそのままきている感じ。脱帽です。
そして今の山口は51歳。
その脳内にインデックスされた古今東西の膨大な知識。それを瞬時に出し入れする機敏な知力。それを51歳のいまもなお維持している、むしろ年々高まってきている?ことの方がもっと恐るべしなのかもしれません。
ちなみに「グーグルに勝つ広告モデル」執筆時、山口はボストンコンサルティンググループ(BCG)というコンサルティングファームに所属していました。
BCGが社員の書籍出版を禁止していたため、ペンネームになっていたのでした。結局、会社にバレて怒られて、嫌になって退社したそうです。なんかロック!そしてなんだかんだペンネームってバレるんですね、という事実もショック!
#韻踏みました。伝わってますか(白目)
#(白目)って、もしかして死語ですか
山口周と葉山
ちなみに山口は5年ほど前、本人曰く「魔がさして」葉山に引っ越してます。それまでは都心(世田谷区)で一般的なシティライフを送っていました。#ちなみにが大渋滞
「魔がさして」というのは面白い表現ですが、要は「飽きた」ということだったみたいです。一般的に「飽きたから」という動機付けにはネガティブなイメージがつきまといますが、どっこい「飽きた」という感情を尊重することを山口はすすめています。
飽きたということは、それ以上同じ環境にいつづけても大きな学びや成長は期待できない、ということ。学びや成長が期待できないということはゆっくりと衰退していくことと同義。それが住まいであれ、職場であれ、飽きてしまった場所に踏みとどまり続けること。それは現状維持バイアスにからめとられてしまった悲しきオールドタイプのサガなのです。「自分の人生を破壊することにつながりかねない大きなリスク」とまで言ってます。
とはいえ、ちょっと飽きたからといって転職でもすっかな〜、というのは万人に許されたオプションではないですよね。
「この仕事はもう飽きた」「ここからはもう逃げたい」というDNAの呼び声に素直に応じて学びつづけ、成長しつづけられるニュータイプになるためには、スキルや知性といった「越境して持ち運びできる武器」を日頃からコツコツと磨きつづけておく必要がありそうです。
私の葉山探索
実は私、山口に触発され、いや「魔がさして」、先日葉山の賃貸物件をみにいってきました。
結論。
「うおおお!めっちゃ住みたい!!!!けどやっぱちょっと遠いからムリ!で、でも、キミがどうしても住んで欲しいって言うなら、か、考えてあげないってこともないんだからねッ!」でした・・・。
逗子までなら横須賀線で1時間くらいだったんですけどね。そこからさらにバスを待つこと15分、バスにのって15分、計1時間30分。DtoDだと正味2時間。チーン。
#BtoBみたいに言うな
われわれはすでにテレワークワールドに転生してきた身。
とはいえ、まだまだ週に1〜2回は物理的に肉体を運ばなければならないわけで。その日々を想像するとまた、現状維持バイアスの力強い腕にガッツリ抱かれてしまうオールドタイプな私なのでした。
とはいえ、そのデメリットをおぎなってなお、あまりあるメリットが葉山にはあるように感じました。
手を伸ばせばそこにある海と山。人工物にさえぎられない広い空。少しくたびれた建物がたちならぶのどかな街並み。ラフなかっこうした人々の顔に浮かぶ混じり気のない微笑。そして。時間の流れがあきらかに緩やかです。バスでしか辿り着けない土地だからこそ守られているもの、オーガニックに残存しているものがたくさんあるように感じました。
昼食後、葉山のメイン通りを30分ほどぶらぶらし、目についた山に登りました。神社の境内でぼーっと自然音に耳をそばだてていると、次第にとおのいていく時間感覚。世界につつまれているような、なにか大きなものと共生しているような、そんな感覚。そんなアフタヌーン葉山をたのしみました。
#なんとなくジブリ的な雰囲気がある
それにしても脳の認知機能って不思議ですね!
人工物が少ない、速く動くものが少ない、人が少ない、おばあちゃん遭遇率が高いなど、郊外特有のあれやこれが、時間を認知する能力に作用しているのでしょうか。
あるいは単に見慣れない景色、初めての土地にいくと情報量が多くて処理するのに時間がかかる=体感時間が長く感じられる、ということなのかもしれませんが。
このあたりはかなり興味がある分野です。脳をうまく錯覚させて体感時間を長く感じさせつづけることができれば、疑似「永遠の命」も夢じゃない!?さておき。
オールドタイプが読む『ニュータイプの時代』
さて本題です。
これは山口の著書全般に共通して言えることですが、今作もとりもなおさず「きもちいい!」。
日常生活のなかで積もりに積もった脳内バイアスを、きれーいに取り払ってくれる、爽快な読書体験をもたらしてくれました。
山口ならではの理知的な文体、それでいて誰も置いてきぼりにしない優しい感じ。古今東西の名著や著名研究者の論文、歴史的事実の引用からもたらされる圧倒的なライブ感。
#机上の理論ではない
さらに、コンサルティングファームのキャリアが長かった山口の特徴として、IBM、セグウェイ、アップル、グーグル、日本のケータイメーカー業界、自動車業界などなど、実業界のエピソードが随所に挿入されていることもまた、我々ビジネスパーソンが本書を自分事化しやすいポイントの一つかと思います。
そして本書最大の醍醐味。
それは、現代社会に漠然とただよう暗黙知をヒョイっと切り抜き、それが横行するにいたった背景やシステムを洗いだし、いまを生きる私たちに「あるべき姿」を見せてくれること。山口が展開する独自のビジョンは私たちに「救済」の感覚を体験させてくれます。
「失われた30年」「超高齢化社会」といった言葉を毎日のように浴びせられてきた私たち。誰もが感じているであろう鬱屈とした感情、息苦しさ、やり場のなさ。そして「仕事にやりがいを感じられない」「人生に意味が見いだせない」「幸福感が感じられない」といったそこはかとない痛み。
「自分の力ではどうにもならんだろう」と思い込んでいたそんな痛みが、その実、社会の共同幻想によって生みだされていた仮想にすぎなかったのかも、そんな気持ちにさせてくれます。
高度経済成長期にきづかれた社会インフラ、システム、価値観。その延長線上としての現代。アメリカのフラクタルを目指してきた日本。わたしたちがぼんやりと不満を内包しながら生きているのは、それらがいつしかすっかり古きものになってしまっていたからなのかもしれません。
最後にもうひとつ。
自分の美意識や倫理観、価値観。もしくはトキメキ、いい匂いなど。山口が推奨するニュータイプのスタイルは、どれも人間性に深くねざしたものです。いっそのこと「自分らしさ」という言葉に言い換えてしまってもいいかもしれません。
わたしたちはとかく他者の物差しに依存しがち。
高度な社会性によって生き延びてきたホモ・サピエンスならではのサガなのかもしれませんが、日本人は特にこの傾向が強いと言われています。いわゆる同調圧力とか空気、などと称されるものですよね。
最初は瑣末なものにすぎなかった忖度が、時とともに雪だるま式に膨張し、いつしか誰も望んでいなかったような壮大で堅牢な暗黙ルールができあがっていく。自分たちの手で自分たちの首を絞め合っているような息苦しい社会。
#バタフライエフェクト・ディイストピア・ソサエティーとなづけよう!フハハハハ!
もちろんそんなディストピアを望むものは誰一人としていません。
ではどうすればいいのか。
まずは個々人が「自分らしくあっていいんだ。いや自分らしくあることこそがこれからの生存戦略にとってむしろ必須要素なんだ」という脳内パラダイムシフトをおこすこと。そして自分の心が発する声に耳を傾け、それを尊重する。次に、ちょこっとだけ勇気をだし、小さくてもいい、アクションにつなげていく。それがいつしかおおきなストリームとなって社会の方向をシフトしていく。
そういうものなのかもしれない。
そんな希望に満ちた社会にいま私たちは生きているのかもしれない。
そんな未来を思い描かせてくれました。
実際、3.5%の人々が声をあげて行動を起こせば社会は転覆できる、というような学説も紹介されていました。
#ごめんなさい。これは本書ではないかも
そして本当の最後の最後に。
山口のインタビュー記事から、いますごく気に入っているコメントを引用して終えたいと思います。
昨年12月に出した『ビジネスの未来』で、山口は、この世界には2種類の人間がいると書いている。「何かおかしい」「理不尽」と感じ、それを変えようとする人と、「世の中はそういうもの」「仕方がない」と受け入れ、うまく立ち回っていこうとする人たちだ。山口は、もしおかしいと思うならば、社会システムを外側から壊すのではなく、静かにシステムの内側に侵入して、システムを変える静かな革命家=「資本主義のハッカー」になることを提案している。社会は、もっと人間的で豊かなものに変えられると考えているからだ。 (出典:「AERA 現代の肖像」)
さーて、次はいつ葉山にいこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
