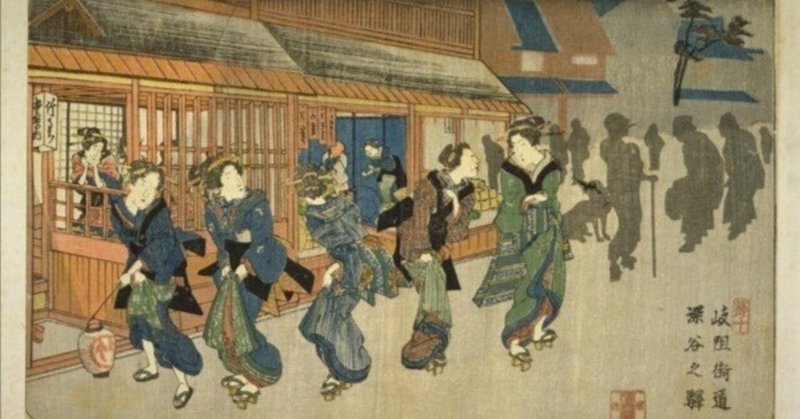
日本語教育研究者と日本語教育の実践 ─ 研究で培われた「鋭敏な目」から洞察を
この数日でTwitterで上のようなテーマとなる発信をしましたので、まとめます。
*便宜のために番号を付けました。ぜひ、おもしろいと思ったの、レスください。
1. 日本語教育に関心を寄せる研究も「研究」なのだから、研究者が「研究」として、「役に立つ」とか「役に立たない」とかは考える必要はなく、自立的・自律的にやればいい!? それだと、日本語教育が研究者の「ダシにされる」ような! そして、そんな傾向は以前から感じている。
2. 一方で、それまで長く日本語教育に従事していた人が(運よく!?)大学のセンセになりおおせたら、「わたしは(今は)研究者で、日本語教師(日本語教育者)ではない!」という態度をしているのも、「かたわらいたい」!
3. やはり、日本語教育実践者(その「矮小型」が日本語教師)というアイデンティティを持っている人と、(日本語教育)研究者というアイデンティティを持っている人との間の溝は深くて大きい。そして「相互に関心を寄せよう! 関わろう!」というかけ声は以前からあるが、あまりそうなっていないような。
4. 一方、日本語教育実践者と(日本語教育)研究者は一人の人において「重なっている」ことは多い。そして、その重なりを「分離」してやっている人と、「分離」しないでやろうとしている人がいる。前者の人の研究は結局関連領域の研究となる。そして、後者の人の研究はややもすると中途半端な研究となる。
5. ぼくは、院生に「日本語教育への示唆を書け!」と言ったことはない!。(あまりに「無軌道な」研究をしている学生には「軌道」を確保するために言ったことはあるかも。)
6. 教育実践者の多くは「実践に役に立つ研究を!」と期待している。また、最近は少し少なくなったけど「実践に役に立つ研究を!」と言っている研究者がいるし、修士論文(や博士論文でも)「日本語教育への示唆を書け!」と指導している先生がむしろふつーという現状がある。研究者はそんな声にどう答える?
7. 研究者が知らないこと/忘れていることの第一は、日本語はそう簡単に身につくものではなく、じっくりした育成が必要ということ(中級までの口頭書記総合基礎日本語段階)。研究者さんがしばしば提案する「派手な学習活動」や無軌道な自律的学習はtruly foreign languageの習得には適していないだろう。
8. 自身の言語と何のつながりもなく、連想もきかない一つの単語を身につける(丸暗記ではなく)だけでもたいへん。文型・文法は「仮初めに習得する」ことはむしろ容易。話題を枠組みとして教育を企画し、話題に関与する語の習得に主要な関心を向けながら、文型・文法も「真に習得させる」というのがいい。
9. 留学生センターなどでは、各コース、各プログラムにはコーディネータがいて、その教員が自身の裁量・責任で行っています。基本、他のコースのコーディネータは口を出さない。厄介なのは「旧守」勢力です。「新しいこと」、「変更すること」に抵抗します。このような状況、どこでも同じだと思います。
10. 別科の場合は、ほぼ毎日勉強するような集中教育で「一貫したカリキュラム」があるかもしれません。そんな場合は、その「一貫したカリキュラム」を専任教員の会議で決めるという形かも。その場合も、厄介なのは「旧守」勢力でしょう。
11. 「研究志向でない先生=旧守勢力」ではありません。研究志向でない「世話焼きのやさしい先生」の中にも第二言語の習得支援について優れた勘をもっている人もいて、そんな先生は、へんこに「旧守」ではありません。ちなみに、この「旧守勢力」の話と研究と実践の乖離の話は別です。
12. 旧守勢力よりもタチが悪いのは、自身の有利な立場と自身の研究関心を振りかざして「新規で『派手』な」教育方法を非常勤講師等に強要する専任教員です。
13. 現場においては研究志向であるかそうでないかはある意味でどちらでもよく、第二言語の習得支援について優れた洞察や勘などをもっているかがキー。そして重要なのは、その洞察や勘などを言葉を尽くして同僚仲間に語ること。その部分が脆弱なのが日本語教育のウィークポイント。https://note.com/koichinishi/n/ned2a651774d0?magazine_key=m13a4a0ab700e
14. 専任・非常勤、研究志向者・研究志向でない人、新人・ベテランなどに関係なく、学生の日本語の習得支援を真剣に考える者という同じ立場でしっかりと対話するべき。そしてその際には、先の発信のように、言葉を尽くして語ることが重要。少し語って、簡単に「立場、思想の相違!」としてしまうのは安易。
15. 「言葉を尽くして語る」ためには、言語の習得や言語の心理などについての一定の知識は確かに必要です。しかし、キモになるのは、知識よりもむしろ「優れた野生の勘」です。
16. 僕には科学信奉はありません。科学的な研究も参考にしますがむしろ言語哲学が重要だと思っています。また、哲学の素養が「考えを言葉を尽くして語る」ことの「体幹」を作ってくれる。現場の意思は当事者たちによる対話によって形づくられる。現場は複合的で科学は根拠を提供することはできないだろう。
17. 研究者には研究で得た知見ではなく洞察がほしい。例えば、文法研究者に期待するのは文型・文法の教え方ではなく、文型・文法は、媒介語を使用しないでどこまで教えることができるか、媒介語を使用した場合にどこまで教えられるか、そして「どんなに頑張ってもここまで」という限界などを論じること。
18. そんなことを、文型・文法の一定のグループごとや、個々の文型・文法ごとに明らかにしてほしい。そして、そういう限界を明らかにした上で、文型・文法に関してどのような指導をどの程度実施するのが、日本語習得上最も有益かを論じてほしい。そんなことを論じてこそ文法研究者の「洞察力」です。
19. 実は、そんな限界付けとグループ分けの作業を『新次元』の第3章の1と2及び第7章で、試みに、しています。わたしは日本語文法研究者ではありませんが、日本語文法「承知」者として。
20. 研究者への期待は、研究活動で養った豊かな知識、視点、洞察などを基礎として、日本語習得の見取り図をどのように描くか、日本語の基礎の育成としてどのような教育企画をするか、どのような学習活動が習得を促進するかなどの見解です。日本語学の人でも、社会言語学の人でも、日本語習得研究の人でも。
21. そうするには、日本語教育の経験が必要ではありますが、経験が限られていても、研究活動で養われた鋭敏な目で日本語の習得と習得支援のキモを捉えて、先のような見解を提示してほしい。それでこそ立派な人文系の研究者! そういう見取り図等なしに「研究の知見が役に立つ」と簡単に言わないでほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
