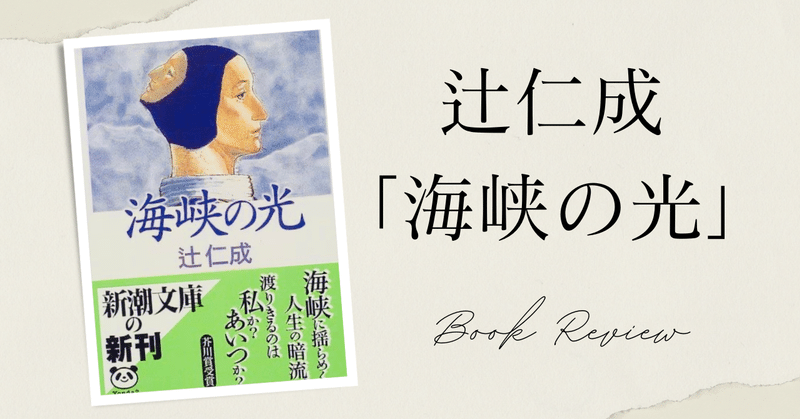
文体から放たれるオーラ|【書評】辻仁成「海峡の光」
小説だろうが詩だろうが、エッセイだろうが評論だろうが、すぐれた作品にはかならずある種の「オーラ」というものがただよっている。たとえそれが、あらすじさえ知らないままにはじめて繙読する作品であろうとも、冒頭の一行ないし数行に目にとめるだけで、これは、とこちらに思わせる一種異様な「佇まい」を感じさせる作品というのが、確かにあるのです。
陸に上がった後も海のことがいつまでも忘れられない。
函館湾と津軽海峡とに挟まれたこの砂州の街では、潮の匂いが届かない場所などなかった。少年刑務所の厳重に隔離された世界も例外ではなく、海峡からの風が、四方に屹立する煉瓦塀を越えてはいともたやすく吹き込み、懐かしいが未だ癒えない海の記憶を呼び覚まさせる。
第116回(1996年下半期)の芥川賞受賞作である辻仁成の「海峡の光」は、このような冒頭ではじまります。わたしは先に、「オーラ」とも「佇まい」とも表現しましたが、それは、「予感」とよんでみてもいい。この冒頭にはすでに、「海」を忘れることができない語り手の後ろめたさであったり、「砂州の街」「少年刑務所」という閉鎖的で息ぐるしいムードであったり、この作品の全体をつらぬく暗い主題が、着実に織り込まれています。

作品のあらすじは、ざっとこうです。語り手の「私」は、もともと青函連絡船の客室係をしていましたが、その廃航がきまると、少年刑務所に職を得ることになります。あるときそこに、ひとりの男が入所しました。花井修という名のその男は、かつて少年時代に「私」をいじめていた優等生であり、「私」は往時の傷がうずくのを感じつつ、看守として花井の監視につとめるのでした。――
やや図式的とはいえ、小説の設定もじつに魅力的だと感じます。かつて自分をいじめていた相手が、ときをへて、受刑者として自分の監視下におかれることになる。被虐と加虐の構図をたくみに転換させながら、「私」の心理的な葛藤をうきぼりにしようとするたくらみは、作者の非凡な発想力を感じさせます。
設定の面だけではなく、この小説は、文体の面からも辻仁成という作家の力量のほどを十分に伝えてきます。たとえば、つぎの描写。
内洋を抜け出る時に見る左舷前方に、照る日を浴びて、凛として輝く函館山は風光絶佳この上なく、父親の魂が宿っていると信じるに相応しい貫禄であった。青森から帰還する時、山は海原の先に蜃気楼のようにじわりと頭を突き出していつも出迎えてくれた。片雲が山の稜線を掠める時、私には父が思い耽り太い眉根を顰めたように感じられ、旭光に赤く染まった父の面輪は漁に出る前のあの勇ましさに満ちた顔貌そのものだった。
芥川賞受賞時の選考会において、ある委員からは「生硬な漢文的スタイルの文章」とも評され、賛否両論あった本作の文体ですが、上記の引用からも顕著にうかがえるように、ほとんど、三島由紀夫のそれを彷彿とさせる力強さがあります。
文体というのは、いわば画家が対照を描く際の色づかい・筆づかいのようなもの。それは作品の主題・モチーフから必然的に導き出されるべきものですが、男性的で精悍な本作を描くにあたってこの文体を選び、しかもそれを全編とおして貫徹することは、中途半端な「模倣」ではできない技術だったはずです。
そしてこの「文体」こそ、わたしが本作に感じた「オーラ」の正体。ぱらぱらとページをたぐるだけで、(まるでゴッホの絵のように)こちらを圧倒してくる凄みがそこかしこに満ちています。
最近でこそ、創作よりもむしろ、息子とのパリでの日々をつづったエッセイや料理エッセイなど、そのやわらかい文章で耳目をあつめている観のある辻仁成ですが、そしてそれはそれでユニークな執筆活動ではありますが、それを下ざさえする小説家としてのたしかな力があることを、この一作はよく教えてくれます。
いまは亡き石原慎太郎も、芥川賞の選考の際に「氏の作家としての力量を感じさせる幅も奥も深い作品である」という好評価をしています。三島、石原といった、よい意味で「マッチョ」なラインに、この「海峡の光」も位置づけることができそうです。じつに、強く、読ませる作品です。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
