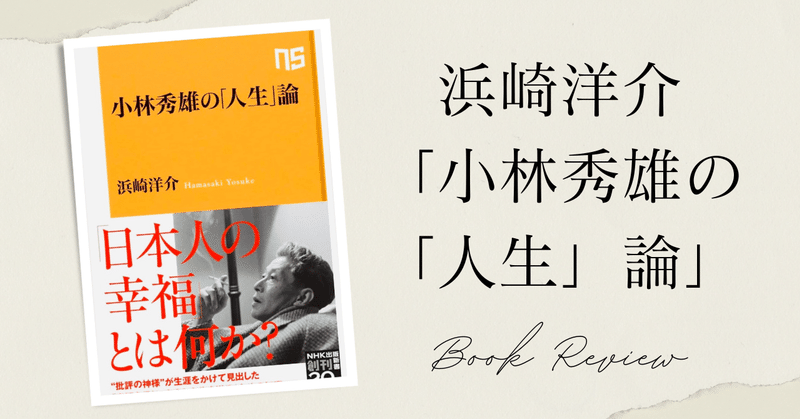
人生いかに生くべきか|【書評】浜崎洋介「小林秀雄の「人生」論」
その名前を聞くだけで、あるいは目にするだけで、なにか胸に迫るものがある。そういう存在がみなさんにはいらっしゃるでしょうか。
小林秀雄。わたしにとっては、まさにこのひとが、そうした存在にほかなりません。
以下、ほとんどが、本書の書評を逸脱し、小林秀雄をめぐる個人的な(感傷的な)メモワールに終始しますが、なにとぞ、ご海容をたまわりたく存じます。
来年、2023年で、死後40年を迎えようとしているこの批評家の名前を、10代、20代、30代の若い読者はどれだけ認知しているのか、正直、なかなか心もとない気がしています(ちょうど死後30年を経た年(つまり2013年)に、センター試験(現・共通テスト)の現代文に小林秀雄の「鍔」という文章が出題され、すこしだけ話題になったことはありましたが……)。
かくいうわたしも、小林秀雄の没後の生まれ。彼が、特に「昭和」という時代にどのような(どれだけの)感化をあたえていたのか、その知的雰囲気を肌感覚としていっさい知らずにいます。
わたしは、大学、大学院と日本の近代文学を専攻していましたが、そこで中心的に研究していたのが、小林秀雄でした。足かけ5年。それは、文学を深く研究するための期間としてはあまりにも短い(短すぎる)時間だったともいえますが、ともかくも、20代の前半という(傲慢で切実な)人生のモラトリアム期を、わたしは小林秀雄の言葉を支えにしてかろうじて「生き抜く」ことができたのでした。
その期間に、わたしは、小林秀雄の全集はもとより、小林秀雄について書かれた研究書、評論、エッセイ、あるいは回顧録のたぐいまで、さまざまに手にとることになりました。そして、ふしぎなことに、それら小林秀雄について語る人びとは(称賛する側も批判する側も)、ある共通した「感覚」を共有しているような気が、いつもわたしにはされていました。
その「感覚」というのは、すなわち、だれにとっても小林秀雄が(わたしがそうであったように)「人生いかに生くべきか」、その指針をあたえる存在として受けとめられている、というものでした。
じじつ、いつからか小林秀雄は「人生の教師」と評されるようになるわけですが、本書(ここでようやく今回取りあげた本に触れることになります)のタイトルにも「人生論」とあるように、昨年出版され(そして先日に山本七平奨励賞を受賞した)この本も、まさしく、その文脈上にあるといってよいでしょう。

著者の浜崎洋介氏は、1978年生まれ。ちょうどわたしとひと回り年が離れているこの著者も、大学院の修士論文で小林秀雄をあつかったそうです。
小林秀雄についての本書の論考にここで詳細に立ち入ることはできませんが、以上の経緯を踏まえつつ、わたしが強い暗示を受けたのが、「あとがき」に書かれている内容でした。
そこで著者の浜崎氏は、本書の成立過程を明かしています。それは、「最初、ゆっくりと半年から一年ほどかけて小林論を用意しようと思っていた」のが、出版社から「どうしても」と急かされ、わずか2、3週間ほどで脱稿した、というものです。
著者はまた、「小林秀雄という文学者の人生と思想を、ある程度まで俯瞰的に、そして分かりやすくまとめ上げるためには、こういう外からの強制力がないと無理だったかもしれない」とも語り、こう付言します、「そうでないと、おそらく私は、小林の一言一句にこだわりながら、この本を、もっと『文学的』に書いていたはずです」。
小林秀雄は語りがたい。これは、小林秀雄に大なり小なり影響を受けたひとならだれでも抱く感懐だろうと思われます。語り手の全人格を賭して向きあわなければ、とうてい歯が立たない、そういう切迫した覚悟をこちらに要請する存在というのは、文学史上そう何人もいるものではありません。
浜崎氏の言葉のはしばしからも、すくなからず小林秀雄から、文学的・思想的影響以上の影響を強く受けたのだろうことが察せられます。と同時に、この著者もきっと、小林秀雄という存在・対象から受けた「直観」を信じて、文芸批評家としての「道」をここまで歩んできのだろう、ということも。
ふたたび個人的な話をしますけれど、本書の著者、浜崎洋介氏に、わたしはある「恩義」を感じてもいます。
わたしが以前に、集英社の「すばるクリティーク賞」(現在は廃止)という批評の賞に応募し、最終候補の一作となったとき、その選考委員のひとりが浜崎氏だったのです。
わたしの文章は、宮崎吾朗のアニメーション映画「ゲド戦記」を拙速に論じたものでしたが、その選考座談会において浜崎氏は、書かれた内容のみでなく、わたしがどのように文章というものに向き合っているか、その姿勢にまで意を汲んだコメントをしてくださったのでした。
……今回の六十九本のなかでこの批評が一番スラスラと最後まで読めたんです。「読みやすさ」というのは、文章の抑制や、論運びの慎重さとも関係しますが、ともすれば恣意的になりがちなアニメ批評において、対象の具体的手触りがあること、「他者」を意識して書けていることの証拠です。つまり、対象作品を丁寧に描写したうえで、そこから自然に立ち上がってくる形で問いと答えの論理が組み上がっている。
浜崎氏をのぞくほかの選考委員がわたしの文章を推すことはありませんでしたが、浜崎氏の言葉は、確実にわたしの「支え」になりました。
そしてわたしが、神秘的文体を駆使した難解で内向的な「批評」ではなく、「他者」への「橋渡し」となるリーダブルな文章を書きたいのだ(それでいいのだ)とあらためて追認できるきっかけとなりました。
過剰な知識で武装し、ともすると、およそわたしたちの生活経験にはなんの役にも立たない知的・観念的遊戯にふけりがちの「批評」界にあって、「読みやすさ」というのは「他者」を意識して書けている証拠だ、そう堂々と語った浜崎氏。
本書もまた、特定の知識人だけにむけた内輪の言葉ではなく、小林秀雄の「こ」の字も知らない一般読者にまでひろく「開かれた」言葉で書かれています。そしてそれゆえにこそ、小林秀雄について(あるいは、小林秀雄を「ダシにして」おのれを語っている浜崎洋介氏について)、読者がある「直観」を得るのに、これ以上はない最良の一冊になっている。わたしは、そう断言します。
ひとりでも多くの迷える(若い)読者が、本書を入り口に、小林秀雄の言葉に触れる機会が増えればと願うばかりです。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
