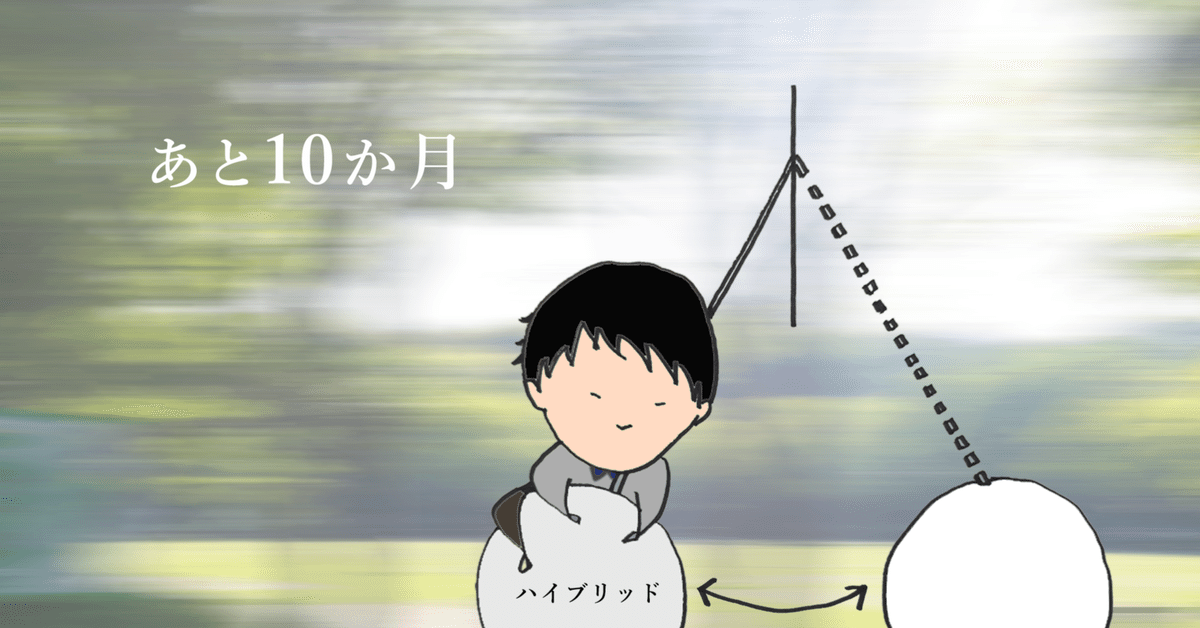
博士論文2022年4月の報告書。
4月の後半にオルガテックTokyo 2022というイベントに参加した。そこでデザインファームであるTakramの渡邉康太郎さんと車メーカーのMAZDAのデザイン役員の前田さんのトークイベントがあったのだが、話題になったのが「ハイブリッドワーク」についてだった。渡邉さんが「ハイブリッドワーク」という言葉に対して、オンラインとオフラインのハイブリッドや地方と都心のハイブリッド、本業と副業(複業)のハイブリッドもあるという一般的な理解を示しながら、同時にもう少し新しい別の切り口の中での「ハイブリッド」もあり得るのではないか、という視点を提示した。
僕がその場でふと思いついたのは、建築家である辻琢磨さんのエッセイのWeb連載「川の向こう側で建築を学ぶ日々」である。これはすでに独立して建築家として活躍されている辻さんが、自身の事務所を経営しながら同時に別の事務所でスタッフとして修行し始め、経営者と所員の行き来というまさに「ハイブリッド」な働き方を実践する中で見えてくるこれからの設計事務所のあり方について綴っていくものである。
このエッセイを興味深く拝読したのでツイートしてみたところ、著者の辻さんからリプライがあった。辻さんはSHUKYU magazineに掲載されていた僕の論考も読んでくれていたらしく、もし機会があれば浜松にもぜひというメッセージをいただいたので、すぐに浜松まで会いにいってきた。ツイートでのやり取りが4月中旬くらいのことで、時間が合ってお会いできたのが4月下旬。色々とお話し、作品を案内していただき、お施主さんともお話しさせていただき、地域の様々な人々にお会いしてお話しさせていただいた。
すでに建築家として活躍している辻琢磨さんが、新たに別の事務所で修行する日々をつづる連載「川の向こう側で建築を学ぶ日々」が非常に生々しく面白い。経営者と所員という2つの視点を行き来しながら事務所を分析。地域での設計事務所のあり方についても考えさせられる。https://t.co/x3FoQh2p5j
— 石田 康平 (@koheii_g) April 13, 2022
はじめまして。お読みいただき有難うございます。SHUKYUの記事、拝読しております。現実を直視する姿勢に大変共感しました。同じ号で岡田武史さんにインタビューしている竹山くん@amiciziasole が僕の高校の同級生で、彼に石田さんの記事を紹介してもらいました。機会と時間がもしあれば浜松に是非。
— 辻 琢磨 (@tsujitakuma) April 15, 2022
メッセージありがとうございます!SHUKYUの記事を読んでいただき、とても嬉しいです!!浜松、ぜひ伺わせてください!
— 石田 康平 (@koheii_g) April 15, 2022
竹山さん@amiciziasole 、記事をご紹介いただきありがとうございます!
SHUKYU magazineに寄稿されていた浜松在住の竹山さんという方とも会い、街を案内していただいた。竹山さんが運営しているお店「みかわや」、障害者施設「レッツ」(ここは非常に面白い雰囲気のある場所だった。帰り際に大量の施設の報告書の冊子ももらった)、写真家の営むおしゃれな本屋(浜松は空軍基地があったため空襲を受けており多くのビルが倒壊した。そのため戦後に複数の主体によってビルが建設されたため、リノベーションやコンバージョンがうまくまとまらなかったりもするらしい。その本屋はそうした中でリノベに着手したビルの中にあり、他にもおしゃれな服屋などが入っている)など色々と訪れた。美容師の人が様々な場を取りまとめていたりもするらしく、建築家や編集者、写真家、アーティストなどが密に繋がり、地域を盛り上げるべく相互連携しながら相乗していく。今回の経験を通して、地方のクリエイティブなコミュニティの中での設計事務所の立ち位置について解像度が高まったように感じられた。そして何より辻さんと竹山さんの案内で街を歩き回り人に会い、人と街の空気感のようなものを感じ取れたことで、エッセイに書かれている内容に対する理解も非常に深まった。とても貴重な経験だった。






博士最後の1年に対する考え方の変化
4月の初めに、「社会に戻る準備」をすることに決めた。この博士論文マラソンもあと1年足らずで終わる。ずっとゼエゼエはあはあ言いながらぼやきながら走ってきたこのマラソンが急にあと少しにも感じられてきた。博士論文の第1稿の提出は今年の11月なので、実質的にはあと7ヶ月ほどでおおよそを仕上げないといけない。そして同時に、博士の次はどうするのかというようなことも考えないといけない。博士の後はどうするの?と聞かれるたびに「何も考えていないんです」と答えてきたけど、そろそろ少しずつ考えてみても良いのかもしれないという気分になってきた。
社会に戻る準備その1:進路の方向性を決める
ひとまず、これまでの自分の研究者としての蓄積は一度捨ててみることにした。端的にいえばアカデミアを離れてみたいということだ。博士を取るような意味があまりないような場所へいこうと思う。これは個人的な仮説なのだが、仮に博士を取れたとして、その意味はむしろアカデミアの外でクリアになってくるような気もする。数年しがみついて取れるその資格自体にあまり価値はないだろう。そのしがみついた時間と忍耐がなんらかの意味は持ちうるとしても。
ということで、7年くらい建築を勉強してきたのに設計実務を知らないというのもなんだかなあと思うので(もちろん設計実務といっても色々なスタンスや粒度、専門性があるにせよ)、一度設計事務所へいってみようと考えている。設計事務所へ行きたいというか、設計という軸となる専門性を身につけたいということ。
映画監督や建築家の作品を見ていると、おそらく力のピークは40歳前後なのだろうと思う。そこで一番いい仕事をできるかどうかが勝負のような気がしているし、あるいはそこでいい仕事ができなければそのあとはしんどいのだろう。宮崎駿は38歳でカリオストロをやって43歳でナウシカを作る。村上春樹がノルウェイの森を書くのが38歳。新海誠が言の葉の庭を作るのが40歳で、君の名はを作るのが43歳。丹下健三は29歳で大東亜のコンペに入り、39歳で広島平和祈念資料館を、45歳で香川県庁舎をつくる。黒澤明は40歳で羅生門を作り、44歳で七人の侍を作る。およそ30代前後で世に出始めて、40代前後で代表作が作られる。小林秀雄がモオツァルトを書くのが44歳。高畑勲のアルプスの少女ハイジは39歳。キューブリックが2001年を作るのが40歳。磯崎新が大分県立大分図書館を作るのは36歳で、群馬県立近代美術館、北九州市立美術館を作るのは44歳。槇文彦がヒルサイドテラスを作るのは41歳、安藤忠雄が住吉の長屋を作るのは35歳。コルビュジェのサヴォア邸が44歳。手塚治のアトムのアニメは35歳、39歳で火の鳥の連載、44歳でブッダ、45歳でブラックジャック。およそこのあたりがボリュームゾーンなのだろう。西沢立衛の豊島美術館も44歳の時。もちろん槇文彦の『風の丘葬祭場』のように、年齢を重ね死生観が醸成されなければ到底作り得ない作品もあるが、体力と経験と精神力がいちばんバランスよく高まってくるのは40歳前後なのだろうと思う。
才能もなくスロースターターな自分がピークを迎えられるとしたら40歳〜45歳くらいなのだろうと思っている。この時にどういうレベルに達していたいかを考えた時、ここからの数年間で設計を身につけたいなあという気持ちになった。今の小さな損得ではなく、自分がピークを迎えられる時に理想的な状態に持っていけるようにしたい。それは今後研究者になりたいと思った時にも有効な経験となるはずだし、何より今のスキルセットのまま研究者を目指しても先が知れているという感じが強くしている。実はこの博士の期間で何よりも強く感じたのはそこだった。最近、自分の経験の乏しさが人の言葉の本当の理解を妨げていると強く感じることが多いし、何より今の自分で語れることの幅があまりに狭い。
そういうわけで、ちょっと設計事務所にいってみようという気持ちになっている。そのことだけを決定してみている。すると「じゃあどういう事務所に行こう?」と悩み始める。そこで志望の判断の基準のようなものを決めてみた。経験的に自分が伸びるのに必要な条件は次のようなものかなあと考えている。
・十分な情報、蓄積(過去の資料とかみながら学ぶのが得意なので)
・ある程度の自由度(これはあんまり重要じゃない)
・最低限の賃金(生活はしたい)
・国際性(あるととても嬉しい)
・コネクションが広がる場所(これは多少は重要)
・自分が良い、すごいと思っている作品を作っているチームであること
特に一番最後の「自分が良い、すごいと思っている作品を作っているチームであること」はすごく重要だと感じている。組織なのだからある程度の歪さはどこにでもあるだろうし、嫌なこともあるだろう。だからこそ、とにかく出来上がったものの可能性を信じられないと忍耐を信じられないのだなと最近わかってきた。そういう意味で、組織の運営のホワイトさよりは作品を信じたいと今は考えてみている。
そういう基準をもとにいくつか事務所をリストアップし、そこにいる人たちにコンタクトを取って話を聞いてみたりしている。これが社会に戻る準備の一つ目。4月の頭から急に初めてみたこと。ロンドンの事務所なども調べてみていたのだが、ちょうど5月末から世界トップ50大学を出ていれば仕事先がなくてもイギリスに3年(博士でないと2年)いられる驚異的なビザが始まることを知った。本来は就職先などの「ホスト」がなければビザは取れない。ロンドンに長くいた人の話によると、これはサービス期間らしい。かつても存在したビザだが、外国人が多すぎるので厳しくしていたという。コロナ禍もあり、EU脱退もあり人が獲得しづらくなっている現在の状況の中で人材を確保するために復活したらしい。日本だと東大と京大の出身者が該当するのだが、普通は2年で博士卒なら3年間は向こうで職探しをしながら暮らせるということで、せっかくなので海外の事務所もとても良いなあと考えている。今はこの程度。来月あたりにはポートフォリオを作ってみて、色々メールで送りつけるということを始められればなあと考えたり。
社会に戻る準備その2:群馬出張
上記の準備活動と紐づいて、4月の後半に群馬へ。なぜかというと藤本壮介さんという建築家の作品を兼ねてより良いなあと思っていたので、事務所にもちょっと憧れがあり、藤本の作品をみにいくため。白井屋ホテルという作品。体験はとても素晴らしかった。とにかく泊まった方がいいと思う。ラウンジ利用などだけではなく。
夕方には、群青の空の色とレアンドロ・エルリッヒの作品「ライティングパイプ」が吹き抜けの空間を照らす。水道管の亡霊ともよばれるレアンドロの作品は、深夜になると虹色に輝く。朝になると、空間の表情はまたガラッと変わっている。漂泊されたような白い空間に朝の日光が差し込みキラキラと輝く。宿泊しているあいだに、時間が経つにつれて空間がどんどん異化していくような幻想的な体験。単なるアートホテルというよりも、多様なアーティストの共振によって体験。
部屋を出るとすぐにパブリックスペースの吹き抜けに面しているので、突然街に出たような感じもあるが、コンクリートの躯体やアート作品がちょうどそのあいだで緩衝材となっているのは初めての体験。美術館でもアートレジデンスでもなくどこかの路地に迷い込んだような感覚が楽しかった。他にも気になる建築家の作品を見て回りたいと考えている。














能の体験~能面をつけて舞台を歩く
4月上旬には、博士論文で取り扱いたいと思っていたので、やっと能を観に行った。4月9日に鑑賞したのだが、この日は知人の主催するイベントがあり、国立能楽堂で能鑑賞の前にプロの能楽師さんによる解説と、能舞台体験などをした。これまでにも能楽師さんと話したり、能面師さんと話して京都の工房にまでいっていたのに、能をみるのは初めて。能は言葉がわからないとかなり理解に苦しむことがある。また意図や構成がわからないとかなり苦しい。そのために「何度かみてやっと良さがわかるもの」としばしば説明される。色々と事前にディスカッションし続けてきて観点と妄想を膨らませてきたおかげで、初めての能も解像度高く眺めることができた。これは良いことだった。

能鑑賞の前のワークショップでは、能面をつけて舞台を歩いてみたりもした。これは強烈な体験だった。この体験を通して、能の理解が格段に深まったからだ。

能面をつけると視界が狭まる。すると体を大胆に動かしたり傾かせるのが怖くなりすり足になり背筋が伸びる。また装束は重いために体の動きはゆっくりになる。おそらく手術ロボットみたいに人の動きの振動や誤差を重さで消しているのだろう。演者の動きの中にアニメーションのような滑らかな連続性が生まれる。また舞台の斜めの道も、かなり連続的に動くことができる。直角だと動きづらい。劇中にも連続的な場所として感じられる効果はあったが、動き方とも関わっている。能面をつけて舞台を歩くことで、こんなにも能への理解が深まるとは思わなかった。

また、能を鑑賞しているときに天狗が出てきたのだが、天狗のつけているお面には口のところに穴が空いていないと事前のワークショップで聞いていた。声が面の向こうへ通らずにシテ方にもろに跳ね返ってくるために大変とのことで、「へえそんなものかな」と思っていたのだが実際に舞台を見て驚いた。能面が口のところに穴が空いていないので音が面を回り込むように広がって聞こえ、能楽師の迫力ある声が空間的に広がってまるでこの世のものではない声のように聞こえる。面をつけているその人が、いたこみたいに見えた。面が演者の命を吸って声を響かせているようにもみえる。次第にその音的な空間性の体感のためか、能面が浮かび上がり、人が縮み、まさにそこに何かが来たという感じがしたし、視界がぼやぼやとした。人の声出しが必死で顔が赤くなるほど、能面の涼しさとの対比で「命を奪い取られている」という感覚がとても強まった。なるほど、能面に口が空いているかいないかだけでこれほどまでに効果があるのかと驚いた。他にもたくさんの気づきを得ることができ、博論の事例データベースが一つ大きく進んだ気がした。これも5月にかけて一度全て蓄積の内容をまとめていく予定。
博論の構成
そうしていろんな経験をしながら、4月の頭から中旬にかけて博論の脚本のようなものをかいた。まだ文章にできていないのでこれから。これは5月中旬までの目標。2週間ほど図書館に通い、毎日8〜9時間くらい考えて書き直していくということをやった。ひとまずこれだけ。A4で29枚。途中で捨てたものも多いが、これもかなり書き直しが入る予定。4月後半は、途中でかなり詰まってうんうん悩んでいたら過ぎてしまった。



ここから先は
2025年3月に「夢における空間論」を書き上げるまで
旧「2023年3月に博士論文を書き上げるまで」。博士論文を書き上げるまでの日々を綴っていました。今は延長戦中です。月に1回フランクな研究報…
サポートは研究費に使わせていただきます。
