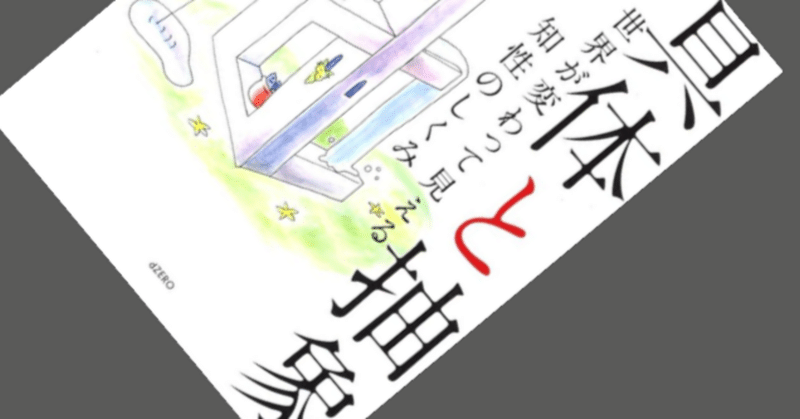
#16 【育成術】具体から抽象へ
こんにちは。エンジニアのこへいです。
先日、思考のレベル上げにオススメされた具体と抽象を読了しました。
130ページで4コマ漫画やイラストが散りばめられておりサクサクと読めるのですが、非常に内容が濃く読み応えがありました。
今回は自分が育成の時に気を付けているポイントと学びを具体と抽象の第10章 価値観に絡めて紹介します。
第10章 価値観 「上流」と「下流」では世界が違う
第10章のポイントを引用します。
会社 の オフィス ワーク で あれ、 工場 の 作業 で あれ、 およそ 仕事 という もの は「 抽象 から 具体」 への 変換 作業 で ある と いえ ます。 いわゆる 仕事 の 上流、 つまり 内容 が 確定 し て い ない「 やわらかい」 企画 段階 から 概要 レベル の 計画 が でき て、 詳細 レベル の 計画 になり、 それ が さらに 詳細 の 実行 計画 へと 流れ て いき ます。 これ は、 商品 を 販売 する のでも、 建物 を 建てる のでも、 イベント を 実施 する のでも、 多く の 仕事 に 当てはまる 流れ です。
注意 す べき は、 上流 の 仕事( 抽象 レベル) から 下流 の 仕事( 具体 レベル) へ 移行 し て いく に ともない、 仕事 を スムーズ に 進める ため に 必要 な 観点 が 変わっ て いく という こと です。
上流と下流の価値観の違いについてもわかりやすく説明されています。
上流
抽象度が高い/全体把握が必須/個人の勝負/少人数で対応/創造性重視/多数決は効果なし
下流
具体性が高い/部分への分割可能/組織の勝負/多人数で対応/効率性重視/多数決が効果あり
上流から下流を一貫した仕事
私の職場では少人数のチームでプロジェクトを担当するため、それぞれのメンバーが上流から下流を対応します。
当然、チームにジョインした直後にプロジェクトの全体把握をして成果を出していくことは現実的ではありません。
そのため、まずは具体的な仕事から任せ、仕事をこなす成功体験を積み上げながら知識面のキャッチアップをフォローし、少しずつ抽象度の高い仕事を任せていきます。
人それぞれの経験や能力に合わせて仕事の振り方を工夫し、各メンバーが自走できるような育成をしています。
飲食店の新入りの育成でいうと
「シェフの気まぐれカレー」が人気の飲食店での育成に置き換えてみます。
シェフの気まぐれというのは抽象的であり、いきなり真似してみろというのは難しいですよね。
そのため、まずは具材を切るというシンプルな作業から始めます。
その際に「気まぐれ」というのは季節に合わせた材料や味付けをしていること。材料の選び方、切り方でどのような魅力を表現しているのか。など上流の価値観をどのように構成しているかを共有していきます。
そして、具材のカット、トッピング、サイドメニュー作り、気まぐれカレーの仕込みのように少しずつ抽象度を上げていき、気まぐれカレーの試作のような上流の仕事へのチャレンジの場を作ることで、お客さんに出せるカレーを作れるレベルに成長してもらう。
というイメージです。
具体と抽象からの学び
具体と抽象では上流と下流では全く異なる世界観での仕事であることが明確に説明されていました。
抽象度の高い仕事を任せられる人とそうでない人の差を経験や能力の有無と考えていましが、生きている世界が異なるというのにとても納得しました。
近年、私のチームは扱うプロジェクトの拡大に伴いメンバーの数が増え多様性が出てきており、下流の仕事が得意なメンバーにも活躍いただいています。
彼には上流を目指してもらうのでなく、下流のエキスパートを目指してもらうのが良いというのが自分の中で明確になりました。
その他の章でも多くの学びがあり、一読の価値があります。
年末年始のお供にいかがでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
