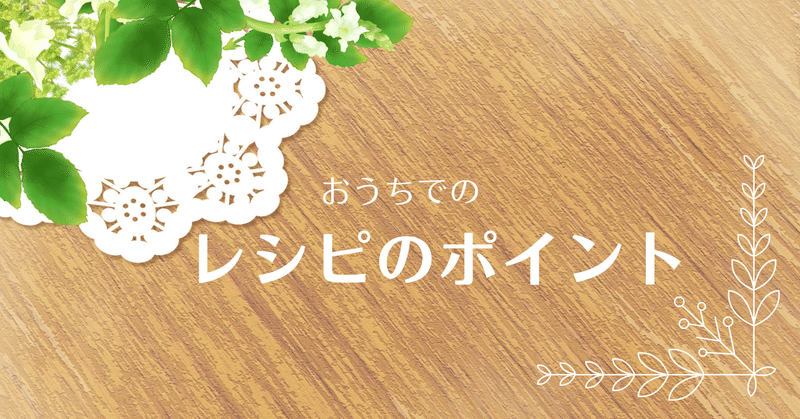
在宅栄養のレシピについて
在宅栄養で大切なことは、「どれだけ継続することが出来るか」これにつきます!
生きることで欠かすことのできない「食事」
それを病気になったから、介護が必要になったから、といって1つ1つみんなと違う食事をしているとかなり大変ですよね。
たくさんの人が、最初はとても手厚くするんだけれど、それが1週間・1か月・3か月・6か月となると「したいことと出来ること」のギャップに苦しまれている印象です。
生活しているのだから、出来る日と出来ない日があって当たり前。
大丈夫。そんなに気負わないで下さい。
今回は、管理栄養士として大切な仕事の1つである「レシピづくりのポイント」についてまとめていきますね!
レシピづくりのポイント
家族構成、食生活環境を考慮して分量を決める。
2人分以上の分量を記載する。
分量は、目分量で記載する。
複雑な調味料の計量は極力避ける。
無駄な出ない分量を考える。
購入可能な食材をチョイスする。
展開メニュー、使いまわし方法も提案する。
ホームヘルパーによる調理は、サービス時間内にできるメニューを提供する。
保存方法、消費目安も一緒に伝える。
さじ加減などに関しては、一緒に体験してもらう。
材料ポイント
・冷蔵庫にあるもの、保存食品を使用する。
・一般的な家庭にあると思われる材料を使ったレシピ、簡単にできるメニューなど、柔軟なレシピを準備する。
・高齢者、家族、ホームヘルパーの人にも、基本的な食事知識を理解してもらい、実践してもらう。
栄養三色運動
・食事知識などについて、最も分かりやすい方法とされている。
「食品群を3色 (赤・緑・黄)の食品群に分ける」
赤:血の色から連想される色。血・肉のもとになるたんぱく質源。
魚介類、肉類、大豆・大豆製品、卵、牛乳・乳製品など
緑:ビタミン・ミネラルの供給源。重要な食物繊維を摂ることが出来る。
緑黄色野菜を中心として、そのほかの野菜、海藻類、果物など
黄:働くもとになるエネルギー源。炭水化物・脂質が含まれる。
穀類、芋類、砂糖、油脂など
・3色の食品を1回の食事に取り入れることで、より良い体力維持をしていくことが出来ると考えられている。
「実践方法」
・主食 (黄)+主菜 (赤)+副菜 (緑)+副々菜 (緑)の「一汁三菜」を意識する。
・この4つを1回の食事に用意することが大切であることを理解してもらう。
「主食以外の食品の選び方」
「ま・ご・た・ち・わ(は)・や・さ・し・い」
ま:豆類。大豆製品などの植物性たんぱく質源。
ご:ごま。ごま・種実類で体にやさしい植物油。
た:卵。必須アミノ酸が揃っている優良たんぱく質。
ち:乳。牛乳・ヨーグルトなどのカルシウム供給源。
わ:わかめなどの海藻類。ミネラル・食物繊維の供給源。
や:野菜類。果物とともにビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源。
さ:魚類・肉類。動物性たんぱく質源。
し:しいたけなどのきのこ類。ビタミン・食物繊維の供給源。
い:芋類。エネルギー・ビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源。
・具体的な料理を示して、応用したものも作ってもらう。
・ゆっくりと説明して、身体の健康を維持するためには毎日の食品の選び方が大切であることを理解してもらう。
・摂取するタイミングを間違えず、規則正しく食べることが、健康への近道であることを理解してもらう。
*以上の内容について、出来たらいいなと思う理想ではあるが、実際には自分の生活もあるため、ここまで上手に行くことは少ない。
「現実は…」
・寝ている時間が長くなることで、食事タイミングが合わない。
→ 食べられる時にしっかりと食べてもらえるように、簡単に作れて冷凍できる料理をいくつか紹介する。
・好き嫌いがあるため、偏りのある食事になる。
→ 嫌いなものは取り除きつつ、別のもので代用できないかを考えて提案する。
・毎日料理をすることは大変だし、休息がない。
→ 冷凍する方法を考えたり、市販品を利用して家族が休息をとることも大切。
・食べてもらうことが出来ない。
→ 少し味を濃くして、栄養素を摂取してもらうことを優先する。
(高血圧などの疾患がある場合には、医師・管理栄養士と相談する。)
基本的に自分でしようと思っている人が多くみられます。
苦しいこともたくさんあると思うので、頼れるところは頼ってみてください。
見たことのない景色が見えてくるかもしれません!
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回も読んでくださると嬉しいです*
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
