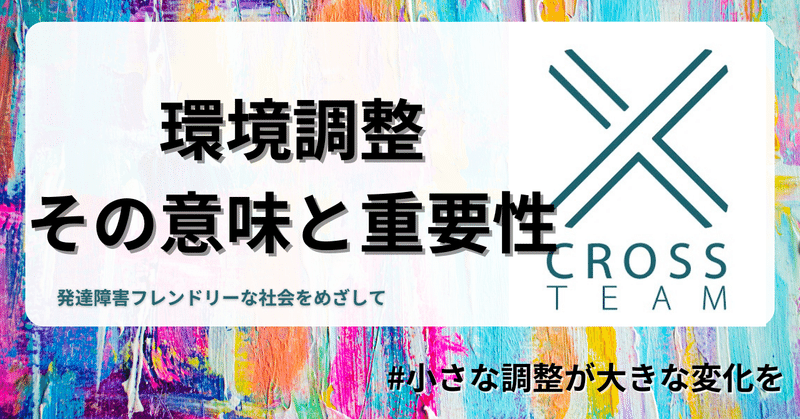
環境調整の意味と重要性
この記事は1,989文字あります。個人差はありますが、3分〜5分でお読みいただけます。
このnoteではVoicy(音声配信)で配信した内容のテキスト版です。ぜひ併せてご活用ください!ちなみに、Voicyは下記チャンネルで毎日更新しています!
今回のテーマは、「自分に合った環境調整の意味と重要性」です。どうぞお付き合いください。
キーワードは「環境」
昨日はVoicyにて澤円さんと対談をさせていただきました(今日の夕方以降にそれぞれのチャンネルでアーカイブ放送します!)。
澤円さんは、(株)圓窓の代表取締役であり、元・日本マイクロソフト株式会社業務執行役員の方で、「プレゼンの神」と呼ばれていたりする、ものすごい方で、昨日もVoicyでお話をさせて頂いたのが不思議なくらいです。
そんな澤さん。ADHDの診断を受けており、また診断を受けたわけではないけれどもASD特性も持っていると公言しておられます。
色々お話をさせていただく中で「環境」というキーワードが出てきました。僕自身も「環境調整が大事」という言葉をよく使うので、それをテーマに少し書いてみようと思った次第です。
一口に環境といっても、幅広い
支援現場に出入りさせていただく際にも、コミュニケーション支援のための絵カードも環境の一つですが、もっと広い視点で見ると、関わる人(=支援者)も大きな環境なんですね。
英国バース大学におられるリチャー・ミルズ先生という専門家の先生が、こんなことをセミナーで話をしていました。
「私たちが変わること、それが唯一できること」
どういうこと?
人を変えることはできません。
僕らも、今日から変わりなさいって言われても変われないですよね。
でも、何かきっかけや気づきがあって、自分自身が「変わってみよう」と思えると変われることはあります。支援現場でも同じです。相手を変えようとするのではなくて、自分が変わることで結果としてうまくいくことはないか探してみることが大切です。
例えば。
大きな音が苦手な方に対して、我慢を強いるのではなくて、どうすれば苦手な音を小さくできるかを考えたり。あるいは、僕らの声のトーンを下げることも大きな環境調整であり、僕らが自分でできることでもあります。
「落ち着いて」「この音でも耐えられるようにして」と相手を変えようとするのではなくて、こちらが変われることを探すことで、結果としてご本人が穏やかに過ごせることを目指す、そんな合意点を見出してみることが重要なのだろうと、僕は思います。
自分に合った環境を
これからの自分の人生を考えるときにも、どんな環境を選ぶのかはとても大切です。
僕も心理の中でも、発達障害という領域を選んでいますが、他の領域だったらどうなっていたのかわかりません。今がうまくできている、役に立てていると自信を持っているわけではありませんが、今よりも馴染めず、役にも立てなかったかもしれません。
また、今とは別の職場にいたらまた違ったかもしれません。
これは、良い悪いの話ではありません。僕らは大なり小なり環境によって影響を受けるものです。だからこそ、自分にとって居心地の良い場所や、成長できる場所、嫌な思いが少ない場所に身を置くということが一つの作戦だと思います。
その際には、自分の長所と苦手を知っておくと、魅力が発揮しやすい/しにくい環境を探す際の手掛かりになるのではないでしょうか。
環境との相互作用で考えてみる
あらゆることは環境との相互作用、つまりお互いに影響し合うものだと思っています。
ASD特性だけで困るのではなくて、それらが不都合として出やすい環境だと困るわけです。
ざわざわした環境が苦手なのに、そうした場所に身を置かざるを得ないと辛いんです。人付き合いが得意じゃないのに、周囲と一緒に行動することを強いられるのもそうです。
自分の特徴と環境から求められることにミスマッチが起きて、かつそれが長く続くと当たり前だけれども、苦しくなってきます。日々の生活の中では、そんなボタンのかけ間違いはないかを確認していくことが必要なことかもしれません。
もし、ずれているなら調整しながら、ピッタリとまではいかなくても、そのズレをどう小さくするかを考えることはできるかもしれません。
でも、環境から影響を受けるって、発達障害に限らず誰でも同じでしょ?
そんな風に思われる方もいると思います。確かに、そうです。
でも発達障害の方々は環境からの影響をより大きく、より強く受けると言われています。そのため、ほんの少し変わったことで大きな影響を受ける可能性があるということは知っておいてもらえればと思っています。
これは、ほんの少しの調整でも大きな支援になり得るということでもあります。
補足はVoicyの配信をお聴き頂ければと思いますので、宜しければVoicyの方も応援していただければと思います!
佐々木康栄
災害時に役立つさまざまな情報
これまでnoteにまとめていましたが、TEACCHプログラム研究会東北支部のホームページに集約しました。宜しければご活用ください。
寄付型セミナー(TEACCHプログラム研究会東北支部)
代表を務めているTEACCHプログラム研究会東北支部で、「寄付型セミナー」を立ち上げています。ぼくの衝動的な行動であることは自覚しています。それでも、今ぼくらにできることを考え、過去に配信したオンラインセミナーを再度配信させていただき、その売上(配信や販売に関わる手数料を差し引いた全額)を能登半島地震の支援・復興に向けた寄付することに決めました。宜しければ応援してもらえると嬉しいです。
その他お知らせ
オンラインサロン「みんなで考える発達障害支援」
クラウドファンディング
▼9月に大阪にて講演会をさせて頂いた「一般社団法人泉大津・発達支援勉強会Lien」さんが、「大阪府泉大津市、及び、泉州地域である近隣市町村一帯が、発達障がいや多様な子どもたちにとってより過ごしやすい地域に」を目指して、クラウドファンディングをされています。特に、4月2日の世界自閉症啓発デーでは、世界中がブルーライトアップされます。これは色々な人に目を向けてもらうための活動でもある一方で、それだけ予算がかかります。
そのため、どの地域でもできるわけではありません。今回、泉大津市内のブルーライトアップをしたい!という想いを叶えるためのクラウドファンディングです。目標金額は220万円です。ちなみに、これは行政と一緒に取り組んでいるものなので、「ふるさと納税」として寄付ができます。
ぼくも応援メッセージを出させて頂いています。どうか皆さんも応援していただけないでしょうか。
皆さんの応援が力になり、その力が地域を進める行動になり、その行動が当事者やご家族の未来になります。
一緒に地域の未来を変えるお手伝いをしてくれませんか?
TEACCHプログラム研究会東北支部関連
▼会員限定動画▼
これまで、会員の皆さんには限定のコラムや動画を配信してきました。現在下記のような動画を配信中です。閲覧にはパスコードが必要です。何度かメールでご案内しておりますが、もし会員の方で「パスコードがわからない!」という方はteacch.tohoku@gmail.comまでご連絡ください。
▼会員限定コンテンツ▼
現在、会員限定の質問フォームを設けています。匿名にしようかとも思ったのですが、会員の方からのご質問であることを確認するためにお名前のご記入をお願いしたいと思います。ご質問については、全てにお返事できるわけではなく、会員の皆さん全体にとって有益だろうと思うものを中心に取り上げて、限定コラムなどで書いていきたいと思います。
▼その他▼
ここに記載した以外にも、東北支部ではさまざまな取り組みを今後もしていきます。会員の皆さんには、「今こんなことを考えています」というのもお届けしますのでお楽しみに。公式LINEもあり、会員以外の方もぜひご登録ください!定期的に情報発信していく予定ですので、「TEACCHって何だろう?」「興味はあるんだけれども、どんな活動をしているんだろう?」という方はぜひご登録ください!
SNS
▼Voicy
▼stand.fm
▼X
https://twitter.com/KoeiSasaki
https://www.instagram.com/koei.sasaki/
https://www.facebook.com/koei.sasaki.5
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
