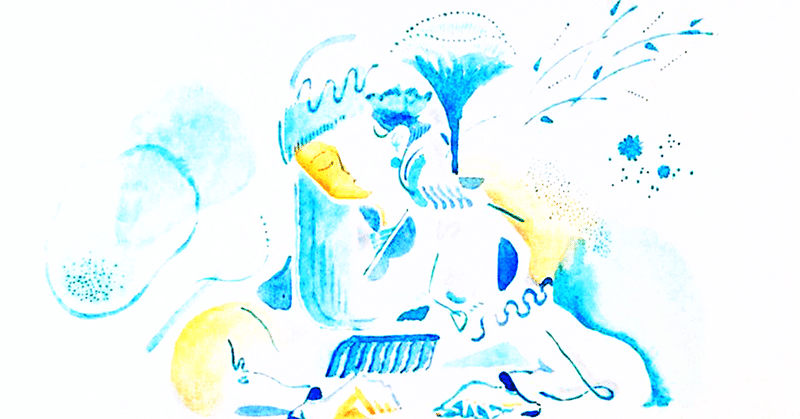
青い椀
ずっと少年でいられると思っていた。よく泣いていたけど、あれだけ誰かを、彼女のさいわいを願っていたあわいは、はじめての、ひかりに満ちていた。
友愛も恋愛もわりきれず、大人になれないまま駆け抜けた、私たち3人をめぐる物語。
無数の断層が、言語を待っている。
断層を水を含んだ指先でなぞり、包み、なだらかな器の曲面をつくる。
2021年 6月
私と彼女は、帰途に着く友人の後ろ姿を、あわいを繋ぐことばも見つけられぬまま、静かに見送った。
友人の痛みに気づけなかった不甲斐なさと、確かに隣にいる彼女とこれからどう生きていけばよいのかと途方に暮れながらも、心の奥底で沸々揺れている本心から必死に目を逸らしていた。
どうしようか、と暫くして同じ言葉が突いて出て、私たちは近くにあった駅前チェーンのカフェに入った。その一角に席を見つけて私たちは腰を下ろした。
私たち3人は大学時代の友人で、今日はそのうちのひとり、ミナの誕生日だった。いつものようにお祝いして、カフェで皆でご飯を食べるのがお決まりのコースだった。ところが今日のミナは様子がいつもと違った。終始何かに怯えているようだった。彼女は、いままでのように振る舞えなくなったという趣旨のことを、ことばに迷いながらとつとつと語りはじめた。最後に会った半年前にも、自分の進路のことで思い悩んでいる節が見受けられたし、少し体調が悪いとは聞いていたが、今日の様子を目の当たりにすると、只事ではないのだろうということだけは解った。
私も、私の隣に座って同じく話を聞いていたアイも、ただ驚きながらも受け止めるしかなかった。
「暫く、会えなくなると思う」
ミナはそう言い残して、両親の迎えの肩を借りながら少し先に停められていた車に乗り込み、姿を消した。
私とアイは、予想外の出来事に、真昼間のロータリーに、虚しく取り残された。
「ミナ、ほんとにもう暫く会えないのかな」
私にもアイにも、ミナが突然姿を消したことのショックは大きかった。
何も返すことばが出なかったが、暫くしてから、3人で会った時に話す筈だった互いの近況について話し始めた。
アイはこの前まで勤めていたデザイン会社を辞め、料理の道を志して専門学校に通い始めていた。その学校での、新しい環境での話を楽しそうにしながらも、少し不安げな表情を見せた。
「バイト先やいままでと違う分野の人たちとなんとか関わるために頑張って、違う私ができちゃった気がする」
そう呟いた彼女に、私は彼女の背中を押したことへの、一度ではない罪悪感を感じた。興味の道を志すことは間違っていないと信じていたが、それが茨の道であることもわかっている。相手のその苦しみに対して何もできない自分の無力さに苛立ちながら、俯く彼女のゆびさきを見ていた。
ひとしきり話して、私たちは店を出て、電車に乗った。そこまで用事があると私は嘘を突いて、彼女の乗り換え駅まで一緒に電車に乗った。並んで座りながら、ぼんやり前を見ていた。改札まで送ろうとする私を、彼女は大丈夫だからと言って手を振った。私もそれじゃあと手を振って、ひとり街の雑踏のなかに残された。明後日から私は新しい職場で働くことが決まっていて、意気揚々としながら朝家を出た。そのときには想像もしていなかった、重く、底の見えない風景が今目の前に広がっていた。この世界に、私とアイだけが放り出されたような感覚だった。私はそれがとてつもなく怖くて、とてつもなく大きな罪悪感に感ぜられた。それ故に、生きなくてはならないと思った。
私は、彼女のことが好きだった。
7月
世の中がコロナとオリンピックで混沌と渦巻く中、私は美術館で働いていた。今期の展示はオリンピックと無関係ではなく、コロナ禍にも関わらず連日多くの人が訪れた。繊細で緻密な作品たちはどれも圧巻で、私もすぐ虜になった。目にした人誰もが子どもに返ったように、覗きこんだり、指差したり、時にそうして悪意なく触れた指先が作品を壊したりもした。そうならないために見守るのが私たちの仕事だった。自分と異なる他者に何気なく触れたとき。相手の呼吸を想像せずに一方的に触れたとき。その相手が自分より小さく密やかな呼吸の持ち主だったとき、簡単に壊れてしまうことがある。そこに悪意がなく、親しみを抱いていたとしても。無意識のうちに他者を傷つけたことが、いままでどれだけあっただろうか。多くのそれは隠されている。わからない。そういうことが、起こらない為に、間を看る。あわいを看る。看る仕事。口ではいくらでも言える。
テレビでは連日、新型コロナウイルスの感染者数が報道された。感染源の特定できないそれは爆発的に広がり、強者を伝って弱者を苦しめた。人が数になり、数が日常になり、医療崩壊が叫ばれるなか、着々とオリンピックは進められているようだった。他者とのあわい。それを紡ぐための祭事、ことばにすれば全部如何様にもかけてしまう。私の仕事も恐らく不要不急、それとも例外に進められる祭事と似た立ち位置なのだろうか。相変わらずの満員電車に乗りながら気の狂いそうな夏の日をひとつずつ潰していった。
スタイリスト
そんな日々の中、職場で笑顔の溢れる人と出会った。その人は自分の本業をスタイリストと名乗った。
いくら多くの人と関わっても、世界は私とアイの2人だけのままだった。それが怖くて私は、去ってしまったミナの代わりを探すように、一緒にいてくれるもう一人を探していた。大学時代の同級生は、アイが会社を辞めて違う道を志したという秘密を守る為に、彼女の希望で候補から外されていた。ミナのような晴れやかさを持ったその人は好適だと思った。
その人は名前を松戸さんと言った。モデルを探していた彼に、私はすぐにアイを紹介した。ミナが戻ってくるまで、せめてもの気晴らしのつもりで。何それと笑いながら、アイは電話の向こう側でいいよと返事をした。
松戸さんの作品づくりは、持ってきた服を着てもらい、対話のなかで自然な姿を撮るスタイルだった。そのひとが、そのひとのまま息ができるように導く、風やひかりみたいな仕事だと思った。
松戸さんにアイを紹介した後、彼は私とアイのふたりの写真も撮りたいと言った。私は元々肌の病気があったため断った。本当は願ってもみないことだったけど、申し訳ない思いが勝りきっぱりと断った。
「じゃあ服のことはいいから、いつか機会があったら、二人でいるところ撮らせてよ。作品じゃなくて、記念写真でもいいから。」
何の問題もない筈なのに、松戸さんの言葉に私は何故か泣きそうな思いでいっぱいになって、堪えきれず部屋で一人泣いた。その夜、短かった髪を更に短く切った。そしてその言葉が実現することはなかった。
夏の終わり
アイと待ち合わせたのは、かつて居た会社の帰りに良く立ち寄っていた駅だった。アイとはあれ以来頻繁に電話はしていたが、会うのは3ヶ月ぶりだった。彼女はボーイッシュな私の格好とは真逆で、清楚な長い髪に前髪を短く切った、古着がよく似合うお茶目な女の子だった。駅からの道を歩きながら近況をかるく語らったのち、アイが顔を上げて言った。
「私ね、もっと早く言おうと思ってたんだけど、彼氏ができたの。」
ひと呼吸おいて彼女は続けた。
「この前会った時話すつもりだったんだけど、ミナがあんな感じだったし、そんな空気じゃなかったから…それに、電話じゃなくて直接言いたかったの。」
彼女の話を聴きながら少しずつ咀嚼していって、私は静かに一人で右ストレートを喰らっていた。
「でも、この前喧嘩しちゃって、」
小さなギャラリーで大きな公園の絵を見ながら紡がれる彼女の言葉に、私の頭の中はぐるぐる混乱していた。
ギャラリーを出た私たちは一先ず飲み屋に入って腹を満たすことにした。
ことばの苦手な私たちは、ひととのあわいを築くとき、ことばが間に合わないことが多くあった。相手からしたらことばが足りないと思われるのかもしれない。そうしたすれ違いは今までも経験があったが、今回もその類の悩みだった。間に合わなかったことばを追って伝えるべきか、すれ違ってしまったあわいを前に迷っているようだった。恋する少女は目の前で唐揚げとビールを口に運びながら、一押しの勇気が欲しいらしく私の方を見た。
「電話、すればいいじゃん。伝えきれなかったことばがあるなら伝えればいい。口にできることばが、伝えるべきことばがあるならー、」
口にしながら、私は大学卒業の頃を思い出していた。
当時いまより遥かに言葉の拙く引っ込み思案だった私は、大切な人にきちんと思いを伝えられぬまま卒業した。卒業式の夜、皆と別れた後、1人地元の駅前のマックで、送るあてもない手紙を書いていた。どうしても喉の奥にひっかかり、そのことばたちが口から発せられることは無かったが、紙面の上には、するすると流れるようにとめどなく記されていった。そんな膨大な量のラブレターを当人たちに渡す気にはとてもなれず、書いてはぱたんと閉じた。そして当時最も大切な友人だったアイとミナにも、ひとり手紙を書いた。ゼミも出身も異なる2人と、何故ここまで親しくなれたのろう。3人で何度もご飯にも、旅行にも行った。2人にはいままでのどの友人とも違う特別な親しさを感じていて、同時にとても尊敬していた。そして本当は、どこか少し遠慮がちな2人を、私は外に連れ出したかった。どこまでも笑って皆で一緒にいられるように守りたかった。強いわけでも、頭がいいわけでもない私が何故そんなことを思ったのかと思うと恥ずかしい。ただ、その笑顔がつづけよと、大学から2人と出会った私には、それを守ることが、自分の使命であるかのように感じていた。卒業してからずっと、その日の風景が自分を動かす核で、卒業してから少しずつ、ことばにして口で伝えることを、転びながら鍛えていった。伝えられない自分を変えたかった。
心地よく酒の回った私たちは地下の店を出て、まだ少し暑さの残る夜風に当たった。アイスたべたいねえという話になりコンビニに入ると、私たちは何故かプリンのコーナーに吸い寄せられた。コンビニを出て少し行ったところに公園があったので、ブランコに2人で腰掛けてプリンを食べながら話した。焼きプリンと、懐かしいミルクプリン。ひとしきり話し終えたアイの表情は会ったときよりも軽やかになっていた。
「じつはね、ここの公園、先週彼と一緒に来て、一緒にこのブランコに座ったの。」
彼女は続けて、人をすきになるって、なんでこうも男女だとめんどくさくなるんだろうと言いながらも、照れながら彼の話をした。その彼女の姿が愛おしくて、その幸せがいっとうつづけばいいと願った。夏の終わりの公園の、朱い電燈の光は金星のようで、愛する人を思いながら、髪を柔らかく光に透かしはにかむ彼女は、うつくしくて仕方なくて、私はたべかけのプリンをカバンに突っ込んだまま、彼女と一緒に声をあげてわらった。
私が誰かをしんから愛おしく思ったのは、それがはじめてだった、
えーえんとなり枝のさきの星をみつめる
好きな人が好きな人をおもい
かたばみのしろい花のようにくるくるするから
ただただ愛おしくて
顔をみてついわらってしまう
たべかけの月がかばんのなかをぺたぺたよごす
それでいい あんしんして つづけよ
霧雨
「いま松戸さんと一緒にいる笑」
アイからのラインに私は複雑な感情が跳ね上がるのを抑えられなかった。当時の自分はミナがいなくなったショックに頭がいっぱいで頭が回らなかったが、この状況を冷静に見ると、彼氏と連絡が取れずにいる彼女に、どこの馬の骨とも知れない男を紹介してしまったともとれた。現に今2人はアイの家の近くで会っている。やってしまったと思った。松戸さんの作家活動、人柄を信頼して話を進めたとはいえ、先日職場の同期に浮いた噂を入れられ忠告されただけに焦りが生じていた。もし危険を感じたらすぐに逃げなねとラインをしてアイを送り出したが、あらぬ心配をしてしまう自分も自分だった。
その日の夜彼女から、「楽しかった!カレーの話とかした〜🍛」とラインがきて、よくわからないがほっと胸を撫で下ろした。
翌日職場で松戸さんと話す機会があり、昨日のことをきいてみたが、楽しかったよの一言で返され、少しだけ煮え切らない思いでふーんと返した。
その後も彼女と松戸さんが会う機会は幾度も会ったが、松戸さんは私にあまりその時のことを話してくれなかった。詳しく言及することを避けているようにも見受けられた。
一方アイは彼氏からの連絡が絶たれたままの期間が長くなり、少しずつ弱ってきていた。
時間はかかるかもしれないけど、信じて待てばいいよ、伝えきれなかったことがあるなら、手紙に託してしまえばいい。私の言ったことなんて本当に無責任でただの我儘な理想論だった。それでも彼女のさいわいを願って、自分にできることは彼女の話をただ聞いて、そんな言葉をかけることぐらいだった。駐車場のガードレールに寄りかかりながらぽつりぽつりと話す彼女の寒く丸まった背中に、コンビニで買ったココアの缶をあてながら、本当は抱きしめて暖めてあげたいのをぐっと堪えながら、弱っていく彼女に何もできない自分の不甲斐なさに触れられなさに苦しくて仕方なかった。夜の霧雨は冷たく、水溜りに映る朱い電燈が泣いているように揺れていた。
その週末の仕事終わり、松戸さんとちょうど閉館作業を共にすることになったので、彼女のことを聞いてみた。
「うん、いいんじゃないの?」
適当な返しに業を煮やして問い返そうとしたとき丁度松戸さんの前のエレベーターが1台上がってきて、「まあ、なるようになるっしょ。そんじゃ、おつかれい」と言いのこして彼は消えた。私が帰るときはとうに彼の姿はなかった。私は勝手に、ミナがいた時みたいに、皆で笑い合える、辛い時に助け合える仲間ができたらいいと思っていた。彼女と共通の友人として、仲間として話せたらどんなに素敵だろう、ミナが帰ってきた時に賑やかなほうがいいに決まってる。私は勝手に、彼にわたしたちの友人になってほしかった、でも当然、私の理想と、彼にとっての私たちとの関係性は違った。彼にとってこれは制作の一環でもあった。当然のはずのよくある思いのすれ違いに、今まで堪えてきたやりきれなさが突然抑えられなくなって、駅の改札で泣いた。暫く止まらなくて、ひとしきり泣いた。
大人になれないぼくら
街はすっかり冬だった
夢の中でアイに会った
彼女の穏やかさを聴いていたら安心して
ただよく眠れよと思って
こんなに待ち焦がれて決めていたことばを
喉を火傷しながら飲み込んで
終電から先を歩いて帰ることにした
言っても言わなくても何を望むかは変わらない
ただ離れた街でさいわいをねがう
果てぬさびしさを気づかれないうちに離れなきゃ
2年振りの道を歩いて帰る
このままえいえんに着かなければいい
どこかすきまに分け入って、はじめからわたしいなかったことにさせてください
月のうえがはんぶんたべられて
やけた星がたくさんおちていました
きょうはおりおんざのなかの星も
道のはしからはしをつうと引く電線もよく見えるのに
いちばんいいたいことはなんもいえない
睡眠薬と珈琲を飲んで鳥のふりをしているね
すぐ寝れるとか言ったけどそんなの嘘に決まってんじゃん
めのまえがよぐみえなくなってきたけど
あなたはどうかしらないでいてください
デヴィッド・ボウイ
「あの時、路地ちゃん駅で泣いていたよね。」
あの日私が駅で泣いていたのを見ていた、というか、見てしまった人がいた。同じバイト先の、一つ下の大原君という男子だった。配属先が違ったのでこれまで仕事で関わる機会は少なかったが、休憩室で会うと時々話しかけてくれるので、顔は知っていた。皆のムードメーカーといった印象の人だった。
「あ、路地ちゃんおつかれー!」
仕事終わりに着替えて出口に向かう階段を上がると、出口の脇で靴紐を結んでいた彼が顔を上げて私に声を掛けた。あまり話したことはなかったが、成り行きで駅まで一緒に帰ることになった。
建物を出ると、彼が急にそわそわしながら
「こんなこと聞くのって悪趣味だよなってわかってるんだけど、だけどどうしても気になっちゃって、聞きたくて待ってたんだ。いや、悪趣味だよなってのはわかってんだけど、、」いつも軽やかに話す印象の彼が、口籠もりながら続けた。
それで一拍置いて彼の口をついて出たのが、先のことばだった。
「この前、駅で悲しそうな顔してたよね、つけてたとかじゃなくて、たまたま見ちゃって、それも2回も。どうしても気になっちゃって。」
まじか。顔がかーっと熱くなるのを感じた。
私の反応を見た彼はつづけて
「もちろん無理に聞こうとは思わないし、話しても話さなくていいから、でもどうしてもほうっておけなくなって、それで待ってたわけ。」
咄嗟の知恵が働かない私はろくな返しができずにただただえーとと取り乱していた。
「わかるよ。突然無性に悲しくなっちゃうことってあるよね。でも泣きたいときは泣いていいと思うし、僕はそれが恥ずかしいことだなんて思わないよ。」
ちげーよ、と言いたかったけどそういうことにしておいたほうが面倒な説明をする必要もない、いやそもそもこのことを話すひつようもない、、言葉に詰まって口だけぱくぱくしている私の様子を見かねたのか、彼が突然こちらをまっすぐ見て言った。
「でもね、路地ちゃんが駅で泣いてて、あの空間で、僕はそれを目にしたとき、なんていうか、すごく、溶けあって見えたんだ。そう、それが言いたかったの。泣いている路地ちゃんが、風景ととけあって見えた」
そう言って彼は少しの間黙って下を向いた。それを聞いて私は驚いて彼のほうを見た。同じ言葉を話すひとだと思った。
彼は、音楽が好きだった。
彼の言葉に気持ちが緩んで、私は彼にアイやミナのことを話しはじめた。変な誤解を招きたく無かったので、松戸さんのことは黙っていた。話すつもりはなかったのに、私はアイのことが好きだということも話してしまった。それがいままで他の誰にも抱いたことのないくらいの思いだと。
電車の扉に寄りかかりながら話す私の声に耳を傾け頷いていた彼は、声をひそめて聞いてきた。
「それはさ、官能的に惹かれているところもあるのかな。どうなんだろう?」
「、はあ?」
思わず聞き返してしまったが、はっきり答えられない自分が恥ずかしかった。
「あ、じゃ俺ここで乗り換えだから、それじゃ!」
酒も入っていないのになんてことを聞いてくる奴だ、空いていた端っこの席にへなへなと座り寄りかかった。扉の閉まる音がして目を閉じた。
「やっぱ答えが聞きたくて戻ってきちゃった」
突然の耳元の声に振り向くと、さっき帰ったはずの彼が隣に座っていて、私は思わず叫んだ。
アイとは大学時代からの友人で、デザインを学んでいた私たちは度々2人での制作を依頼されることもあり、制作の過程や感覚、ことばを共有できる貴重な仲間だった。私は彼女との制作を通して、他者とともにつくること、ひとつのものを誰かと作り上げていくことの歓びを知り、それを生きがいに思うようになった。いわば私が生きる理由、つくることしか取り柄のない私が、この世界で生きていく身振りを気づかせてくれた人でもあった。その時点で既に、かけがえのない存在だった。ただ、時を経ると共に彼女の人間的な魅力の一つずつを知っていく度に、次第に愛おしさが募っていった。
ハグしたいとか、触れてみたいとか、以前なら気にせずできたような気がすることも、愛おしさが募るほど決してできなくなっていった。そしてもどかしさが募った。これは官能的に惹かれてるってことなのかな?私は彼女を守れるくらい強く、できることなら男の子になりたい。心だけなら、少年でいられると思っていた。
「この気持ちが何なのか、自分でもよくわからない。」
私がひととおり話し終えると、彼は暫く間をおいたあと、先程とは違う落ち着いた様子でゆっくり話しはじめた。
「そういう人がいるって羨ましいよ。一言では表せないけど、君と彼女はとても深いところで繋がっている。その関係は誰にだって壊せない。
でも、一つはっきりさせたほうがいいことがある。路地ちゃん、君は女の子でも、男の子でもいい、どちらでもなりたい方になればいいと思うんだ。彼女にとってどんな存在になりたいか、すぐにでも自分のなかで決めたほうがいいよ。それは、彼女の為にも、君の為にもね。」
何かあったらLINEしてと言って送ってくれた彼のラインのアイコンは、デヴィッドボウイのアルバムジャケットを模して、夜道に佇む彼の姿だった。
トークルーム
路地:
帰るとき全然うまく話せなかったけど、
しんからのことばを伝えられる唯一の手段が、わたしにとってはつくることだったから、
それを取り戻したくて、この美術館に来たの
こないだ話した彼女が、嬉しそうに話すときの姿によく似てる白い花があってね、
来月の彼女の誕生日に、それを描く、
私がいちばん望むのは彼女のさいわいだから、
それが描けたら、彼女とも、制作とも、ちょうどよいあわいが築けると思ってて。
ここ数年の間に、身の回りで死に立ち会うことや、身近な人が去っていくことが続いて、ひとやつくることとの距離感も迷走してたんだけど、
でももう生きるほうに向かえると思ったの、
大原くんが話をきいて返してくれたことが、その一押しになったと思ってて、
だからほんとに、ありがとう :)
大原:
路地ちゃんは一つ決断というか、ケジメをつけることにしたんだね😉
例の女の子へ、その娘に似た花を描いてプレゼントするのとても良いと思う(あんまり良いとか悪いとか言うの好きじゃないけど💦)。
きっと、彼女と君が幸せになれる選択なんじゃないかな〜。
路地ちゃんにとって絵を描くことは最大の自己表現の一つだろうから、君からの彼女へのメッセージはきっと上手く伝わるよ!
それに、絵を描くことは路地ちゃんにとって呼吸をするのと同じくらい生きる上で重要なことだろうから、それはこれからも君にとって欠いてはいけない営みの一つであり続けると思う。だから、そういう意味でも彼女の為に絵を描いてあげることは、路地ちゃんが今できる最も前向きな選択なんじゃないかな。
でも、無理せずにね😌
完成したら、ぜひ見せてよ!もちろん、気が向いたらね😉
路地:うん、きっとね!ありがとう☺️
・
この冬に出会ったひとと、かろやかな約束をした。いままでかたちにならなかった無数の断片と記憶と感情が、ひとつの結晶に結びつこうとしている、間に合うかはわからない、間に合いたいな、よろこびもかなしみもすべて含んだこの風景を、やっぱり私は愛おしいと思う。
ひさびさにがしがしと描き散らしながら、やはり自分は生きるために描いているのだと思った。自分にとってのことばを長く手離していたら、抜け殻になって当然だった。
摩擦の痛みのもどかしさを、ずれていく断層を、ゆるやかな呼吸で繋ぎなおすための自らの手段。
ひとつずつ肌理をたしかめて、かたちにおこして、無数の断章を、星の位置をたしかめるように配置して、線で結ぶように再構成していく。
それは自分にとって器を作るような感覚でもあった。声にならなかった思いをひとつひとつ掬うように、ゆるやかに指先でうつわの側面を形作ってゆく。
誰ひとり溢れることなく間に合いますように。
アイ
彼女は、吉本ばななさんの小説に出てきそうな子だった。
ばななさんの本を読みながら、私はなんどもアイのことを思い出していた。ばななさんの物語を読んでいると、アイに初めて会ったときからずっと感じていた、どうしようもなく純粋な、それによる寂しさのような不思議なものを感じて、彼女のまわりだけ空気が違うように思えた。それがなんなのかはずっとわからなかったが、その穏やかな佇まいのなかに、突き抜けるような純粋さとやさしさを持っている子だということだけは、鈍感な私にもわかった。それ故の脆さや寂しさも、気配に感じていた。
ばななさんの小説は、読めば読むほど自分の記憶や経験、感情の中にいままでにないぐらい嬉々として染み渡っていった。追いつかないくらいに、沢山の澄んだ水が、ずっと身体中乾いていて欲していたのに気づけなかったその水が、絶え間なくすごい勢いで私の中になだれ込んでくるようだった。彼女はばななさんが描く世界の中にいるようで、やさしくて、素敵な勇気があって、あまりに脆いくらい純粋で、寂しくて、鮮やかだった。
ある秋に、彼女の住む部屋に訪れた。
その部屋が、街が、夜が、彼女そのものだった。
あんまりに優しかった。
キッチンに立つ背中を、見て動けなくなった。
すべてを、毛布で包むように、
キッチンに置かれた椀が光を受けて、微かに青く光った。
彼女の街で見た、夜のような、すべてを柔らかく包む毛布のような
わたしたちの好きなもの、好きな人、
言葉や肌触りは違っても、その奥にあるものはおんなじだった。
私は臆病で体裁ばかり気にするから、
あけすけな言葉や感情にむずむずしてしまって
乾いた言葉ばかり選んでしまう。
それは好みだと思っていたけど、ほんとはただ私がおっかなびっくりなだけで、
アイの使う言葉はそれとは違う、鮮やかで美しいんだよ。
そうしてきらきらしたものがこちらまで反射して、そっか、そうやって世界とかかわって、生きているんだって、思って、
透明な、小さいときにすきだった、水色の液のなかに花のボタンときらきらした粒が浮き沈みして、ゆれていたコップ、ハローキティのコップを思い出す、
光にかざしてゆれるひかりがほんとうにきれいで、そのときの、どきどきする愛おしさみたいなもの
そう、こういうこと。
こういうこと、それから、相手に伝えることってなんなんだろう。
私のみたいに何度も屈折する歪なレンズじゃなくて、とてもきれいなレンズをもつひとに出会ったときの、言葉の運び方、というか、何を、私はその人に伝えようとしてるんだろう。
どうかこれ以上、となりゆく背中にかなしみの積もらぬよう、どうか。
坂道、夜
3年前、私は自身の制作の為、会社を辞めて、フリーターになった。以来、コンペの為と嘯きながら、誰に見せるでもない、自分だけにわかることばのようなイメージを吐き出し続けていた。それらはあまりに拙く、荒々しく、継接ぎで、切実で、膨大だった。
私は何よりも、自分の大切な人が壊れることが怖かった。そんな過去と、予感があったからだった。がむしゃらに作れば回避できるような気がしていた。でも、そんなことはなかった。
ミナが去ったとき、その事実に愕然として、以来暫くつくることを放棄した。制作から離れていた時間は長かった。再び筆を取ったとき、私にはもう自信も実力も無く、ただ夢想するイメージだけが空回りした。そして以前にも増して、臆病になっていた。大切なものは見えているのに、自分が手を伸ばせば壊してしまいそうだった。密やかな呼吸でつくられたうつくしい存在に、自らの呼吸の身体の尺度を心得ぬ者が手を出して壊してしまう、それは過去の私で、現在はそれを看視するのが私の仕事で、同時に現在の私でもあった。子どもの時からずっと付き纏ってきた恐怖心は、この頃ピークに達していた。
私は白い花の絵を描き上げることのできぬまま、坂道に立った。アイの誕生日には、絵ではなく一冊の詩集を渡すことにした。明日、バイト先の同期の人から誘いを受けていた。私は足取りの朧げなまま、それを承諾した。街は既に真夜中だった。私は彼女に電話をかけた。いつもの調子で話したあと、私は彼女に好きだと言った。だから幸せであってほしいと言った。どう思われてもよかった。自分がどんな人間であっても、ただ祈ることはできると思った。
「やっぱり路地ちゃんはすごいよ、」
「何それ、笑」
「だって私、ほんとに大事なこと、ちゃんとことばにして言えないもん」
坂道に静かに通り抜ける風が心地よかった。
彼女は彼の連絡を待ち続けていた。その間に、少しずつ自分の進路の舵を切っていた。彼女は自身の関心のあった料理の分野から離れて、デザインの仕事に戻ることを決意した。春には既に次の就職先が決まっていた。
翌日、同僚と会って、その日から私たちは付き合い始めた。でも長くは続かず、春の夢を見ているようだった。
アイとは、その間もずっと友人だった。アイといまむかしの浮いた話をしながら、そうだこれでよいのだと、どこか自分を納得させていた。
回送列車、夜
ひらひらとはんかちをひろげる手元に陽のさすのを遠く眺めている
・
遅れて足元響き去る夜行列車微かな水路
・
託された筆ほどくにはまだ遠く、力なく詫びている
・
煙の中に消えた子の、目と髪に透けたひかりがきれいだったことしか
・
声を取り戻す為に月をひとつ借りました お返しする頃には生きられるようになっていてください
・
いつかの冬
携帯を置いて、
いつも乗る電車の終点、乗り継いで更に終点、
森を抜けて、陽の沈む海へ降りて、
結局死ねなくて、
インスタントカメラに映った写真と、
干からびて苔むした小さなウニと、
遠くの国の、知らない人の書いた手紙、1942年の消印のついた、
それだけ抱えて、泣きながら夜のバスに乗って帰った
そのとき撮った写真の半分くらいは、露光不足で何も写っていなくて、
のこりの半分くらいの滞留した空気のなかに、ひかっていた、いくつか、
そのうちの一枚、
春の、すこし、手前、
このあと吹いた春風のなかで、
永遠の約束をした、確かにあのとき、再生された声があった、再生されたふたつの生があった、再生された、
なのにそこからまたいつの間にか落っこちていたのはなぜだろう、
昔バスの隣で笑っていた友人が、テレビの向こうに映るビルの、炎と黒煙の上がるビルの中で、いなくなった、夏に、映像は何度も、何度もあちこちの液晶で、何度も、
それから2週間して別の友人に会った、何か埋めようのない、壁を感じた、
とんとんと、狂った足音が、ひとには聞こえないように近づいているのを感じた、いまに始まったことではなかったから、
守らなくてはいけないとまた思った、
狂っていたのは私でもあるが、
もう誰が見てもわかる状態には狂った、世界が、
私はまた一人守れなくて、一人はもう大丈夫だと思えるところまで、見届けた、そう、彼女は、友人だ、たったひとりの、しんから愛した友人、
また、再生できるだろうか、
そのときだと信じている、すがっている。
2022年 6月 半地下
蒸し返す熱気と湿気で頭がおかしくなりそうな地下道を歩いているとき、突然ミナからのラインと着信があった。驚いて通用口から外に出て、半地下の隠れ蓑から折り返し電話をかけた。電話に出たのはあまりに懐かしい声だった。相変わらずの声の調子になんだ元気そうじゃんと涙が出てきた。この一年は先が見えなかっただけに、どこまでも果てしなく思えて、気が狂いそうに長く感じた。思いがけず晴れた霧に唖然としながらも、早々に会う次の約束を取り付けた。半地下から空を見上げながら、ミナに再び会えることの果てしないよろこびと、このあまりに強く心に打ち付けられた一年のことを思った。
再会
一年ぶりだった。
3人で会った。
ミナは、金髪に髪を染めていた。服装も変化していた。緊張が解けて話し始めると、いつものミナだったが、何かが違っていた。去年のあの日と、変わっていなかった。でも、再び会おうと思ってくれたことは私たちにとって大きかった。
アイも、ずっと連絡の途絶えていた彼と連絡が取れたと話した。少しずつ繋がりが戻ってきたようだった。
私たちはいつもみたいに喋り倒して、すっかり夜になった。道ばたでアイスを食べてこぼして、帰り際は改札付近で呆れるくらい立ち話を続けて、げらげら笑って、ひとしきり話してから名残惜しく別れた。
ずっと、この時を待っていた。皆が少しづつ傷を抱えていて、でも会えばこうやって笑って話すことができた。私は、アイとミナが楽しそうに話している姿をぼんやり眺めながら、もう大丈夫だと思った。もうきっと、大丈夫だと思った。地元駅に着いてもすぐ帰る気になれず、0時を回るまで駅のベンチでぼうっとしていた。
回送列車、ミナ
いつからか、私はアイとミナの2人と共にいる事に、罪悪感を感じていた。
アイとミナは同じ高校の出身で、その頃からの親友だった。私が2人に出会ったのは、大学に入ってからだった。クラスは違ったが、それぞれとサークルや講義などで別々の繋がりがあって、いつしか3人一緒にいるようになった。
終わりのときが来たのかなとは思っていた、それは卒業旅行のときだった。楽しいはずなのに、何故こんなに閉塞感があったんだろう、割と初めから、会った瞬間くらいから思っていた。その思い込みなのかなんなのかがよくなかったのかもしれない。
それでも帰ってきて暫く経ってからは、その数日間のことが楽しい思い出話として何度も持ち上げられた。ああ、こういうふうになったんだ、また何事も無かったかのように、また以前よりすこし仲良くなった。そう捉えてよかったんだ、と思ってどこか安心した。
言うなれば向き合うべきことを先延ばしにしていたのかもしれない。私は人と、自他の核心部分について深く語り合うほどの仲になったことはいままでなかった。一度だけあったが、そのときは最悪の形で破綻した。だからほぼ無いに等しかった。
だから誰かと深い仲になるのが怖くて、また破綻させてしまうような気がして、一定のラインを踏み込むことを躊躇っていた。というより、逃げようとしていたのかもしれない。自分が誰かを壊してしまう前に、触れるまえに、逃げようとしていたのかもしれない。
自由でいるか、心からの幸せの中にいてほしい。
あなた自身にとって、そこに向かうことのできる道を選択してほしい。
なにか抑えたり、不自由したりするくらいなら言ってほしいし、関係性だって変えたっていい。
殴り合うのが望みならそれでもいい。
おまえの希望は意志はないのかと言われるかもしれないが、私はあなたが幸せになる道にあわよくば協力したいというのが希望です。
ドライに聞こえるかもしれないけどそれが自身の自然であるといまは思う。
一般的に多くの人が持つような器用さは多分お互い持っていないので、不思議なことになっても当然だと思うし、べつにそれが悪いとは思わない。
これをミナに伝えていれば、何か変わったんだろうか。
傷つけないためと逡巡して
妙なまちがいかたをするまた
乗り換え駅
深く降りたところに家路
己の断層で走れよ唄えよ
臆しているから吐いた
足元の水脈を見ぬふりするなよ
距離を長らく隠してただろ
愚かの限りを尽くしきればいい
置き手紙
松戸さんへ
お久しぶりです、美術館でお世話になった路地です。お元気ですか?
いつの話やねんって感じですが、この前はありがとうございました。
写真はアイと予定の合う日に渡してください。
頼んどいて待たせといて何やねんて感じだと思いますが、うっかりまた彼女のこと好きになっちゃうと苦しいので、私は同席するのはやめときます。
どうでもいいけど、言うか言うまいかもごもごしてたのはそういうことです。
多分彼女も私も強がりだからよく息の仕方を忘れるし、ニュートラルなんじゃそりゃって前は思ってたけど、やっとわかった気がします。
彼女は学生時代から周りに愛されてた。でも彼女自身はどこか自信なさげで、時折外に踏み出せずにいるところが、見ていてもどかしかった。
そのままでいいから、人とかかわってくるくる小さく嬉しそうに揺れる、その姿が愛おしかったから、無理に繕う必要はなくて、でも私が言うんじゃ説得力なくて、だからその点一番説得力ありそうな人にかたちにしてもらえてほんとによかった。
変化の中で少しずつ変わっていく、自然体に帰っていく彼女の姿が、本当にきれいだった。
信じる姿はうつくしかったけど、それより前みたいに馬鹿みたいにふざけて笑ってほしかったから、
だから、前に一枚だけ見せてもらった、松戸さんと彼女が一緒に写ってる写真見たときや、撮影の時に一緒に公園で歌ってたって話とか聞いたとき、正直嬉しくて泣きそうになって。
この前会った彼女も前のやわらかさに、自分の場所に帰りつつある気がして、しんそこ安心したんです。
勿論彼女自身自分で道を開いていく力を持っている人だけど、
私一人じゃ絶対そうやって日のあたる場所に連れ出せなかったから、あのタイミングで松戸さんと知り合えて本当によかったと思った。
一年前私が何より望んでたのは、彼女がそうやって前みたいに誰かとちょっとふざけて笑ったり普通に過ごしてる風景だったから、
だから写真まだ見てないけど、超勝手ですが、私は満足なんです。
あの期間の私たちの間に松戸さんが居てくれたことが、私たちの風景を少しずつ変えたから、
スタイリストってそういうことだったのかあと勝手に思って、嬉しかった。
前に松戸さんのやってること、その人が自分の呼吸のまま変化できる場を生み出す光や風みたいって言ったけど、
そうやって生きられた風景確かに生き続ける風景は、当人は勿論、うまく息ができずに泣いていた過去の自分や周りの人も掬ってくれた。
この前お会いした時、制作を続けるのがしんどいことがあるって言ってた気がするけど、
ずっと続けていてほしいと勝手に思いました。
私はまだ自分のことばで大切な人に向き合ったり、その姿を描き留めることがうまくできないけど、
松戸さんの活動や写真を見ていて、自分のことばで生きて人と関わっていく姿を見て、自分も諦めたくないなって思いました。
色々書きすぎましたが、アイに変なこと言わないでくださいね。
またいつかお会いできたら嬉しいです。どうかお元気で!
路地
・
メールを打ち終わって私はpcを閉じた。
アイとミナと会った後、私はバイト先を辞めて、配送業者に転職した。少し伸びかけていた髪をまたばっさり切った。暫く私は、姿を消すことにした。
配送業者で一夏働き、そこで身体を壊した後は、坂の上の小さな会社で撮影の仕事を始めた。そこで私は上司と恋仲になった。生活ががらりと変わった。どこか大原くんに似ていた上司に、また私は洗いざらい話しては泣いた。自分がいない方が良いほうにまわる世界があると思った。だから、もう2人とも会わないつもりだと、自分で言いながらも、心に何かが劈いていた。タバコの匂いに夜道に首筋に縋り付く日々だった。
カーブミラー
久しぶりに、昔使っていたペンを走らせた。
どこまでも行けるような気がして、調子に乗ってSNSに上げたドローイングは久々の高反響だった。
結局行きたかった展示には行かず、ジュンク堂まで歩いていって画集を買った。
帰って画集をぱらぱらめくると、懐かしさに胸が苦しくなった。私がかつていた世界、初めて彼女たちに見せた絵もこんな童画であった。その後長い間、私は自分の作品を否定し続け、おそらくそうして他者をも傷つけた。でもそうして一番ズタズタになり、それでも認めようとしない面倒臭い人間が私だった。彼女たちと皆で笑っていたあの頃が懐かしくて愛おしくて、帰りたくなった。変わってしまったもの、変えてしまったもの、学生時代から、どこか自身の鏡のような存在でもあったミナが崩れてしまったのは当然だった。私がミナを変えてしまった。何度も口にしては静かに押し戻されたこの言葉は、自分のことをゆびさしていた。
何もかも辛くなって、携帯も置いたまま湾岸まで1人歩きに行ったとき、インスタントカメラをひとつ持って行った。そのカメラの最後の一枚に写っていたのは、夜の海岸から戻る長い長い道の入り口に立ったカーブミラーだった。フラッシュを焚いてしまったのでミラーは白く反射し、真っ暗闇の中に小さく傾いて立つ姿が写った。
それは3年前、姿を消そうとした自分と、この夏に本当に姿を消してしまった自分の自画像だった。
ai
坂の上の会社で出会った彼は、狼みたいなひとだった。
私は姿を消すと決めていたのに、本当は寂しかった。
彼も寂しいひとだった。
川縁のカフェで話したその日から、そういう関係になった。
互いの素性もまだよくわからぬままベッドの上で抱き合って、逆さになったまま耳元で「あいしてる」と言われた。
私はこの一年あまりの間、このことばについてずっと考えて、悩んで、振り回されてきた。
私は彼女を愛してた。それは間違いなかった。でも、次に進まなくてはいけなかった。愛は無限であり、有限であった。他者と渡りあうということは、それを認め、他者を想像し、自らの愛のかたちを変えていくことだった。それが、愛するひとのさいわいを願うということだった。
私は、少し間違えた。このとき気づいた。2人と連絡を絶ってから、3ヶ月余りが経過していた。
・
路地:
アイさん、こんにちは。ずっと連絡もせず心配かけてしまってごめんね。元気にしてますか。
どの口が言ってんやって思われるのも重々承知ですが、よかったら都合の良いとき、電話かけてもいいですか。
まず謝りたいのと、やっぱり元気にしてるか気掛かりなのと。まじでとりとめもない、ただのだる絡みなので、もし許してくれるなら。
話すととりとめも無いですが、先ず生存報告と、謝りたいのと。ごめんなさい。気が向いたら、返信待ってます。
・
私の誕生日に連絡をくれたミナとは、すこし電話で話をしていた。私は、自分が思っていた以上にはるかに2人に、特にアイに心配をかけていたようだった。たちの悪いことに、突然連絡を絶ってしまったことは、アイの彼氏のときと同じで、しかもその相談に乗っていた私が姿を消したのだから、ひどく傷ついて当然だった。
久々のアイとの電話は、ことばがうまく出ずに、代わりに涙ばかりが出た。アイは静かに怒っていた。
2人に会ったのは、クリスマスイブだった。
先にカフェに入っていた2人は、前に会ったときと様子が違っていた。当然だった。アイはまだ私を許していないようだった。松戸さんからも、アイが路地のこと心配してたけど…とメールがきていた。私はアイにちゃんと謝るつもりが、うまくことばにならず、あっという間に約束の時間が来てしまった。私は2人に持ってきていたクリスマスプレゼントを情けなく渡した。ミナが「そっか、路地ちゃんもう時間か、」と言うと、さっきまでずっと黙っていたアイが「デートでしょ」とつっけんどんに言った。私は何も言えなくなった。
帰り道、悲しくて悲しくて泣きながら帰った。帰ってからは彼に抱きついてわんわん泣いた。
光線
手紙を書いた、交番の目の前のマックで
冴えない頭のまま真夜中にメールを送った
行く末は誰にもわからない
・
一昨日、月を見ながら一心にあるく彼は少年だった
今日は涙でよく見えなかった
・
お前にとっての愛を選べと言われているようだ
そうだこの日々は火傷なのだと思い出した
・
・
・
それからまた少しづつ、3人で会うようになった。やはりアイはどこか私に対してよそよそしかった。そのまま夜になって電車を降りて別れようとしたとき、ミナがあわあわしながらちょっと2人とも待って!と行って手を引いて3人とも電車から降りた。私とアイが唖然としていると、ミナが
「このままバイバイしちゃだめじゃない?このままだと、本当に3人ばらばらの方向へ行っちゃうような気がする、」
私たち2人の手を握ったままミナが目に涙を溜めながら続けた。こういうときのミナは誰よりも鋭かった。
私たちはスイッチが入ると場所を問わず長い立ち話を始める癖があったので、とりあえず改札階に場所を移動した。
アイは、元々片耳が聞こえづらかったが、それが最近悪化してきているらしかった。つづけて、
「路地ちゃんのことは許したいけど、まだ気持ちが追いつかなくて、今までみたいに普通に話せないかもしれない」と目に涙を溜めたまま言った。
私の軽率な行動は、簡単には埋められない溝を生んでいた。この時自分がした所為の大きさを、ようやく思い知った。守ると心に決めた相手を、深く傷つけていた。
2023年 6月
21年6月
あの日から2年が経った。
私は撮影の会社を退職して、美術関係の仕事に戻った。
会社で出会った彼とは付き合いを続けていた。
ミナの誕生日が刻々と近づく中、私は久方ぶりに、現代美術館に足を運んだ。
コレクション展と、写真展。
展示全体のテーマに惹かれてコレクション展目当てで訪れる。暫く自分が離れていたメディアアートの領域の空気感と肌理、痛いくらい生々しい息遣いに触れて、懐かしさに落ち着く。
ふわふわしながら写真展へと足を踏み入れる。
そこでは震災と戦争のことが語られていた。そこで語られることに、私はそのとき当事者として居合わせてはいない。ただ他者の語りに耳を傾けて、目の前にうつしだされた風景に目を凝らし、想像することしかできない。日常では覆い隠された、当事者の独白、とつとつと語る姿、都合の悪い事実、それらは切実なものとなって目の前に現れ、強い残像を焼き付けて流れていく。日常に帰ったとき、それらは私たちの視界からは隠されている。それでも、残像は消えない。他者の痛みに直面したとき、痛みから目を背けず、その残像を咀嚼し、みずからの呼吸を身体をむすびなおしながら想像し、他者とともに、生きられるあわいを紡ぐことができるだろうか。
見た順番からか、主題故か、写真展が印象の殆どとして残った。コロナや戦争、手に負えない歪みに過去が覆われことばが消えてゆく前に、これ以上さらわれてはいけないもの、おしころしてはいけないもの、目をそむけてはいけないものがそこにあった。それはコロナ禍で浮き彫りになった、自らの身体の延長線上で何が起きているのか、何が起きてしまったのか、隠されていた風景を同じように突きつけるものでもあった。それは自らの、他者を想像する力の衰えていたことを、無様にも浮き彫りにした。
見終わってショップに入ると、あるものが目を引いた。
パウルクレーの描いた天使だった。
クレーの描いた忘れっぽい天使、私はこの絵が好きで、以前ミナのいない日、アイにこのポストカードを贈ったことがあった。この天使の安らかな表情と線は、誰かを失ってしまう不安に、もしかしたら既に失ってしまったのかもしれないという際限のない恐れに、隣に寄り添い穏やかに見守り、そんな自分にも居場所とささやかな希望を与えてくれるような、そんな印象を受けた。今は自分の部屋の窓の上の棚にも、その絵のポストカードを額に入れて立てかけている。
私はミナに、天使の描かれたハンドクリームを買った。チューブには鈴をつけた天使が描かれていて、忘れっぽい天使の描かれた巾着袋に入っている、とても可愛らしかった。
過去の自分を責め続けるミナが、少しでも解放されればいい。
傷つけてしまったアイの心が、少しでも癒されればいい。
美術館から帰って、窓の上の天使の絵を眺めながら、2人のことを想って眠りについた。
夢
わたしたち 間違ってたのかもしれない
かれんだあの裏に描きつけられた何枚ものコンテ画
おわりに1枚の、体温の絵
ベッドの前に座り下着にくつしたのまま足を投げだすひと
はるは、ひとの数だけあるのだと
彼女の朝のいろを見て、そうだこんな姿だったねと喉がつかえた
ことばをね、
こみ上げ喉と鼻がつまって先が言えない
身体に、身振りに、
代わりに涙が続きを言おうと駆け降りてくる
ただ帰りたかっただけである
大義名分などはなからない
また一緒に帰りたかっただけである
それだけのために厄介な身振りとことばでさんざ踊ったさんざ繰り返した
その何ものも、裁かなくていいよ
あと少し、そのために、
だからもう少しそこで待っていてほしい
2023年 7月
7月になった。七夕の次の日に、2人に会った。
私たちは誕生日プレゼントを渡したり、久々にふざけあったり、ひとしきり話した。
けれども、この前とも、去年とも変わらず、ミナは、ひたすらに何かを恐れていた。それは昔の自分とも似ていたから、身の回りの沢山の人たちや作品に救われていた当時を思い出して、友人を紹介したり好みの合いそうな作品を勧めたりもしたけど、ミナには殆ど拒絶された。他者や作品が自身に及ぼす影響の大きさ、変化を恐れているようだった。
私もアイもただ、泣きながら話すミナの語りを聞いていることしかできなかった。ふざけあうことはできたけど、一番言いたいことを言えば相手が崩れてしまいそうで、何も言わずにただ耳を傾け、唯一の、誰もさばかれぬ居場所を護ることを選んだ。
自分もミナの語る不安に心当たりがあったから共感の言葉を口にしたが、どれもミナには届かないようで、虚しくなった。けれど、羨望と劣等感とやるせなさを包み隠さず露わにするミナに対して、友人だからできることが、まだ何かあるはずだった。ミナが、洗いすぎてボロボロになった手を寒そうに擦り合わせる様子を見ながらぼんやり考えていた。手を伸ばしても伸ばしても空回りして何もできないのが悔しかった。
「ガラス越しに2人といるような気がする」
この言葉は以前から、彼女がふと口にする言葉だった。今日もその言葉を聞いた。それを壊したかった。でもできずに、また時が経ってしまった。
「花火したいね」
ミナがお手洗いに立ったとき、アイが私に向かってぽつりと言った。
アイがミナに渡した誕生日プレゼントは、色とりどりの花火だった。アイが提案することは、いつだってワクワクするようなことだった。私たちは思わず笑みが溢れた。
調べると、花火のできる海があるらしかった。ミナが戻ってきて、私たちは、夏の終わりにまた会って花火をする約束をした。
ミナはまた心配そうな顔をしたが、きっと行ってしまえば大丈夫なんだ。私にはこの約束が希望のひかりに思えた。
不安だっていい、怖くたっていい、寂しくたっていい、やるせなくたっていい。
小さな火を囲みながら、またゆっくり語り合えばいい。
4年前、3人であの海に行って、朝日が登るのを見た。
3人ともまだ生まれたての子鹿みたいに頼りなさげで、震えながらも、社会を目の前にそれぞれが夢と密かな希望に満ち溢れていた。
大学を卒業して1年余りだった私たちは、それから別々の道を大きく旋回しながら歩んでいくことになる。
また3人並んで、地平線を、打ち寄せる波を眺めながら話がしたい。
隣に座る、密やかな呼吸を想像し、そのこまやかさに乗せてことばを交わしたい。
身体生い立ち価値観生活何もかもが異なる私たちが、誰もが生きられる密やかなあわい。
愛してる、私はこのことばを、それぞれの呼吸を想像し、自らもその尺度の対岸に立って紡ぐことができるだろうか。
あの入り江で、私たちはもう一度、生きられるあわいをさぐる。
あとがき
愛おしく思ったものの呼吸を再生するように、線を引く、ことばを書く。
それは語られない無数の風景を、誰かを想像するための、生きられた場所となる。
語られぬ、故に尊いともいえる無数の風景や生活の数々が、あまりに不条理に奪われていった。
新型コロナウイルスが世界中に拡大したとき、感染者数や死者数は毎日報道され、無数の人々の生命が数字によって置き換えられた。はじめは衝撃を受けたが、日を追うごとに増加し、安定していく数値に慣れていく自分がいた。
誰かにとり最も愛おしく思う人、風景があまりにも多く唐突に奪われ、しかもそのことに時間を追うにつれ慣れて、忘れていきかけていた自分の感覚の推移に恐ろしくなった。
奇しくも私たち3人がすれ違っていったこの3年間は、コロナの広がりと重なっていた。
自他が影響を及ぼす、及ぼされる、その意味が病的なまでに深刻な重みを持ってしまった社会下で、繊細な感覚の持ち主だったミナが精神的に極度に苦しんでしまったのは無理もないことだった。
異なるもの同士が生きられるあわいはどこにあるのだろう。
これまでも、そしてこれからも、生きていく上で誰もが最も切に直面するこの問いは、昨今の社会下でより切迫した問いに変化した。
語られることのない声が、掌ほどの小さな想像が、隣り合わせ生きられる場が、何よりも必要。
身体信仰生立ち何もかもが異なる僕らがそれでも共にただ居ることのできる過程、共生に向かう過程に何よりも必要な小さなプラットフォームが欲しいと思った。このエッセイも、共生に向かう過程を記録した、自分にとって生きられるあわいを探るための一つの小さなプラットフォームだ。ここから私は日々に帰り、自他ともに生きられるあわいをこれからも探し続ける。
愛についての気付きは勿論だが、ミナのように繊細な感覚を持った他者とどう付き合うかは、子どもの頃から私にとって重要なテーマだった。自分や自分に近しい人が何かのきっかけで崩れてしまったとき、関わりかたを間違えて相手を傷つけてしまったことが何度もあった。ただ、今思えば、ミナのような繊細な感覚、密やかな呼吸をもつ部分は誰の中にも少なからず存在する。それとどうかかわり、互いに生きられる関係性を築いていくか。誰と接する時も同じことだった。ただ、目の前の、時に遠くの相手の呼吸を、その尺度を、身体をもって想像できるか。コロナ下で自他に作用する影響について考えていたとき、ようやくそのことに気づいた。
この文章は当初エッセイとして書き始めました。ただどうしてもことばの数が収まりきらず、こちらの部門に応募させていただくことにしました。友愛も恋愛もわりきれない私が恋愛について書くのもおかしな話ですが、しんから愛おしく思う心の動きが生まれたとき、それはすべて恋のようにひかりかがやいて見えて、だから、愛の感情ををひとつに規定したり、ラベリングする必要などないと思うのです。私はこれからも、ずっと少年のままで、少女のままで、目の前の愛おしさに、かなしみに、よろこびに、しんから向き合える人でいたいと思う。
路地
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
