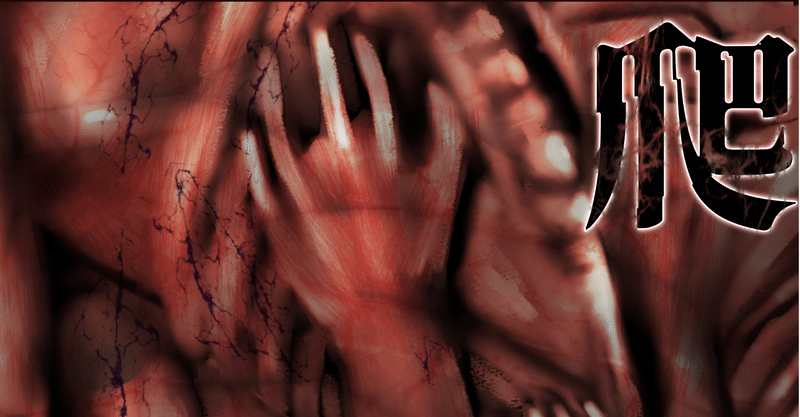
『ヘベムニュラの落星(おちぼし)』08
(01) https://note.com/kobo_taro/n/n52895d13d196
(02) https://note.com/kobo_taro/n/n2fa61e863c7d
(03) https://note.com/kobo_taro/n/n3714e1ae6566
(04) https://note.com/kobo_taro/n/nc4c2e5954b4a
(05) https://note.com/kobo_taro/n/n4589cc684f0c
(06) https://note.com/kobo_taro/n/nc0ec2a2deef7
(07) https://note.com/kobo_taro/n/n468d588079f1
お昼休みのことである。おのおの机を寄せて給食を食べようというところで、突然教室の空気が変わった。ぼくは教室の隅で一人で食事をとっていたため、一歩引いてその様子がよく分かった。最初に声を上げたのは、工藤と一番よく一緒にいる女子だった。
「ねえ美夏。どういうこと? 」
「どういうことって? なに? 」
工藤はさっきまで和気あいあいと談笑していた友人が急に声のトーンを変えたことに焦りのような、まずい空気を感じている様子だった。彼女の手には携帯電話が握られており、それをすぐさま閉じてカバンに放り込んでいた。
見られてはいけないものを見られたのだと察するには十分な慌て方だった。
「市波……彩瀬」
女子生徒がそうつぶやくと一瞬、教室中でがたりと椅子を引く音が一斉に鳴った。クラスメイト全員が工藤を見ていた。
「は? なに? なんなの? みんなして変だよ」
女子生徒は、工藤に向かってゆっくりと指をさした。
「市波彩瀬と一緒に映った写メを持ってた」
「市波? なんで? 私が? そんなわけないじゃん。千里、変なこと言わないでよ」
「嘘をつくなア! ! ! 」
窓ガラスが割れるかと思わされる大音声だった。女子生徒は工藤のカバンにつかみかかり、工藤はそれを必死に止めようとする。がたがたと周辺の机にぶつかり、その上の配膳がひっくりかえって飛び散った。それを構うことなく二人は必死に攻防を繰り返していた。奇妙なのは、周囲の人間がそれを傍観しつつも、それとは別の理由で戸惑っている様子が見えたことだった。なに? 工藤と市波? なんで? ほかにももしかしているの? お前まさか市波と関係あるんじゃないだろうな? あるかボケ。お前こそどうなんだ。
市波彩瀬との関係性を引き金に、教室中が混乱と疑念に包まれていた。
「お前、そういえば入学式の時、市波の隣に座ってたよな? 」
工藤と女子生徒とは無関係の場所で声が上がる。
「あなたが前、市波彩瀬と一緒にトイレから出てきたの見たわ! 」
「市波と同小だって話してたの誰だっけ? 」
瞬く間に教室に広がった疑心暗鬼は、些細な出来事の断片を雪だるまみたいに大きくし、みんな市波彩瀬との接点の有無についてお互いを詰問し始めた。
「ほら! ほら! やっぱり! そうよ! 」
工藤の方から大きな声が上がった。鼻血を出してうずくまる工藤の目の前に女子生徒が携帯電話を掲げて叫んでいる。
「これも市波、これも市波。これも、これもこれもこれも! 」
「かえし……」
工藤は女子生徒に縋り付いて蹴とばされる。
「触るな! ! 触るな! 触るな! 」
工藤を踏みつける女子生徒は酷く興奮していた。
誰も、止めない。みんな見ているだけだ。こいつらはみんな透明人間だった。ぼくは、違う。少なくともそうありたかった。
「おい、やめ――」
ぼくが言いかけたところで人垣の間から青山と取り巻きが現れた。午前は教室はおろか学校にいなかったし、ついさっき来たのかもしれない。青山は周囲の人間にぶつぶつ話を聞き事情について収集していた。
「へえ、工藤が市波とか」
青山は下品に舌なめずりをすると、工藤に歩み寄る。
「な、なに」
「来いよ」
「いや! 」
青山は工藤を無理やり立たせると、取り巻きと囲んで教室の外へ連れ出した。残された教室はこの騒ぎに荒れ放題だったが、おかしなことに他のクラスメイト達はその後何も起きていなかったかのように平然と掃除をし始めた。
ぼくは、恥ずかしいことに青山が怖かった。工藤を連れ出す青山に向かって、やめろと言い出す勇気が出なかった。
今から追いかけようか。でも、青山に勝てっこない。すっかり冷めた給食はまだ手を付けておらず、みんながそうするように、ぼくも全部忘れて元のように過ごすべきだと思った。ぼくはこの時ほど自分が嫌いになったことはない。
しかし、箸を取り出そうとカバンを探った時、それが指先に触れた。初めてそれを見つけた時が再現されているみたいだった。ぼくは震えた。どくりと、徐々に心臓の鼓動の一つ一つが重たくなるのがわかる。
――拳銃。おもちゃではない。正真正銘実物の。
周囲の目がぼくに向いていないことを注意深く確認すると、ぼくは机の横にぶら下がった体育着用の布袋を空にしてその中に銃を握った手を突っ込んだ。布袋の入り口のひもを絞める。不格好な見た目ではあるが、この薄布の向こうに実銃を握られているのだとは誰も思うまい。
ぼくは深呼吸をして勢いよく席から立ちあがる。緊張のせいでぎこちなくなった足取りで教室から飛び出した。
(kobo)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
