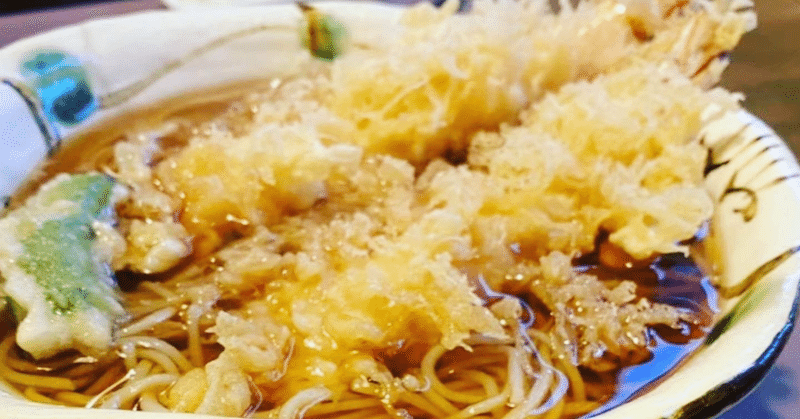
芥川龍之介は漱石文学を継承したか? ①
私はこれまで繰り返し、太宰治が芥川龍之介文学を継承する様を指摘してきた。
しかしいかに憧れがあったとは言え、太宰は芥川に対してさえ遠慮がない。
芥川が激賞する芭蕉の句をスルーして天狗になる。芥川の場合、夏目漱石文学に対してはもう少しクールなところがあり、勿論速読の芥川なら主要な作品は読んでいたと考えられるものの、その直接的な影響を見出すことは困難である。やっと昨日になって、
漱石の『彼岸過迄』と芥川の『葱』に微かな設定の近似を見つけただけで、これが漱石文学の継承と云えるかと言えば、とてもそうは思えない。では全く何も継承していないと言い切れるのかと云えば、そう言い切る自信はない。今現在はそうした曖昧な地点にいる。
例えばエゴイズムを悔い、自殺をするという夏目漱石の『こころ』のテーマを、芥川がその生涯を通じて引き継いだという程度のことは言える。それは和辻哲郎が和辻倫理学という形でエゴイズムの問題を昇華させたことの裏返しのようでさえある。しかしそのいずれも、太宰が芥川作品に対して挑んだような、本当の意味での文学の継承とは言い難い。
むしろスタイリステックな作風に拘り、絢爛豪華な大盛作品を書き、蟹と云う字を嫌悪し、天皇陛下万歳を叫んだ三島由紀夫と太宰治の関係のような反発が見られれば分かりやすいものを、芥川は森鴎外に対するあこがれも隠さず、スタイリステックな作風で書き続け、そして正体不明な「保吉もの」へ向かう。どうも夏目文学の継承が見当たらない。
それでもあえて言えば、夏目漱石文学において誰もが持てあます部分、例えば「怪しい色をした雲」や、「世界が今朗らかになったばかりの色をしている」や「野だは大嫌いだ。こんな奴は沢庵石をつけて海の底へ沈めちまう方が日本のためだ」や「すると先生がいきなり道の端へ寄って行った。そうして綺麗に刈り込んだ生垣の下で、裾をまくって小便をした」といったいささかまともではないところをややふわふわした形で引き受けたとは言えるかもしれない。
この「ふわふわ」はよくよく読んでみると漱石の本質的なところと繋がっている。
漱石の場合のふわふわは根本義の部分で言えば、認識論、世界認識の在り方に関わるものだ。確かに芥川にもそれに近い感覚がある。
ただ芥川はやや現実主義者のようなところがあり、漱石程抽象的には考えていない。
〇物、我(dual)
通俗 〇時間、空間、数
〇因果律
……と断じるまで浮世離れできない。また作者が読者に還元的感化を齎すと言い切る迫力はない。「保吉もの」の「ふわふわ」は漱石由来とする根拠はまるでない。むしろ佐藤春夫や稲垣足穂の影響を疑うことの方が簡単だ。そうだ。止めよう。無理に話を作ったらおしまいだ。
漱石山房記念館「夏目漱石と芥川龍之介」
— 薬味柑橘 (@SpiceOrange) November 20, 2022
二人の交流は漱石の亡くなる一年ほどだが芥川龍之介に与えた影響は絶大だったとか。漱石が「鼻」や「芋粥」の感想を送った手紙が展示されていたが、絶賛や指摘も愛があってこれ受け取ったら嬉しいだろうなという言葉がたくさん。漱石さんって人たらしだわ… pic.twitter.com/AqWCIqARy2
多くの芥川龍之介作品を朗読した中島敦ですが、同僚(岩田一男)の問い「芥川、好きか?」に「僕、あの(芥川)全集売っちゃってね」、一方で『某博士が新聞で芥川の文章をけなしていた』と聞くと「学者先生に何がわかる」(中島敦全集別巻)と反発したり…複雑な思いが見え隠れ?写真は会報5(1982年)。 pic.twitter.com/Ld0r1yH5Mq
— 12月4日没後80年 中島敦の会@NANK (@NANK19751207) November 19, 2022
電子書籍リリース情報
— T&H (@TandH1130413) November 15, 2022
芥川龍之介『犬と笛』の出典について
「犬と笛」は日本神話の衣を纏っていますが、その典拠は西洋の「三匹の犬」に関する民話であり、中でもスウェーデン民話が大変近い話であることが新たにわかりました。#犬と笛#芥川龍之介#童話 https://t.co/wtWv2vEDZp pic.twitter.com/VYGxGEgics
芥川龍之介の「羅生門」のモデルにもなった羅城門。
— hiroshi21kawasaki (@hiroshi21kawa14) November 18, 2022
今はのどかな公園です。#京都 pic.twitter.com/ZJQcKZ4CcS
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
