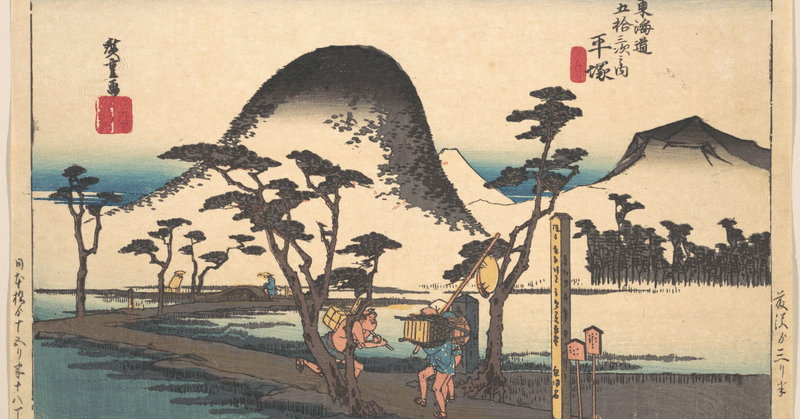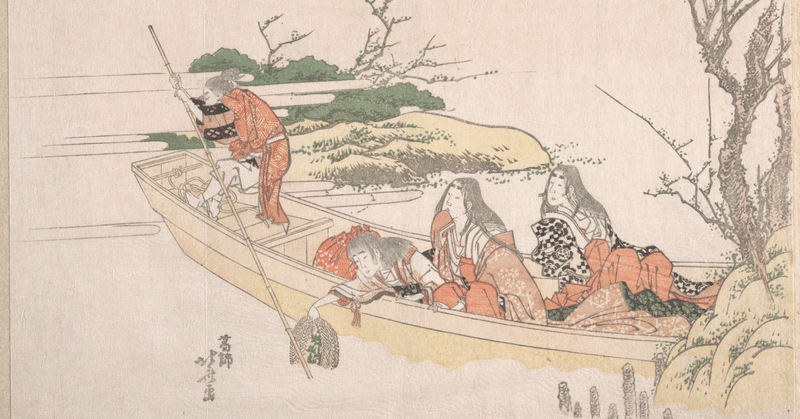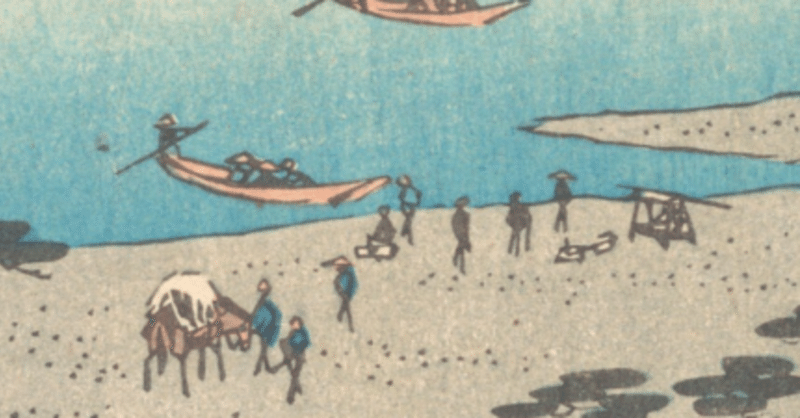2024年5月の記事一覧
穴蛇を檀家に配る冬の川 夏目漱石の俳句をどう読むか106
穴蛇の穴を出でたる小春哉
解説に「穴蛇は冬眠していた蛇」とある。
これは難しい。
穴蛇のちょいと出てみる小春かな
これなら解る。
しかし蛇の穴は見えても蛇がいるかいないかは、棒きれか何かで突いてみなくては確かめられない。
つまりそこに穴だけあっても「穴蛇の穴を出でたる」かどうかは厳密には解らないわけだ。すると漱石はいかもの食いをしようと蛇を探して歩いていたのであろうか。
それ
古池や冬の日残る枯れ尾花 夏目漱石の俳句をどう読むか105
蒲殿の愈悲し枯れ尾花
漱石がまた歴史ミステリーを仕掛けてくる。本当に伊予というのは訳の分からない土地柄で、あちこちから伝説を引っ張ってくるのが生きがいなのであろうか。
新田義宗の墓、これは仕方ない。
三好秀保は漱石の責任だ。
しかしこの句には「範頼の墓に謁して二句」と添えられている。源範頼は……確かに伝説があるな。
解説には諸説が紹介されている。
漱石は果たしてどんな感じだ
凩に馬やり過ごす月夜哉 夏目漱石の俳句をどう読むか104
凩に牛怒りたる縄手哉
雨風の自然現象や世界の成り立ちを生き物がどう受け止めているのかは謎である。猫はどうも自動車に挨拶しているような気配がある。しかし自然現象に関してはおおむね仕方のないものとして理解しているように見える。
牛が凩に怒っている場面というのは見たことがない。
あまた度馬の嘶く吹雪哉
このように馬が吹雪に嘶いていたので、風に牛馬が亢奮するという場面は昔はあちこちで見られたこ
花嫁の亥の子を見れば焚火かな 夏目漱石の俳句をどう読むか103
花嫁の喰はぬといひし亥の子哉
炉開きに亥の子餅はつきものののようである。漱石は歳時記をなぞるようにして詠んでくる。解説には花嫁が亥の子を猪の子と間違えたとある。その花嫁がどこの花嫁なのかは書かれていない。
これは本当に漱石が炉開きに招かれて、道也の釜を贈って、奥さんを紹介されて……という流れなのか?
しかしそもそも亥の子餅は見ればわかるだろう。
到来の亥の子を見れば黄な粉なり
到
吾妹子の南天の実は四畳半 夏目漱石の俳句をどう読むか102
炉開きや仏間に隣る四畳半
爐開きや左官老い行く髪の霜 芭蕉
爐開きやあつらへ通り夜の雨 一茶
爐開きや雪中庵のあられ酒 蕪村
我庵の煖爐開きや納豆汁 子規
爐開きや蜘蛛動かざる灰の上 虚子
どうも子規と漱石は炉開きと仏を因縁づけようとしている。まあ子規は納豆汁を通しての間接的な因縁づけだが、これもちゃんと納豆汁の句を詠んできたからわかること。
禅寺や丹田
なき母の倅のつけし綿帽子 夏目漱石の俳句をどう読むか101
なき母の湯婆やさめて十二年
この句はもう一度やったような気がしていたが気のせいだろうか。漱石の母が亡くなったのが明治十四年なので、明治二十八年に読むと二年勘定が合わない、と書いたような気がする。音の調子にしても、
なき母の湯婆やさめて十四年
十四年で全然おかしくない。
この二年の差が何を意味するのかは定かではない。漱石の記憶が曖昧な時期だったのか、単に計算を間違えたのか。
この時
黙然とそれはいかめし火鉢かな 夏目漱石の俳句をどう読むか100
五つ紋それはいかめし桐火桶
全国弁当祭りで大人気のイカメシの句である。
……違うな。
五つ紋の桐火桶が厳めしいという意味の句か。
いや、違うな五つ門は羽織のことだろう。正装だ。
正装をして桐火桶に当たっていて厳めしいということか。
暮れなのに正月みたいだ。
冷たくてやがて恐ろし瀬戸火鉢
今度は火桶ではなく火鉢だ。
冷たかった火鉢に火を起こして、次第に熱くなって
銅瓶に心元なき冬構 夏目漱石の俳句をどう読むか99
門閉ぢぬ客なき寺の冬構
昨日パチンコ屋さんの前を通ったら、空調機入れ替えのために休業しているのに、女の子が「休業」と書かれたホワイトボードを持って道行く人に「本日休業でーす。明日は営業してまーす」と連呼していた。そこまでやらなくてもいいのになと思った。
この寺は、門が開いていたら漱石が客となっただろうか。実は冬構ではなくて事件に巻き込まれていた可能性はないだろうか、とは漱石は考えなかったよ
雪の日や取次に出ぬ塩煎餅 夏目漱石の俳句をどう読むか98
雪の日や火燵をすべる土佐日記
これは見たままの句で居眠りをして土佐日記が火燵布団の上に落ちて滑った?
雪の日や松山で読む土佐日記
紀貫之の『土佐日記』は『土佐日記』と言っても土佐から大阪を経て京に戻る話なので、なんとなく里心がついていたのかもしれませんね。
応々と取次に出ぬ火燵哉
応々と人をすかせるやなぎかな
応々といへどたたくや雪の門
いずれも向井去来の句だと思うが、何故か丈草
嫁が君犬盗みたる三布蒲団 夏目漱石の俳句をどう読むか97
さめやらで追手のかゝる蒲団哉
川柳のような句である。二度寝しようとして蒲団が引き戻されたという程度の意味か。
これは自分のことなのか観察者なのか読み手の立ち位置が見えない句である。
まあ頭で考えた句ということであろう。
毛蒲団に君は目出度寐顔かな
え?
女?
子規の評点「〇」。これは松枝清顕みたいな嘘自慢なのか、赤裸々な告白なのか。そりゃまあこの年でそういうことがない方が
頭巾きて蒲団に包む大蛇かな 夏目漱石の俳句をどう読むか96
蛇を斬つた岩と聞けば淵寒し
湧が淵三好秀保大蛇を斬るところ、と添え書きがある。
これに対して岩波の解説は「大蛇を退治したのは土地の豪族で鉄砲の名手だった三好蔵人秀勝である」としている。根拠は『愛媛県百科大辞典』だそうだ。なら新田義宗もちゃんと……。
これ関係ないか。
こういうことか。三好長門守秀吉長男三好蔵人之助秀勝。之助がぬけとるやん。あかんでそんなもん。直す時にはびしっと直さん
つめたくも太刀を頂く塚の霜 夏目漱石の俳句をどう読むか95
つめたくも南蛮鉄の具足哉
解説によれば円福寺において新田義宗、脇屋義治の遺物を観て詠まれた句のようだ。
この脇屋義治の方は「伊予国温泉郡に逃れたとの伝承」があるので遺品が伝えられているのは、おおっとなる事実である。新田義宗は伊予とは無関係なので何故遺品が伝わってるのか謎である。もしかしたら阿波に落ち延びたという伝説の先に伊予があるのか。だとしたら漱石はかなりの大発見をしてるのではなかろうか
家も捨て東西南北納豆汁 夏目漱石の俳句をどう読むか94
冬籠り黄表紙あるは赤表紙
解説に「黄表紙、赤表紙は江戸時代の通俗的な絵入り読み物」とある。これは黄表紙の中に赤本が含まれることから、黄表紙と赤表紙を同一視した誤解ではなかろうか。黄表紙は大人向けの読みもの、赤表紙は子供向けの絵本である……と決めつけてはいけないな。赤表紙にはいろんな種類の本がある。赤本が赤表紙と呼ばれることもあったから、まあこの辺りは以下減にしておこう。
この句は前の「古道
五六寸水仙白く城下町 夏目漱石の俳句をどう読むか93
炭売の鷹括し来る城下哉
子規の評点「◎」。解説に「鷹括」の説明はない。ということはそのまま、城下町に炭売りがやってきて、その荷に鷹が括りつけられていたという意味になるのだろうか。
その鷹もまた売り物なら、鷹売りともなろうが、兎に角黒いから炭売りと見做されているわけだ。まさか炭売りが町で鷹狩りはすまい。
そもそもたかというのが恐ろしいような感じがして、炭売りとは合わない感じがする。その合わ