
吾妹子の南天の実は四畳半 夏目漱石の俳句をどう読むか102
炉開きや仏間に隣る四畳半
爐開きや左官老い行く髪の霜 芭蕉
爐開きやあつらへ通り夜の雨 一茶
爐開きや雪中庵のあられ酒 蕪村
我庵の煖爐開きや納豆汁 子規
爐開きや蜘蛛動かざる灰の上 虚子
どうも子規と漱石は炉開きと仏を因縁づけようとしている。まあ子規は納豆汁を通しての間接的な因縁づけだが、これもちゃんと納豆汁の句を詠んできたからわかること。
禅寺や丹田からき納豆汁
この句を読んでゐなかったらこの関係性は見えなかった。
漱石の句の意味は、仏間の隣の四畳半で炉開きの茶会をしたよという程度の意味か。なかなか結構なことだ。納豆汁も俳句も茶の湯も日本の伝統文化だ。仏教ももう何百年もの間日本でいじくりまわされて、すっかり日本の中に溶け込んでいる。

虚子の句を見ても、
爐を開けて仏に近き心かな 虚子
茶の湯の心は仏教的静寂と通じていると見做しているのかと思われるようなところがある。


いや、これは子規の
爐開きや厠に近き四畳半
……のパロディか?
爐開きや蟇はいづこの椽の下 子規
爐開きや越の古蓑木曾の笠
爐開きや猫の居所も一人前
爐開いて僧呼び入るゝ遊女かな
爐開きや炭も櫻の歸り花
爐開や叔父の法師の參られぬ
爐開や我に出家の心あり
爐開や赤松子われを待ち盡す
離れ家に爐開早し老一人
爐開て殘菊いけし一人哉
爐開の藁灰分つ隣かな
爐開や厠に近き四疊半
爐開や故人を會すふき膾
爐開や細君老いて針仕事
爐開に一日雇ふ大工哉






昔は四畳半がまるまる炉?


足利義政の時代に茶の間が四畳半になった?

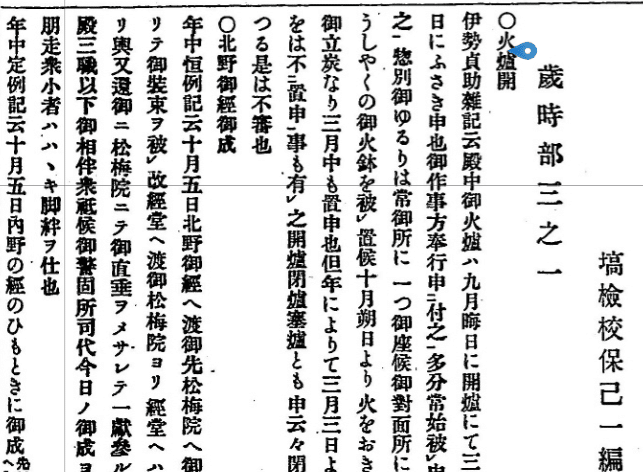


つまり炉は「いろり」のことなのね。囲炉裏開きか。
四畳半仏間に隣る囲炉裏かな
こういうことなのね。
炉開きに道也の釜を贈りけり
この句はちょっとわからない。道也の釜というものがあったとして、それはもう二百年前の骨董品なのでいくらで取引されるものか解らない。高給取りの漱石とはいえ、そうやすやすと人に贈れるものでもあるまい。
いや、全然安いな。
買おうかな。
口切や南天の実の赤き頃
わかる。
口切にこはけしからぬ放屁哉
わかる。
吾妹子を客に口切る夕哉
わからない。
解説に「客に妻を初めて紹介する句意」とある。
それは解るんだけど、漱石の立ち位置と何故「吾妹子」なのかが解らない。
一体どういう心境なんだろう。
能本に居る頃の漱石氏は何度上京したか私はそれを知悉しない。今も記憶に殘つてゐる一つの光景がある。それは漱石氏が何日の何時の汽車で新橋から歸住するといふことを知らせて來たので、私は新橋へ見送りに行つた。さうして待合室に立つてゐる洋服姿の漱石氏を見い出したので、汽車の出るまで雜談をしてゐた。いよいよ汽車が出る場合になつて私は改札口まで漱石氏を見送つて行つた。私の外に漱石氏を見送る人は一人もない樣子であつたのだが、その改札口を出る時に氏は自分の切符の外に二枚の切符を持つてゐてそれを氏の傍に近づいて來た二人の婦人に手渡しゝた。さうして私と別離を叙して後に氏はその婦人を隨へて改札口を奥へ這入つて行つた。一人の婦人は二十格好の年の若い人であつた。他の一人の婦人は五十格好のやゝ老い人であつた。私は漱石氏の後ろ姿を見送ると同時にこの二人の婦人の後ろ姿をも見送つて暫く突つ立つてゐた。さうして此二婦人が漱石氏とどういふ關係の人であらうかといふとを考べるともなく考へた。その時の漱石氏と若い婦人の面に表はれた色から推して、「奧さんを貰つたのかな」と考へた。奥さんを貰ふといふやうな話は今迄一言も聞かなかつたのである。然し乍らどうもこれはさう判斷するより外に考へのつけやうがなかつた。後になつてこの想像は正しい想像であつて、その若い婦人が今日の夏目未亡人、老婦人の方が未亡人の母堂であることを明かにした。
右の光景を記憶して居るところから言つても、漱石氏が新妻迎への爲め熊本から一度上京したことだけは疑いのない事柄であるが、其他にも上京したことがあつたかどうか、それは私には分らない。
熊本時代、漱石は高浜虚子に嫁さんを紹介しなかった。照れくさいのか何なのか、高浜虚子の文章だけ読んでいると漱石は完全なる変人である。この夏目漱石の結婚は明治二十九年、翌年熊本五高に移って後のこととされているが、もしかしたらその前年からそれらしい話そのものはあったのではないか、と疑いたくなるような句である。
元義の歌には妹または吾妹子の語を用ゐる極めて多し。故に吾妹子先生の諢名を負へりとぞ。けだし元義は熱情の人なりしを以て婦女に対する愛の自ら詞藻の上にあらはれしも多かるべく、彼が事実以外の事を歌に詠まざりきといふに思ひ合せても吾妹子の歌は必ず空想のみにも非ざるべし。『古今集』以後空想の文字に過ぎざりし恋の歌は元義に至りて万葉の昔に復り再び基礎を感情の上に置くに至れり。
吾妹子という言葉自体が愛情の言葉で、人の嫁さんには使えない。使ったらまずいことになる。では空想か。
それもおかしい。
こりゃ、困った。
まあ、明日考えよう。
[附記]
蛇笏くらいまで炉開きの句を読んでいるけれど、囲炉裏がないと読めないわけで、マンション住まいの人はもう炉開きの句は詠めないわけね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
