
同人ゲーム『narcissu』(2005)プレイ感想
ステージ☆なな制作『narcissu』(ナルキッソス)は、わたしが人生で初めてプレイしたノベルゲーム/ビジュアルノベルである。数年前、年下のアメリカ人のオタク(Geek)友達に薦められて、staemのアカウントを取得してプレイしたのだった。その時の感想は……「お~マジで死ぬんだ……」というようなモノで、何しろ初めてのビジュアルノベル/美少女ゲームだったから、好きも嫌いもよく分からなかったと思う。
あれから幾年かが経ち、ノベルゲームのプレイ数も100を越えたので、今一度じぶんの《原点》に立ち戻ってみようと思った。ちょうど先日『120円の春』でねこねこソフトに入門したのもあり、片岡とも作品繫がりで……という狙いもある。
プレイメモ
steamで無料DLしてきた。2ndと同梱されているやつ
デフォルト言語が英語で、日本語設定にしてもコンフィグ画面は英語のまま

免許取得→入院→末期病棟
お互いに初っ端からため口かい
それぞれ何歳なんだろう 「主人公」は免許とった直後だから20歳くらいか。セツミの方は8年前に中1ってことはやはり20歳くらい……同い年っぽいな。

テキスト非表示機能がなさそう
重いのかなんかのか、テキストの表示が滑らかでない。製品版を購入するべきだった?
セツミ ヒロインには名前がある 無表情
呼び捨てを指摘されてて草
セツミのほうが年上なの? ほんとかな
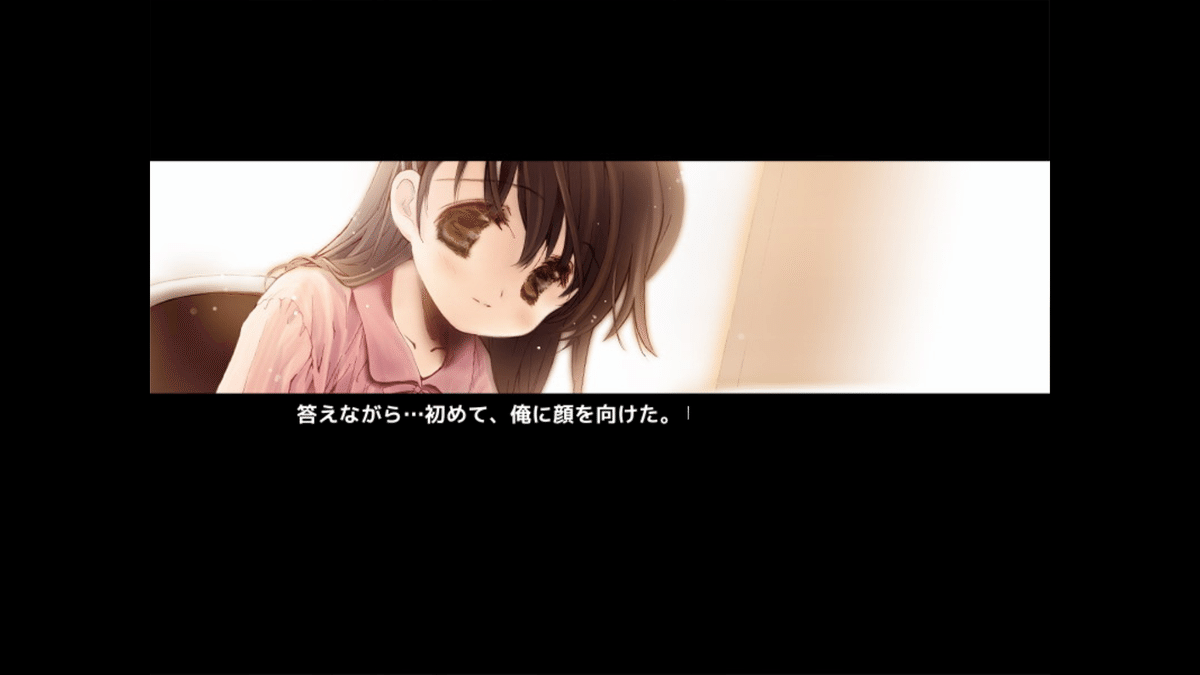

世紀末~00年代初頭の、いわゆる「引きこもり」的メンタリティの表現としての末期患者、終末病棟「7階」。〈世界〉から隔絶されて、行き場のなくなった男女は逃避行を始める。うーむ古典的……
00年代初頭ってセカチューとかも流行ってたもんなぁ(小説2001年, 映画2004年)
7階の15cmだけ開いた窓は、自分たち患者が外に逃げるのを防ぐ「檻」であり、同時に彼らを外の社会=世界から守る「砦」でもある。
「主人公」から声をかけて出発するんだな 逆だと思ってた
銀のクーペの車言葉ってなんだっけ 車言葉くわしくないから分かんないな……有識者おしえてほしいです!
やけに車の内装や運転操作にかんする描写やCG素材が多くてこだわりを感じる。
水戸街道
さらっと窃盗罪 『120円の春』でもあったように、犯罪は「ふたり」から〈世界〉を引き離して甘美な関係を構築するために都合のよい過程である。ロードムービーであり、「車」という小さな閉塞空間をふたりだけの世界としている。まさにタイトル通り、自己陶酔的な物語だが、そんな自意識過剰な自己陶酔は、社会との健全な関係構築を拒否した自己喪失的な精神性に裏打ちされていることを見事に表しているともいえる。
淡路島…… 日本神話? 『おやすみプンプン』と混ざって鹿児島まで行くんだと勘違いしてた
セツミの自分語りは、完全にオタクの隠喩としか読めない。現実から切り離されて、虚構=地図に耽溺するのが好き
病弱ヒロイン系の物語や、逆に男主人公が最終的になんやかんやで死ぬ系の物語はたくさんあるが、それなら当然、本作のように両方が病身で死ぬ心中パターンもある。この種の特徴は、男主人公とヒロインの間に「救う/救われる」といった非対称性を持ち込むのではなく、「男主人公=ヒロイン」という同一化の等式を打ち出すことになる(しかない)点だろう。セツミ視点の一人称叙述もわりと差し挟まれているのもそのため。読者(プレイヤー)≒「主人公」≒セツミ、という相等関係。
埼玉県の入間から八王子へ
「別にどこか具体的な目的地に行きたいわけじゃない」と何度も自分たちに言い聞かせるように呟くふたり。あくまで現状から、〈世界〉から、「死」から逃げたいだけだと唱える。「目的地」を持つということは、時間のなかで前を向き、生への意志を持つことに他ならない。しかし彼女らは時間=世界から疎外されている。ということにしたい。さもないと世界のなかで生きる虚しさを目の当たりにしなければならなくなり、それはとてもじゃないが耐えられないのだから。ゆえに、前を向くのではなく「逃げる」というかたちで常に後ろを振り返りながら、あるいは目を瞑りながら破滅へとひた走る。そのような、否定のかたちでしか自らの生、実存を肯定できない。ふたりは自分たちの生をそういうものとしてプロデュースしたい(せざるをえない)……という物語。

終末病棟の15cmだけ開いた窓と明らかに響き合う、車の「10cmほど開けた窓」!
ガソリンスタンド店員=外の世界との接触の間口が、入院時よりもさらに狭くなっていることを示す。無論それは、かわりにセツミと「主人公」の二者関係の閉塞性がこの逃避行ドライブによって高まっているということでもある。


人物の一人称視点の風景だけでなく、こうした客観的なショットもある。世界のなかの車(クーペ)のなかのふたり(見えない)
「主人公」が免許をとった直後に病院送りになったように、セツミは中学で水着を使う時期の直前に入院したことが大きなモチーフ(象徴)となっている。(そのように逆算して設定・執筆されている)
エメラルドの海に浸る同い年くらいの水着グラビアモデルの女性への羨望。「胸の大きな傷跡」……
これ、男女ペアでなく、セツミがひとりで7階を逃げ出して入水自殺する話だったらもっと研ぎ澄まされていてすごかったかもしれないな。これだと、病気で可哀想なふたりだけど、最後にお互いに一緒にいられる相手に出会えてよかったね、みたいな捉え方も十分にできてしまう。それが悪いってわけじゃないけど…… この雰囲気、やりたいことのラディカルさ、鋭さはひとり旅のほうが増したはず。だって人生はひとり旅じゃないか。
でもそれじゃあセカイ系にはならないんだよな。ひとりで逃げ出して海まで辿り着いて死ねる "強さ" がある奴は、そもそもお呼びでない。弱い者たちが「世界」から閉じこもって愚かしくも身を寄せ合う点にセカイ系の本質がある。「世界か自分か」という──どちらにせよ実質的に世界に対してひとりで戦いを挑んでいる英雄であることは変わらない──問題系ではなくて、あくまで「世界かヒロインか」だから。つまり、ここでは「自分」というものが表面上顕わになっておらず、隠蔽=希薄化されている。いまここにいる自分というノベルゲームの視点主体を隠して忘れて、いないことにする。それこそが、このゲームの希う「死」への欲望だろう。世界がこわい。社会と関わりたくない。引きこもりたい。いなくなりたい。消えたい。──そんな、この時代特有の、いや、ある種とても普遍的な精神に要請されて出現したのが本作のようなセカイ系作品なのだろう。

世界から逃げて自己忘却=死を希求するにあたって、自分以上にヒロインからは「世界」の垢を省いておく必要がある。世界に汚れていない純粋無垢なヒロインとしての、生まれつき病弱な少女。「7階」の先輩であり、(入院=引きこもり)人生の先輩としてのセツミ。そんな彼女は地図を眺めて妄想のなかでドライブするのが好きだった。これは一見、外の世界を(「主人公」より)よく知っているように思えるが、彼女のそれは現実の世界の知識ではなく、あくまでリアルから遊離した情報や想像の産物(=フィクション)である。虚構の住人であるセツミの導きによって旅をする「主人公」達は、なるほど確かに、現実を拒否して虚構へとのめり込んでいく、典型的な引きこもり(オタク)の生き様を体現しており、その虚構の果てに、希っていた「死」という救済が待ち受けている、としている。
車内、タオルで身体を拭く。「見ないでよ」と言われたのにガラスの反射でガッツリ胸まで見てて草

「ガラス(鏡)に映る自分」は露骨にnarcissuの原義を引用しているのだろう。そこから「更に向こうに」ヒロインの裸体を見出す、というのは単なる同型反復に終わらない見事な神話オマージュかもしれない。このシーンがおそらく本作のセクシュアルなドラマの極限なのだし(エロゲならHシーンになっていた)。ヒロインの無防備な裸体に「傷」を見る(→そういう他者発見こそがポルノである)、というエロゲでも典型的な物語構造。
一号線 平塚 まだ神奈川か
箱根を越え……えっ、もう名古屋!? 静岡スキップされてて草 国道22号
無表情ヒロイン赤面ノルマ達成 好きな洋服買えて良かったね 気に入ってサイドミラーで見てるのかわいい
国道21号線 岐阜 どんどん進むな
瀬田ICから名神高速に乗る 草津へ なんかボーカル挿入歌が流れ出したぞ すげぇ往年のメロドラマ感
地理と車種に詳しいセツミ オタク大歓喜
桂川PA 京都か
二度目の窃盗&器物損壊 「犯罪(の刑罰)」はこれからも生きようと思っている人間にのみ抑止力となる 無敵の人には効かない
吹田JCTで中国自動車道へ 大阪に入っている
神戸JCTから山陽自動車道へ そして明石海峡大橋! 開通は98年だからまだ結構新しい ふたりより若い
おせっかいなカップルのせいということにして記念写真時にくっ付くことに成功 じりじりと、ゴールへと近づくごとにふたりの距離も縮まっている。
砂浜で練習してセツミにも普通免許を発行(譲与) 冬の夜の寒い車内で膝枕ノルマ達成
灘黒岩水仙郷 ほんとに水仙の名所があるのね
2/2 ナルシスとエコーの神話を聞き、自分たちと比べる

あ、「主人公」とセツミをナルシスとエコーに対応付けるんじゃないくて、「現実」と自分(たち)の喩えにするのか
おわり!!!
あれ、「主人公」も一緒に死なないんだっけか 近いうちに死ぬにせよ
続編で語られてるのかな
総プレイ時間:3時間25分
感想まとめ
いやぁ~・・・・・・ ザ・古典、ですね~……
ものすごく泣かせようとする演出があるわけではなく、淡々と「諦観」という情念を飼い馴らして、簡潔にして短編美少女ノベルゲームの金字塔としての風格を備えている…………
そんなに感動するわけでもないし、むしろ本作に代表される病身逃避行セカイ系のギャルゲはめっちゃ嫌いとさえ言える(と再確認した)けれども、それでもひとつの古典的な名作ではあることを認めざるを得ない。
今回やり直して思ったことは、ちゃんとロードノベルとして具体的な道や地域の名前を細かく出して、ふたりの旅路を読者が追えるように書かれているんだなぁと好感を持ったこと。ふたりは世間や社会から逃げて旅に出ているんだから、具体的な地名やルートに言及しないままのほうが抽象的で普遍的な旅として演出もできただろうに、そうはしなかった。これは、ふたりがそれでもやはり現実の「世界」と繋がっていたかった、拠り所としたかったことの証左だと読みたい。車関係も明らかにライターのこだわりで事細かに描写されていた。ふたりが何の病気なのかも、「主人公」の名前が何なのかも一切わからないけれど、ふたりが乗った車、ふたりが辿った道筋、ふたりが旅の終わりで行きついた場所は、たしかにこの現実に実在するものである。ふたりという虚構がたしかにわれわれの現実と地続きであったことを、この作品は示し続けている。
上に書いたけど、20世紀末の先行きが見えない閉塞的な社会背景から生まれた00年代前半の世間的な「純愛」ブーム、その渦中の2005年に発表されたゲームである、という時代性を非常に感じた。すべてを時代や社会背景によって説明する作品解釈には与したくないが、しかしながら今の自分はある程度そうした社会の歴史の重みを尊重しなければいけないと理解しつつある。
今年に入ってプレイしたノベルゲーム(エロゲ)でいえば、『終末の過ごし方』(1999)、『アカルイミライ』(2003)などが、それぞれの個性を放ちながらも、この『narcissu』(2005)と響き合うような時代の精神性を基底としていたように思う。
それは、大雑把にいえば「世間 vs 自分」という図式を仮構して、ドン・キホーテのように世間に対して無謀な戦いを挑むのではなく、逃げ出して自らの殻に閉じこもろうとする引きこもりのメンタリティである。「自らの殻」なんてものにリアリティを感じられないくせに、それゆえに、閉じこもる行為によって〈自己〉なる曖昧で不明瞭なものをなんとか取り繕って形作ろうとする。
こうした状況を物語・フィクションで表現しようとする際に、「ひとり」で「世界」から逃げ出して死ぬ(脱出する)、という話のほうがより純粋で "正しい" ような気がするのに、なぜか男主人公とヒロインという「ふたり」の人物によるメロドラマとして成立するのはなぜだろう。そのようなことを、本作を再プレイしながら行く当てもなく考えていた。むろん、「美少女ゲーム」なのだから、ヒロインとの甘酸っぱい(プラトニックな)イチャイチャ、恋愛っぽい要素を入れるためには、男女ふたりが必要なのだといわれたらそれは当たり前の話である。言うまでもない。それはそうなのだけれど、私はそれ以外の角度からこの問いを考えたい。
たとえば「ノベルゲーム」という形式・視点の問題として。終盤で「主人公」が車内から使い捨てのカメラを取り出してセツミを撮るように、「視る主体/視られる客体」という非対称な関係を「男=主人公/女=ヒロイン」というジェンダーの二元論に素朴に対応させているとしたら。セツミの生への、ふつうの人生への執着のモチーフが、他の何でもなく「水着のグラビアアイドル」であることもまた、この(帰り路はない)一方通行の視線=旅という主題を強固にする。
ノベルゲームの視点は、一人称を擬装する。画面の手前、"こちら側" に「主人公」なる視点人物がいて、その人物が今見ている世界・風景が画面に映っているということにする。そしてその奥、画面の "むこう側" には無表情な22歳の女性の横顔が、あるいはこちらを見て微笑む彼女の姿が映る。この空間の奥行きをディスプレイ(平面)に仮構するシステムこそがノベルゲームである。
説明もなにもなく、われわれは──初めてノベルゲームを遊ぶ者でさえ──そのルールを無意識に了解して読み進めることができる。本作のラストシーン、海に足を浸からせて、両手に靴をもって、こちらにポーズをとりながら笑いかけるセツミを、フィルムのきれたカメラで撮り続ける「主人公」…という場面はまさに、こうしたノベルゲームの作り上げる一方方向の舞台空間の力学を象徴している。東から西へ、陸から海へ、という方向性。
『narcissu』は、ノベルゲームは、けっしてあの場面を海側から、セツミ視点で描くことはないのである。なぜなら、"向こう側" にいる存在(ヒロイン)とは死ぬべき者であるから。見ずに見られる/撮らずに撮られる者だから。セツミが「主人公」より年上でなければならないように、ふたりの死ぬ順番は絶対にこうでなければならない。そうでなければ、ノベルゲームは終わることも始まることもできないのだから。
ひとつ前の文、ひとつ前のページの文章にたやすく「戻る」ことができる小説と異なり、ビジュアルノベル/ノベルゲームは本質的に不可逆のノベルであり、そこにノベルゲームの原理的な "ゲーム性" がある。一度クリックしてしまったら、もう「現在」は不可逆で、さっきの台詞、さっきの描写に本当の意味で戻ることはできない。「一本道」であり、かつ、「一方通行」であること。そんなノベルゲームの本質が、真に研ぎ澄まされたかたちで凝集した作品だった。
宣伝
ノベルゲームの「男主人公」と「ヒロイン」の視線の非対称な関係に着目したジェンダー論は、こちら ↑ の寄稿文でも扱っています。(というか、およそ全てのノベルゲームを遊ぶときに必ず考えざるを得ない観点です、自分にとっては。)
その寄稿文の元ネタがこちら↑
こちら『白昼夢の青写真』のCASE-2でも、男主人公とヒロインの〈視線〉の扱いについて興味深いものがあってテンション上がっている様子が見られます。
その他のノベルゲームnote
『たねつみの歌』が発売されるまでに、みんなもやろう「国シリーズ」!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

