
旧植民地で「星の王子さま」を読む
この記事はシンガポールから書いています。(これは大事なことです。)
ミンダナオで見つけた「星の王子さま」
12月にフィリピンはミンダナオにある妻の家の大掃除をしていたら、7,8年前に上の子にあげたサンテグジュペリの「星の王子さま」(T.V.F. Cuffe訳でペンギン出版の英語版)を見つけました。私自身も「星の王子さま」を読んで育ったこともあり、懐かしい気持ちになりました。下の子はまだ4歳半なのだけれど、「読んでみる?」ときいてみると「読む」というので朗読しました。バラとの別れやきつねを「飼いならす」下りはあいかわらず泣けるものがあります。
冒頭の部分を読んでから「ぞうを食べたうわばみの外側」の絵を見せて「これ、何の絵かわかる?」ときいてみると、案の定、うちの下の子は「帽子」と答えました。「ちゃんと聞いてなかったでしょ。サンテグジュペリさん悲しむよ」とからかうと、むきになって怒っていたけれど、その後、彼はドハマりしました。まだ「星の王子さま」の内容が理解できるようになるには早いだろうと思ったのだけれど、子供でも大人みたいな間違いをすることもあるようで、特に冒頭から星の王子さまの出身地である小惑星B612の話までは特に気に入ったようです。先月から私は既に数十回読まされています。
息子に数十回も「星の王子さま」を読まされる過程で、私の読み方も変化してきました。かつては「星の王子さま」をサンテグジュペリの文脈で読んでいたのですが、私はポストコロニアリズムを勉強した東南アジア在住の歴史家です。だんだんとシンガポール、東ティモール、フィリピンなどの旧植民地という空間から、フランス文学である「星の王子さま」を読むというスタンスにシフトしてきました。学者の悲しい性です。
今世紀になってから各国で保護期間が切れて、星の王子さまのたくさんの翻訳が出ているけれど、ペンギンの英語版を読んでいて「あれ?」と思った部分がありました。アジア史家が、西洋人の作品を読んだり、小説を読んだりするとよく感じる「ピンと来た」感じと違和感の両方です。
小惑星B612について発表したトルコの天文学者のくだりです。「星の王子さま」の出身地を説明するために挿入されている話ですが、若干本筋から脱線したような形で語られる部分です。ネットで見つけた研究社のバージョンだと以下のようになっています。
王子さまがやって来た星は小惑星 B612 だと思うが、それにはちゃんとした理由がある。
この小惑星を、1909 年にトルコのある天文学者が、望遠鏡で一度だけ観測したことがある。その天文学者は国際天文学学会で自分の発見についてすばらしい発表をした。ところが、そのとき彼がトルコ風の変わった服装をしていたというので、誰も彼の言うことを信じなかった。
大人というのはそういうものだ ・・・
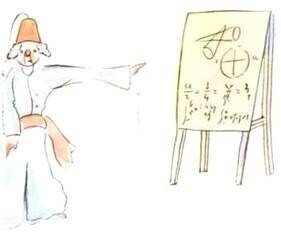
しかし、幸いなことに、小惑星 B612 の名誉は回復されることになった。トルコの独裁者が国民に対してヨーロッパ風の服を着なければ死刑にするという法律を作ったからだ。そこで、その天文学者はとても洗練された服を着てもう一度発表した。すると、今度はみんなが彼の報告を受け入れたのだ。
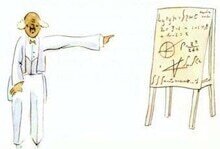
↑研究社の「星の王子さま」へのリンク。
「星の王子さま」におけるトルコ
研究社版では(おそらく他のいくつかの日本語版でも)省略されているのですが、ペンギン版(そしてフランス語版)だとトルコの天文学者が再度小惑星B612について発表したのは、「1920年」と明記されているんです。
トルコの天文学者が「トルコ風の変わった服」をしていたのが1909年、独裁者が「ヨーロッパ風の服を着なければ死刑にするという法律を作った」のが1920年と聞くと、世界史を勉強した人はピンとくるものがあるかもしれません。第一次大戦、オスマン帝国の崩壊、トルコ革命です。
約600年間続いたオスマン帝国も、1914年-18年の第一次世界大戦の結果弱体化し、1923年にトルコ民族の国民国家であるトルコ共和国に取って代わられます。この運動の指導者、ムスタファ・ケマル・アタテュルクのもとで1925年に成立したのが、いわゆる「帽子法」、ヨーロッパ風の服の着用を強制する法律です。
↑「トルコの帽子革命」の書評
星の王子さまのパイロットが言及している「トルコの天文学者」や「B612」はもちろん架空の話で、しかも「1920年」という日付は歴史学的には若干の時代錯誤なのですが(帽子法の制定は1925年なので)、サンテグジュペリは西洋人のスノビッシュな感じと同時にトルコ革命のおかしさを皮肉っていたわけですね。「星の王子さま」のフランス語版の出版が、1943年4月なので、第二次大戦中の時期から第一次大戦前や戦間期の出来事を振り返っていたのです。
↑学術的な質についてはトルコは専門ではないので厳密に評価できないのですが、小笠原先生のオスマン帝国史はコンパクトで読み物としては楽しめるものでした。アタトゥルクの時代にオスマンは「後ろ向き」「時代遅れ」というレッテルを貼られたのですが、ここ数十年間に再評価が進んでいるそうです。
トルコにおいては、オスマン帝国とアタトゥルクの改革の歴史的評価が別れていることもあり、「星の王子さま」の翻訳にもかなりゆれがあるそうです。
↑「星の王子さま」におけるアタトゥルクの遠回し表現であるところの「トルコの独裁者」は、ある版では「偉大な指導者」別の版では「憎むべき暴君」と訳され、論争になっているそうです。
星の王子さまにおけるトルコの下りから、サンテグジュペリはトルコ革命に関しては冷ややかに見ていたという印象を受けます。西洋のスノビズムと同列に「大人たち」の事柄として扱っています。
サンテグジュペリと植民地主義、第二次大戦
彼が当時のフランス帝国・オスマン帝国、そしてナショナリズムの勃興をどう考えていたのかというと、当時のフランス人として「普通」な感覚を持っていたのではないかと感じます。
「人間の大地」の前半や彼の伝記を読んでみると、パイロットとしての語り手、そしてサンテグジュペリは 当時植民地であったセネガルのダカールやベトナムに様々な郵便を届けることでフランス帝国の行政に実質的に関わっていることがわかりますが、それを問題視している様子は全くありません。帝国に対する「反逆者たち」がひょっこり姿を見せることもあり、時にはサンテグジュペリは同情的であったりもします。ですが、なぜ反逆しているのか、彼らが何を考えているのか、フランス人であるサン・テグジュペリ自身の植民地での存在がどう受け止められているのか、このような事柄が問われることはありません。つまり、フランスの植民地関係については心の隅で気づいてはいながら、沈黙しているのです。
一方で、「星の王子さま」の執筆時期におきている第二次大戦におけるフランス、直前のスペイン紛争の状況に関しては彼は非常にはっきりと意見を述べています(彼の「ある人質への手紙」を参照してください)。「ぞうを飲み込むウワバミ」、その半年の休憩期間、ウワバミに関する子どもたちの警告、警告を「帽子の何が怖いんだ?」と見逃してしまう大人たち、というのも当時のナチスドイツの台頭、侵略、そして人間性を失ったコミュニケーションの隠喩と読むことが出来ます。植民地の問題ではなくて、西洋を蝕む問題がサンテグジュペリにとっての「本当の問題」なのです。
もちろん、サンテグジュペリは植民地主義を主題にする著者ではないという弁解もできますし、本来、植民地で読まれることを想定して書かれた作品でもないのでしょう。そして、作品自体には世界文学のひとつとして恒久的な価値があるでしょう。
ですが、シェイクスピアを旧植民地で読むと全く違う印象を持つように、旧植民地で座り込んで「星の王子さま」を読めば、植民地時代のフランス文学が持ってるオリエンタリズムが背景にあることも見えてくるのです。
私の星の王子さま論はひねくれているので、うっとりしたい人は友達のマダムスノウさんがアメブロで書いてるのでどうぞ。
よろしければサポートお願いします。活動費にします。困窮したらうちの子供達の生活費になります。
