
「開発の全過程を体験!」エンジニアインターン生&先輩社員インタビュー
木村情報技術では、長期インターンシップを随時受け入れています。インターンシップを通じて、基本的なビジネススキル・ビジネスマナーに加えて、開発スキルやIT業界に関する深い専門知識が身に付きます。
現役のエンジニアからのサポートもあるので、実務レベルのコミュニケーション能力、問題解決能力、論理的思考力など幅広い知識とスキルが得られます。
この記事では、実際に長期インターンシップに参加した学生と、その指導役を務めた先輩社員のインタビューをお届けします。
■インターン生プロフィール

片山陸人(かたやまりくと)さん
佐賀大学大学院 理工学研究科 知能情報工学コース
情報系を専攻、プログラミングやセキュリティを学んでいる。
研究内容:RPAに関する研究、PCの事務作業を自動化する技術。

井上魁斗(いのうえかいと)さん
佐賀大学大学院 理工学研究科 知能情報工学コース
研究内容:画像処理に関する研究。画像生成に関するアルゴリズムを活用し、落とし物を検出、管理するアプリケーションの研究・開発。
■先輩社員プロフィール

徳山鐘三(とくやましょうぞう)さん
システム開発本部 第三開発部 課長代理
Web講演会(ライブ配信)システムの設計・構築、基盤システムの開発、機器選定などを経て、現在は生成AI関連の研究開発や、企業向けシステムの提案やマネージャー業務に従事。

山口尚昭(やまぐちなおあき)さん
システム開発本部 技術創造チーム
Web講演会(ライブ配信)システムや、企業向けシステムの構築やカスタマイズなどを経て、現在は生成AIを中心とした研究開発に従事。
1.インターンシップの内容

山口先輩:今回のインターンでは、片山さんと井上さんには生成AIに関する開発業務を担当してもらいました。
生成AIは日々進化していて、様々な分野で活用が広がっていますが、その評価システムはまだ確立されていません。当社は生成AI関連サービスも開発・提供しているため、評価システムの開発は重要な課題の1つです。
このプロジェクトでは、生成AI評価システムの設計からデプロイまで、一通りの開発工程をお任せしました。開発言語については、最新のトレンドに合わせ指定しました。フロントエンドにはReactを使用し、バックエンドやサーバーサイドの開発にはPythonを用いました。また、フレームワークとしてはFastAPIを活用しました。
開発においては、おふたりの自主性を尊重し、信頼して業務をお任せしました。週に2回ほどのペースで来社していただき、開発期間は約4か月間に渡りました。
片山さん:まず先輩社員に要望をヒアリングしてから、要件定義、設計、評価を繰り返しました。Pythonは以前から経験がありましたが、Reactを使ったのは今回が初めてでした。上流から下流まで、一通りの工程を経験できたのはとても貴重でした。
完成したシステムにはまだ満足していない部分もありますが、やはり愛着は感じますね。
今回のインターシップではチーム開発を行いましたが、大学ではチーム開発をあまり経験していなかったので新鮮でした。
私と井上くんは、業務時間が異なることが多かったので、どこまで作業が進んでいるか、テキストコミュニケーションで引き継ぐのは思ったよりも大変でした。どうしたら相手に伝わるのか、考えるいい機会になりました。会社に入ったらこういう場面も多いと聞いていますので、本当に良い経験になりました。
井上さん:自分は大学の授業や研究でPythonを使ってきました。Reactも大学院に入ってから少しずつ触り始めていました。不明点があれば、片山くんに質問したりして、自分ひとりではなくGitを使ってチームで開発した経験はとても価値を感じました。
2.インターンの日の流れ

片山さん:私は社員の方と同じく、9時から18時まで勤務していました。まず朝礼があり、その後すぐ開発作業に入りました。途中、分からない点があれば先輩社員に相談し、また開発に戻る、という繰り返しでした。一日の終わりには進捗報告も行っていました。
井上さん:私は福岡から佐賀に通勤していて、11時から17時までの勤務でした。片山くんとは勤務時間が異なりましたが、勤務中は同じく不明点を確認しながら黙々と開発を進めていました。
片山さん:先輩社員に質問といえば、途中から先輩社員と席が離れたことがありましたが、やはり席は近いほうがすぐに質問できて便利だと感じました。
井上さん:自分は勤務スタートがズレていたこともあって、片山くんに質問することが多かったかもしれません(笑)。 片山くんと2人で相談して進めることもありました。
山口先輩:確かに、インターンのお2人で相談して対応している姿も見かけました。お2人とも優秀で、安心してお任せしていました(笑)。
3.インターンシップに参加したきっかけ
片山さん:大学院のある授業で、木村情報技術の人事担当・田中さんが来られたことがありました。そこで、木村情報技術で長期インターン募集していると紹介があり、ちょうど開発経験を積めるアルバイトを探していたので、これもご縁だと思って応募しました。
佐賀大学の中では、地元企業である木村情報技術の名前はよく耳にします。佐賀でプログラミングをするなら木村情報技術だと思いました。
井上さん:私も大学の授業で、木村情報技術のインターン募集に関する紹介動画を見たことがありました。佐賀でIT系のインターンシップをするなら、木村情報技術だとも思っていました。
実は自分はサッカーが好きで、サッカーJ1「サガン鳥栖」のユニフォーム胸スポンサーとしても、木村情報技術の名前はよく聞いていました。
また、同じ佐賀大学の片山くんもインターンに参加すると聞いていたことや、以前はユーデミーでの学習やハッカソンへの参加経験もありましたが、自分では成長に焦りを感じていたので、今回のインターンに応募することを決めました。
4.完成したシステムへの評価と感想

山口先輩:生成AI評価システムの出来は、十分に要望を満たしていました。UIの部分が、あともう一息という感じでしたね。利用者の使いやすさをさらに向上させられれば完璧だと思います。
井上さん:今回開発したシステムは生成AIを評価するもので、BCP(Business Continuity Planning)も関連していました。BCPは大学で学んでいましたが、実際に仕事として関わることで、実践的な理解が深まりました。
不慣れな言語へのキャッチアップに苦労しましたが、しっかり動くものが作れたと思っています。
片山さん:私はUI担当で、データを表にする工程がありましたが、思ったよりも難しくて大変でした。その点は先輩社員に相談しながら進めました。
システム開発にイチから関われたことは、とても良い経験になりました。実際にコードを書いて、それが思った通りに動いたときのやりがいはひとしおでした。
また、社員のみなさんが活発でよく挨拶をされることも印象的でした。部屋の端と端にいても、大きな声で挨拶が返ってきました。
徳山先輩:途中のレビューで、新しい機能をリクエストするという無茶ぶりをしてしまいましたが、最終的にはしっかりと形にしてくれました。デプロイして、十分みんなが使える状態になっています。本当にお疲れ様でした、ありがとう!
この生成AI評価システムについては、今後は我々社員が引き継ぎますが、私たちシステム部門だけでなく、社内でももっとお客様に近いメンバーにも使ってもらうことで、より良いシステムにブラッシュアップされると思っています。
片山さん:新機能の追加要望への対応は、既に作っていたものを全体的に少しずつ修正することになるので、確かに大変でした。でも、その結果発生するバグを一つ一つ修正してく作業は面白かったです。
5.将来の夢

片山:エンジニアリングの面では、開発に関するあらゆることをゼロから経験することができました。このインターンシップのおかげで、次に何か開発する際も、スムーズに進められる自信がつきました。
卒業後は、東京で働く予定です。今回の経験を活かして、お客様に合わせ最善の解決策を提示できるSIerになりたいと考えています。
また、報・連・相の大切さを再認識しました。自分はコミュニケーションに多少は自信がありましたが、いざ仕事になると、自分が何が分からないのかを言語化して社員に伝えることが難しく、つまづいてしまいました。インターンシップを通じて、「ここまで終わりました」「次はここをします」といったように、相手にとって分かりやすく、自分の考えをまとめて伝えらることを心がけました。
井上さん:インターンシップに来るまではフロントエンドしか触ったことがなく、バックエンドは未経験でした。今回のインターンシップを通じて、フロントエンドもバックエンドも両方開発できるようになりました。技術的に大きく成長できたと感じています。
卒業後は、できれば教育関連のウェブ会社で働きたいと考えています。お客様の課題を技術で解決できるエンジニアを目指しています。
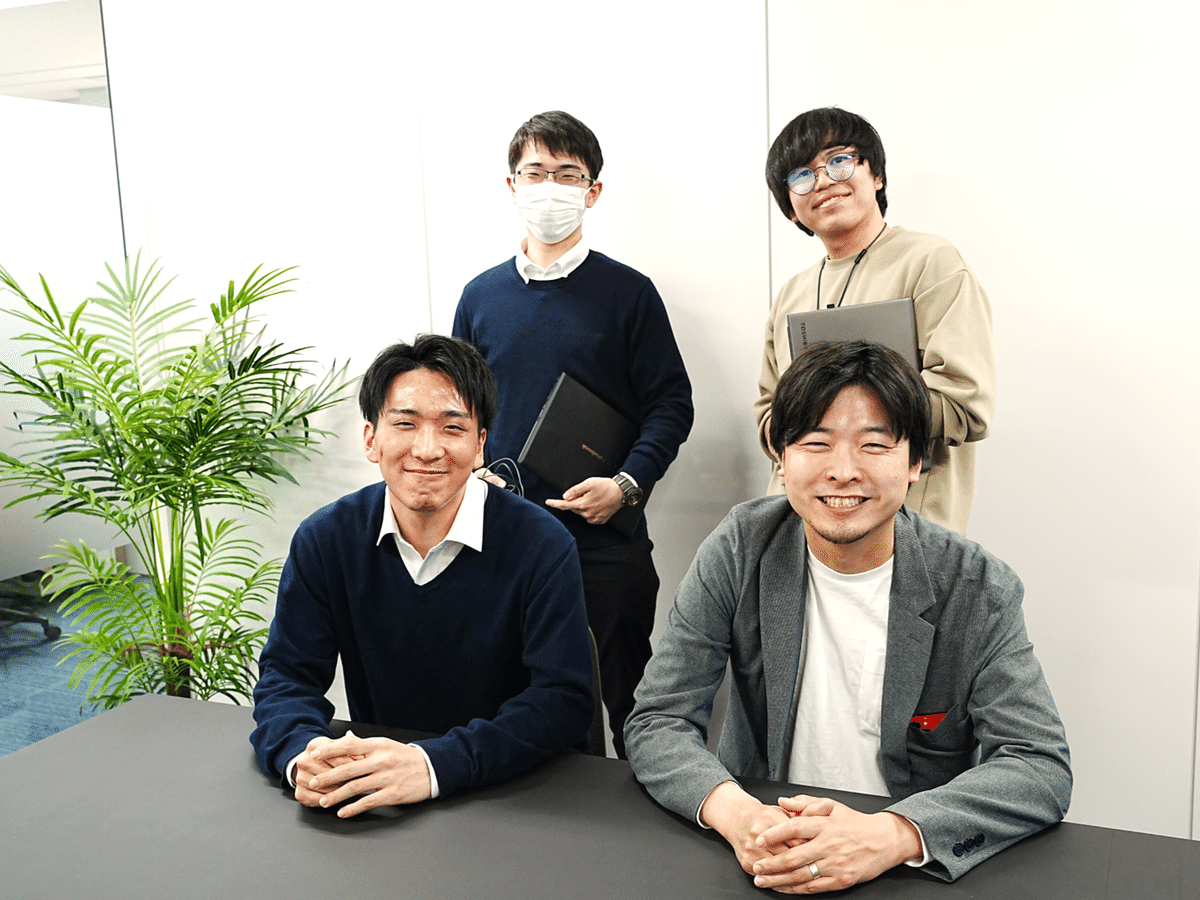
手前側(左から):片山さん、徳山先輩
■インターン生の募集について
木村情報技術では、1Day仕事体験と長期インターンシップの両方を随時受け付けています。
実際の業務を通じてスキルを磨き、エンジニアとして成長したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
エントリーお待ちしています!

本件に関するお問合せ先
木村情報技術株式会社
採用担当:田中・中村
電 話:0952-97-9491
メール:recruit@k-idea.jp
HP:https://www.k-idea.jp/recruit
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
