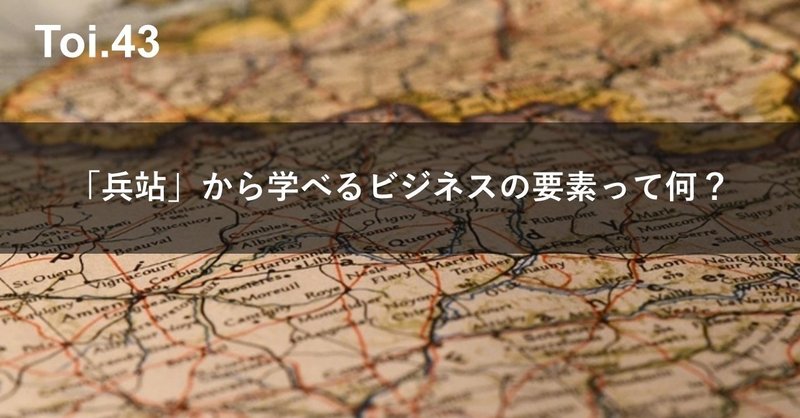
「兵站」から学べるビジネスの要素って何?
こんにちは。Kid.iAです。
ビジネスシーンで使われる「ロジスティクス」の元となっている軍事用語「兵站」について書いてきて、本日で早くも3回目となります。

前回投稿では輸送手段の変化を軸に「兵站の歴史」について書きました。
今回はそうした歴史も踏まえつつ、軍事用語でもある「兵站」から学ぶことができる「ビジネスの要素」には何があるのかを、双方の共通点や相違点を考えていくことでまとめていきたいと思います。

相違点
まず違っているところって何があるのかなと考えてみて、真っ先にでてきたことが「輸送する対象」が異なることです。

兵站は「軍隊を動かし、かつ軍隊に補給する実際的方法」という意味からも分かる通り、戦いに必要な「兵士や弾薬、食糧」といったものを輸送します。
一方で、ビジネスにおけるロジスティクスは個々の商売に必要な「製品や材料、什器」といったものを輸送します。
これ以外にも細かいものは多くあれど、大きな違いとしては「軍事」と「ビジネス」というそれぞれの目的に起因する「輸送対象の違い」、これ一つだけなのかなと思いました。
共通点
相違点以上に多いなと思ったのが共通点です。元となって使われている言葉なので当たり前の話なのですが、その中でも何が共通要素として重要になるのかを考えたところ以下に書く「3つ」に絞ることができました。
共通点その①
一つ目は「輸送手段」です。

2020年時点で「馬車」を使うことは滅多にないと思いますが、それ以外の輸送手段としては現在のビジネスシーンでも同様に使用されているのが「鉄道、自動車、船、飛行機」です。
また重要な共通要素として挙げられることが、前回投稿「兵站の歴史」でも述べたモルトケやヒトラーの失敗のように輸送手段を「どれか一つに頼ろうとしてはいけない」ということです。
目的や状況によって全ての輸送手段の「最適バランス」を見つけることが、兵站と同様ビジネスでも大切になってくることだと思います。
共通点その②
二つ目は「役割」です。

軍隊はA地点からB地点へ、食糧といったモノだけでなく前線で戦う兵士も含めて「正しい時間に、正しい場所へ送れるかどうか」、また「輸送手段の過剰や不足によってその移動が妨げられることがないかどうか」が一つの要素になります。
これはビジネスにおいても同様です。
そして最も重要な要素と言えるのが、可能な限り過不足なく「必要な数量を補給すること」です。
つまり軍事にもビジネスにも「消費量」や「必要量」の計算ができる兵站人材と、それを可能にするシステムが必要と言えます。
共通点その③
最後、三つ目は「不確実性」です。

景気含めその時々の市場環境に左右される販売数量や、労働スト等による生産遅延・輸送遅延リスクなど、ビジネスには「計画段階では読めない」様々な不確実性が存在します。
そしてそれ以上に不確実性の霧が濃いのが「戦場」と言えます。人と人の戦い。心理的な焦りや恐怖などに加えて相互作用性の高さがその不確実性を高めます。
ではどうすればいいのか?
軍事においてもビジネスにおいても共通して大切なことは、こうした「不確実性」を受け入れ(前提として持ち)「臨機応変」に対応できるようにすることではないでしょうか。
状況が変わるのであればその「情報」をいかにして得るか、得た上で「俊敏に」対応できるかが勝敗を左右するといえます。
まとめ
ここまで書いたことをまとめると以下です。

兵站から学ぶビジネス要素という観点から言えば、より大切なのは「共通点」の方だと言えます。
輸送するものが何であれ、過去の歴史における失敗などを共通する部分から学ぶことで現代のビジネスにも活かすことができます。
見る人によっては具体性に欠けるかもしれませんが、まとめる中で改めて上記3点はとても大切な要素だと感じました。
次回は兵站シリーズ最終回となります。
兵站の歴史、軍事とビジネスの共通点を踏まえた上で、ロジスティクスが生み出す価値や価値基準について書いていけたらと思います。
もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️
今後の創作の活力になります。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
(追記)以下、シリーズ全編をまとめています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
