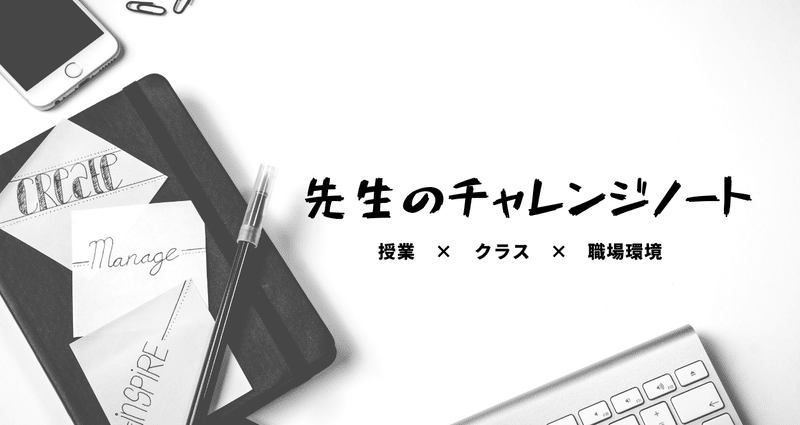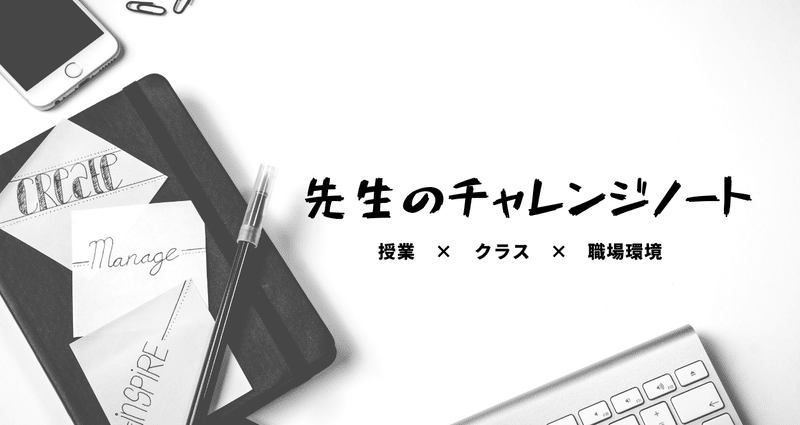自己紹介| 『7つの習慣』と教師とわたし
はじめましてこんにちは。私は、学校の教員として働いている女性です。社会科教員として地歴分野を中心に教えています。
noteを細々と始めて2年が経ちました。もともと文章を書くことが好きで、誰かと考えを共有することが好きだったので始めたのですが、今では自分自身の思考整理ツールとして救われている大切な場所となっています。
どのくらいの人が今までのnoteを親身に読んでくださってるのかは分かりません。でもせっかく続けているのだし、改めて自己紹介を書いてみようという気になりました。