
『カレンダーストーリーズ』ウラ11月 「魔術の娘」 【掌編小説】作:仲井陽
一回死んでみよう、と賀野が言ったとき、私たちは戸惑った。
湖面を渡る夜風は凍てつくようで、私の二の腕には鳥肌が立っていた。昼の陽気に騙されて半袖のニットで出てきてしまったせいだ。一方、同じように薄いパーカーを羽織っただけの師走原は道中のミニストップで買ったソフトクリームなんか食べていて、寒さを感じる神経が死んでるんじゃないかと思った。かすかに口紅のついた乳白色の滴りが砂利の上に落ちた。賀野は黒のコートに身を包み、景色と溶け合っていた。彼女の背後にはあらゆる光を呑み込んで暗い湖が広がっていた。
もしこの場に誰かが通りかかったとしたら、きっと異様な光景に見えただろう。山奥の湖畔に佇む三人の若い女。時刻は23時30分。近くに停めた車から漏れる明かりがなければ、ここにいることすら気付かれないかもしれない。もっとも、こんな時間に通りかかるのは遭難した登山者か、死体を遺棄する専門職の方々ぐらいだろうけど。
「それで? 本当に死ぬの? なに、今回は臨死体験?」
指に垂れたソフトクリームを舐めとって師走原が言った。まるで、そんなことで動じるもんか、みたいな余裕ぶった言い方だった。しかし賀野は答えず、思わせぶりに含み笑いをした。揺れる長い髪と相まって、だんだんと魔女みたいになってきたな、と私は思った。
賀野は特別な女の子だった。人より感受性が強く、周囲の環境に対する勘の鋭さみたいなものを持っていて、そのせいかまだ発見されてない不思議な現象を見つけるのが得意だった。不思議な現象といっても二重の虹だとか蜃気楼だとか、SNSで回ってきそうなありふれたものじゃなくて、もっと超常現象に近いもの、SFやファンタジーの世界で起こるような非現実的なものだ。彼女に言わせればあくまで『ごく限られた条件でのみ観測できる物理現象』らしいのだが、私や師走原にとっては奇跡や魔術と同じだった。
例えばそれはこんなふうだ。――気温16℃、湿度65%から72%の時に、揚げたジャガイモを耳に挟み、大学ノートの上に片足で立ちながら、筋肉少女帯の『香菜、頭をよくしてあげよう』の替え歌を歌うと、空中を歩くことが出来る――。またはこう。――南西からの風、海抜2mから2m60cmの屋外で、銀杏の匂いを嗅ぎながら(必ずしも銀杏自体が要るわけではない)、67歳の女性の頭上で銅とポリエチレンとマヌカハニーを一定の力で擦り合わせると、7分だけ時間が巻き戻る――。他にも、新月の夜にチワワの写真を見ながらンッブィーア語の子守唄を聞くと、どんな不眠症患者でも(あるいは10時間以上寝続けた直後でも)一瞬で意識を失って眠りに落ちるとか、ゴマ油であえたネギと大根をカスタムしたMac Book Proでプレスすると2歳若返るとか。
何がどういった関係でそうなるのか全然分からないし、何を手掛かりに思いつくのかもさっぱりだったけど、こういったことを賀野はふとした拍子に発見するのだった。そして一人で検証を繰り返したあと、見つけたものの中からとっておきを選んで、私と師走原にだけこっそりと教えてくれた。賀野は注目されたいタイプの人間じゃないし、おおっぴらにしたくないのは分かっていた。ただ、せっかく見つけた驚きを誰かと共有したいんだろう。世界の真理に触れる裏ワザは、親しい友人である私たちにだけ与えられたギフトだった。
この秘密の会合は大抵冬の初めに開かれるので、毎年11月に入ると私も師走原もそわそわして、賀野からの連絡を待ち望んだ。そして日時と場所だけを記したそっけないメールが届くと、私たちはそれがどんなに人里離れた場所であろうとも(そもそも人目につかない方がいいし)いそいそと出かけ、宙に浮かんだり、時間を巻き戻したり、互いの身体を交換したり、若返ったり、3kg痩せたりして楽しんだ。それはどんなテーマパークでも決して味わえない、本物の、特別な体験だった。
だから死という言葉に一瞬怯んだものの、それは賀野の露悪的な言い回しに過ぎなくて、またいつものワクワクするワンダーな出来事が待ってるんだと思ってた。あの子の名前が出てくるまでは。
「臨死体験っていうのは近いかもね」
賀野は言った。
「死んだ人と会えるやり方が分かったんだ。今回はそれ。久しぶりに穂木田に会いたくない?」
穂木田。その名前を聞いた瞬間、私は深い穴に突き落とされた。
「うっそ! 会いたい会いたい! ほんとに!? ほんとに会えるの!?」
師走原が興奮して賀野の肩をつかんだ。目じりに涙を溜めながら、まるで火のついたねずみ花火みたいな騒ぎようだった。無理もない。穂木田がいなくなって一番悲しんだのは師走原だったから。高校の途中まで私たちは四人組で、特に穂木田と師走原は同じバスケ部だったこともあり、私や賀野には言わないような深い悩みまで話し合う仲だった。のんびりしてどこか抜けてる穂木田は、気忙しい師走原にとって居心地が良かったんだろう。穂木田が死んだあと、師走原はしばらく引きこもりになった。大学受験にも失敗し、一度は自殺未遂までした。彼女の人生は、友人の死によって確実に変わってしまった。
私は、鳥肌が立っているというのに、首筋から噴き出す汗が止まらなかった。そして動揺を悟られないよう、精いっぱいの笑顔を作って言った。
「いいね。超懐かしい!」
賀野は肩を揺すられながらも、私の目をじっと見つめて離さなかった。まるで反応を窺うように。ほころびが出ないか観察しているように。いや、過敏になっているからそう見えるのかもしれない。私は粟立ったままの二の腕をさすりながら、ありもしない上着を求めて視線をさまよわせた。
「じゃあ、いいね。今回は穂木田と会うってことで」
そう言って賀野は笑った。目の奥が笑ってないのはいつものことで、そこから何かを読み取ることはできなかった。
――放課後、私は教室に一人残って勉強をしている。冬の空はあっという間に光を失い、シルエットを作っていた夕焼けも夜の闇に溶けてしまう。廊下の向こうからどこかのクラスではしゃぐ女子の声が響いてくる。私は制服の袖から下に着込んだセーターを引っ張りだし手の甲を覆う。それでも指先がかじかむので、ぐーぱーとストレッチを行い、あげくクルクルとペンを回し出す――
11月の湖は冷たく、無数の得体の知れないものたちが足元で泳ぎ回っているような感じがした。私は賀野に手を引かれ、服を着たままゆっくりと歩みを進めた。ぬるぬるした湖底は次第に深くなっていき、肌と下着とニットの隙間に暗い水の感触が染みわたった。そして、私たちの口の中にはナットともずく酢が入っていた。
「だいじょーぶー!? そろそろ見えなくなるよー!」
岸から師走原の声がした。振り向くと彼女の掲げる和ロウソクの灯りが随分と心もとなく揺れた。
「らーいろーぶー! ごごげあうあらー!」
賀野の声はナットともずく酢に邪魔されて、うがいの途中で怒鳴ったみたいになった。多分『大丈夫、ここでやるから』と言ったんだろう。賀野は手を放すと、私に目で合図をした。水面が胸の高さにあった。私は頭の中でさきほど教えられた、そしてこれから行う手順をシミュレートした。
死者と会うためには、生と死の狭間の、いわゆる三途の川のような場所へ行かなければならないらしい(賀野はその場所を『仄暗いところ』と呼んだ)。普通は瀕死の状態、例えば事故や病気なんかで死にかけないと辿りつけないのだが、この方法だったらそういう危険を冒さないで済むのだそうだ。ただし、冷たい夜の湖で和ロウソクに照らされてナットともずく酢を口に含んだまま手旗信号をしつつ十秒間浮かばなければならず、賀野曰く、危険性が少ないにしてもゼロではないということだった。まず、成功すると仮死状態に近づき半分意識を失ってしまうので、うっかり沈むと溺れかねない。だから岸で見張る人間が必要だし、またその状態を解くには車のクラクションが最適で、一定時間ごとに鳴らさなければ戻って来られなくなるそうだ。
つまり、三人同時に『仄暗いところ』へ行くことは不可能で、私たちは最初に誰が残るかについて話し合わなければならなかった。真っ先に穂木田に会いたがったのは師走原だったが、彼女は泳げないうえ夜の湖は不気味過ぎた。私は私で、賀野が何を企んでいるのか分からなかったので、最初の一人になるのは避けたかった。ただ、賀野自身も今回は若干及び腰だった。理由を尋ねると、まだ最後まで試してないから、と言った。
「だって一人だと出来ないでしょ? いや、上手くいくとは思うんだけど」
この一言がきっかけになって、賀野と私の二人がかりでまず試してみようということになった。泳げない師走原は安全が確認された後で実行することに決まり、私は拒否できる理由を思いつかなかった。
「ひゃあ、ひくよ!」
賀野は『じゃあ、行くよ!』と叫び、仰向けに浮かんで腕をばたつかせた。私もそれにならい体を浮かせると、少し遅れて教わった通りの手旗信号を始めた。醜いシンクロナイズドスイミングだった。暗がりで何度も水面を叩く動きは溺れているのとほとんど変わらず、私は賀野から決して目を離さなかった。溺れたふりをして、いつ沈めようとするか分からなかったからだ。岸からは遠く、賀野が私に襲い掛かっても、暴れているのか溺れているのか手旗信号をしているのか、水しぶきに紛れてしまうだろう。私は呼吸の度に侵入してくる水を吐き出しながら、猜疑心が頭の中で膨れあがっていくのを感じた。もしかしたら一回死んでみようというのは賀野の本心から出た言葉で、仮死状態になったらそれっきり死んだきりのままで、この冷たい湖に打ち捨てられてしまうんじゃ――、そこまで考えたところで、急に目の前が明るくなった。
――よそのクラスの女子は帰ってしまったのか、いつの間にかあたりは静まり、人の気配がしなくなっている。私は立ち上がり、気分転換も兼ねて校舎をうろつく。蛍光灯の平べったい明かりと薄暗がりのグラデーションを次々と通り抜け、埃っぽいコンクリートに張り付いた入学からの思い出をなぞって歩く。そうしているうちに私は格好の憂さ晴らしを思いつく――
気づくと私は小高い丘の上に立っていた。空は高く乳白色で、眼下にはあらゆる季節の花が咲き誇り、見渡す限りどこまでも花々に彩られた草原が続いていた。辺りには温かな気配が漂っていた。まるで味わったことのない感覚だった。安らぎが胸の中いっぱいに広がり、自分は存在しているだけで価値があるのだという確かな実感を際限なく呼び起こした。もしかしたら母親に抱かれた赤ん坊はこんな気持ちなんだろうか。あるいは日向ですやすやと眠る子猫は。不安や焦りといったネガティブな感情は影すら見せず、大きく息を吸うと太陽の匂いがした。『仄暗いところ』という呼び名とは裏腹に、輝きに満ちた場所だった。
少し離れたところに賀野がいた。私より早く到着したらしく、すでに誰かと会話をしていた。相手はもちろん穂木田だった。そののんびりした顔を目にした瞬間、幸福感は急速に翳り、恐れと懐かしさが心臓を締め上げた。
「じゃあ本当に」と賀野が言った。まだ私が来たことに気づいてないようだった。
「自分から飛び降りようと思ったんだね?」
確認するというよりも、信じられないといったニュアンスが強かった。
「そうだよー。なんで信じないのー?」
そう言って困ったように穂木田は笑った。小さな目をくりくりと見開いて、あの頃のまんまの顔で。なんということだろう。九年前から全く変わらない彼女の姿を見て、初めて私は自分が年を取ったことに気づいた。永遠に高校生のまま留まっている彼女は、とても子供っぽく見えた。
穂木田は私を見つけると、嬉しそうに手を振った。
「あ、来たー! 久しぶりー!」
まるで同窓会に遅刻してきた旧友を迎えるようだった。同じく振り返った賀野の目の中に、ほんの一瞬だけ、苦々しい色が差した。聞かれたくない話を聞かれたような感じだった。穂木田は手を振りながら続けた。
「いま話してたんだよー、心配だねーって。もし失敗して来れなかったらどうしようって。でも師走原が付いてるって言うし、だったら安心だーって」
相変わらず下手なウソだ。私は穂木田のこういうところが大嫌いだった。抜けててどんくさくて、一見人に配慮しているようでそのくせ圧倒的に想像力が足りなくて、結局は全部裏目に出てしまうところが。さっきの幸福の残滓がなければ、きっと笑顔を作れなかっただろう。私は駆け寄って、「会いたかったー。全然変わってないねー」と言った。
そうやって下手なウソに乗ったまま、私たちはしばらく当たり障りのない会話を続けた。互いの近況、同じクラスだった時の友人や担任の噂話、最近の師走原について……。決して彼女の死については触れなかった。水たまりを大きく迂回するように、会話の先にあの日の影を感じ取ると、私も穂木田もそこへ向かわないようにハンドルを切り、不自然なほど話題にすることを避けた。賀野はそんな私たちを眺めているだけで、会話に入って来ようとしなかった。
違和感があった。穂木田は何を考えているんだろう。私はともかく、どうして穂木田まで避ける必要があるんだろう。賀野にも話してないみたいだし、何もかもぶちまけて恨みを晴らすチャンスなのに。それとも、死者になると自分が死んだときのことを忘れてしまうんだろうか。いや、だとしてもウソをつく必要はないはずだ。いったいどういうつもりなんだろう。これじゃまるで、私をかばってるみたいじゃないか。
「……でね、今いるところって本当に素敵で、ここもいいけど、ここより何十倍も穏やかで幸せなとこでさー」
穂木田はにこにこと笑いながら、自分が今いる、死んだ後の世界について語っていた。なんだか本当に恨みや悲しみとは無縁の存在になったみたいだった。私は急に、頭の裏側が熱くなっていくのを感じた。
恨んでないだって? 本当に? 私はずっと忘れなかったっていうのに?
まるで昨日のことのように鮮明に焼き付いて片時も離れず、ずっとずっと苦しめられてきたっていうのに?
目の前にいるのは、紛れもなく十代の穂木田だった。あの頃のままの、かつて私たちと同じところにいた彼女だった。
――放課後、私は教室に一人残って勉強をしている。私たちは高校三年で、迫りくる受験や窮屈な人間関係に日々息苦しさを募らせている。冬の空はあっという間に光を失い、シルエットを作っていた夕焼けも夜の闇に溶けてしまう。廊下の向こうからどこかのクラスではしゃぐ女子の声が響いてくる。
私は制服の袖から下に着込んだセーターを引っ張りだし手の甲を覆う。それでも指先がかじかむので、ぐーぱーとストレッチを行い、あげくクルクルとペンを回し出す。浪人回し、という名称を思い出して慌ててやめるも、やってしまったことに少しへこむ。私は形のはっきりしない苛立ちに囚われている。不安と言い換えてもいいが、この時の私はそうとは決して認めない。
廊下を男子生徒が通り過ぎる。確かバスケ部で、師走原の好きな人だ。ただ、彼は穂木田のことが好きで、すでに告白して振られているが、それでも彼女のことをまだ好きでいる。穂木田は告白されたことを決して師走原に言わないが、師走原は穂木田と彼の態度からなんとなく察しが付いていて、それでも何も気づかないフリをしている。私はそういう全てを本当に気持ち悪いと思っている。
気づくとあたりは静まり返り、よそのクラスの女子も帰ってしまったのか、人の気配がしなくなっている。私は立ち上がり、気分転換も兼ねて校舎をうろつく。蛍光灯の平べったい明かりと薄暗がりのグラデーションを次々と通り抜け、埃っぽいコンクリートに張り付いた入学からの思い出をなぞって歩く。
理科室の前を通りかかった時、壁に掲げられた温度計と湿度計が目に留まる。そして私は格好の憂さ晴らしを思いつく。踵を返し、元いた教室へと必要な物を取りに戻る途中、体育館へと続く通路の前で、女バスに顔だけ出していた穂木田とばったり出会う。私は反射的にさっき見た男子の横顔を浮かべる。体育館の方から運動部特有の、何と言っているのか分からない掛け声が絶え間なく聞こえてくる。私は暗い屋上に一人で出るのが少し怖くて、穂木田だけど仲間に誘う。彼女は渋るが、強く頼まれると断れないことを私は知っている。ただ、他意があったわけではない。少なくともこの時はまだ。
屋上に出ることは禁止されていたが、鍵がずっと壊れていて、鍵が壊れていることを知っている生徒なら誰でもこっそりと出入りできる。外は思ったより寒くなかったが、それでも息を吐くと白い。鼻の奥で仄かに雨の匂いを感じる。私は持ってきた大学ノートを地面に広げると、その上に立ち、右足を上げる。先日賀野が私たちに教えてくれたやり方を思い浮かべ、じゃがりこを一本取り出して耳に挟み、小声で次のように歌う。
「かーなっ、きーみのっわるーい、むしーをたーべちゃーいーけなーいーよ-、かーなっ、かーらだーじゅうーに、へんなあざがーでっきるかっらー」
続きは割愛するが、そうやって歌いながら上げた右足を宙に踏み出すと、何も無い空間に確かな感触を得て、見えない足場ができる。そのまま右足に重心を移し、左足を持ち上げると、いよいよ私の体は地面から離れる。それが二歩、三歩と続き、私は自在に空中を歩く。屋上の縁を越え、四階建ての校舎の外へと出て、足元の遥か下に広がる暗いグラウンドと校舎の反対側にあるプールの上をひと回りして、また屋上に近づく。
いい気分になった私は、穂木田にも同じことをさせようとする。彼女は怖がっていてあまり乗り気ではないが、大学ノートを開かせ、じゃがりこを耳に挟ませ、片足を上げさせる。この時、穂木田の上げている足が右ではなく、左であることに私は気づく。しかし彼女のそういう雑な部分にうんざりしていた私は何も言わない。間違った手順でやるとどうなるんだろうという好奇心と嗜虐心も後押しをする。
彼女は私に続いて歌い出す。輪唱のように、私のすぐ後を追いかけて歌う。しかしそれも歌詞の一部を間違えたり、音を外したりしている。それでも彼女の振り下ろした左足が宙にかかる。そのまま右足を浮かして、彼女もまた空中歩行者となる。ただそれはとても不安定で、ガス欠の車のようにガクガクと揺れ、非常に頼りない。彼女もそれに不安を感じていて、決して校舎の縁から外へ出ようとしないが、私はそのグズグズとした様子がまた気に食わず、強引に彼女の手を取って地上十数メートルの空中へ連れ出そうとする。安定しなくても浮かべてるんだし、いざとなれば自分が支えるつもりでもいる。私は意地悪く、「さっきあの人見かけたよ。あの、師走原の好きな人。穂木田もストレス溜まってるんじゃないの? ずっと黙ってるとさ。パーッと発散しようよ。気持ちいいよ、空歩くの」なんてことを言う。
そうして穂木田は仕方なしに屋上の縁を越える。ただ、足元の地面が遠くなって恐怖が増したのか、彼女はまた音程を外してしまう。その瞬間、私の手に数十キロの重さが一気にかかる。繋いだ手が紙みたいに千切れる。悲鳴が耳を刺す。穂木田の体はあっという間に地面に激突し、正面玄関入口のコンクリートに赤いカーペットが広がる。私は焦り、混乱し、それでも証拠だけは残しちゃいけないと、素早く大学ノートをかっさらって、人目に付かない裏の林へと透明な階段を駆け下りる――。
追憶に浸っていたせいで私は会話に専念できず、私も穂木田も「ああ……」とか「そうそう……」とか言い合うようになって、話の継ぎ目を見失ってしまった。柔らかな風が足元の草花を揺らし、甘い香りが鼻先をかすめた。気まずい沈黙が私たちの間に横たわっていた。
するとタイミングを見計らっていたのか、賀野が口を開いた。
「……私はね、穂木田。ずっと私は、自分のせいであんたが死んだんじゃないかって思ってる」
誰も何も言わなかった。賀野は続けた。
「ねえ、本当に自分の意思で飛び降りたの? 嘘でしょ? だって自殺するほどの悩みなんかなかったじゃん」
「ひどーい。私だって人並みに悩んでたんだよー?」と穂木田が笑った。
「人並みの悩みって思うなら自殺はしないよ。ねえ、正直に言って。本当はあのとき空中を歩こうとしたんじゃないの? ほら、その前の週にみんなで試したじゃん。あれやろうと思ったんじゃないの?」
詰め寄る賀野に対し、穂木田は腕組みをして、おでこに皺を寄せた。彼女が困った時によくやる、懐かしいポーズだった。私は蚊帳の外から二人のやり取りを眺めていた。何を言っても藪蛇になるような気がした。
やはり賀野は、穂木田の死に疑いを抱いていたのだ。
「でもさ」
穂木田が言った。
「私そもそもさ、ああいう難しい手順を覚えるの苦手じゃん。教えてもらってもいっつも上手く出来ないしさー。やろうと思わないと思わない?」
「一人だったらね」
賀野は穂木田から視線を逸らさずに言った。
「私は、誰かに誘われたんじゃないかって思ってる」
賀野は今、隠そうともせずに私を疑っていた。決して私の方を見ようとせず、切り揃えられた黒髪が小刻みに揺れていた。私は何も言えなかった。凍ったように固まって、身動きが取れなかった。唾を呑み込むことすら、自分が犯人だと自供しているような気がして出来なかった。
「なんて言ったらいいのかな……」
穂木田がおでこに手を当てて考え込んだ。細い指先が何度も眉毛の上をなぞった。
「私はさ、あのとき本当に悩んでてね。賀野にも話したと思うけど、友情と恋愛の板挟みみたいな、まあ人並みな悩みなんだけど、私にとっては大問題でさ。部活も引退した直後だったし、なんか、もやもやが溜まってて。嫌になったんだよね、全部。本当に」
「それで飛び降りたって?」
賀野は表情一つ変えなかった。
「そうだよ。いや、だってさ、誘われてもやらないって。私、じゃがりこだって持ってなかったしさ。出来るわけないもん」
そのとき、遠くから車のクラクションが聞こえた。30分経ったら鳴らすよう師走原と取り決めてあったのだ。
「時間……」
私は誰ともなしに呟いた。クラクションの音が聞こえたタイミングじゃなきゃ戻れないと言ったのは賀野だ。しかし当の本人は穂木田を見据えたまま動こうとしなかった。
もう一度、今度は少し長めにクラクションが鳴った。
「賀野、どうすんの?」
私はしびれを切らし、賀野の肩を揺すった。しかし彼女は振り向きもせずに言った。
「じゃがりこってなに?」
「え?」
穂木田の目に初めて不安の色が浮かんだ。
「私そんなやり方教えてないけど? マックのポテトだったじゃん、一緒にやったときは。師走原がチャリで買いに行ってさ。出来るかなってやってみたら出来てさ。なに? なんでじゃがりこになってんの? 誰がそんなやり方したの?」
三度目のクラクションが鳴った。穂木田の顔からは笑顔が消えていた。賀野は微動だにしなかった。私は、賀野の肩から手を離すタイミングを失ってしまった。
「……いや、もうさ、いいじゃん」
穂木田がうつむいたまま首を振った。
「誰が悪いとか、ほんとはどうだったとか、私べつに気にしてないしさ。そんなことでみんなの仲が悪くなる方が嫌だしさ」
しかし賀野は黙ったままだった。四度目のクラクションが聞こえた。
「……いったん戻った方がいいんじゃない?」
私は再度賀野の肩を揺すったが、無言のまま振り払われただけだった。穂木田を射抜くように見つめるその横顔は、鉄で出来てるみたいだった。こうなった賀野には何を言っても無駄で、そのことは私たちが一番よく知っていた。
「……分かった。じゃあ、先に行ってるね」
私は観念し、一人で帰ることに決めた。すると次の瞬間、私の身体は暗い湖に浮かんでいた。滲んで揺れる夜空は澄み渡り、月が出ていないせいか星がやたら輝いて見えた。
「どうだった!?」
岸に上がる私へ、師走原がタオルを差し出しながら駆け寄ってきた。私はじゃぶじゃぶと足で水際を掻き分け、タオルを受け取ると、顔にまとわりつく水滴を拭った。もずく酢とナットは歩いてる途中で水の中へ吐き捨てた。頭の中は万華鏡みたいにぐちゃぐちゃだった。これからやらなければいけないことと、やってはいけないこと、それらの算段が次々と浮かんでは入り乱れて、寒さを感じる余裕なんかなかった。
「賀野は?」
湖面に浮かんだまま起きてこない彼女を見て、師走原は不安がった。私は顔の水滴をすっかりふき取ると、焦りを気付かれないよう肩と腕をごしごし擦りながら言った。濡れた服が肌にへばりついて鉛のようだった。
「賀野はまだ残るって」
「はあ?」
「穂木田と話があるからって言ってた」
私は体験したことを簡潔に話した。無事に穂木田と会えたこと、『仄暗いところ』は素晴らしく、穂木田も(死んだ人間をそう言うのも変だけど)元気そうだったこと、賀野はどうやら穂木田の自殺を疑っていたらしく、その真意を問い質そうとしていること……。もちろん、私が疑われているということは上手く省いて説明した。この非現実的な状況と冷えて濡れそぼる私の姿が、無表情な演技に説得力を持たせてくれた。
師走原は、始めのうちはあれこれ質問していたが、だんだんと真剣な顔つきになり、最後は黙って頷くだけになった。真っ直ぐな眼差しにはこれっぽっちも疑いがなかった。
私は言った。
「だから、師走原に早く来てほしいって。次は私がクラクション鳴らす番で、一緒に穂木田の話を聞いてほしいって言ってた」
その後のことはよく憶えている。
私はもずく酢とナットを師走原の口へ流し込むと、手順を確認して彼女を湖へと送り出した。泳げない恐怖を友情で塗りこめて、師走原はしばらくバシャバシャと湖面を叩いていたが、どうやら上手くいったらしく、やがて賀野の隣で静かになった。私は和ロウソクを突き出して、灯りがてらてらと反射する暗い湖面に目を凝らした。意識が旅立ち、仮死状態になった二人は、死んだ魚のように並んで仲良く腹を見せ、口をだらしなく開けながらプカプカと浮かんでいた。美しき友情の死骸、という言葉が頭に浮かんだ。
私は和ロウソクを湖に投げ捨て、車に乗り込んだ。エンジンをかけると、賀野の好きな、よく分からない民族音楽がカーステレオから流れ出した。私は深呼吸をして、ハンドルに頭を預けた。
このとき私の頭にあったのは、とにかく時間が欲しいということだった。誰にも邪魔されず、一人でじっくりと対策を練るための時間が。師走原をあちらへやったのも、本当にただ邪魔をされたくなかったからで、クラクションをいつ鳴らすか、そもそも鳴らすかどうかまでをも裁量の下において、何者にも妨げられずに考え抜きたかった。しかし、どれだけ時間をかけたところで選択肢は二つしか思いつかず、どちらを選んでも苦しむことは目に見えていた。私はジレンマに引き裂かれていた。
大丈夫、すでに経験済みじゃないか、黙って知らないふりをしていればいい、どうせ分かりはしないんだから、という思いと、もうやめよう、全てを告白して楽になろう、これ以上罪を抱えたくない、という思いが、数分おきにくるくると入れ替わった。
その後取った行動について、もし言い訳をさせてもらえるならば、この時の私は酷く混乱していて、正常な判断ができる状態じゃなかった。それは自分でも分かっていたし、だから気分を変えようとして、一旦湖を離れたのだ。山道をひと回りしながら頭を冷やした後、本当に戻って来ようと思っていた。
ただし、その夜が新月で、車内に流れていた音楽がンッブィーア語の子守唄だと気づいたのは、車を走らせてからすぐの時点でカーナビにチワワの写真が映し出されたからだった。どうやってなのかは知らないが、こうなることを予測していたのか、あらかじめ賀野が罠を仕掛けていたのだ。一瞬で眠りに落ちた私はそのままガードレールに激突し、高らかなクラクションが彼女の勝利宣言のようにいつまでも山の中にこだました。
そのおかげで賀野たちは目を覚まし、山道を朝まで歩かなければいけなかったものの、無事に生還することができた。それを私がこうして喜べるのは、穂木田の言った通り、ここがとても素晴らしいところだからだ。不安も苛立ちも悪意もなく、私はようやく穏やかで幸福で光に満ちて――。
ウラ11月「魔術の娘」/作:仲井陽
cover design・仲井希代子(ケシュ ハモニウム × ケシュ#203)
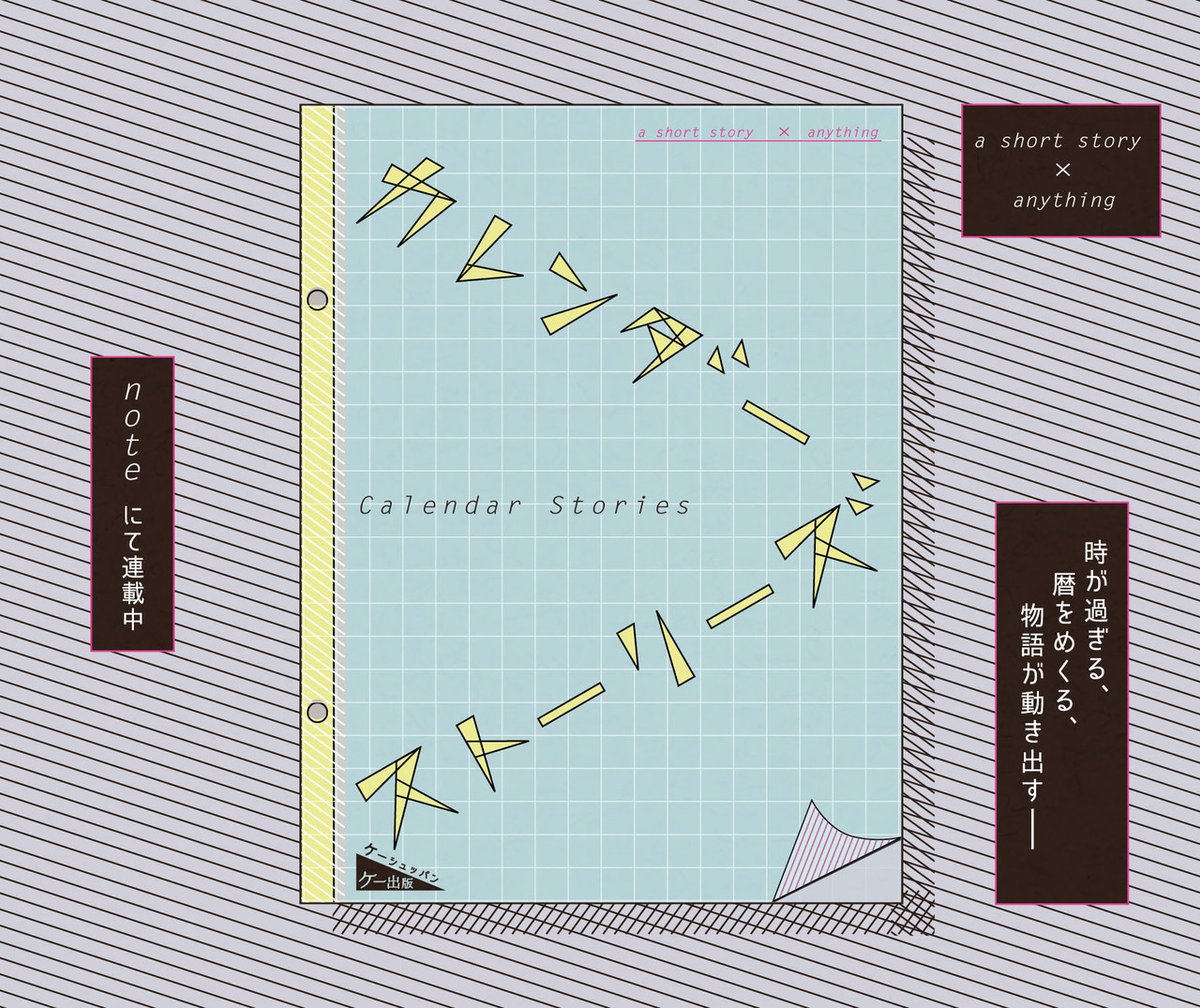
*『カレンダーストーリーズ』とは…"丘本さちを"と"毎月のゲスト"が文章やイラスト、音楽などで月々のストーリーを綴っていく連載企画です。第一月曜日は「オモテ○月」として丘本の短編小説が、第三月曜日は「ウラ○月」としてゲストの物語が更新されます。
※2016年 10月の更新をもって『カレンダーストーリーズ』の連載は終了しました。お読みいただいた皆様ありがとうございました。
11月のゲスト:仲井陽(なかいみなみ)
1979年生まれ、石川県出身。演劇と自主映画にどっぷり漬かったのち、現在、映像作家として主にアニメーションを作って暮らしている。(ex:NHK Eテレ『100分de名著』『グレーテルのかまど』など)
また、ラジオドラマの脚本執筆(NHK FMシアター『引き出したのなら仕舞っておいて』)、2015年には、奇妙で不可思議な町『田丁町(たひのとちょう)』を舞台とした連作短編演劇群『タヒノトシーケンス』を立ち上げるなど、活動は多岐に渡る。
◆2015/12/5 21:00〜 NHK FMにて 上記『引き出したのなら仕舞っておいて』放送予定
http://www.nhk.or.jp/audio/html_fm/fm2015028.html
●ケシュ ハモニウム(問い合わせ)
Web → http://www.kesyu.com
Facebook → https://www.facebook.com/kesyuhamo
Twitter → https://twitter.com/KesyuHamonium
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
